目的から探す
ホーム > 県政情報 > 県の概要 > いばらき統計情報ネットワーク > いばらき統計情報ネットワーク(統計課) > 分野別≪産業連関表≫ > 平成17年(2005年)茨城県産業連関表
ページ番号:12792
更新日:2016年8月30日
ここから本文です。
平成17年(2005年)茨城県産業連関表
平成17年(2005年)茨城県産業連関表は,茨城県内における1年間(平成17年暦年)に行われたすべての財・サービスの産業間の取引や産業と最終消費者(家計等)間の取引及び他地域間の取引を一覧表にとりまとめた経済活動の見取り図です。本県では,昭和55年(1980年)表を公表以降,西暦の末尾が0または5の年を対象に5年ごとに作成しており,今回が6回目のものとなります。
公表内容は,13部門,37部門及び108部門の統計表(生産者価格評価表,投入係数表,逆行列係数表(閉鎖型及び開放型),雇用表及び最終需要項目別生産誘発額等に関する分析表)と,これらを活用した県経済の全般的な構造解析です。
目次
見たい項目をクリックして下さい。
利用上の注意
1.前回(平成12年表)との変更点
平成17年茨城県産業連関表は,前回(平成12年表)とは部門分類が一部異なっており,今回より新たに推計したものもありますので,時系列では単純に比較できない場合があります。なお,主な変更点は以下のとおりです。
- これまでの部門で該当する部門がなかったため,「インターネット附随サービス」を新設した。(37部門では「情報通信」に計上)
- 「石油・天然ガス」部門と列部門の「石炭」を統合し,「石炭・原油・天然ガス」とした。(37部門では「鉱業」に計上)
- 「出版・印刷」,「調査・情報サービス」及び「娯楽サービス」の一部を統合して「映像・文字情報制作」とした。(37部門では「情報通信」に計上)
- 日本標準産業分類の改定に伴い「重電機器」と「その他電気機器」を統合し,「産業用電気機器」とした。(37部門では「電気機械」に計上)
- 「その他自動車」を「その他の自動車」を「その他の自動車」と「自動車部品・同付属品」に分割した。(37部門では輸送機械に計上)
- 日本標準産業分類の改定に伴い「その他製造工業製品」,「対事業所サービス」及び「対個人サービス」のそれぞれの一部と「通信・放送」を統合し,「情報通信」とした(37部門)
- 平成12年表では,「再生資源回収・加工処理」部門を新設し,「屑・副産物」は一括して「再生資源回収・加工処理」部門に投入され,当該部門から需要部門に産出されることとし,「屑・副産物」の投入に回収及び加工に係る経費を加えたものを生産額として計上した。しかし,平成17年表においては,「再生資源回収・加工処理」部門には「屑・副産物」の回収及び加工に係る経費のみを生産額として計上した。
2.輸移出入
37部門のうち「金融・保険」,「不動産」,「情報通信」及び「その他の公共サービス」の輸移出入の推計については,適当な資料が見当たらないため,純輸移出入扱いで推計しています。
(例:県内生産額-中間需要-県内最終需要がマイナスならば,マイナス額をすべて輸移入に計上し,輸移出は0とする。)
3.全国の数値
文中の全国の数値は,総務省など10府省庁が共同で作成した「平成17年(2005年)産業連関表」の数値となっています。
平成17年茨城県産業連関表からみた県経済の概要
平成17年茨城県経済の概況
平成17年茨城県産業連関表から,平成17年の茨城県経済の概況をみると,財・サービスの総需要は,35兆7,911億円となりました。
このうち,36.9%の13兆2,077億円が県内産業の生産に必要な原材料や燃料として使用する中間需要であり,31.8%にあたる11兆3,629億円が県内最終需要の消費・投資となっています。また,残りの31.3%にあたる11兆2,205億円が茨城県外への輸移出となっています。
この総需要に対して財・サービスを供給するために,70.4%にあたる25兆1,884億円は県内で生産され,29.6%にあたる10兆6,027億円は不足分として県外からの輸移入により供給されています。県内需要(中間需要+県内最終需要)に占める県内生産品(県内生産額-輸移出)の割合を示した県内自給率は56.8%となっています。
県内生産額25兆1,884億円の内訳をみると,県内産業の生産に用いられた原材料や燃料の中間投入が13兆2,077億円であり,県内生産額の52.4%を占めています。また,県内生産額のもう一つの要素である粗付加価値は11兆9,807億円であり,主な項目の構成比をみると,雇用者所得が47.3%,営業余剰が21.8%,資本減耗引当が19.0%となっています。
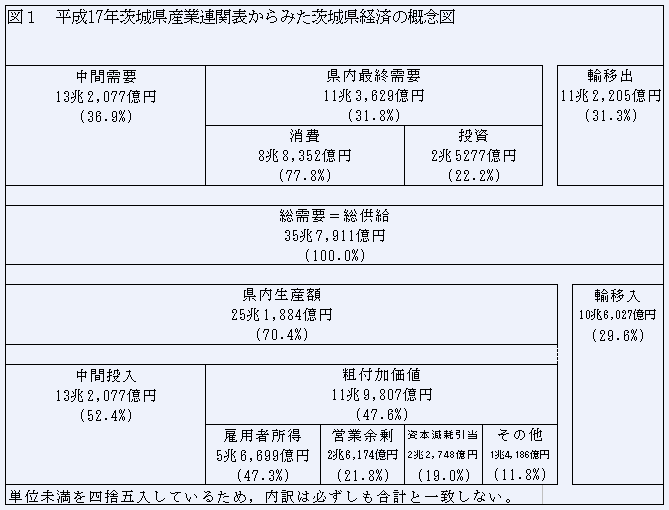
県内生産額
1.県内生産額の推移
平成17年の県内生産額は25兆1,884億円であり,平成12年に比べて2.2%増加した。
平成17年の県内生産額は25兆1,884億円となり,平成12年に比べて2.2%の増加となりました。
伸び率を時系列でみると,昭和55年から昭和60年は26.8%,昭和60年から平成2年は25.6%,平成2年から平成7年は10.6%と二桁の伸び率で推移してきたところで,平成7年から平成12年はほぼ横ばいの0.1%となりましたが,平成12年から平成17年は2.2%に伸び率が増加しました。
また,全国の伸び率1.4%を上回りました。全国の伸び率を上回った主な要因として,第2次産業が全国では4.0%減少したのに対し,本県では3.3%増加したことが挙げられます。一方で第3次産業は全国では5.4%増加したのに対し,本県では1.0%の増加にとどまりました。
本県の伸び率に対する寄与度をみると,第2次産業が1.8%,第3次産業が0.5%であり,第2次産業が経済成長の主要因となったことが分かります。
用語の解説
県内生産額
一定期間内に県内に所在する事業所の生産活動によって生み出された財・サービスの総額をいう。
寄与度
全体の変化率に対して各項目がどの程度影響を与えているかを示すものである。(内訳の期末の値-内訳の期首の値)÷全体の期首の値×100の式により計算される。
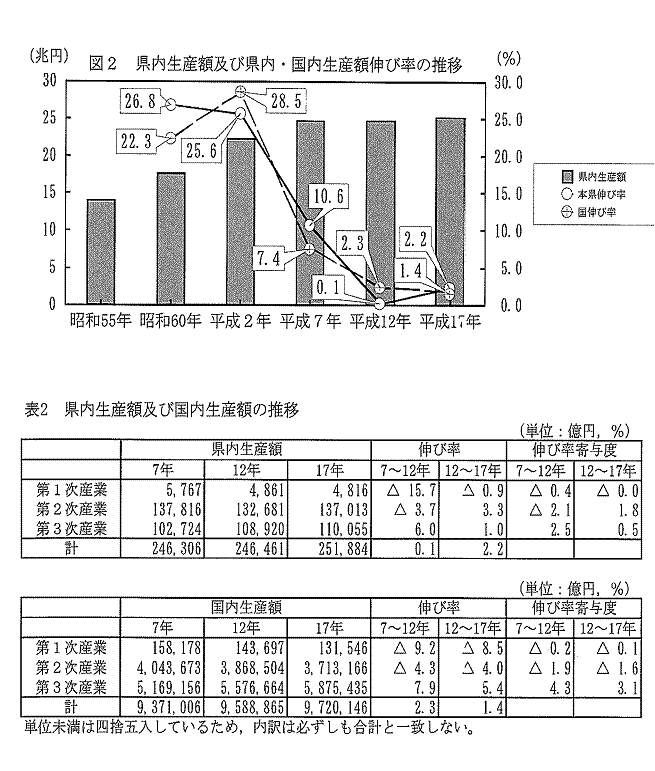
2.県内生産額の産業別構成比
県内生産額の産業別構成比をみると,第1次産業は1.9%(-0.1ポイント)第2次産業は54.4%(+0.6ポイント),第3次産業は43.7%(-0.5ポイント)となり,第2次産業が全国の構成比(38.2%)を大きく上回り,第3次産業が全国の構成比(60.4%)を大きく下回る産業構造になっている。
平成17年の県内生産額の産業別構成比を13部門でみると,最も割合が高いのは「製造業」で48.4%を占め,次いで「サービス」が16.1%,「建設」が5.8%,「不動産」が5.5%の順になりました。
平成12年と比較してみると,「製造業」(46.4%→48.4%),「不動産」(4.8%→5.5%),「電力・ガス・水道」(3.2%→3.8%),「公務」(3.5%→3.9%)の割合が上昇しました。一方,「建設」(7.3%→5.8%),「サービス」(17.4%→16.1%),「運輸」(4.8%→4.0%),「商業」(6.1%→5.5%)などの割合が低下しました。
第1次・第2次・第3次産業別にみると,第2次産業の割合が53.8%から54.4%に上昇しました。一方,第1次産業の割合は2.0%から1.9%に,第3次産業は44.2%から43.7%に低下しました。全国の構成比と比較してみると,第2次産業が全国の構成比(38.2%)を大きく上回り,第3次産業が全国の構成比(60.4%)を大きく下回る産業構造になっています。
用語の解説
産業
13部門における,第1次・第2次・第3次産業の区分は,次のように区分した。
- 第1次産業:農林水産業
- 第2次産業:鉱業,製造業,建設
- 第3次産業:電力・ガス・水道,商業,金融・保険,不動産,運輸,情報通信,公務,サービス,分類不明
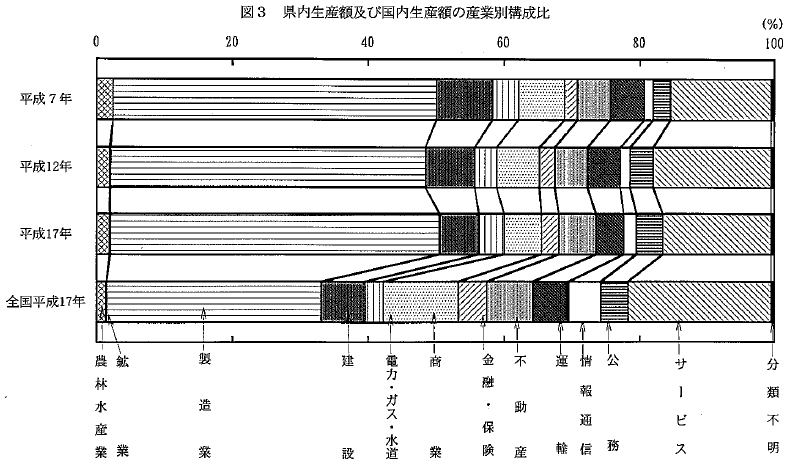
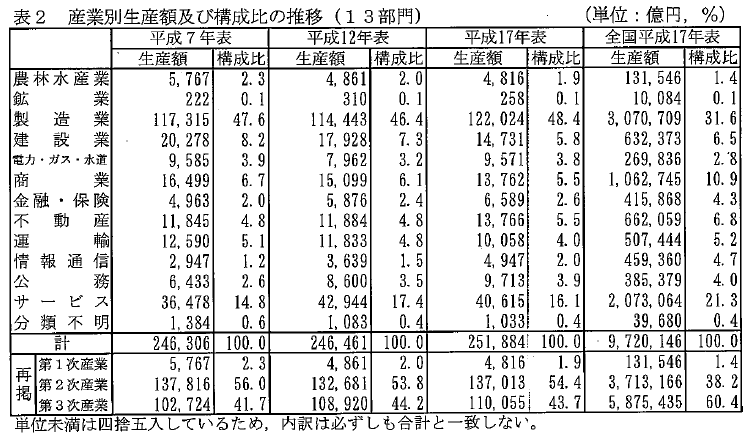
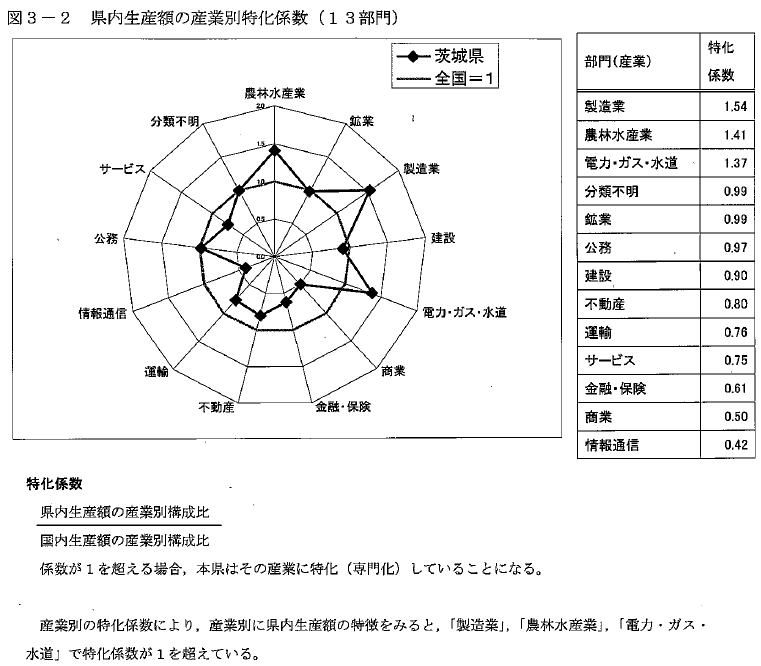
3.県内生産額からみた茨城県の主要産業
平成17年に最も生産額が多かった産業は「鉄鋼」であり,次いで「化学製品」,「飲食料品」,「一般機械」,「不動産」の順になっている。
また,全国シェアが最も高い部門は「非鉄金属」であった。
県内生産額を産業別(37部門)にみると,平成17年に最も生産額が多かった産業は「鉄鋼」で1兆7,667億円(平成12年13位)であり,次いで「化学製品」1兆6,876億円(平成12年5位),「飲食料品」1兆6,551億円(平成12年〔食料品〕2位),「一般機械」1兆5,303億円(平成12年3位),「不動産」1兆3,766億円(平成12年8位)の順になっています。
上位5部門のうち,「鉄鋼」,「化学製品」,「一般機械」,「不動産」の生産額は平成12年と比べて増加しましたが,「飲食料品」の生産額は減少しました。全国では上位5部門のうち4部門が第3次産業であるのに対して,本県では4部門が製造業になっています。
また,製造業以外で全国と比べて生産額の構成比が高い部門は,「教育・研究」(4.4%,全国3.8%),「電力・ガス・熱供給」(3.0%,全国1.9%)及び「農業」(1.8%,全国1.1%)となっています。
次に,全国の生産額に占める本県生産額の割合(全国シェア)の上位10部門をみると,「非鉄金属」が8.1%となり平成12年に引き続き最も高くなりました。以下,「鉄鋼」7.0%,「化学製品」6.1%,「一般機械」5.0%の順になっており,全国シェア上位10部門全てが製造業となっています。
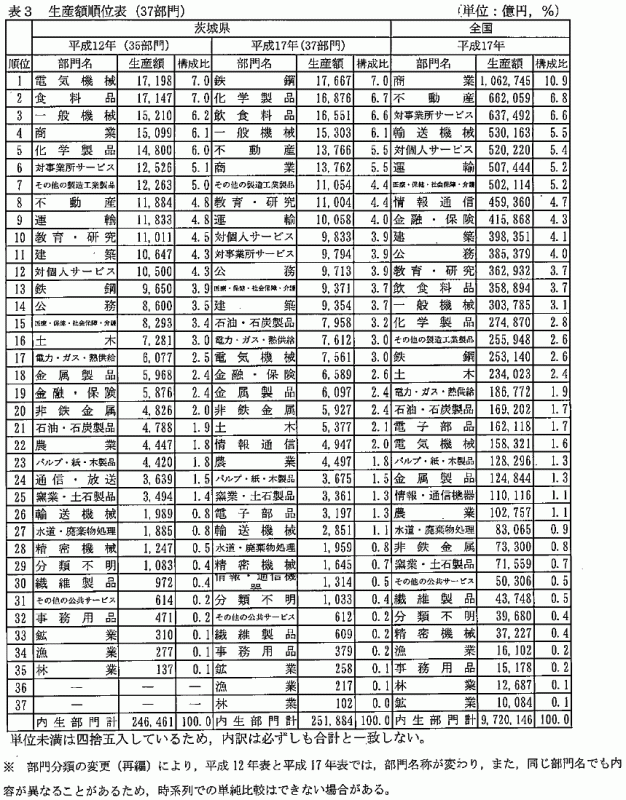
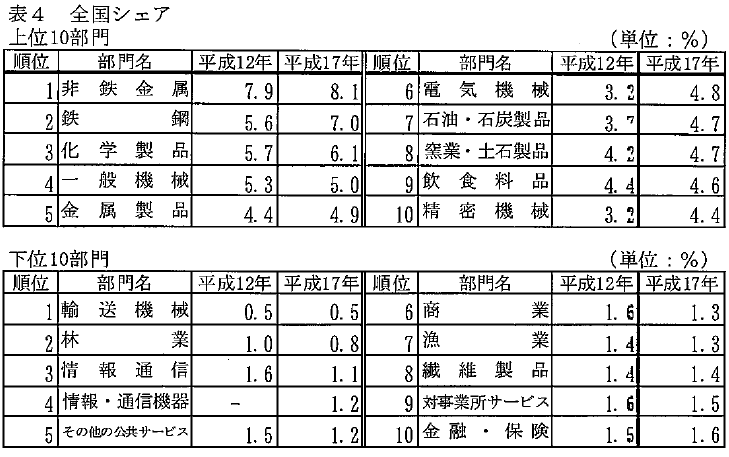
投入構造
1.中間投入と粗付加価値
県内生産額に占める原材料等の中間投入の割合は52.4%であり,平成12年(49.6%)と比べて2.8ポイント上昇した。
平成17年の県内生産額25兆1,884億円のうち,生産のために必要となった原材料,燃料等の中間投入は13兆2,077億円(中間投入率52.4%),生産活動によって新たに付け加えられた粗付加価値は11兆9,807億円(粗付加価値率47.6%)となりました。中間投入率を産業別にみると,第1次産業48.9%,第2次産業67.0%,第3次産業34.5%となっており,第2次産業で高く,第3次産業で低くなっています。
時系列で中間投入率をみると,平成12年は平成7年と比べて0.1ポイント低下しましたが,平成17年は平成12年と比べて2.8ポイントの上昇になりました。
また,全国の中間投入率(48.0%)に比べて4.4ポイント高くなっていますが,中間投入率の高い第2次産業の県内生産額に占める構成比が全国の構成比を大きく上回っているためです。
用語の解説
中間投入(率)
各産業が生産活動をするために必要な原材料・燃料等の購入費用をいう。一般に財部門では高くなり,サービス部門では低くなる。なお,生産設備等の購入費用は資本形成とされ,中間投入には含まれない。中間投入率=中間投入÷県内生産額
粗付加価値(率)
生産活動によって新たに付け加えられた価値をいう。家計外消費支出(交際費や接待費など企業その他の機関が支払う家計消費に類似する支出),雇用者所得,営業余剰,資本減耗引当,間接税及び補助金から構成される。粗付加価値率=粗付加価値÷県内生産額
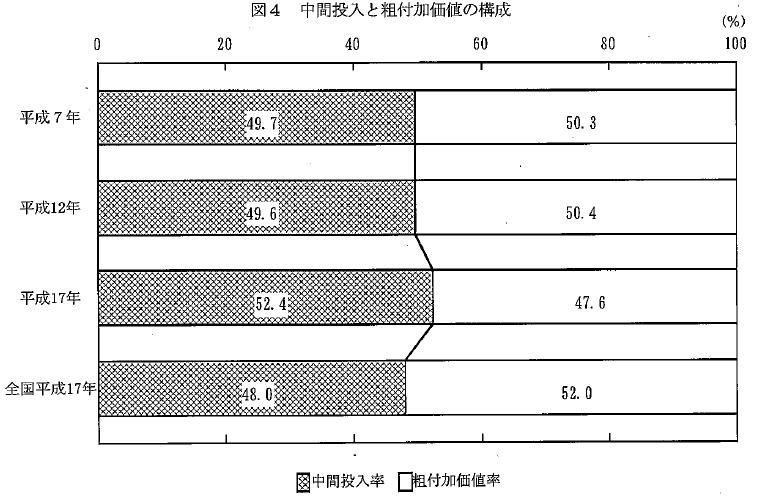
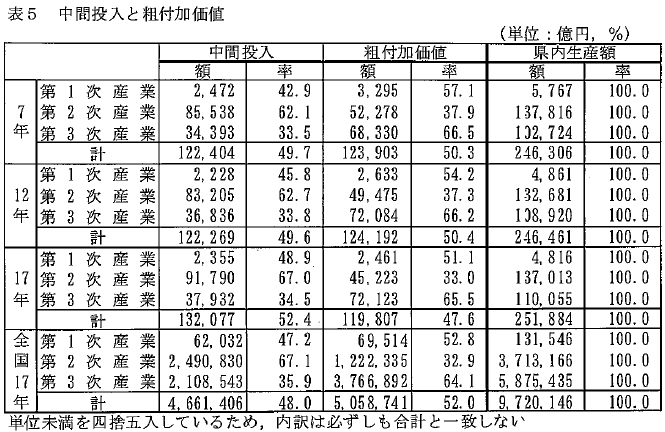
2.産業別中間投入率
中間投入率を産業別にみると,「鉄鋼」,「化学製品」,「輸送機械」などの製造業が高く,「不動産」,「教育・研究」,「公務」,「その他の公共サービス」などが低い比率となっている。
平成17年の中間投入率を産業別(37部門)にみると,「化学製品」(77.5%),「鉄鋼」(77.4%),「輸送機械」(76.2%)など製造業が高く,製造業以外では,「林業」(59.1%),「鉱業」(56.7%),「運輸」(56.0%),「建築」(53.2%)などが高い比率となりました。
一方,「不動産」(13.1%),「教育・研究」(22.0%),「公務」(23.4%),「その他の公共サービス」(32.7%)などが低い比率となりました。
平成12年から平成17年への中間投入率の変化をみると,「鉱業」(60.4%から56.7%に3.7ポイント低下),「その他の公共サービス」(34.8%から32.7%に2.1ポイント低下)など,10部門で中間投入率の低下がみられました。
一方,「石油・石炭製品」(61.8%から70.4%に8.6ポイント上昇),「化学製品」(71.0%から77.5%に6.5ポイント上昇),「輸送機械」(70.9%から76.2%に5.3ポイント上昇),「林業」(54.1%から59.1%に5.0ポイント上昇)が5ポイント以上上昇しました。
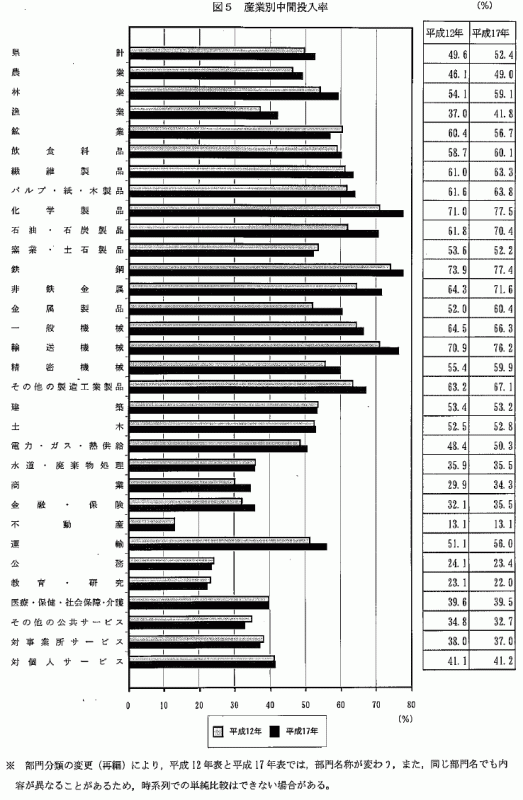
需要構造
総需要は35兆7,911億円で,内訳をみると,中間需要は36.9%,県内最終需要は31.8%,輸移出は31.3%となっており,平成12年に比べて県内最終需要構成比が低下し,中間需要,輸移出の構成比が上昇した。
平成17年の総需要は35兆7,911億円であり,平成12年の34兆5,425億円に比べて1兆2,486億円(伸び率3.6%)の増加となりました。(平成7年から平成12年の増加額2,936億円,伸び率0.9%)
総需要の内訳をみると,原材料や燃料として販売された中間需要が13兆2,077億円(構成比36.9%),消費・投資として販売された県内最終需要が11兆3,629億円(構成比31.8%),茨城県外へ販売された輸移出が11兆2,205億円(構成比31.3%)となりました。総需要の構成比を平成12年と比べると,中間需要は1.5ポイント上昇,県内最終需要が1.6ポイント低下,輸移出が0.1ポイント上昇しました。
産業別にみると,第1次産業,第2次産業は平成12年と比べて,中間需要,輸移出が増加し,県内最終需要が減少しました。一方,第3次産業は県内最終需要及び輸移出が増加し,中間需要が減少しました。
用語の解説
総需要
中間需要+最終需要
中間需要
各産業部門で生産された財及びサービスのうち,原材料や燃料として販売された額をいう。
最終需要
県内最終需要+輸移出
県内最終需要
県内で行われた消費,投資の合計額をいう。家計外消費支出,民間最終消費支出,一般政府最終消費支出,県内総固定資本形成及び在庫純増からなる。
輸移出
各産業部門で生産された財及びサービスのうち,県外の需要(県外からの旅行者等の県内における需要も含む)を賄うために販売した額をいう。
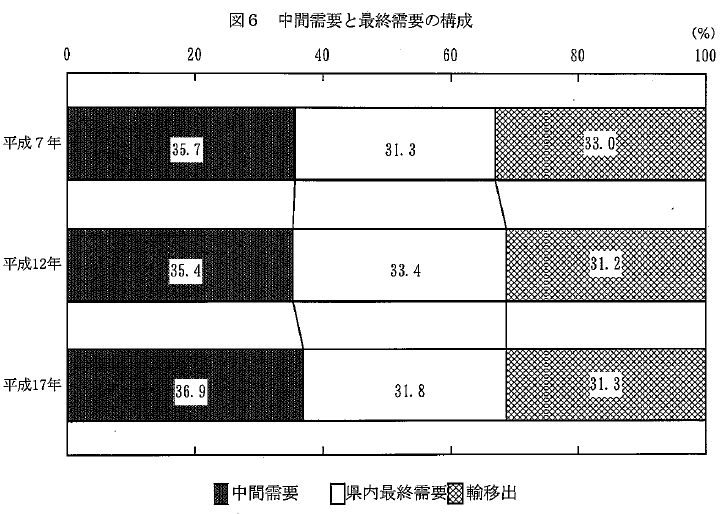
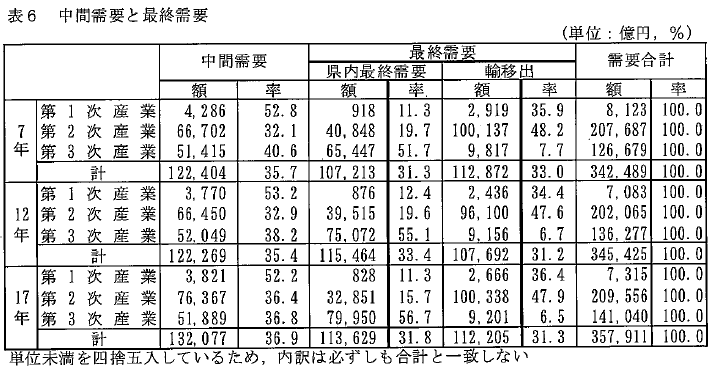
県際構造
1.輸移出・輸移入・県際収支
輸移出から輸移入を差し引いた県際収支は6,178億円の輸移出超過となり,平成12年と比較すると,県際収支は2,551億円減少した。
茨城県と県外との取引についてみると,輸移出の総額は11兆2,205億円,輸移入の総額は10兆6,027億円,輸移出から輸移入を差し引いた県際収支は6,178億円の輸移出超過となりました。平成12年と比較すると,県際収支は2,551億円減少(平成12年は8,729億円の輸移出超過)しました。
輸移出額を産業部門別(37部門)にみると,平成17年に最も輸移出額が多かった産業は「一般機械」で1兆4,248億円であり,次いで「飲食料品」1兆4,026億円,「化学製品」1兆2,594億円の順になっています。また,輸移入額は「商業」が9,888億円で最も多く,次いで「飲食料品」8,008億円,「化学製品」7,955億円の順になっています。
一方,県際収支をみると,輸移出超過額の大きな産業は,「一般機械」8,491億円,「飲食料品」6,018億円,「電気機械」4,777億円の順になっており,製造業16部門のうち11部門が輸移出超過になっています。また,輸移入超過額の大きな産業は「商業」8,395億円,「鉱業」6,058億円,「対事業所サービス」3,904億円の順になっており,第3次産業は「電力・ガス・熱供給」,「教育・研究」,「医療・保健・社会保障・介護」の3つ以外の部門は輸移入超過になっています。
用語の解説
輸移出
各産業部門で生産された財及びサービスのうち,県外の需要(県外からの旅行者等の県内における需要も含む)を賄うために販売した額をいう。
輸移入
県内の需要に対応するために,県外で生産された財及びサービスの購入額をいう。(県外への旅行者等が県外で購入する場合も含む)
県際収支
輸移出-輸移入
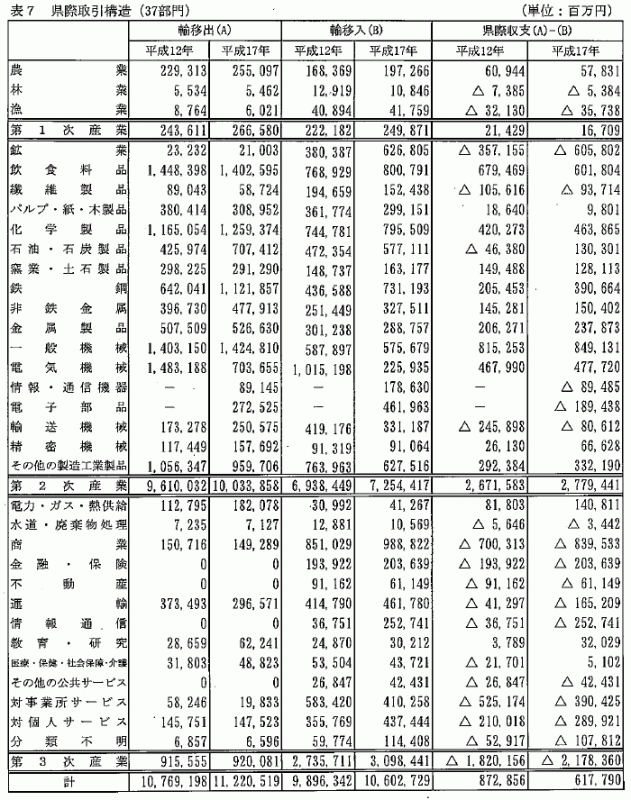
2.産業別県内自給率
平成17年の産業全体の県内自給率は56.8%であり,平成12年と比べて1.6ポイント低下した。
平成17年の産業全体の県内自給率は56.8%となり,平成12年と比べて1.6ポイント低下しました。
産業別(37部門)にみると,特に「鉱業」(0.8%),「繊維製品」(1.4%),「電子部品」(9.3%),「輸送機械」(9.4%),「精密機械」(7.0%)は10%未満の県内自給率になっています。
平成12年から平成17年への県内自給率の変化をみると,「化学製品」(29.7%から35.0%に5.3ポイント上昇)が5ポイント以上上昇しました。
一方,「その他の公共サービス」(69.6%から59.1%に10.5ポイント低下),「林業」(38.8%から30.4%に8.4ポイント低下),「農業」(56.1%から49.7%に6.5ポイント低下),「商業」(61.5%から55.4%に6.1ポイント低下),「対個人サービス」(71.8%から65.6%に6.1ポイント低下),「運輸」(66.1%から60.6%に5.6ポイント低下)が5ポイント以上低下しました。
用語の解説
県内自給率
県内需要に占める県内生産品の割合をいう。すべての県内需要を県内生産で賄う閉鎖経済であれば自給率は100%となる。なお,産業連関表の定義上,「建築」,「土木」,「公務」及び「事務用品」は自給率100%となっている。
県内自給率=(県内生産額-輸移出)÷県内需要
県内需要=中間需要+県内最終需要
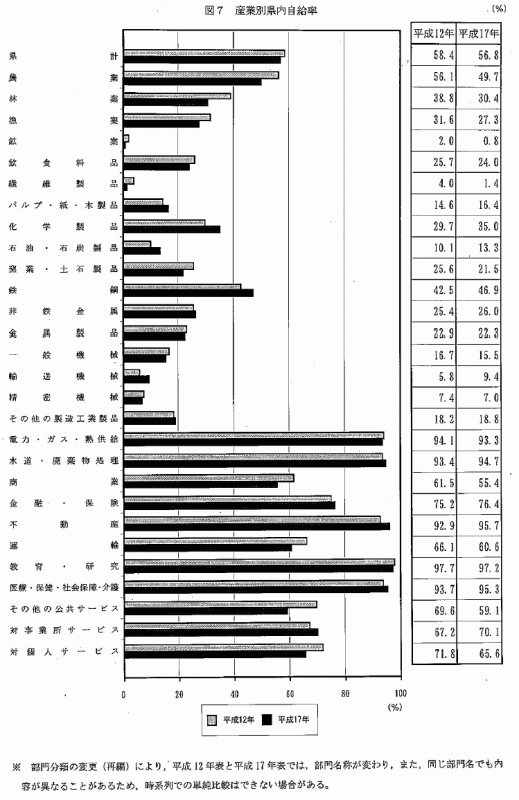
生産波及の大きさ
茨城県内における生産波及の大きい産業は,「鉄鋼」,「鉱業」,「化学製品」などであり,逆に生産波及の小さい産業は「石油・石炭製品」,「不動産」,「漁業」などである。
逆行列係数表により1単位当たりの最終需要に対する生産波及の大きさをみると,全産業平均で1.3109倍となり,平成12年の1.3110倍と比較して,ほぼ横ばいの△0.0001ポイントの低下となりました。
産業別(37部門)にみると,「鉄鋼」(1.5495倍),「鉱業」(1.4658倍),「化学製品」(1.4408倍)などが生産波及の大きい産業となっています。一方,「石油・石炭製品」(1.1144倍),「不動産」(1.1386倍),「漁業」(1.1778倍)などが生産波及の小さい産業となっています。
また,平成12年の生産波及の大きさと比較すると,上昇した産業は「鉄鋼」(0.0650ポイント),「金属製品」(0.0608ポイント),「その他の製造工業品」(0.0408ポイント)などが挙げられます。一方,低下した産業は「事務用品」(△0.0609ポイント),「対事業所サービス」(△0.0497ポイント),「鉱業」(△0.0396ポイント)などが挙げられます。
用語の解説
逆行列係数
ある産業に対して1単位の最終需要が発生した場合,各産業の生産が究極的にどれだけ必要になるかという,生産波及の大きさを示す係数。数学上の逆行列を求める方法で算出することからこのように呼ばれる。なお,本文中の生産波及の大きさは,逆行列係数表の列和(タテ方向の合計)を指している。例えば,農業の逆行列係数の列和は1.2830であるが,これは農業に1億円の最終需要が発生し,すべて県内生産で賄われた場合,農業を含む本県の産業全体に1.2830億円の生産が究極的に誘発されることを示している。
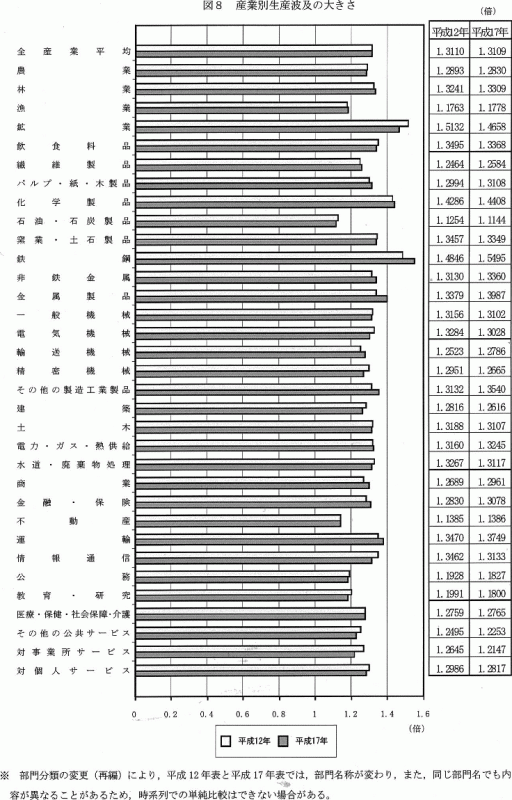
概要版報告書
- 概要版報告書はPDF形式です。
統計表
- 統計表はエクセル形式です。
- 統合大分類(13部門)(エクセル:111キロバイト)
- 統合中分類(37部門)(エクセル:239キロバイト)
- 統合小分類(108部門)(エクセル:951キロバイト)
- 部門分類表(エクセル:187キロバイト)
詳細版報告書
- 詳細版報告書はPDF形式です。
平成17年(2005年)茨城県産業連関表〔平成22年9月刊行〕
- 表紙・はじめに・目次(PDF:139キロバイト)(6頁)
- 第1部.解説編
- 第2部.計数編
- 部門分類及び部門別生産額表(PDF:481キロバイト)(10頁)
- 13部門表(PDF:633キロバイト)(14頁)
- 37部門表(PDF:1,540キロバイト)(32頁)
- 108部門表(PDF:3,925キロバイト)(52頁)
- <付録>用語の解説(PDF:340キロバイト)(6頁)
経済波及効果分析シート(平成28年8月30日掲載)
- 統計表はエクセル形式です。
- 経済波及効果分析シート(13部門)(エクセル:339キロバイト)
- 経済波及効果分析シート(37部門)(エクセル:838キロバイト)
- 経済波及効果分析シート(37部門-イベント用)(エクセル:1,160キロバイト)
過去の茨城県産業連関表
総務省統計局(リンク)