目的から探す
ホーム > 県政情報 > 県の概要 > いばらき統計情報ネットワーク > いばらき統計情報ネットワーク(統計課) > 分野別≪産業連関表≫ > 平成7年(1995年)茨城県産業連関表
ページ番号:12796
更新日:2015年4月1日
ここから本文です。
平成7年(1995年)茨城県産業連関表
目次
見たい項目をクリックして下さい。
- 概要〔平成12年3月31日公表〕
- 詳細版報告書(平成7年茨城県産業連関表)〔平成12年12月刊行〕
- 表紙・はじめに・目次(PDF:134キロバイト)
- 第1部.解説編
- 第2部.計数編
- 部門分類及び部門別生産額表(PDF:266キロバイト)(10頁)
- 13部門表(PDF:458キロバイト)(14頁)
- 32部門表(PDF:1,558キロバイト)(32頁)
- 93部門表(PDF:3,955キロバイト)(52頁)
- <付録>用語の解説(PDF:198キロバイト)(6頁)
平成7年(1995)茨城県産業連関表の概要
1.はじめに
平成7年茨城県産業連関表は,茨城県内における1年間(平成7暦年)の経済のすがたをとりまとめたもので,産業間において取り引きされた全ての財貨・サービスについて,生産活動を通じた産業間の相互依存関係を明示する形で,これらの財貨・サービスの経常的な取引を行列(マトリクス)形式で,体系的に一つの完結した表にまとめたものです。
産業連関表を作成することによって,詳細な生産活動単位ごとの県経済の規模や経済活動相互の取引状況を明らかにすることができます。
本県においては,昭和55年表を公表以来,5年ごとに公表することにしており,平成2年表に続き4回目の表として,作成いたしました。
今回の公表部門は,13部門,32部門,93部門の3表です。
今回公表する内容は,平成7年における本県の経済構造分析のために必要な基礎的数値と,これを活用した県経済の全般的な構造解析となっております。
2.概要
図1は,平成7年茨城県産業連関表を図式化したもので,図をヨコ(行)方向にみるとその産業の生産物が原材料としてどの産業にいくら売れたか(=中間需要),また,製品としてどれだけ家計等で消費したか,企業等が投資したか(=最終需要)の販路構成がわかります。
また,タテ(列)方向に沿ってみると,その産業が,生産のためにどの産業(各行部門)からどれだけの生産物を購入したか(=中間投入),生産のために労働力をどれだけ必要としたか等(=粗付加価値)の費用構成が読みとれます。
ヨコ方向にみると,本県における財貨・サービスの総需要は,34兆2,489億円で,このうち県内産業の生産に必要な原材料として使用する財貨・サービスの中間需要は,12兆2,404億円で,残る22兆85億円は,民間最終消費支出,県内総固定資本形成等の県内最終需要10兆7,213億円と輸移出11兆2,872億円に向けられています。この総需要に対して財貨・サービスを供給するために,県内で24兆6,306億円を生産し,残る9兆6,182億円を県外から輸移出しています。
また,タテ方向に県内生産額の内訳をみると,原材料等として12兆2,404億円を中間投入し,新たに12兆3,903億円の粗付加価値を生み,雇用者所得,営業余剰,資本消耗引当等に分配されています。
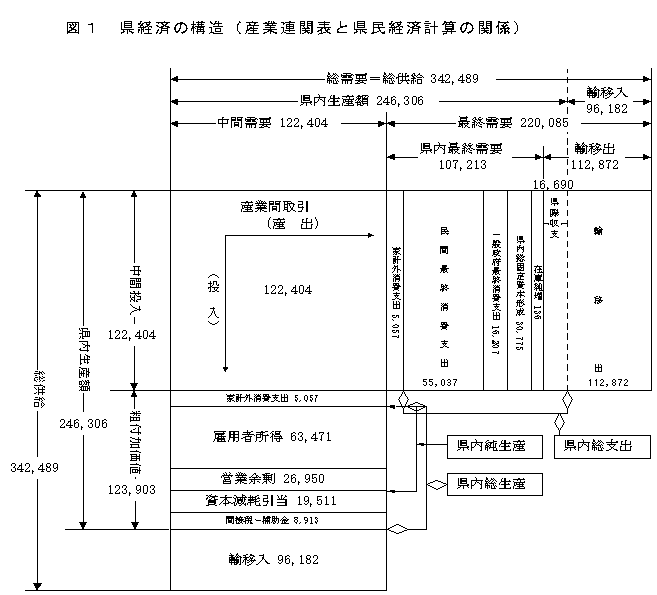
3.構造分析
(1)県内生産額
-県内生産額は,24兆6,306億円-(平成2年に比べて10.6%増)
県内生産額は24兆6,306億円で,平成2年の22兆2,647億円に比べて,2兆3,659億円(伸び率10.6%)増加しましたが,平成2年の対昭和60年増加率(25.6%)の半分以下の伸び率にとどまりました。単純に5年で除すと1年平均約2.1%の増加率になります。
全国の伸び率(平成7年/平成2年)は7.4%ですから,全国の伸び率を3.2ポイント上回ることになります。
また,産業別にみると,第2次産業が13兆9,200億円と最も多く,次いで第3次産業10兆1,340億円,第1次産業5,767億円となっています。
県内生産額に占める産業別割合は,第1次産業で0.4ポイント低下し2.3%,第2次産業で5.8ポイント低下し56.5%,第3次産業で6.1ポイント上昇し41.1%となり,その割合を高めています。
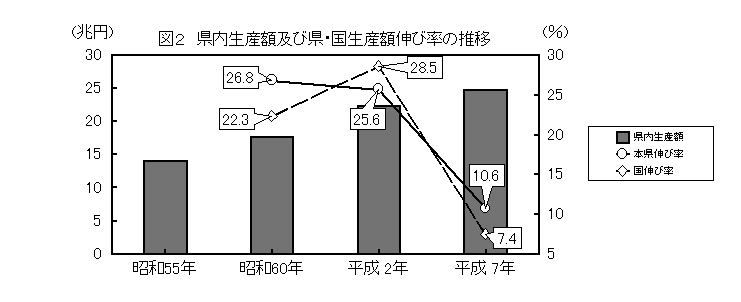
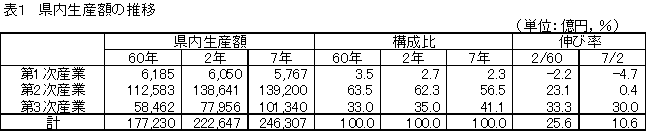
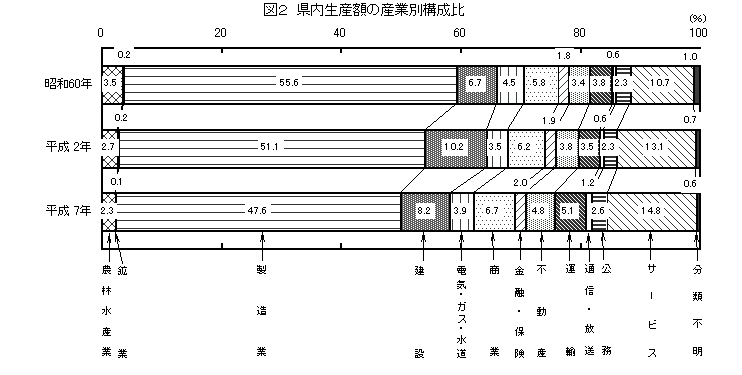
(2)投入構造(費用構成)
-粗付加価値は,12兆4,179億円-(平成2年に比べて18.7%増)
県内生産額24兆6,306億円の費用構成をみると,生産に必要な原材料等の中間投入は,12兆2,404億円で,平成2年に比べて4,329億円(伸び率3.7%)増加しています。一方,生産活動により雇用者所得,営業余剰,資本消耗引当等に分配される粗付加価値は,12兆3,903億円で,平成2年と比べて1兆9,330億円(同18.5%)の大幅な増加となっています。
これは,本県のおける産業の高次化が順調に進んだ結果と考えられます。
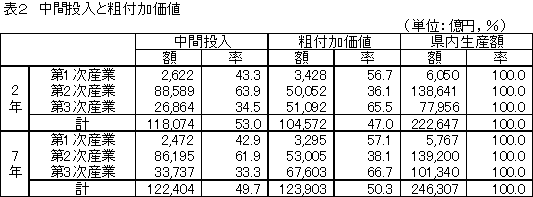
(3)需要構造(販路構成)
-総需要は,34兆2,489億円-(平成2年に比べて9.8%増)
財貨・サービスの需要面をみると,総需要は34兆2,489億円で,平成2年の31兆1,938億円に比べ3兆551億円(伸び率9.8%)増加しています。
需要部門別にみると,県内の生産活動による中間需要が12兆2,404億円,民間最終消費支出が5兆5,037億円,県内総固定資本形成が3兆775億円等の県内最終需要は10兆7,213億円となっています。また,県外需要である輸移出は,11兆2,872億円になっています。
これを平成2年と比べると,中間需要は4,329億円(伸び率3.7%),県内最終需要は1兆4,984億円(同16.2%),輸移出は1兆1,237億円(伸び率11.1%)それぞれ増加しています。
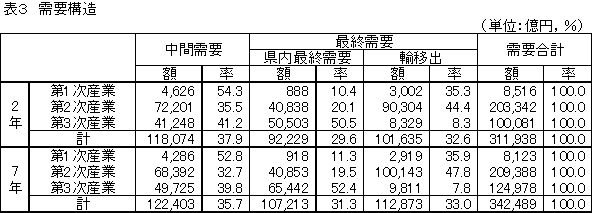
用語の意味
- 総需要額=中間需要額+最終支出額
- 最終需要:県内最終需要と輸移出からなる。
- 県内最終需要:家計外消費支出,民間最終消費支出,一般政府最終消費支出,県内最終総固定資本形成,在庫純増からなる。
- 輸移出:茨城県内で生産された財貨・サービスを茨城県外に販売すること。
(4)生産波及効果
-全産業平均の生産波及効果は,1.31倍-(平成2年に比べて0.2ポイント増)
産業連関表は,これまでみてきたように,直接読みとれるデータとして貴重なものであるが,この他に生産波及効果を計測する道具として重要な意味をもっています。
産業連関表を活用した分析事例
- 各種イベント開催の経済波及効果
- 公共投資等の経済波及効果
- 工場立地による経済波及効果
など
1単位の需要増加に対する生産波及は,全産業平均で1.31倍となり,平成2年の1.29倍を0.02ポイント上回る結果となりました。
生産波及の大きさを,各産業部門ごとにみると,鉱業(1.51),分類不明(1.41),運輸(1.37),電力・ガス・水道(1.37),製造業(1.32)が大きな部門になっています。
また,各産業ごとに平成2年と生産波及の大きさを比較すると,増加した産業が鉱業の0.15ポイント,通信・放送の0.12ポイント,電力・ガス・水道の0.09ポイントなどがあげられます。逆に減少した産業をみると,運輸の△0.05ポイント,不動産の△0.04ポイント,製造業の△0.03ポイントなどになっています。
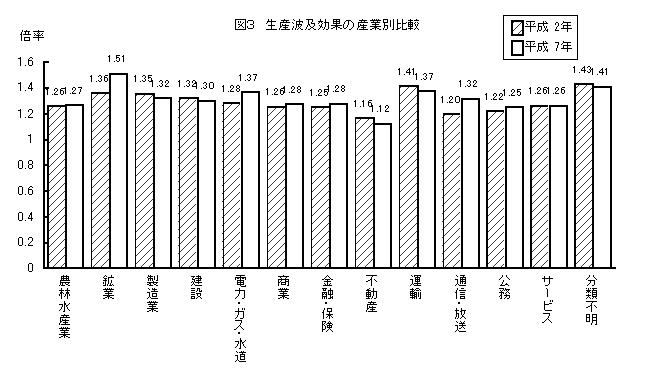
平成7年(1995)茨城県産業連関表のダウンロード
- 産業連関表はエクセル形式です。
茨城県産業連関表
総務省(リンク)