目的から探す
ホーム > 県政情報 > 県の概要 > いばらき統計情報ネットワーク > いばらき統計情報ネットワーク(統計課) > 分野別≪住宅・土地≫ > 令和5年住宅・土地統計調査の結果の概要
ページ番号:70296
更新日:2025年3月28日
ここから本文です。
令和5年住宅・土地統計調査の結果の概要
令和7年2月18日更新
敷地面積、増改築・改修工事等の状況、耐震改修工事等の状況、高齢者等のための設備工事の状況、高齢者が住む住宅のバリアフリー化率、住環境を追加
令和7年3月28日更新
世帯が所有している土地の状況を追加
目次
調査の概要
1.調査の目的
住宅・土地統計調査は、我が国における住宅及び住宅以外で人が居住する建物に関する実態並びに現住居以外の住宅及び土地の保有状況その他の住宅等に居住している世帯に関する実態を調査し、その現状と推移を全国及び地域別に明らかにすることにより、住生活関連諸施策の基礎資料を得ることを目的としている。調査は昭和23年以来5年ごとに実施しており、令和5年住宅・土地統計調査はその16回目に当たる。
2.調査の時期
調査は、令和5年10月1日午前零時現在で実施した。
3.調査の地域
全国の令和2年国勢調査の調査区の中から全国平均約5分の1の調査区を抽出し、これらの調査区において令和5年2月1日現在により設定した単位区のうち、約20万単位区について調査した。
茨城県では5,225単位区、約8万8千住戸・世帯を対象として調査した。
4.調査の対象
調査期日において調査単位区内から抽出した住宅及び住宅以外で人が居住する建物並びにこれらに居住している世帯(1調査単位区当たり17住戸、計約8万8千住戸・世帯)を対象とした。ただし、次に掲げる施設及びこれらに居住する世帯は、調査の対象から除外した。
(1)外国の大使館、公使館、領事館その他の外国政府の公的機関や国際機関が管理している施設及び外交官・領事官やその随員(家族を含む。)が居住している住宅
(2)皇室用財産である施設
(3)拘置所、刑務所、少年刑務所、少年院、年鑑別所、婦人補導院及び入国者収容所
(4)自衛隊の営舎その他の施設
(5)在日米軍用施設
5.調査事項
世帯に配布する調査票甲及び乙並びに調査員が記入する建物調査票により、次に掲げる事項を調査した。
【調査票甲】
(1)世帯に関する事項
ア.世帯主又は世帯の代表者の氏名
イ.構成
ウ.同居世帯に関する事項
エ.年間収入
(2)家計を主に支える世帯員又は世帯主に関する事項
ア.従業上の地位
イ.通勤時間
ウ.子の住んでいる場所
エ.現住居に入居した時期
オ.前住居に関する事項
(3)住宅に関する事項
ア.居住室の数及び広さ
イ.所有関係に関する事項
ウ.家賃又は間代等に関する事項
エ.構造
オ.床面積
カ.建築時期
キ.設備に関する事項
ク.建て替え等に関する事項
ケ.増改築及び改修工事に関する事項
コ.耐震に関する事項
(4)現住居の敷地に関する事項
ア.敷地の所有関係に関する事項
イ.敷地面積
ウ.取得方法・取得時期等
(5)現住居以外の住宅に関する事項
ア.所有関係に関する事項
イ.利用に関する事項
(6)現住居以外の土地に関する事項
ア.所有関係に関する事項
イ.利用に関する事項
【調査票乙】
上記【調査票甲】(1)~(6)に、以下の事項を加えて調査した。
(3)住宅に関する事項
サ.現住居の名義
(4)現住居の敷地に関する事項
エ.所有地の名義
(5)現住居以外の住宅に関する事項
ウ.所在地
エ.建て方
オ.取得方法
カ.建築時期
キ.居住世帯のない期間
(6)現住居以外の土地に関する事項
ウ.所在地
エ.面積に関する事項
オ.取得方法
カ.取得時期
【建物調査票】
(1)住宅に関する事項
ア.世帯の存しない住宅の種別
イ.種類
(2)建物に関する事項
ア.建て方
イ.世帯の存しない建物の構造
ウ.腐朽・破損の有無
エ.建物全体の階数
オ.敷地に接している道路の幅員
カ.建物内総住宅数
キ.設備に関する事項
ク.住宅以外で人が居住する建物の種類
6.調査の方法
調査票甲・乙は、調査員、調査員の事務を一部行う指導員及び調査員事務を受託した事業者が、調査世帯に調査書類を配布し、調査世帯が、インターネットにより回答する方法、記入した調査票を調査員等に提出する方法又は郵送により提出する方法により行った。また、建物調査票は、調査員等が建物の外観を確認したり、世帯や建物の管理者に確認するなどして作成した。
7.結果の公表
結果は、住宅数概数集計、住宅及び世帯に関する基本集計、住宅の構造等に関する集計及び土地集計から成り、インターネットへの掲載、報告書の刊行などにより公表する。
(注)市及び人口1万5千人以上の町村について、結果表章(人口は令和2年国勢調査時点)
8.利用上の注意
(1)本文及び図表の数値は、表章単位未満の位で四捨五入しているため、総数と内訳の合計は必ずしも一致しない。
(2)「-」は、該当数値がないもの、又は数字が得られないものを示す。
調査結果の概要
1.総住宅数と総世帯数
総住宅数は139万900戸、2018年から4.7%の増加となり、過去最多
1世帯当たりの住宅数は、1.16戸となった
2023年10月1日現在における茨城県の総住宅数は139万900戸で、2018年と比べ4.7%(6万2,000戸)増加、総世帯数は、119万9,500世帯で、2018年と比べ、5.7%(6万4,700世帯)の増加となっている。
1世帯当たりの住宅数について、1963年までは総世帯数が総住宅数を上回っていたが、1968年に逆転し、その後は総住宅数が総世帯数を上回っており、2023年は1.16戸となっている。<図1、表1>
〈全国〉
- 総住宅数は6504万7千戸、2018年から4.2%の増加となり、過去最多
- 1世帯当たりの住宅数は1.16戸と、2013年以降は同水準で推移
図1.総住宅数、総世帯数及び1世帯当たり住宅数の推移-茨城県(1958年~2023年)
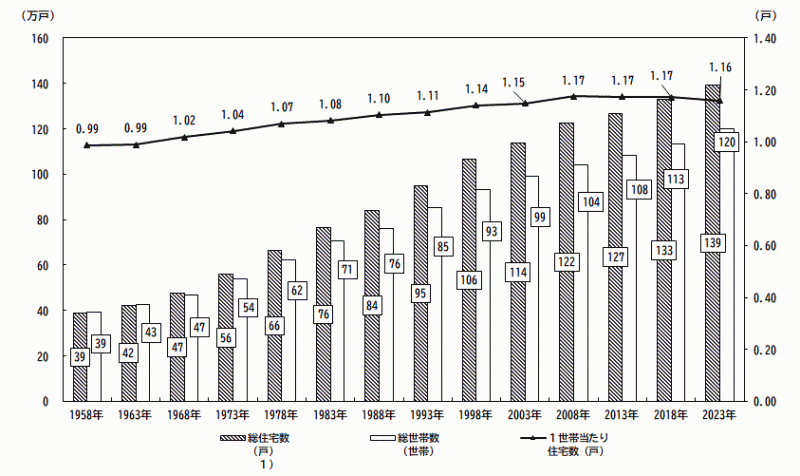
表1.総住宅数、総世帯数及び1世帯当たり住宅数の推移-茨城県(1958年~2023年)
| 年次 | 実数 | 5年間の増減数 | 5年間の増減率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総住宅数 (戸) 1) |
総世帯数 (世帯) |
1世帯当たり 住宅数(戸) |
総住宅数 (戸) |
総世帯数 (世帯) |
総住宅数 | 総世帯数 | |
| 1958年 | 388,000 | 393,000 | 0.99 | - | - | - | - |
| 1963年 | 423,000 | 428,000 | 0.99 | 35,000 | 35,000 | 9.0 | 8.9 |
| 1968年 | 474,470 | 466,160 | 1.02 | 51,470 | 38,160 | 12.2 | 8.9 |
| 1973年 | 560,300 | 537,400 | 1.04 | 85,830 | 71,240 | 18.1 | 15.3 |
| 1978年 | 664,000 | 620,600 | 1.07 | 103,700 | 83,200 | 18.5 | 15.5 |
| 1983年 | 763,800 | 705,300 | 1.08 | 99,800 | 84,700 | 15.0 | 13.6 |
| 1988年 | 842,200 | 762,700 | 1.10 | 78,400 | 57,400 | 10.3 | 8.1 |
| 1993年 | 949,300 | 852,500 | 1.11 | 107,100 | 89,800 | 12.7 | 11.8 |
| 1998年 | 1,064,800 | 933,400 | 1.14 | 115,500 | 80,900 | 12.2 | 9.5 |
| 2003年 | 1,135,900 | 989,300 | 1.15 | 71,100 | 55,900 | 6.7 | 6.0 |
| 2008年 | 1,223,800 | 1,041,700 | 1.17 | 87,900 | 52,400 | 7.7 | 5.3 |
| 2013年 | 1,268,200 | 1,081,200 | 1.17 | 44,400 | 39,500 | 3.6 | 3.8 |
| 2018年 | 1,328,900 | 1,134,800 | 1.17 | 60,700 | 53,600 | 4.8 | 5.0 |
| 2023年 | 1,390,900 | 1,199,500 | 1.16 | 62,000 | 64,700 | 4.7 | 5.7 |
1)居住世帯なしの住宅を含む。
2.空き家
空き家数は19万6,200戸、空き家率は14.1%と2018年よりも減少
賃貸・売却用や二次的住宅(別荘など)を除く空き家が1万5,000戸の増加
総住宅数のうち、空き家は19万6,200戸と、2018年(19万7,200戸)と比べ、1,000戸減少し、総住宅数に占める空き家の割合(空き家率)は14.1%と、2018年(14.8%)から0.7ポイント減少した。
空き家数のうち、「賃貸・売却用及び二次的住宅を除く空き家」は9万3,200戸と、2018年と比べ、1万5,000戸の増加となっており、総住宅数に占める割合は6.7%となっている。
〈図2-1・表2-1〉
〈全国〉
- 空き家数は900万2千戸と過去最多、空き家率も13.8%と過去最高
- 賃貸・売却用や二次的住宅(別荘など)を除く空き家が36万9千戸の増加
図2-1.空き家数及び空き家率の推移-茨城県(1988年~2023年)
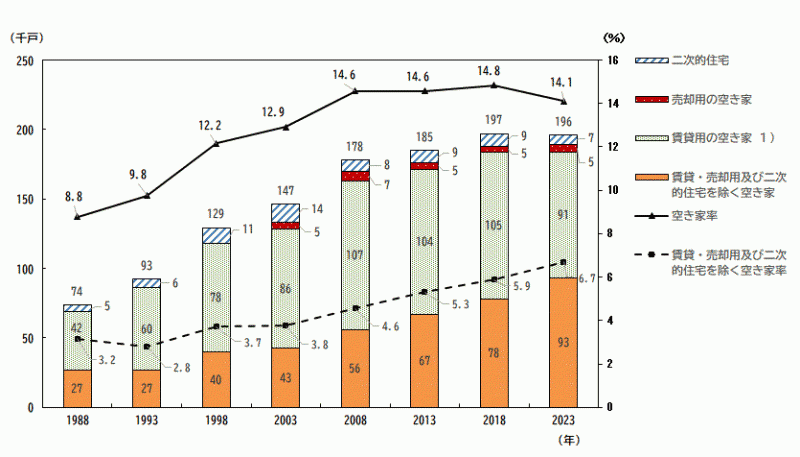
1)1988年から1998年までは、「賃貸用の空き家」に「売却用の空き家」を含む。
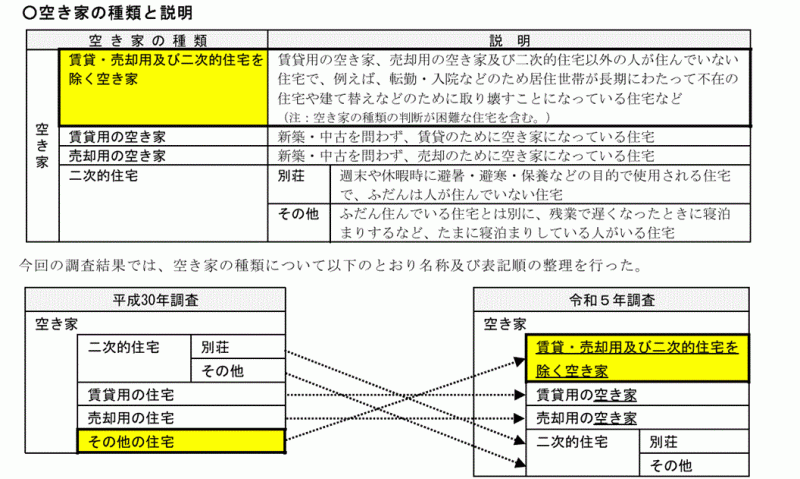
表2-1.居住世帯の有無別住宅数の推移-茨城県(1993年〜2023年)
| 年次 | 総数 | 居住世帯あり | 居住世帯なし | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 同居世帯 あり |
総数 | 一時 現在者 のみ |
空き家 | 建設中 | ||||||
| 総数 |
賃貸・売却用 |
賃貸用の 空き家 |
売却用の 空き家 |
二次的住宅 | |||||||
| 実数(戸) | |||||||||||
|
1993年(平成5年)
|
949,300 | 846,900 | 2,400 | 102,400 | 5,100 | 92,600 | 26,700 | 59,700※ | - | 6,200 | 4,600 |
|
1998年(平成10年)
|
1,064,800 | 926,900 | 3,300 | 137,900 | 5,500 | 129,400 | 39,700 | 78,400※ | - | 11,300 | 3,000 |
|
2003年(平成15年)
|
1,135,900 | 983,000 | 3,700 | 152,900 | 4,100 | 146,700 | 42,700 | 85,700 | 4,700 | 13,500 | 2,100 |
|
2008年(平成20年)
|
1,223,800 | 1,036,200 | 3,700 | 187,600 | 7,200 | 178,400 | 55,900 | 107,200 | 6,900 | 8,400 | 2,000 |
|
2013年(平成25年)
|
1,268,200 | 1,076,100 | 3,400 | 192,100 | 5,500 | 184,700 | 67,200 | 104,100 | 4,900 | 8,500 | 1,900 |
|
2018年(平成30年)
|
1,328,900 | 1,126,600 | 5,600 | 202,300 | 3,500 | 197,200 | 78,200 | 105,400 | 4,500 | 9,000 | 1,500 |
|
2023年(令和5年)
|
1,390,900 | 1,187,400 | 7,600 | 203,500 | 3,900 | 196,200 | 93,200 | 90,700 | 5,400 | 6,800 | 3,400 |
| 割合-1(%) | |||||||||||
|
1993年(平成5年)
|
100.0 | 89.2 | 0.3 | 10.8 | 0.5 | 9.8 | 2.8 | 6.3※ | - | 0.7 | 0.5 |
|
1998年(平成10年)
|
100.0 | 87.0 | 0.3 | 13.0 | 0.5 | 12.2 | 3.7 | 7.4※ | - | 1.1 | 0.3 |
|
2003年(平成15年)
|
100.0 | 86.5 | 0.3 | 13.5 | 0.4 | 12.9 | 3.8 | 7.5 | 0.4 | 1.2 | 0.2 |
|
2008年(平成20年)
|
100.0 | 84.7 | 0.3 | 15.3 | 0.6 | 14.6 | 4.6 | 8.8 | 0.6 | 0.7 | 0.2 |
|
2013年(平成25年)
|
100.0 | 84.9 | 0.3 | 15.1 | 0.4 | 14.6 | 5.3 | 8.2 | 0.4 | 0.7 | 0.1 |
|
2018年(平成30年)
|
100.0 | 84.8 | 0.4 | 15.2 | 0.3 | 14.8 | 5.9 | 7.9 | 0.3 | 0.7 | 0.1 |
|
2023年(令和5年)
|
100.0 | 85.4 | 0.5 | 14.6 | 0.3 | 14.1 | 6.7 | 6.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 |
| 割合-2(%) | |||||||||||
|
1993年(平成5年)
|
- | - | - | - | - | 100.0 | 28.8 | 64.5※ | - | 6.7 | - |
|
1998年(平成10年)
|
- | - | - | - | - | 100.0 | 30.7 | 60.6※ | - | 8.7 | - |
|
2003年(平成15年)
|
- | - | - | - | - | 100.0 | 29.1 | 58.4 | 3.2 | 9.2 | - |
|
2008年(平成20年)
|
- | - | - | - | - | 100.0 | 31.3 | 60.1 | 3.9 | 4.7 | - |
|
2013年(平成25年)
|
- | - | - | - | - | 100.0 | 36.4 | 56.4 | 2.7 | 4.6 | - |
|
2018年(平成30年)
|
- | - | - | - | - | 100.0 | 39.7 | 53.4 | 2.3 | 4.6 | - |
|
2023年(令和5年)
|
- | - | - | - | - | 100.0 | 47.5 | 46.2 | 2.8 | 3.5 | - |
| 増減数(戸) | |||||||||||
|
1993年〜1998年
|
115,500 | 80,000 | 900 | 35,500 | 400 | 36,800 | 13,000 | 18,700※ | - | 5,100 | -1,600 |
|
1998年〜2003年
|
71,100 | 56,100 | 400 | 15,000 | -1,400 | 17,300 | 3,000 | 7,300※ | - | 2,200 | -900 |
|
2003年〜2008年
|
87,900 | 53,200 | 0 | 34,700 | 3,100 | 31,700 | 13,200 | 21,500 | 2,200 | -5,100 | -100 |
|
2008年〜2013年
|
44,400 | 39,900 | -300 | 4,500 | -1,700 | 6,300 | 11,300 | -3,100 | -2,000 | 100 | -100 |
|
2013年〜2018年
|
60,700 | 50,500 | 2,200 | 10,200 | -2,000 | 12,500 | 11,000 | 1,300 | -400 | 500 | -400 |
|
2018年〜2023年
|
62,000 | 60,800 | 2,000 | 1,200 | 400 | -1,000 | 15,000 | -14,700 | 900 | -2,200 | 1,900 |
| 増減率(%) | |||||||||||
|
1993年〜1998年
|
12.2 | 9.4 | 37.5 | 34.7 | 7.8 | 39.7 | 48.7 | 31.3※ | - | 82.3 | -34.8 |
|
1998年〜2003年
|
6.7 | 6.1 | 12.1 | 10.9 | -25.5 | 13.4 | 7.6 | 9.3※ | - | 19.5 | -30.0 |
|
2003年〜2008年
|
7.7 | 5.4 | 0.0 | 22.7 | 75.6 | 21.6 | 30.9 | 25.1 | 46.8 | -37.8 | -4.8 |
|
2008年〜2013年
|
3.6 | 3.9 | -8.1 | 2.4 | -23.6 | 3.5 | 20.2 | -2.9 | -29.0 | 1.2 | -5.0 |
|
2013年〜2018年
|
4.8 | 4.7 | 64.7 | 5.3 | -36.4 | 6.8 | 16.4 | 1.2 | -8.2 | 5.9 | -21.1 |
|
2018年〜2023年
|
4.7 | 5.4 | 35.7 | 0.6 | 11.4 | -0.5 | 19.2 | -13.9 | 20.0 | -24.4 | 126.7 |
注1)※は、「賃貸用の空き家」に「売却用の空き家」を含む。
注2)割合-1は、総住宅数に占める割合
割合-2は、空き家の総数に占める割合
空き家のうち、一戸建が9万8,800戸(50.4%)、共同住宅が8万9,900戸(45.8%)
一戸建の空き家の約8割が賃貸・売却用や二次的住宅(別荘など)を除く空き家
共同住宅の空き家の約8割が賃貸用の空き家
空き家を建て方別にみると、一戸建が9万8,800戸(空き家総数に占める割合50.4%)、共同住宅が8万9,900戸(同45.8%)などとなっている。
また、一戸建及び共同住宅における空き家の種類別割合をみると、一戸建は「賃貸・売却用及び二次的住宅を除く空き家」が最も多く81.2%(8万200戸)となっており、共同住宅は「賃貸用の空き家」が最も多く85.1%(7万6,500戸)となっている。<表2-2、図2-2>
〈全国〉
- 空き家のうち、一戸建が352万3千戸(39.1%)、共同住宅が502万9千戸(55.9%)
- 一戸建の空き家の約8割が賃貸・売却用や二次的住宅(別荘など)を除く空き家
- 共同住宅の空き家の約8割が賃貸用の空き家
表2-2.住宅の建て方、空き家の種類別空き家数及び割合-茨城県(2023年)
| 空き家の種類 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 総数 |
賃貸・売却用及び 二次的住宅を除く空き家 |
賃貸用の 空き家 |
売却用の 空き家 |
二次的住宅 | |
| 実数 | |||||
|
総数
|
196,200 | 93,200 | 90,700 | 5,400 | 6,900 |
|
一戸建
|
98,800 | 80,200 | 8,600 | 4,000 | 6,000 |
|
長屋建
|
6,800 | 1,200 | 5,500 | 0 | 100 |
|
共同住宅
|
89,900 | 11,300 | 76,500 | 1,300 | 800 |
|
その他
|
700 | 500 | 100 | 0 | 100 |
| 割合-1(%)1) | |||||
|
総数
|
100.0 | 47.5 | 46.2 | 2.8 | 3.5 |
|
一戸建
|
50.4 | 40.9 | 4.4 | 2.0 | 3.1 |
|
長屋建
|
3.5 | 0.6 | 2.8 | 0.0 | 0.1 |
|
共同住宅
|
45.8 | 5.8 | 39.0 | 0.7 | 0.4 |
|
その他
|
0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
| 割合-2(%)2) | |||||
|
総数
|
100.0 | 47.5 | 46.2 | 2.8 | 3.5 |
|
一戸建
|
100.0 | 81.2 | 8.7 | 4.0 | 6.1 |
|
長屋建
|
100.0 | 17.6 | 80.9 | 0.0 | 1.5 |
|
共同住宅
|
100.0 | 12.6 | 85.1 | 1.4 | 0.9 |
|
その他
|
100.0 | 71.4 | 14.3 | 0.0 | 14.3 |
1)空き家の総数に占める割合
2)住宅の建て方別空き家の総数に占める割合
図2-2.住宅の建て方(一戸建及び共同住宅)、空き家の種類別割合-茨城県(2023年)
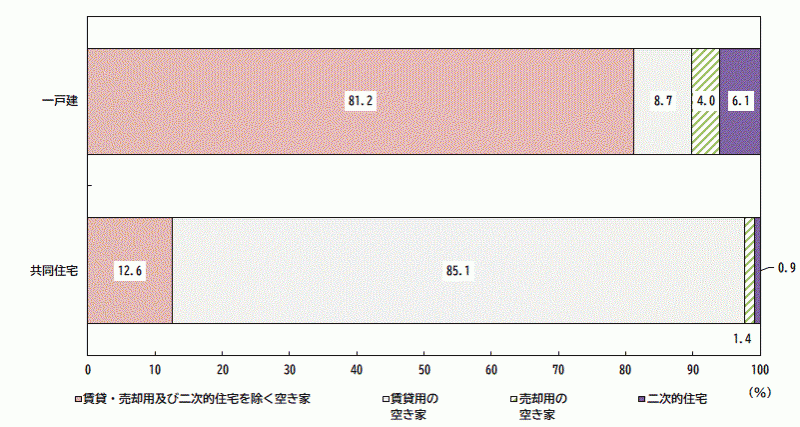
3.住宅の建て方
住宅を建て方別にみると、一戸建が83万2,100戸(70.1%)、共同住宅が32万7,700戸(27.6%)、このうち、共同住宅はこの30年間で約2.1倍の増加
居住世帯のある住宅(以下「住宅」という。)を建て方別にみると、一戸建が83万2,100戸、長屋建が2万5,000戸、共同住宅が32万7,700戸となっており、2018年と比べ、一戸建が2.1%の増加、長屋建が21.6%の減少、共同住宅が17.6%の増加となっている。このうち、共同住宅は1993年から2023年までの30年間で約2.1倍増加しており、住宅全体に占める共同住宅の割合は27.6%で過去最高となっている。<図3-1、表3>
〈全国〉
- 住宅を建て方別にみると、一戸建が2931万9千戸(52.7%)、共同住宅が2496万8千戸(44.9%)、このうち、共同住宅はこの30年間で約1.8倍の増加
図3-1.住宅の建て方別住宅数の推移-茨城県(1993年~2023年)
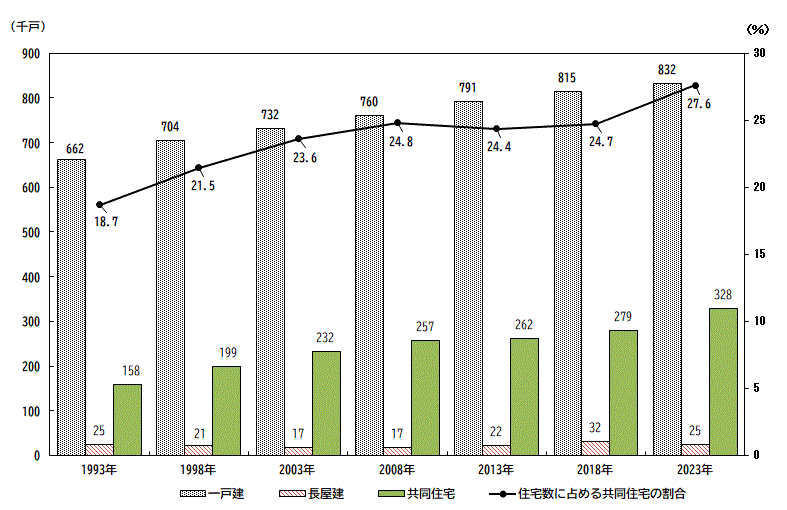
1〜2階建の共同住宅の割合が増加し、3階建以上の共同住宅の割合は減少
共同住宅について建物全体の階数別にみると、「1~2階建」が18万1,100戸(共同住宅の総数に占める割合55.3%)、「3~5階建」は10万700戸(同30.7%)、「6~10階建」は2万5,600戸(同7.8%)、「11~14階建」は1万2,900戸(同3.9%)、「15階建以上」は7,200戸(同2.2%)となっている。
2018年と比べると、2階建以下の共同住宅の割合は増加している一方、3階建以上の共同住宅の割合は減少している。<図3-2、表3>
〈全国〉
- 6階建以上の共同住宅の割合が増加しており、共同住宅の高層化が進行
図3-2.共同住宅の階数別割合の推移-茨城県(1993年〜2023年)
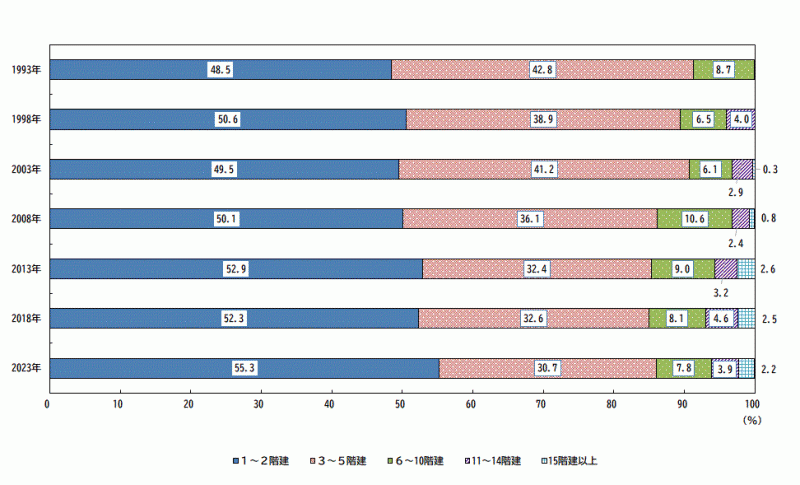
表3.住宅の建て方、階数別住宅数の推移-茨城県(1993年〜2023年)
| 年次 | 総数 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | その他 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 1〜2階建 | 3〜5階建 | 6〜10階建 | 11〜14階建 | 15階建以上 | |||||
| 実数(戸) | ||||||||||
|
1993年(平成5年)
|
846,900 | 662,300 | 24,700 | 158,300 | 76,700 | 67,800 | 13,700 | - | - | 1,600 |
|
1998年(平成10年)
|
926,900 | 704,000 | 21,200 | 199,000 | 100,600 | 77,400 | 13,000 | 8,000 | - | 2,800 |
|
2003年(平成15年)
|
983,000 | 731,700 | 17,200 | 232,000 | 114,900 | 95,500 | 14,100 | 6,800 | 700 | 2,100 |
|
2008年(平成20年)
|
1,036,200 | 759,800 | 17,300 | 257,000 | 128,800 | 92,700 | 27,200 | 6,200 | 2,000 | 2,100 |
|
2013年(平成25年)
|
1,076,100 | 791,300 | 21,500 | 262,100 | 138,600 | 84,900 | 23,600 | 8,300 | 6,700 | 1,200 |
|
2018年(平成30年)
|
1,126,600 | 814,800 | 31,900 | 278,600 | 145,800 | 90,800 | 22,500 | 12,700 | 6,900 | 1,300 |
|
2023年(令和5年)
|
1,187,400 | 832,100 | 25,000 | 327,700 | 181,100 | 100,700 | 25,600 | 12,900 | 7,200 | 2,700 |
| 割合-1(%)1) | ||||||||||
|
1993年(平成5年)
|
100.0 | 78.2 | 2.9 | 18.7 | 9.1 | 8.0 | 1.6 | - | - | 0.2 |
|
1998年(平成10年)
|
100.0 | 76.0 | 2.3 | 21.5 | 10.9 | 8.4 | 1.4 | 0.9 | - | 0.3 |
|
2003年(平成15年)
|
100.0 | 74.4 | 1.7 | 23.6 | 11.7 | 9.7 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.2 |
|
2008年(平成20年)
|
100.0 | 73.3 | 1.7 | 24.8 | 12.4 | 8.9 | 2.6 | 0.6 | 0.2 | 0.2 |
|
2013年(平成25年)
|
100.0 | 73.5 | 2.0 | 24.4 | 12.9 | 7.9 | 2.2 | 0.8 | 0.6 | 0.1 |
|
2018年(平成30年)
|
100.0 | 72.3 | 2.8 | 24.7 | 12.9 | 8.1 | 2.0 | 1.1 | 0.6 | 0.1 |
|
2023年(令和5年)
|
100.0 | 70.1 | 2.1 | 27.6 | 15.3 | 8.5 | 2.2 | 1.1 | 0.6 | 0.2 |
| 割合-2(%)2) | ||||||||||
|
1993年(平成5年)
|
- | - | - | 100.0 | 48.5 | 42.8 | 8.7 | - | - | - |
|
1998年(平成10年)
|
- | - | - | 100.0 | 50.6 | 38.9 | 6.5 | 4.0 | - | - |
|
2003年(平成15年)
|
- | - | - | 100.0 | 49.5 | 41.2 | 6.1 | 2.9 | 0.3 | - |
|
2008年(平成20年)
|
- | - | - | 100.0 | 50.1 | 36.1 | 10.6 | 2.4 | 0.8 | - |
|
2013年(平成25年)
|
- | - | - | 100.0 | 52.9 | 32.4 | 9.0 | 3.2 | 2.6 | - |
|
2018年(平成30年)
|
- | - | - | 100.0 | 52.3 | 32.6 | 8.1 | 4.6 | 2.5 | - |
|
2023年(令和5年)
|
- | - | - | 100.0 | 55.3 | 30.7 | 7.8 | 3.9 | 2.2 | - |
| 増減率(%) | ||||||||||
|
1993年〜1998年
|
9.4 | 6.3 | -14.2 | 25.7 | 31.2 | 14.2 | -5.1 | - | - | 75.0 |
|
1998年〜2003年
|
6.1 | 3.9 | -18.9 | 16.6 | 14.2 | 23.4 | 8.5 | -15.0 | - | -25.0 |
|
2003年〜2008年
|
5.4 | 3.8 | 0.6 | 10.8 | 12.1 | -2.9 | 92.9 | -8.8 | 185.7 | 0.0 |
|
2008年〜2013年
|
3.9 | 4.1 | 24.3 | 2.0 | 7.6 | -8.4 | -13.2 | 33.9 | 235.0 | -42.9 |
|
2013年〜2018年
|
4.7 | 3.0 | 48.4 | 6.3 | 5.2 | 6.9 | -4.7 | 53.0 | 3.0 | 8.3 |
|
2018年〜2023年
|
5.4 | 2.1 | -21.6 | 17.6 | 24.2 | 10.9 | 13.8 | 1.6 | 4.3 | 107.7 |
1)住宅の総数に占める割合
2)共同住宅の総数に占める割合
4.住宅の構造
住宅の非木造化が進行、この30年間で非木造の割合が17.9%から28.3%に上昇
住宅の構造別割合の推移をみると、1993年から2023年までの30年間で住宅全体に占める非木造の割合が17.9%から28.3%に上昇している一方、木造の割合が82.1%から71.7%に低下しており、住宅の非木造化が進行している。<図4、表4>
〈全国〉
- 住宅の非木造化が進行、この30年間で非木造の割合が31.9%から46.0%に上昇
図4.住宅の構造別割合の推移-茨城県(1993年~2023年)
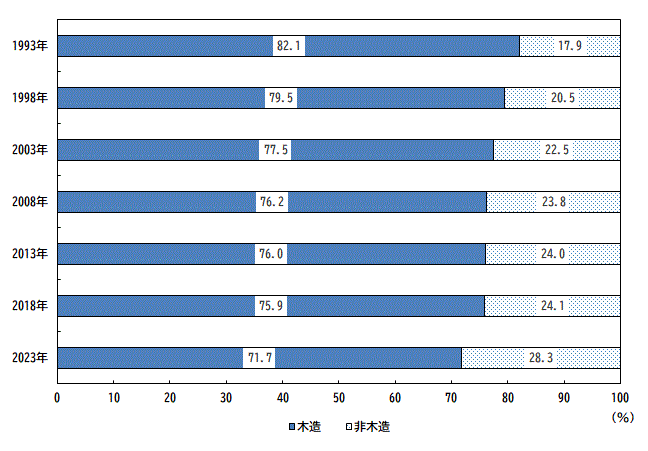
表4.住宅の構造別住宅数の推移-茨城県(1993年〜2023年)
| 年次 | 総数 | 木造 | 非木造 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 鉄筋・鉄骨 コンクリート造 |
鉄骨造 | ブロック造 | その他 1) |
|||
| 実数 | |||||||
|
1993年(平成5年)
|
846,900 | 695,700 | 151,300 | 133,500 | - | 2,500 | 15,300 |
|
1998年(平成10年)
|
926,900 | 736,700 | 190,200 | 160,900 | - | 3,000 | 26,300 |
|
2003年(平成15年)
|
983,000 | 761,800 | 221,200 | 151,800 | 67,700 | - | 1,700 |
|
2008年(平成20年)
|
1,036,200 | 789,800 | 246,400 | 157,600 | 86,700 | - | 2,100 |
|
2013年(平成25年)
|
1,076,100 | 817,800 | 258,300 | 154,200 | 102,900 | - | 1,200 |
|
2018年(平成30年)
|
1,126,600 | 855,600 | 271,000 | 169,100 | 100,400 | - | 1,500 |
|
2023年(令和5年)
|
1,187,400 | 851,900 | 335,500 | 179,300 | 154,700 | - | 1,500 |
| 割合(%) | |||||||
|
1993年(平成5年)
|
100.0 | 82.1 | 17.9 | 15.8 | - | 0.3 | 1.8 |
|
1998年(平成10年)
|
100.0 | 79.5 | 20.5 | 17.4 | - | 0.3 | 2.8 |
|
2003年(平成15年)
|
100.0 | 77.5 | 22.5 | 15.4 | 6.9 | - | 0.2 |
|
2008年(平成20年)
|
100.0 | 76.2 | 23.8 | 15.2 | 8.4 | - | 0.2 |
|
2013年(平成25年)
|
100.0 | 76.0 | 24.0 | 14.3 | 9.6 | - | 0.1 |
|
2018年(平成30年)
|
100.0 | 75.9 | 24.1 | 15.0 | 8.9 | - | 0.1 |
|
2023年(令和5年)
|
100.0 | 71.7 | 28.3 | 15.1 | 13.0 | - | 0.1 |
1)1998年までの「その他」は鉄骨造を含む。2003年以降の「その他」はブロック造を含む。
5.住宅の所有の関係
持ち家は82万3,500戸、持ち家住宅率は69.4%
住宅を所有の関係別にみると、持ち家が82万3,500戸で、住宅全体に占める持ち家住宅の割合(以下「持ち家住宅率」という。)は69.4%となっており、2018年と比べ、1.3ポイントの低下となっている。1993年から2023年までの30年間における持ち家住宅率の推移をみると、70%前後でほぼ横ばいとなっている。
借家は31万2,000戸で、住宅全体に占める割合は26.3%となっており、2018年と比べ、ほぼ同率となっている。借家の内訳をみると、「民営借家」が25万7,000戸(住宅全体に占める割合21.6%)と最も多く、次いで「給与住宅」が2万8,700戸(同2.4%)、「公営の借家」が2万2,800戸(同1.9%)、「都市再生機構(UR)・公社の借家」が3,400戸(同0.3%)となっている。<図5、表5>
〈全国〉
- 持ち家は3387万6千戸、持ち家住宅率は60.9%
図5.持ち家数、借家数及び持ち家住宅率の推移-茨城県(1993年~2023年)
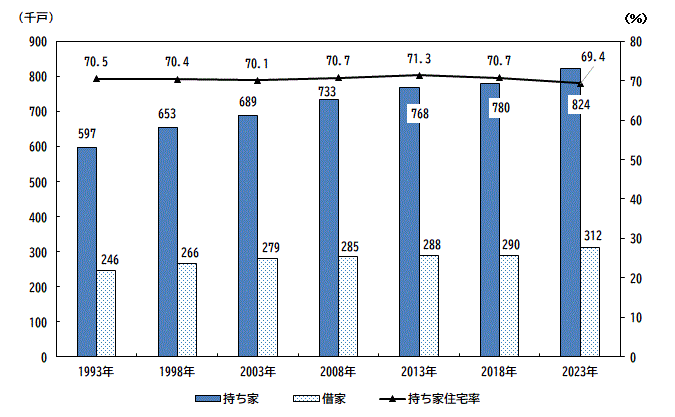
表5.住宅の所有の関係別住宅数の推移-茨城県(1993年〜2023年)
| 年次 | 総数 1) |
持ち家 | 借家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 公営の借家 | 都市再生機構(UR) ・公社の借家 2) |
民営借家 | 給与住宅 | |||
| 実数(戸) | |||||||
|
1993年
|
846,900 | 597,200 | 245,600 | 29,800 | 8,800 | 157,000 | 50,000 |
|
1998年
|
926,900 | 652,800 | 265,800 | 30,400 | 8,000 | 183,500 | 43,800 |
|
2003年
|
983,000 | 688,800 | 278,700 | 36,000 | 6,900 | 194,300 | 41,400 |
|
2008年
|
1,036,200 | 732,900 | 285,300 | 30,100 | 5,800 | 217,200 | 32,200 |
|
2013年
|
1,076,100 | 767,700 | 287,800 | 25,400 | 5,200 | 234,900 | 22,400 |
|
2018年
|
1,103,300 | 780,300 | 290,100 | 26,900 | 3,000 | 243,200 | 17,100 |
|
2023年
|
1,187,400 | 823,500 | 312,000 | 22,800 | 3,400 | 257,000 | 28,700 |
| 割合(%) | |||||||
|
1993年
|
100.0 | 70.5 | 29.0 | 3.5 | 1.0 | 18.5 | 5.9 |
|
1998年
|
100.0 | 70.4 | 28.7 | 3.3 | 0.9 | 19.8 | 4.7 |
|
2003年
|
100.0 | 70.1 | 28.4 | 3.7 | 0.7 | 19.8 | 4.2 |
|
2008年
|
100.0 | 70.7 | 27.5 | 2.9 | 0.6 | 21.0 | 3.1 |
|
2013年
|
100.0 | 71.3 | 26.7 | 2.4 | 0.5 | 21.8 | 2.1 |
|
2018年
|
100.0 | 70.7 | 26.3 | 2.4 | 0.3 | 22.0 | 1.5 |
|
2023年
|
100.0 | 69.4 | 26.3 | 1.9 | 0.3 | 21.6 | 2.4 |
1)住宅の所有の関係「不詳」を含む。
2)2003年までは「公団・公社の社宅」として表章
6.住宅の規模
1住宅当たり居住室数、延べ面積は減少、1人当たり居住室の畳数は増加
住宅のうち居住専用に建築された住宅(以下「専用住宅」という。)について、1住宅当たりの住宅の規模をみると、居住室数は4.75室、居住室の畳数は36.68畳、延べ面積(居住室のほか玄関、トイレ、台所などを含めた住宅の床面積の合計)は104.47平方メートルで、1人当たり居住室の畳数は15.45畳、1室当たり人員は0.5人となっている。
建て方別に1993年から2023年までの30年間の推移をみると、1住宅当たり延べ面積については、一戸建は2013年までは増加が続いていたが、2018年以降減少傾向となっている。共同住宅は1998年から2018年までは増加が続いていたが、2023年は減少となった。一方で、1人当たり居住室の畳数は一戸建、共同住宅共に増加が続いている。<表6、図6>
〈全国〉
- 1住宅当たり居住室数、延べ面積は減少、1人当たり居住室の畳数は増加
表6.専用住宅の建て方別住宅の規模の推移-茨城県(1993年〜2023年)
| 住宅の規模 | 1993年 | 1998年 | 2003年 | 2008年 | 2013年 | 2018年 | 2023年 | ||
| 総数 | 1住宅当たり居住室数 | (室) | 5.11 | 5.13 | 5.16 | 5.09 | 5.09 | 4.91 | 4.75 |
| 1住宅当たり居住室の畳数 | (畳) | 34.24 | 34.80 | 36.28 | 36.41 | 37.10 | 36.88 | 36.68 | |
| 1住宅当たり延べ面積 | (平方メートル) | 98.78 | 102.07 | 105.19 | 106.22 | 107.31 | 106.97 | 104.47 | |
| 1人当たり居住室の畳数 | (畳) | 10.15 | 10.99 | 12.10 | 12.87 | 13.80 | 14.56 | 15.45 | |
| 1室当たり人員 | (人) | 0.66 | 0.62 | 0.58 | 0.56 | 0.53 | 0.52 | 0.50 | |
| 一戸建 | 1住宅当たり居住室数 | (室) | 5.76 | 5.86 | 5.96 | 5.94 | 5.93 | 5.73 | 5.61 |
| 1住宅当たり居住室の畳数 | (畳) | 39.24 | 40.36 | 42.48 | 42.89 | 43.58 | 43.29 | 43.51 | |
| 1住宅当たり延べ面積 | (平方メートル) | 114.47 | 120.54 | 125.31 | 127.56 | 128.83 | 128.18 | 126.74 | |
| 1人当たり居住室の畳数 | (畳) | 10.63 | 11.56 | 12.85 | 13.68 | 14.65 | 15.45 | 16.39 | |
| 1室当たり人員 | (人) | 0.64 | 0.60 | 0.55 | 0.53 | 0.50 | 0.49 | 0.47 | |
| 共同住宅 | 1住宅当たり居住室数 | (室) | 2.83 | 2.81 | 2.79 | 2.69 | 2.67 | 2.62 | 2.55 |
| 1住宅当たり居住室の畳数 | (畳) | 17.02 | 17.43 | 17.87 | 18.11 | 18.70 | 19.18 | 19.12 | |
| 1住宅当たり延べ面積 | (平方メートル) | 44.29 | 43.98 | 45.28 | 45.74 | 45.98 | 48.27 | 47.39 | |
| 1人当たり居住室の畳数 | (畳) | 7.57 | 8.22 | 8.60 | 9.31 | 10.06 | 10.82 | 11.64 | |
| 1室当たり人員 | (人) | 0.79 | 0.75 | 0.74 | 0.72 | 0.70 | 0.68 | 0.65 | |
図6.専用住宅の建て方別1住宅当たり延べ面積、1人当たり居住室の畳数の推移
-茨城県(1993年~2023年)
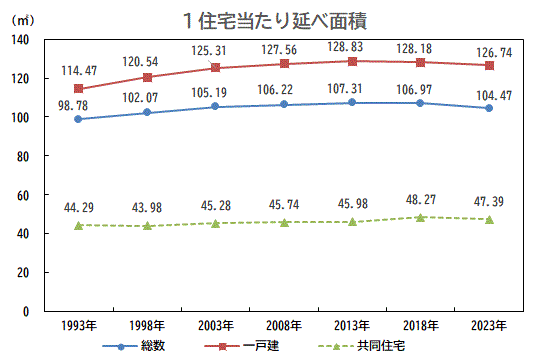
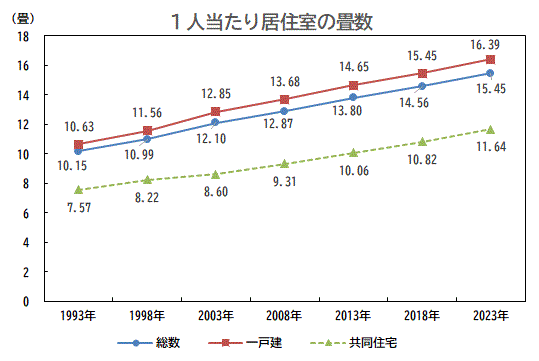
7.借家の家賃
借家の1か月当たり家賃は5.1%の増加
借家(専用住宅)の1か月当たり家賃は47,517円となっており、2018年と比べ、5.1%の増加となっている。これを借家(専用住宅)の種類別にみると、「公営の借家」が22,330円(14.0%増)、「都市再生機構(UR)・公社の借家」が56,629円(10.3%増)、「民営借家(木造)」が49,220円(5.3%増)、「民営借家(非木造)」が53,569円(4.5%増)、「給与住宅」が27,128円(9.2%増)となっており、いずれも増加している。
借家(専用住宅)の1畳当たり家賃は、2,597円となっており、「民営借家(非木造)」が3,083円と最も高く、次いで、「都市再生機構(UR)・公社の借家」が2,608円などとなっている。<表7、図7>
〈全国〉
- 借家の1か月当たり家賃は7.1%の増加
表7.借家(専用住宅)の種類別家賃の推移-茨城県(2003年~2023年)
| 年次 | 総数 1) |
公営の借家 | 都市再生機構(UR)・ 公社の借家 2) |
民営借家 (木造) |
民営借家 (非木造) |
給与住宅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1か月当たり家賃(円) | ||||||
|
2003年 |
41,980 | 21,500 | 44,250 | 45,567 | 54,854 | 20,720 |
| 2008年 | 44,547 | 21,083 | 46,432 | 46,922 | 54,067 | 21,972 |
| 2013年 | 45,323 | 20,176 | 55,506 | 46,365 | 52,049 | 24,583 |
| 2018年 | 45,231 | 19,590 | 51,320 | 46,727 | 51,253 | 24,841 |
| 2023年 | 47,517 | 22,330 | 56,629 | 49,220 | 53,569 | 27,128 |
| 増減率(%) | ||||||
| 2003年~2008年 | 6.1 | -1.9 | 4.9 | 3.0 | -1.4 | 6.0 |
| 2008年~2013年 | 1.7 | -4.3 | 19.5 | -1.2 | -3.7 | 11.9 |
| 2013年~2018年 | -0.2 | -2.9 | -7.5 | 0.8 | -1.5 | 1.0 |
| 2018年~2023年 | 5.1 | 14.0 | 10.3 | 5.3 | 4.5 | 9.2 |
| 1畳当たり家賃(円) | ||||||
| 2003年 | 2,292 | 1,090 | 2,461 | 2,407 | 3,320 | 1,032 |
| 2008年 | 2,479 | 1,061 | 2,447 | 2,415 | 3,371 | 1,122 |
| 2013年 | 2,461 | 1,016 | 2,716 | 2,316 | 3,074 | 1,265 |
| 2018年 | 2,426 | 967 | 2,556 | 2,286 | 2,998 | 1,262 |
| 2023年 | 2,597 | 1,097 | 2,608 | 2,501 | 3,083 | 1,637 |
| 増減率(%) | ||||||
| 2003年~2008年 | 8.2 | -2.7 | -0.6 | 0.3 | 1.5 | 8.7 |
| 2008年~2013年 | -0.7 | -4.2 | 11.0 | -4.1 | -8.8 | 12.7 |
| 2013年~2018年 | -1.4 | -4.8 | -5.9 | -1.3 | -2.5 | -0.2 |
| 2018年~2023年 | 7.0 | 13.4 | 2.0 | 9.4 | 2.8 | 29.7 |
1)住宅の所有の関係「不詳」を含む。
2)2003年までは「公団・公社の借家」として表章
図7.借家(専用住宅)の種類別1畳当たり家賃-茨城県(2023年)
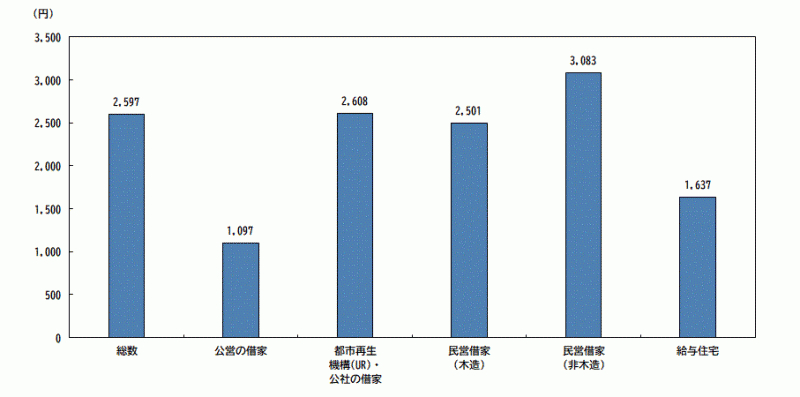
8.高齢者のいる世帯の状況
主世帯の46.6%が高齢者のいる世帯
高齢者のいる世帯のうち、高齢単身世帯が25.7%を占める
65歳以上の世帯員がいる主世帯(以下、「高齢者のいる世帯」という。)の推移をみると、2018年には50万世帯を超え、2023年では55万3,200世帯となっており、主世帯全体に占める割合は46.6%と、2018年に比べ、0.4%ポイントの上昇となっている。
75歳以上の世帯員がいる主世帯は2023年では31万9,900世帯となっており、主世帯全体に占める割合は26.9%となっている。<図8-1>
高齢者のいる世帯について、世帯の型別割合をみると、高齢単身世帯は25.7%(14万2,400世帯)で過去最高となっている。また、高齢者のいる夫婦のみの世帯は29.4%(16万2,600世帯)、高齢者のいるその他の世帯が44.9%(24万8,200世帯)となっている。<図8-2、表8-1>
〈全国〉
- 主世帯の42.7%が高齢者のいる世帯
- 高齢者のいる世帯のうち、高齢単身世帯が32.1%を占める
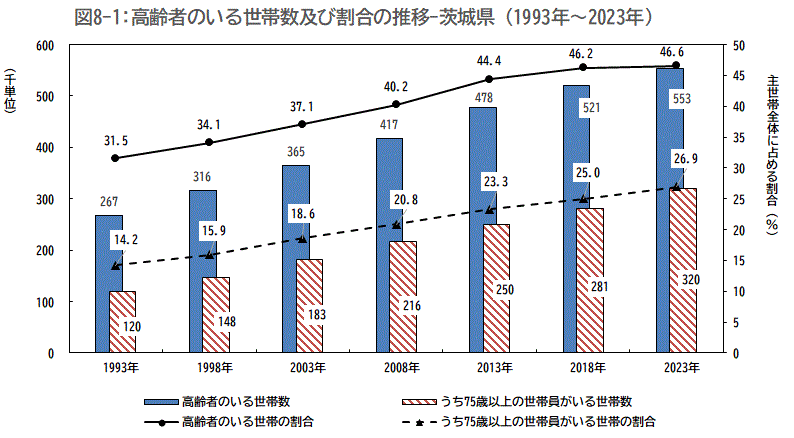
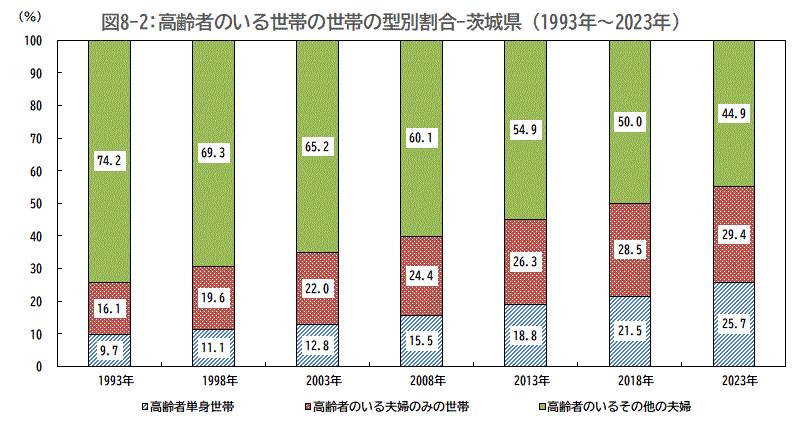
表8-1.高齢者のいる世帯の世帯の型別世帯数-茨城県(1993年〜2023年)
| 主世帯 総数 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| うち高齢者のいる世帯 | うち75歳以上の 世帯員がいる世帯 |
|||||
| 総数 | 高齢者単身世帯 | 高齢者のいる 夫婦のみの世帯 |
高齢者のいる その他の世帯 |
|||
| 実数(戸) | ||||||
|
1993年(平成5年)
|
846,900 | 267,100 | 25,900 | 42,900 | 198,300 | 120,400 |
|
1998年(平成10年)
|
926,900 | 316,000 | 35,100 | 61,800 | 219,100 | 147,700 |
|
2003年(平成15年)
|
983,000 | 364,800 | 46,700 | 80,200 | 237,900 | 182,500 |
|
2008年(平成20年)
|
1,036,200 | 416,800 | 64,700 | 101,600 | 250,500 | 216,000 |
|
2013年(平成25年)
|
1,076,100 | 478,000 | 89,800 | 125,900 | 262,300 | 250,400 |
|
2018年(平成30年)
|
1,126,600 | 520,800 | 112,100 | 148,200 | 260,500 | 281,400 |
|
2023年(令和5年)
|
1,187,400 | 553,200 | 142,400 | 162,600 | 248,200 | 319,900 |
| 割合-1(%)1) | ||||||
|
1993年(平成5年)
|
100.0 | 31.5 | 3.1 | 5.1 | 23.4 | 14.2 |
|
1998年(平成10年)
|
100.0 | 34.1 | 3.8 | 6.7 | 23.6 | 15.9 |
|
2003年(平成15年)
|
100.0 | 37.1 | 4.8 | 8.2 | 24.2 | 18.6 |
|
2008年(平成20年)
|
100.0 | 40.2 | 6.2 | 9.8 | 24.2 | 20.8 |
|
2013年(平成25年)
|
100.0 | 44.4 | 8.3 | 11.7 | 24.4 | 23.3 |
|
2018年(平成30年)
|
100.0 | 46.2 | 10.0 | 13.2 | 23.1 | 25.0 |
|
2023年(令和5年)
|
100.0 | 46.6 | 12.0 | 13.7 | 20.9 | 26.9 |
| 割合-2(%)2) | ||||||
|
1993年(平成5年)
|
- | 100.0 | 9.7 | 16.1 | 74.2 | 45.1 |
|
1998年(平成10年)
|
- | 100.0 | 11.1 | 19.6 | 69.3 | 46.7 |
|
2003年(平成15年)
|
- | 100.0 | 12.8 | 22.0 | 65.2 | 50.0 |
|
2008年(平成20年)
|
- | 100.0 | 15.5 | 24.4 | 60.1 | 51.8 |
|
2013年(平成25年)
|
- | 100.0 | 18.8 | 26.3 | 54.9 | 52.4 |
|
2018年(平成30年)
|
- | 100.0 | 21.5 | 28.5 | 50.0 | 54.0 |
|
2023年(令和5年)
|
- | 100.0 | 25.7 | 29.4 | 44.9 | 57.8 |
1)主世帯総数に占める割合
2)高齢者のいる世帯の総数に占める割合
高齢者のいる世帯の89.9%が持ち家、高齢単身世帯の22.9%が借家に居住
高齢者のいる世帯が居住する住宅の所有の関係別に割合をみると、持ち家が89.9%、借家が9.9%となっており、主世帯全体の持ち家の割合(69.4%)に比べ、持ち家の割合が20.5ポイント高くなっている。一方、高齢単身世帯では、借家の割合が22.9%と、高齢者のいる世帯全体と比較して借家の割合が高くなっている。
<図8-3、表8-2>
〈全国〉
- 高齢者のいる世帯の81.6%が持ち家、高齢単身世帯の32.2%が借家に居住
図8-3.世帯の型、住宅の所有の関係別割合(高齢者のいる世帯)-茨城県(2023年)
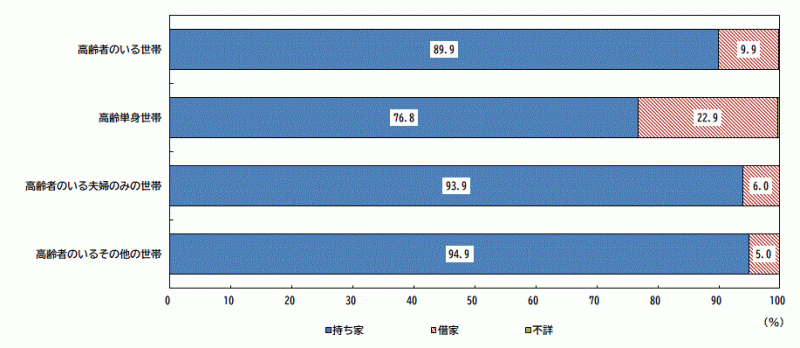
表8-2.世帯の型、住宅の所有の関係別主世帯数及び割合(高齢者のいる世帯)
-茨城県(2023年)
| 総数 1) |
持ち家 | 借家 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 公営の借家 | 都市再生機構(UR) ・公社の借家 |
民営借家 | 給与住宅 | ||||
| 木造 | 非木造 | |||||||
| 実数 | ||||||||
|
主世帯
|
1,187,400 | 823,500 | 312,000 | 22,800 | 3,400 | 98,400 | 157,900 | 28,700 |
|
うち高齢者のいる世帯
|
553,200 | 497,500 | 54,800 | 12,600 | 1,800 | 21,400 | 17,600 | 1,400 |
|
高齢単身世帯
|
142,400 | 109,300 | 32,600 | 7,600 | 700 | 12,500 | 11,100 | 700 |
|
高齢者のいる夫婦のみの世帯
|
162,600 | 152,700 | 9,700 | 2,200 | 600 | 3,400 | 3,200 | 300 |
|
高齢者のいるその他の世帯
|
248,200 | 235,500 | 12,500 | 2,800 | 500 | 5,500 | 3,300 | 400 |
| 割合(%) | ||||||||
|
主世帯
|
100.0 | 69.4 | 26.3 | 1.9 | 0.3 | 8.3 | 13.3 | 2.4 |
|
うち高齢者のいる世帯
|
100.0 | 89.9 | 9.9 | 2.3 | 0.3 | 3.9 | 3.2 | 0.3 |
|
高齢単身世帯
|
100.0 | 76.8 | 22.9 | 5.3 | 0.5 | 8.8 | 7.8 | 0.5 |
|
高齢者のいる夫婦のみの世帯
|
100.0 | 93.9 | 6.0 | 1.4 | 0.4 | 2.1 | 2.0 | 0.2 |
|
高齢者のいるその他の世帯
|
100.0 | 94.9 | 5.0 | 1.1 | 0.2 | 2.2 | 1.3 | 0.2 |
1)住宅の所有の関係「不詳」を含む。
高齢者等のための設備がある住宅は住宅全体の54.5%、3.2ポイントの上昇
高齢者等のための設備がある住宅は64万7,600戸で、住宅全体の54.5%となっており、2018年と比べ、3.2ポイント上昇している。住宅の設備状況の割合をみると、「手すりがある」が45.2%、「またぎやすい高さの浴槽」が20.8%、「廊下などが車いすで通行可能な幅」が14.5%、「段差のない屋内」が20.6%、「道路から玄関まで車いすで通行可能」が8.5%となっており、いずれも2018年と比べ上昇している。<表8-3>
〈全国〉
- 高齢者等のための設備がある住宅は住宅全体の56.0%、5.1ポイントの上昇
表8-3.高齢者等のための設備状況別住宅数―茨城県(2018年、2023年)
| 高齢者等のための設備状況 | 2018年 | 2023年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 実数 | 割合(%) | 実数 | 割合(%) | |
| 住宅総数1) | 1,126,600 | 100.0 | 1,187,400 | 100.0 |
|
高齢者等のための設備がある2)
|
577,500 | 51.3 | 647,600 | 54.5 |
|
手すりがある
|
492,800 | 43.7 | 536,800 | 45.2 |
|
またぎやすい高さの浴槽
|
223,900 | 19.9 | 247,300 | 20.8 |
|
浴室暖房乾燥機3)
|
- | - | 252,900 | 21.3 |
|
廊下などが車いすで通行可能な幅
|
160,700 | 14.3 | 172,600 | 14.5 |
|
段差のない屋内
|
231,100 | 20.5 | 244,400 | 20.6 |
|
道路から玄関まで車いすで通行可能
|
94,300 | 8.4 | 100,700 | 8.5 |
1)高齢者等のための設備状況「不詳」を含む。
2)複数回答であるため、内訳の合計とは必ずしも一致しない。
3)2023年調査から回答選択肢に追加
9.現住居以外の住宅の所有状況
現住居以外の住宅を所有している主世帯は11万1,200世帯(9.4%)
うち空き家を所有している世帯は3万3,500世帯(2.8%)
世帯が所有する空き家のうち、45.1%は賃貸・売却用や二次的住宅(別荘など)を除く空き家
主世帯のうち、現住居以外の住宅を所有している世帯は11万1,200世帯(主世帯全体に占める割合9.4%)となっている。居住世帯のある住宅を所有している世帯は8万8,200世帯(同7.4%)、居住世帯のない住宅(空き家)を所有している世帯は3万3,500世帯(同2.8%)となっている。
世帯が所有する居住世帯のない住宅(空き家)の主な用途別割合をみると、「賃貸・売却用及び二次的住宅を除く空き家」が45.1%と最も高くなっている。<表9、図9>
〈全国〉
- 現住居以外の住宅を所有している主世帯は475万3千世帯(8.5%)
- うち空き家を所有している世帯は141万6千世帯(2.5%)
- 世帯が所有する空き家のうち、47.5%は賃貸・売却用や二次的住宅(別荘など)を除く空き家
表9.現住居以外に所有する住宅の主な用途別主世帯数、住宅数-茨城県(2023年)
| 主世帯総数 | うち現住居以外の住宅を主有している世帯 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 2) |
居住世帯のある住宅 | 居住世帯のない住宅 | ||||||||||
| 総数 | 親族居住用 | 貸家用 | 売却用 | その他 | 総数 | 賃貸・売却用 及び二次的住宅を 除く空き家 |
貸家用 | 売却用 | 二次的住宅 ・別荘 |
|||
| 世帯数1) | 1,187,400 | 111,200 | 88,200 | 51,800 | 22,000 | 1,300 | 16,100 | 33,500 | 20,800 | 3,200 | 2,200 | 8,000 |
|
割合(%)
|
100.0 | 9.4 | 7.4 | 4.4 | 1.9 | 0.1 | 1.4 | 2.8 | 1.8 | 0.3 | 0.2 | 0.7 |
| 所有する住宅数 | - | 145,000 | 94,000 | 39,000 | 50,000 | 0 | 4,000 | 51,000 | 23,000 | 20,000 | 1,000 | 7,000 |
|
割合(%)
|
- | - | 100.0 | 41.5 | 53.2 | 0.0 | 4.3 | 100.0 | 45.1 | 39.2 | 2.0 | 13.7 |
1)複数の住宅を所有する場合、それぞれの住宅の主な用途について世帯を計上しているため、内訳は総数に一致しない。
2)現住居以外に所有する住宅の主な用途「不詳」を含む。
図9.現住居以外に所有する住宅の主な用途別割合-茨城県(2023年)
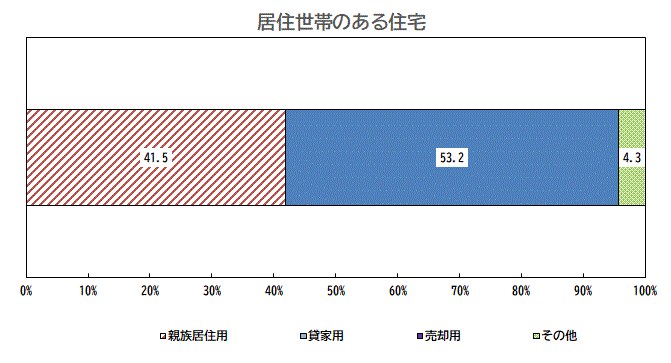
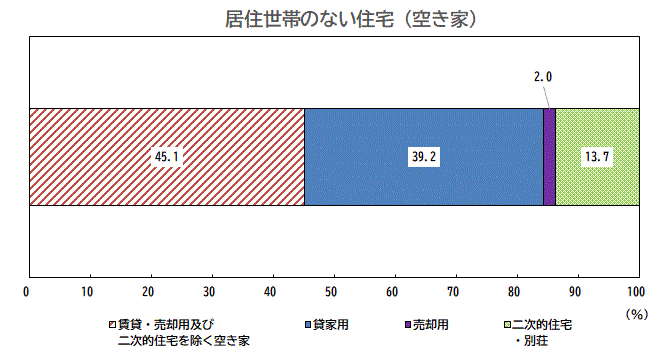
10.敷地面積
1住宅当たりの敷地面積は、394.15平方メートルで全国1位
一戸建住宅の1住宅当たりの敷地面積は、394.80平方メートルで全国1位
1住宅当たりの敷地面積は、394.15平方メートルで、全国平均の261.01平方メートルを133.14平方メートル上回り、全国1位となった。また、一戸建住宅の1住宅当たりの敷地面積は、394.80平方メートルで、全国平均の262.45平方メートルを132.35平方メートル上回り、同じく全国1位となった。
なお、前回調査に比べ、1住宅当たりの敷地面積で0.82平方メートル、一戸建住宅の1住宅当たりの敷地面積で11.5平方メートル、それぞれ狭くなった。<表10-1、表10-2、図10>
〈全国〉
- 1住宅当たりの敷地面積は、261.01平方メートルで前回調査に比べ、9.25平方メートル広くなった
- 一戸建住宅の1住宅当たりの敷地面積は、262.45平方メートルで前回調査に比べ、2.77平方メートル広くなった
表10-1.1住宅あたりの敷地面積順位-上位5都道府県(2018年・2023年)
| 2018年 | 2023年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 住宅数(戸) | 敷地面積(平方メートル) | 都道府県 | 住宅数(戸) | 敷地面積(平方メートル) |
| 茨城県 | 846,700 | 394.97 | 茨城県 | 783,600 | 394.15 |
| 山形県 | 311,800 | 367.69 | 山形県 | 285,800 | 391.91 |
| 岩手県 | 369,300 | 361.46 | 岩手県 | 322,600 | 373.06 |
| 秋田県 | 314,900 | 356.28 | 秋田県 | 278,800 | 372.26 |
| 栃木県 | 563,000 | 351.77 | 福島県 | 479,600 | 366.90 |
表10-2.一戸建住宅の1住宅あたりの敷地面積順位-上位5都道府県(2018年・2023年)
| 2018年 | 2023年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 住宅数(戸) | 敷地面積(平方メートル) | 都道府県 | 住宅数(戸) | 敷地面積(平方メートル) |
| 茨城県 | 814,800 | 406.30 | 茨城県 | 781,800 | 394.80 |
| 岩手県 | 352,600 | 374.76 | 山形県 | 285,500 | 392.20 |
| 山形県 | 305,200 | 373.94 | 岩手県 | 321,900 | 373.69 |
| 秋田県 | 306,200 | 364.35 | 秋田県 | 278,400 | 372.66 |
| 福島県 | 512,800 | 361.55 | 福島県 | 478,800 |
367.31 |
図10.1住宅あたりの敷地面積順位-全国(2023年)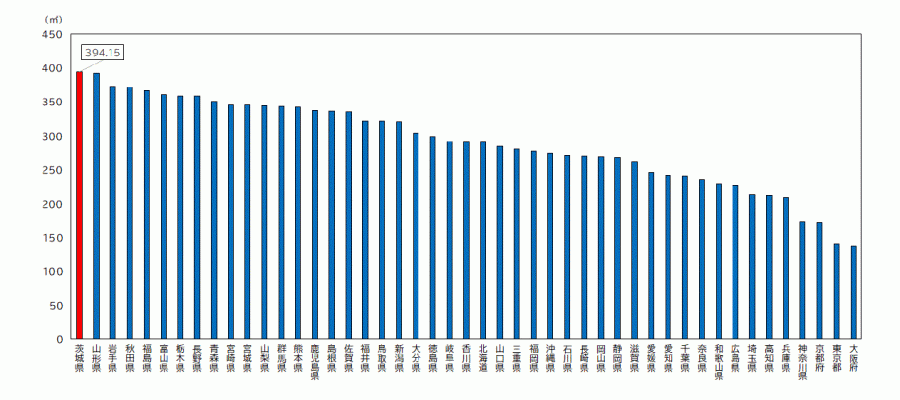
11.2019年以降に行われた増改築・改修工事等の状況
2019年以降に増改築・改修工事等が行われた持ち家の割合は約3割、「台所・トイレ・浴室・洗面所の改修工事」の割合が最も高い
2019年以降に増改築・改修工事等が行われた持ち家は23万1,200戸で、持ち家全体の28.1%となっている。増改築・改修工事等の内容の割合をみると、「台所・トイレ・浴室・洗面所の改修工事」が15.8%と最も高く、次いで「屋根・外壁等の改修工事」が12.6%、「天井・壁・床等の内装の改修工事」が7.0%などとなっている。
2019年以降に増改築・改修工事等が行われた持ち家の割合を建築の時期別にみると、「1981~1990年」が38.2%と最も高く、次いで「1971~1980年」が37.1%、「1991~2000年」が34.7%などとなっており、2000年以前に建築された持ち家の3割以上が2019年以降に増改築・改修工事等を行っている。
<表11、図11-1、図11-2>
〈全国〉
- 2019年以降に増改築・改修工事等が行われた持ち家の割合は約3割、「台所・トイレ・浴室・洗面所の改修工事」の割合が最も高い
表11.建築の時期、2019年以降の住宅の増改築・改修工事等の
状況別持ち家数-茨城県(2023年)
| 建築の時期 | 2019年以降の住宅の増改築・改修工事等の状況別持ち家数 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 工事等を した 1) |
工事 等をして いない |
||||||||
| 増築・ 間取りの 変更 |
台所・ トイレ・ 浴室・ 洗面所の 改修工事 |
天井・壁・ |
屋根・ 外壁等の 改修工事 |
壁・柱・ 基礎等の 補強工事 |
窓・壁等の 断熱・結露 防止工事 |
その他の 工事 |
||||
| 実数(戸) | ||||||||||
|
総数2)
|
823,500 | 231,200 | 21,300 | 129,800 | 57,800 | 104,100 | 11,000 | 18,800 | 78,300 | 592,300 |
|
1970年以前
|
67,600 | 21,100 | 3,000 | 13,200 | 5,500 | 7,600 | 1,200 | 1,400 | 8,700 | 46,500 |
|
1971〜1980年
|
123,500 | 45,800 | 5,500 | 29,400 | 13,200 | 18,300 | 2,500 | 3,500 | 17,900 | 77,700 |
|
1981〜1990年
|
143,900 | 55,000 | 4,800 | 35,500 | 18,100 | 24,600 | 2,300 | 4,800 | 18,800 | 88,900 |
|
1991〜2000年
|
163,100 | 56,600 | 2,800 | 30,300 | 11,100 | 28,100 | 2,000 | 4,900 | 15,300 | 106,600 |
|
2001〜2010年
|
142,500 | 31,400 | 1,700 | 10,900 | 4,100 | 17,100 | 700 | 1,200 | 8,000 | 111,100 |
|
2011〜2020年
|
142,100 | 15,500 | 2,400 | 6,800 | 3,800 | 6,100 | 1,400 | 2,100 | 7,100 | 126,600 |
|
2021〜2023年9月
|
26,900 | 2,900 | 1,000 | 1,900 | 1,400 | 1,200 | 700 | 900 | 1,500 | 24,000 |
| 割合(%) | ||||||||||
|
総数2)
|
100.0 | 28.1 | 2.6 | 15.8 | 7.0 | 12.6 | 1.3 | 2.3 | 9.5 | 71.9 |
|
1970年以前
|
100.0 | 31.2 | 4.4 | 19.5 | 8.1 | 11.2 | 1.8 | 2.1 | 12.9 | 68.8 |
|
1971〜1980年
|
100.0 | 37.1 | 4.5 | 23.8 | 10.7 | 14.8 | 2.0 | 2.8 | 14.5 | 62.9 |
|
1981〜1990年
|
100.0 | 38.2 | 3.3 | 24.7 | 12.6 | 17.1 | 1.6 | 3.3 | 13.1 | 61.8 |
|
1991〜2000年
|
100.0 | 34.7 | 1.7 | 18.6 | 6.8 | 17.2 | 1.2 | 3.0 | 9.4 | 65.4 |
|
2001〜2010年
|
100.0 | 22.0 | 1.2 | 7.6 | 2.9 | 12.0 | 0.5 | 0.8 | 5.6 | 78.0 |
|
2011〜2020年
|
100.0 | 10.9 | 1.7 | 4.8 | 2.7 | 4.3 | 1.0 | 1.5 | 5.0 | 89.1 |
|
2021〜2023年9月
|
100.0 | 10.8 | 3.7 | 7.1 | 5.2 | 4.5 | 2.6 | 3.3 | 5.6 | 89.2 |
1)複数回答であるため、内訳の合計とは必ずしも一致しない。
2)建築の時期「不詳」を含む。
図11-1.2019年以降の住宅の増改築・改修工事等の内容別持ち家の割合-茨城県(2023年)
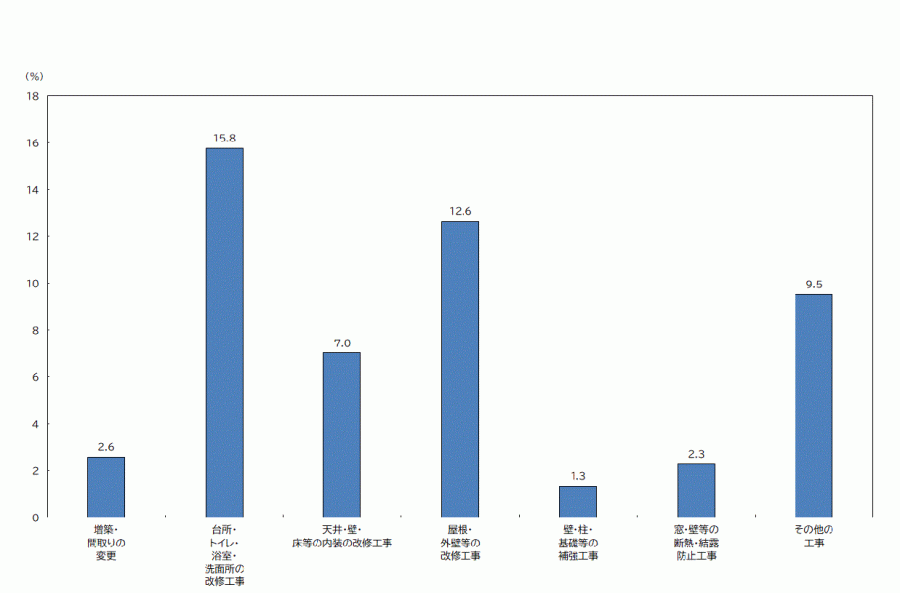
図11-2.建築の時期別2019年以降に増改築・改修工事等が行われた
持ち家の割合-茨城県(2023年)
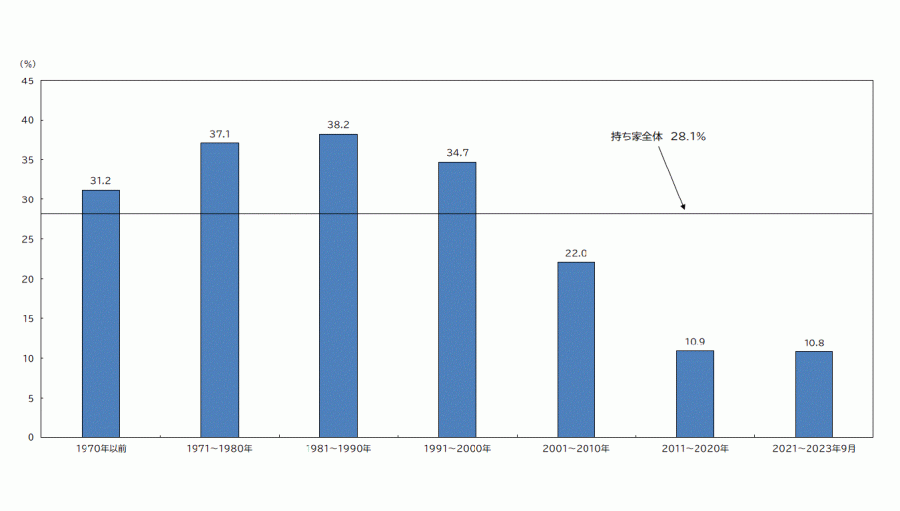
12.2019年以降に行われた耐震改修工事の状況
2019年以降に耐震改修工事が行われた持ち家の割合は2.2%、「壁の新設・補強」の割合が最も高い
2019年以降に耐震改修工事が行われた持ち家は1万8,100戸で、持ち家全体の2.2%となっている。耐震改修工事の内容をみると、「壁の新設・補強」が7,600戸(2019年以降に耐震改修工事が行われた持ち家に占める割合42.0%)と最も多く、次いで「基礎の補強」が6,600戸(同36.5%)、「金具による補強」が5,900戸(同32.6%)などとなっている。
耐震改修工事が行われた持ち家の割合を建て方別にみると、一戸建の2.3%に対し、長屋建は6.3%で、一戸建に比べ4.0ポイント高くなっている。また、構造別にみると、木造の2.3%に対し、非木造は1.4%で、木造に比べ0.9ポイント低くなっている。<表12>
〈全国〉
- 2019年以降に耐震改修工事が行われた持ち家の割合は1.9%、「壁の新設・補強」の割合が最も高い
表12.住宅の建て方・構造・建築の時期、2019年以降の住宅の耐震改修工事の
状況別持ち家数-茨城県(2023年)
| 住宅の建て方・ 構造・ 建築の時期 |
2019年以降の住宅の耐震改修工事の状況別持ち家数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | うち 工事をした 1) |
||||||
| 壁の新設・ 補強 |
筋かいの 設置 |
基礎の補強 | 金具による 補強 |
その他 | |||
| 実数(戸) | |||||||
|
総数
|
823,500 | 18,100 | 7,600 | 4,600 | 6,600 | 5,900 | 3,700 |
|
(建て方)
|
|||||||
|
一戸建
|
781,200 | 17,900 | 7,500 | 4,500 | 6,500 | 5,900 | 3,600 |
|
長屋建 |
1,600 | 100 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
|
共同住宅
|
38,700 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
|
その他
|
1,900 | 100 | 0 | - | - | 0 | 100 |
|
(構造)
|
|||||||
|
木造
|
711,900 | 16,600 | 7,000 | 4,400 | 6,000 | 5,500 | 3,400 |
|
非木造
|
110,500 | 1,500 | 600 | 200 | 500 | 400 | 300 |
|
(建築の時期)
|
|||||||
|
1980年以前
|
191,100 | 5,200 | 2,100 | 1,200 | 1,300 | 1,600 | 1,400 |
|
1981年以降
|
618,600 | 12,500 | 5,400 | 3,300 | 5,100 | 4,200 | 2,200 |
| 割合-1(%)2) | |||||||
|
総数
|
100.0 | 2.2 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.4 |
|
(建て方)
|
|||||||
|
一戸建
|
100.0 | 2.3 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.5 |
|
長屋建
|
100.0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
|
共同住宅
|
100.0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
|
その他
|
100.0 | 5.3 | 0 | - | - | 0 | 5.3 |
|
(構造)
|
|||||||
|
木造
|
100.0 | 2.3 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.5 |
|
非木造
|
100.0 | 1.4 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 |
|
(建築の時期)
|
|||||||
|
1980年以前
|
100.0 | 2.7 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.7 |
|
1981年以降
|
100.0 | 2.0 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.4 |
| 割合-2(%)3) | |||||||
|
総数
|
- | 100.0 | 42.0 | 25.4 | 36.5 | 32.6 | 20.4 |
|
(建て方)
|
|||||||
|
一戸建
|
- | 100.0 | 41.9 | 25.1 | 36.3 | 33.0 | 20.1 |
|
長屋建
|
- | 100.0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
|
共同住宅
|
- | 100.0 | 0 | - | - | - | 0 |
|
その他
|
- | 100.0 | 0 | - | - | 0 | 100 |
|
(構造)
|
|||||||
|
木造
|
- | 100.0 | 42.2 | 26.5 | 36.1 | 33.1 | 20.5 |
|
非木造
|
- | 100.0 | 40.0 | 13.3 | 33.3 | 26.7 | 20.0 |
|
(建築の時期)
|
|||||||
|
1980年以前
|
- | 100.0 | 40.4 | 23.1 | 25.0 | 30.8 | 26.9 |
|
1981年以降
|
- | 100.0 | 43.2 | 26.4 | 40.8 | 33.6 | 17.6 |
1)複数回答であるため、内訳の合計とは必ずしも一致しない。
2)建て方、構造及び建築の時期別の持ち家総数に占める割合
3)建て方、構造及び建築の時期別の住宅の耐震改修工事をした持ち家数に占める割合
13.2019年以降に行われた高齢者等のための設備工事の状況
2019年以降に高齢者等のための設備工事が行われた持ち家の割合は12.3%、世帯内の最高齢者が75歳以上の主世帯では約2割となった
2019年以降に高齢者等のための設備工事が行われた持ち家は10万1,300戸で、持ち家全体の12.3%となっている。高齢者等のための設備工事の内容の割合をみると、「階段や廊下の手すりの設置」が6.6%、「トイレの工事」が5.3%、「浴室の工事」が5.2%、「屋内の段差の解消」が2.0%などとなっている。
また、世帯内の最高齢者の年齢階級別にみると、「75歳以上」が19.9%と最も高く、次いで「65~74歳」が13.0%、「55~64歳」が7.8%などとなっており、年齢階級が高くなるほど割合は高くなっている。
<表13、図12-1、図12-2>
〈全国〉
- 2019年以降に高齢者等のための設備工事が行われた持ち家の割合は13.0%、世帯内の最高齢者が75歳以上の主世帯では2割を超える
表13.世帯内の最高齢者の年齢階級、2019年以降の高齢者等のための設備工事の
状況別持ち家数-茨城県(2023年)
| 世帯内の 最高齢者の 年齢階級 |
2019年以降の高齢者等のための設備工事の状況別持ち家数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 工事をした 1) |
|||||||
| 階段や廊下 の手すりの 設置 |
屋内の段差 の解消 |
浴室の工事 | トイレ の工事 |
その他 | 工事をして いない |
|||
| 実数(戸) | ||||||||
|
総数
|
823,500 | 101,300 | 54,400 | 16,200 | 42,700 | 44,000 | 6,500 | 722,200 |
|
45歳未満
|
71,500 | 1,200 | 500 | 200 | 500 | 400 | 100 | 70,300 |
|
45〜54歳
|
103,500 | 3,200 | 1,400 | 600 | 1,400 | 1,200 | 200 | 100,300 |
|
55〜64歳
|
119,500 | 9,300 | 4,000 | 1,500 | 4,200 | 3,900 | 500 | 110,200 |
|
65〜74歳
|
195,700 | 25,500 | 12,200 | 4,200 | 11,900 | 11,500 | 1,200 | 170,100 |
|
75歳以上
|
294,300 | 58,500 | 34,200 | 9,200 | 23,500 | 25,700 | 4,000 | 235,800 |
| 割合(%) | ||||||||
|
総数
|
100.0 | 12.3 | 6.6 | 2.0 | 5.2 | 5.3 | 0.8 | 87.7 |
|
45歳未満
|
100.0 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 98.3 |
|
45〜54歳
|
100.0 | 3.1 | 1.4 | 0.6 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 96.9 |
|
55〜64歳
|
100.0 | 7.8 | 3.3 | 1.3 | 3.5 | 3.3 | 0.4 | 92.2 |
|
65〜74歳
|
100.0 | 13.0 | 6.2 | 2.1 | 6.1 | 5.9 | 0.6 | 86.9 |
|
75歳以上
|
100.0 | 19.9 | 11.6 | 3.1 | 8.0 | 8.7 | 1.4 | 80.1 |
図12-1.2019年以降の高齢者等のための設備工事の内容別持ち家の割合-茨城県(2023年)
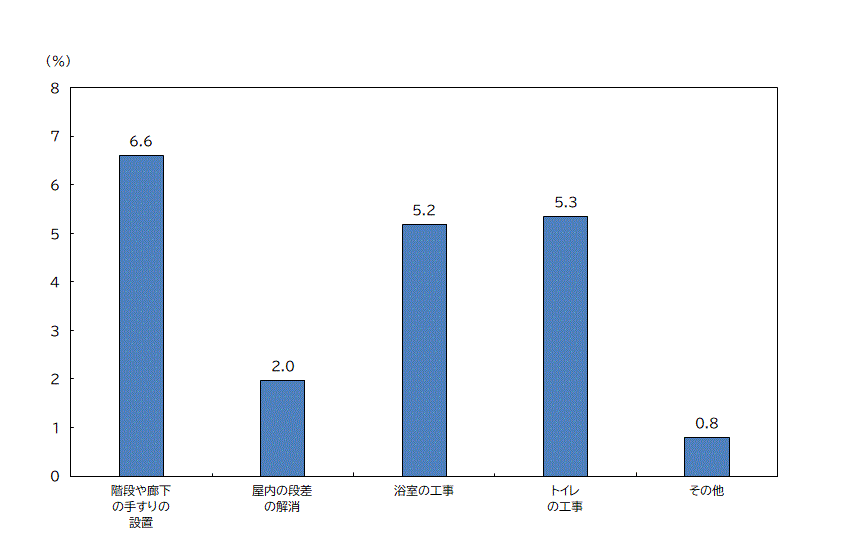
図12-2.世帯内の最高齢者の年齢階級別2019年以降に高齢者等のための設備工事が
行われた持ち家の割合-茨城県(2023年)
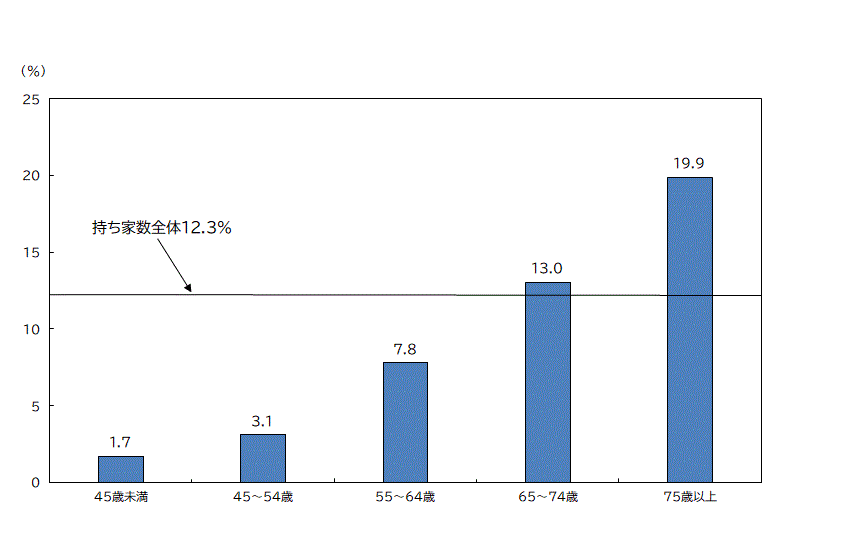
14.高齢者が住む住宅のバリアフリー化率
高齢者が住む住宅の一定のバリアフリー化率は41.3%で、2018年と比べ2.1ポイント上昇
65歳以上の世帯員のいる主世帯(以下「高齢者のいる世帯」という。)(55万3,200世帯)のうち一定のバリアフリー化住宅に居住している世帯は22万8,700世帯で、高齢者のいる世帯に占める割合(以下「一定のバリアフリー化率」という。)は41.3%となっている。また、高度のバリアフリー化住宅に居住している世帯は4万7,100世帯で、高齢者のいる世帯に占める割合(以下「高度のバリアフリー化率」という。)は8.5%となっている。2018年と比べると、一定のバリアフリー化率は2.1ポイント、高度のバリアフリー化率は0.6ポイントそれぞれ上昇している。
一定のバリアフリー化率について、住宅の建て方、所有の関係別にみると、一戸建が42.7%、共同住宅(持ち家)が58.2%、共同住宅(借家)が20.0%などとなっている。<表14、図13-1、図13-2>
〈全国〉
- 高齢者が住む住宅の一定のバリアフリー化率は45.4%で、2018年と比べ3.0ポイント上昇
|
注)一定のバリアフリー化住宅とは、人が居住する住宅について、高齢者等のための設備・構造のうち、2箇所以上の「手すりの設置」又は「段差のない屋内」がある住宅をいい、高度のバリアフリー化住宅とは、2箇所以上の「手すりの設置」、「段差のない屋内」及び「廊下などが車いすで通行可能な幅」がいずれもある住宅をいう。 |
表14.住宅の建て方、所有の関係別高齢者のいる世帯数
(一定のバリアフリー化住宅に居住する世帯数、高度のバリアフリー化住宅に居住する世帯数)
-茨城県(2018年、2023年)
| 年次、 住宅の建て方、所有の関係 |
高齢者のいる世帯数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実数 | 割合(%) | |||||
| 総数 | うち一定の バリアフリー化 |
うち高度の バリアフリー化 |
総数 | うち一定の バリアフリー化 |
うち高度の バリアフリー化 |
|
| 2018年 | ||||||
|
総数
|
520,800 | 203,900 | 41,400 | 100.0 | 39.2 | 7.9 |
|
一戸建
|
476,100 | 190,500 | 36,300 | 100.0 | 40.0 | 7.6 |
|
共同住宅(持ち家)
|
10,700 | 5,400 | 1,400 | 100.0 | 50.5 | 13.1 |
|
共同住宅(借家)
|
28,200 | 7,000 | 3,500 | 100.0 | 24.8 | 12.4 |
|
長屋建・その他
|
5,400 | 1,000 | 200 | 100.0 | 18.5 | 3.7 |
| 2023年 | ||||||
|
総数
|
553,200 | 228,700 | 47,100 | 100.0 | 41.3 | 8.5 |
|
一戸建
|
496,300 | 212,100 | 42,800 | 100.0 | 42.7 | 8.6 |
|
共同住宅(持ち家)
|
13,400 | 7,800 | 2,700 | 100.0 | 58.2 | 20.1 |
|
共同住宅(借家)
|
37,000 | 7,400 | 1,300 | 100.0 | 20.0 | 3.5 |
|
長屋建・その他
|
6,200 | 1,400 | 300 | 100.0 | 22.6 | 4.8 |
図13-1.高齢者のいる世帯のバリアフリー化率-茨城県(2018年、2023年)
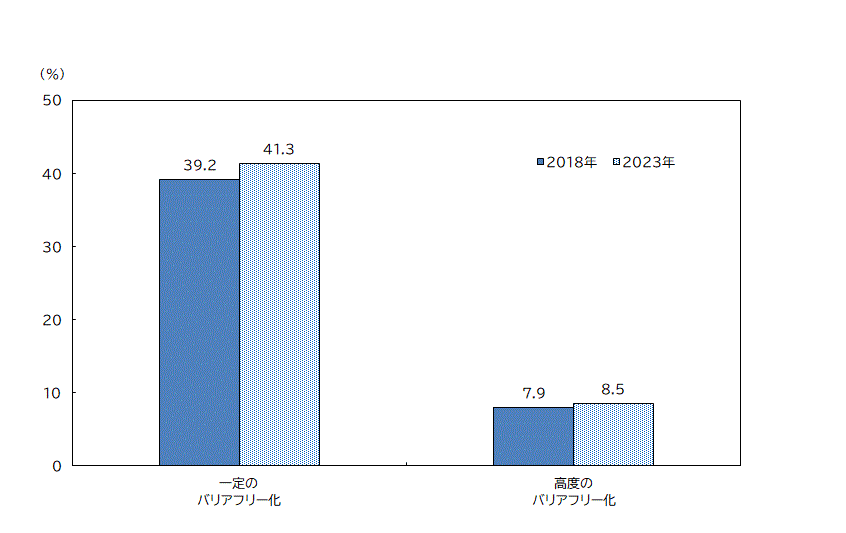
図13-2.高齢者のいる世帯の住宅の建て方、所有の関係別一定のバリアフリー化率
-茨城県(2018年、2023年)
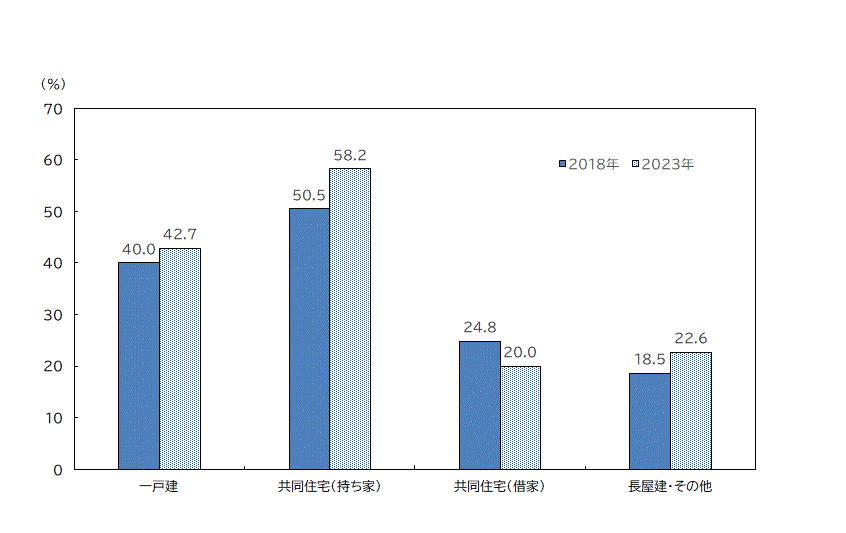
15.住環境(最寄りの老人デイサービスセンターまでの距離)
最寄りの老人デイサービスセンターまでの距離別世帯割合(高齢者のいる世帯)は、この20年間で「500m未満」が3倍以上に上昇、「1,000m以上」は5割弱に低下
高齢者のいる世帯について、最寄りの老人デイサービスセンターまでの距離別世帯数をみると、「500m未満」が13万600世帯(高齢者のいる世帯に占める割合23.6%)、「500~1,000m未満」が16万4,000世帯(同29.6%)、「1,000m以上」が25万8,600世帯(同46.7%)となっている。
距離別世帯割合の推移をみると、2003年から2023年までの20年間で「500m未満」が7.7%から23.6%と3倍以上に上昇している一方、「1,000m以上」が80.0%から46.7%に低下している。<表15、図14>
〈全国〉
- 最寄りの老人デイサービスセンターまでの距離別世帯割合(高齢者のいる世帯)は、この20年間で「500m未満」が2倍以上に上昇、「1,000m以上」は半分以下に低下
表15.最寄りの老人デイサービスセンターまでの距離別世帯数の推移(高齢者のいる世帯)
-茨城県(2003年〜2023年)
| 年次 | 最寄りの老人デイサービスセンターまでの距離別世帯数(高齢者のいる世帯) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実数 | 割合(%) | |||||||
| 総数 | 500m未満 | 500〜1,000m未満 | 1,000m以上 | 総数 | 500m未満 | 500〜1,000m未満 | 1,000m以上 | |
| 2003年 | 364,800 | 28,200 | 44,900 | 291,700 | 100.0 | 7.7 | 12.3 | 80.0 |
| 2008年 | 416,800 | 58,900 | 92,300 | 265,500 | 100.0 | 14.1 | 22.1 | 63.7 |
| 2013年 | 478,000 | 88,100 | 114,500 | 275,400 | 100.0 | 18.4 | 24.0 | 57.6 |
| 2018年 | 520,800 | 113,400 | 146,300 | 261,000 | 100.0 | 21.8 | 28.1 | 50.1 |
| 2023年 | 553,200 | 130,600 | 164,000 | 258,600 | 100.0 | 23.6 | 29.6 | 46.7 |
図14.最寄りの老人デイサービスセンターまでの距離別世帯割合の推移(高齢者のいる世帯)
-茨城県(2003年〜2023年)
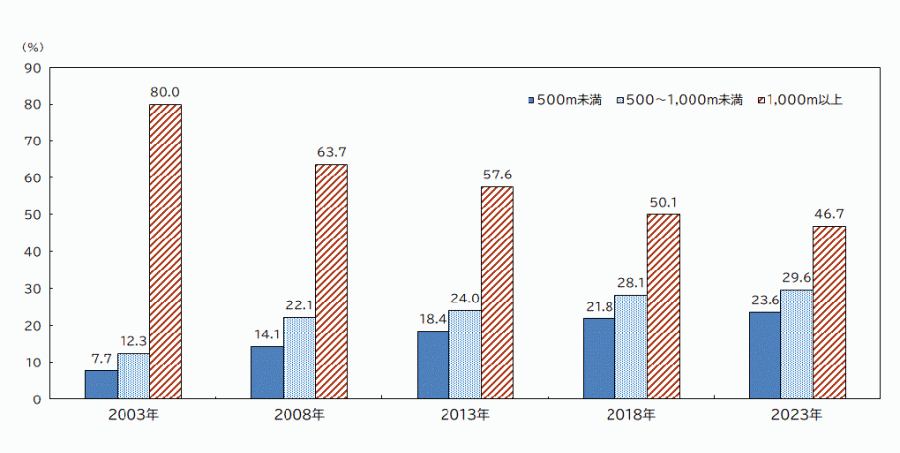
16.世帯が所有している土地の状況
現住居の敷地を所有している世帯は58.4%
現住居の敷地以外の土地を所有している世帯は17.8%
主世帯(118万7,400世帯)のうち、現住居の敷地を所有している世帯は69万4,000世帯で、主世帯に占める割合は、58.4%となっている。
また、現住居の敷地以外の土地を所有している世帯は21万1,000世帯(主世帯に占める割合17.8%)となっており、このうち現住居の敷地以外の宅地などを所有している世帯は、12万2,000世帯(同10.3%)となっている。<表16>
〈全国〉
- 現住居の敷地を所有している世帯は47.1%
- 現住居の敷地以外の土地を所有している世帯は11.8%
表16.土地の所有状況別主世帯数-茨城県(2023年)
| 総数 | 土地を所有している世帯 | |||
|---|---|---|---|---|
| 現住居の敷地を 所有している |
現住居の敷地 以外の土地を 所有している |
|||
| 現住居の敷地 以外の宅地など を所有している |
||||
| 実数 | 1,187,400 | 694,000 | 211,000 | 122,000 |
| 割合(%) | 100.0 | 58.4 | 17.8 | 10.3 |
「自営業主」は、現住居の敷地を所有している世帯と現住居の敷地以外の土地を所有している世帯の割合が高い
現住居の敷地を所有している世帯について、主世帯に占める割合を家計を主に支える者の従業上の地位別にみると、「自営業主」が84.5%と最も高く、次いで「無職」が81.3%、「雇用者」が63.5%となっている。
また、現住居の敷地以外の土地を所有している世帯についてみると、こちらも同様の傾向となっており、「自営業主」が47.3%と最も高くなっている。<図15>
〈全国〉
- 「自営業主」は、現住居の敷地を所有している世帯と現住居の敷地以外の土地を所有している世帯の割合が高い
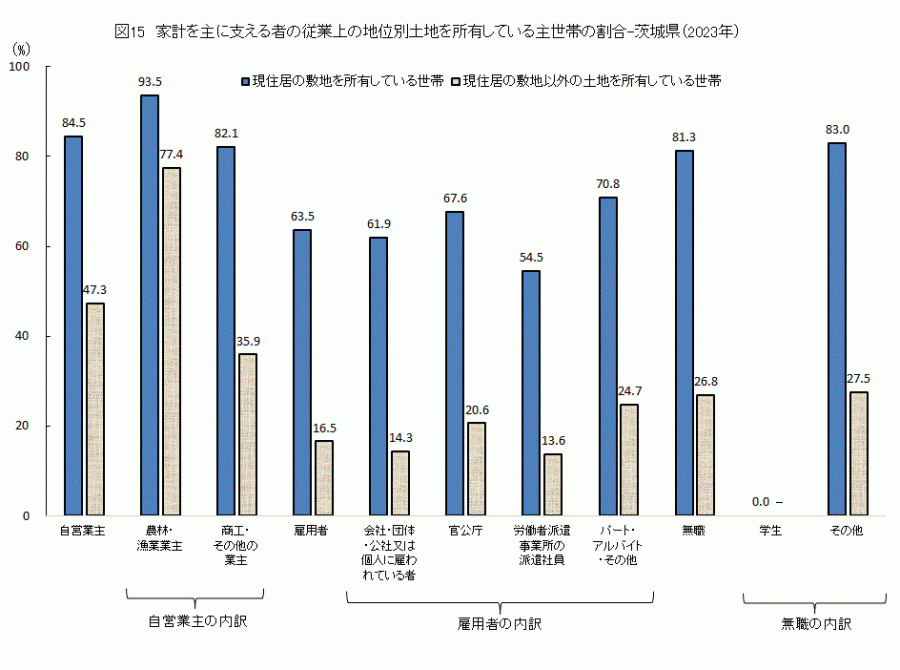
- 住宅・土地統計調査の結果(茨城県)は、分野別≪住宅・土地≫を御覧ください。
- 住宅・土地統計調査の結果(総務省統計局)は、住宅・土地統計調査(外部サイトへリンク)を御覧ください。