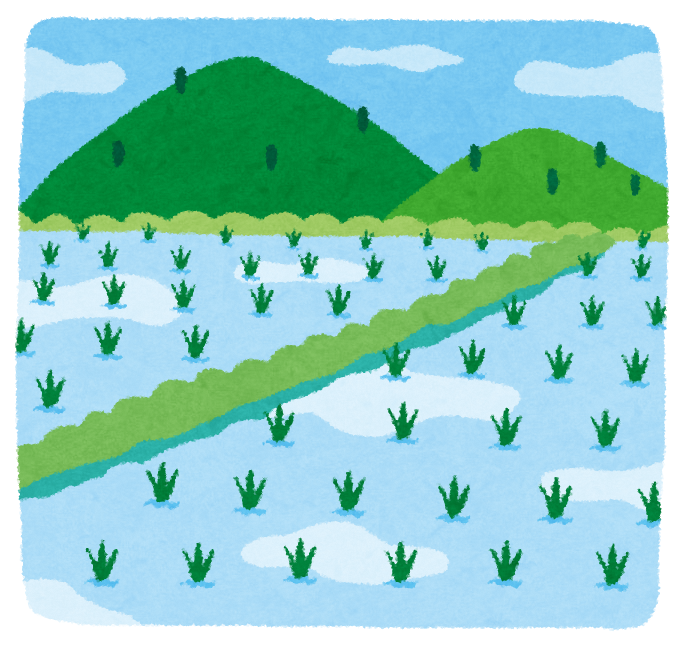目的から探す
ホーム > しごと・産業 > 農林水産業 > 農林事務所 > 県北地域 > 県北農林事務所振興・環境室畜産振興課 > 野生動物からの農作物被害を防ぐ > 2.鳥獣害対策について
ページ番号:46266
更新日:2020年2月2日
ここから本文です。
2.鳥獣害対策について
イノシシをはじめとする鳥獣害への対策についてです。
被害対策の基本的な考え方です。
1.鳥獣害対策の基本
鳥獣害対策の基本は,次の三つが主な柱になります。
1 野生動物の個体管理(地域への侵入を抑える)
2 農作物の被害防除(侵入されても被害が出なくする)
3 野生動物が来ない環境(ひきつける要素を取り除く)
この3つを連携させることが,鳥獣害対策には重要です。

1野生動物の個体管理(地域への侵入を抑える)
野生動物による農作物被害を無くすための方法として,まずはじめに「すべて捕獲して絶滅させる」事を思いつく人は多いと思います。
山からやってくる農作物を荒らす害獣を全て排除してしまえば,そもそも農作物への被害自体が無くなるわけです。
シカとサルは生息している頭数の半分を毎年捕獲していけば,地域にいる頭数はだんだん減っていきます。5割の狩猟圧力で十分な効果が出るわけです。
それに対して,イノシシは高い繁殖力を持っていて,生息している頭数の半分を捕獲しても,次の年には元の数に戻ってしまいます。
捕獲で生息頭数を減らすには,毎年7割以上を捕獲するという,高い狩猟圧力をかける必要があるのです。
しかし,山にいる動物全てが山を下りて農作物を荒らすわけではありません。たまたま山から出てきた個体がそのまま地域に定着し,農作物を荒らすようになるのです。
ですので,山の中にいる野生動物の個体数を減らす個体数の管理と,地域に定着して被害を出している動物の駆除は分けて考える必要があります。
山の中の野生動物の個体数を減らすことができれば,山から地域へ下りてくる個体の数も減ります。
そのうえで,地域に定着した個体への対処が必要になります。
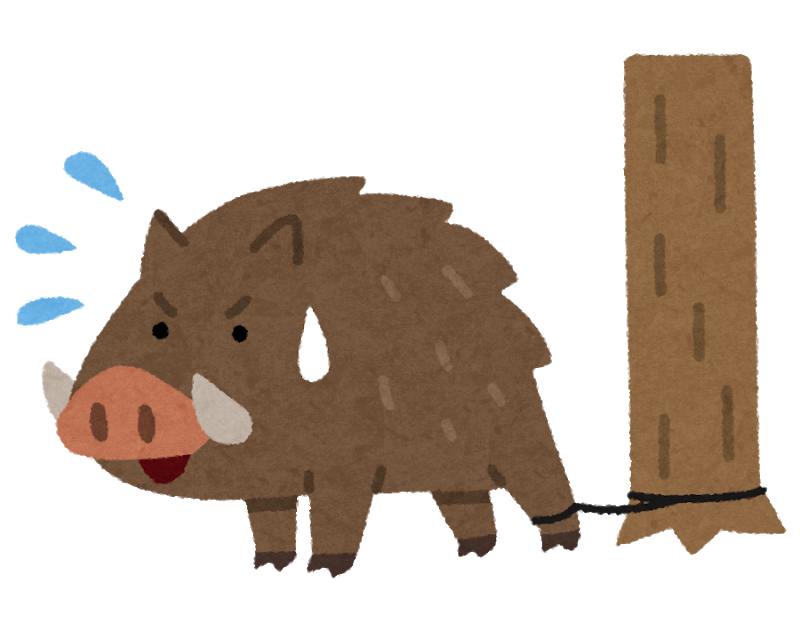
2農作物の被害防除(侵入されても被害が出なくする)
山奥にいるイノシシの個体数管理とは別に,既に地域に入り込んでいるイノシシ等への対策も必要です。
イノシシの行動半径は2km以下なので,だいたいの場合,地域で農作物を荒らしているイノシシと,山の中で暮らしているイノシシは別の個体です。
山と地域を行き来するイノシシというのはまず考えにくく,山奥での個体管理の影響を受けない可能性が高いのです。
結果,地域にいるイノシシを排除しないと,農作物への被害が止まりません。
そこで,まず最初に,電気柵などの防護柵で農地を囲うことから始めます。こうして農作物をイノシシ等から守ります。
電気柵等の防護柵は,正しく運用すれば,高い防護能力を持っているのです。
しかし,イノシシ等が消えてなくなるわけではありません。特に,その地域で生まれ育ったイノシシは,山の中で生活する事がとても難しいので,そのまま地域に留まります。
地域に定着したまま放置すれば,いつかは防護柵の綻びから中に侵入される可能性があります。
そのため,なるべく早くその個体を駆除する必要があります。
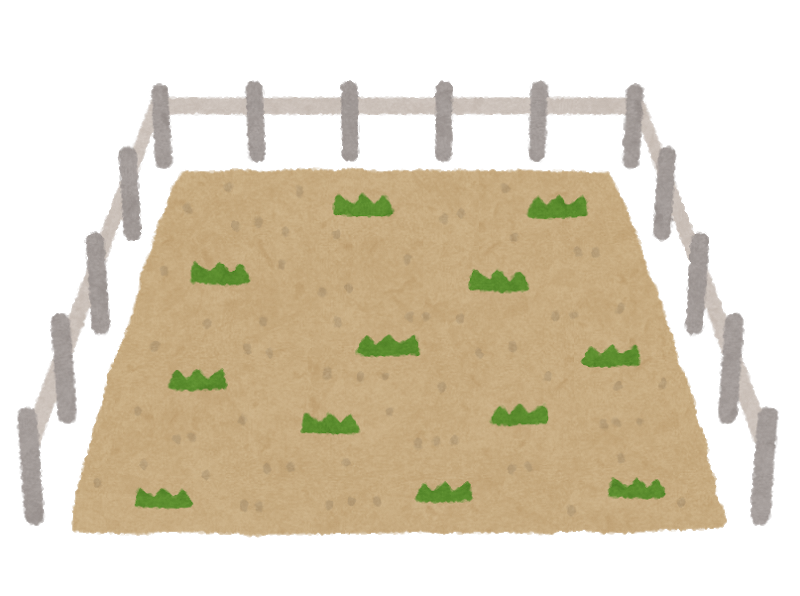
3野生動物が来ない環境(ひきつける要素を取り除く)
イノシシほか野生動物にとって,生きること=エサさがしと言っても過言ではありません。
飼われているイヌやネコは,飼い主のところに行って,ごはんをくれるまでねだったり,勝手に奪って食べたりできますが,野生ではそうはいきません。
生活時間のほぼすべてを使って,食べられるものを探し続けているのです。
地域内の農作業で野菜くずや蔓などの作物残渣が発生しますが,これは野生動物にとっては貴重な食料です。
また,誰も管理していない果樹が実れば実を落とします。こちらも野生動物には大切な食料です。
簡単に見つけられる栄養豊富な食料ですので,それを目当てにやってきます。そして,それ以外の,イノシシ等に食べられると困る作物も食べてしまうのです。
動物には人間の都合などは一切わかりません。食べ物がある=食べる,でしかありません。
地域の中にいるイノシシ等を駆除しても,外から新しい個体がやってきます。
そして,電気柵等の防除柵で農作物への被害を防いでいても,長い間定着されれば,いつかは綻びが生まれます。
そこで,地域の環境を野生動物が生活するには適さない環境にすることで,野生動物が地域に定着するのを妨げるのです。
イノシシが隠れて休息できる藪を刈り払うことで,地域の中でのイノシシの居場所を無くせます。
作物残渣や放置果樹の処理を徹底することで,食べ物を探しに来てもイノシシは食べ物を得られません。
イノシシにとって,探しに来ても何も得られない,居心地の悪い空間にするのです。
こうして,山から下りてきたイノシシが地域へ定着出来ないようにしていきます。

2.イノシシの生息域拡大を防ぐ
地域の環境をイノシシが生活できない環境にしても,そこにいるイノシシが消え去るわけではありません。
山から下りてきたイノシシが再び山に帰っていけばよいのですが,イノシシの行動半径2kmのなかに,他の営農している地域があると,そちらへ移動することがあります。
一番山の奥深い地域でしっかりと対策を行った結果,行き場を失ったイノシシが山を下って他の地域に移り住み,全体を見ると生息域が拡がるケースは珍しくありません。
これらの繰り返しで,山から市街地までイノシシの生息域が拡大してしまったケースもあります。
そこで,移動先の地域でも同様に,イノシシが来ない環境の整備と,移動したイノシシの駆除を行います。
イノシシ対策は単独の地域の対処ではなく,複数の地域が連携していく必要があるのです。
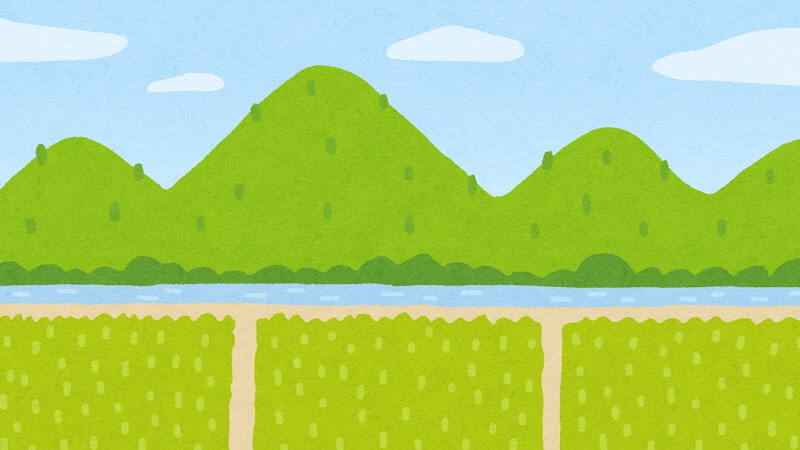
3.関連リンク
埼玉県庁農林部農業技術研究センター生産環境・安全管理研究担当(外部サイト)
イノシシを含むアライグマ,ハクビシン等の中型動物に対応した獣害防止柵「楽落くん」を開発した機関です。他にも多数の防止柵を開発しています。
また,カラス等様々な野生鳥獣について研究も行っています。
ふるさとけものネットワークは,野生動物(けもの)の課題で悩む地域(ふるさと)を対象に、各地で対策支援を行っている団体のネットワーク組織です。
獣害対策の専門機関として、自治体単位での各地の現状や課題を把握し、最適な技術や情報を提供しています。
地域が自立的に対策ができ、それが持続的な里山保全となる、その支援を行っています。