目的から探す
ホーム > しごと・産業 > 農林水産業 > 農林事務所 > 県北地域 > 県北農林事務所振興・環境室畜産振興課 > 野生動物からの農作物被害を防ぐ > 6.中型動物の農作物被害防止柵(略称:楽落くん)について
ページ番号:45502
更新日:2020年3月4日
ここから本文です。
6.中型動物の農作物被害防止柵(略称:楽落(らくらく)くん)について
正しく運用すればイノシシの農地への侵入防止に効果的な電気柵ですが,ハクビシン,アナグマ,アライグマなど,より小型の動物には効果が薄い場合があります。
そこで,埼玉県庁農林部の農業技術研究センターで開発された,イノシシ以外も含めた中型動物の農作物被害防止柵(略称:楽落くん)についてもご紹介します。
埼玉県農林部農業技術研究センター生産環境・安全管理研究担当(外部サイト)
「楽落くん」に関する,よくある疑問について
楽落くんの運用などで寄せられた疑問について,代表的なものをいくつか掲載しています。
まず,5.イノシシよけのための電気柵設置についてで説明した,以下の3つのルールを思い出してください。
- ルール1 設置は一日で完了させる。
- ルール2 隙間は20cm以下にする。
- ルール3 電気は常に流し続ける。
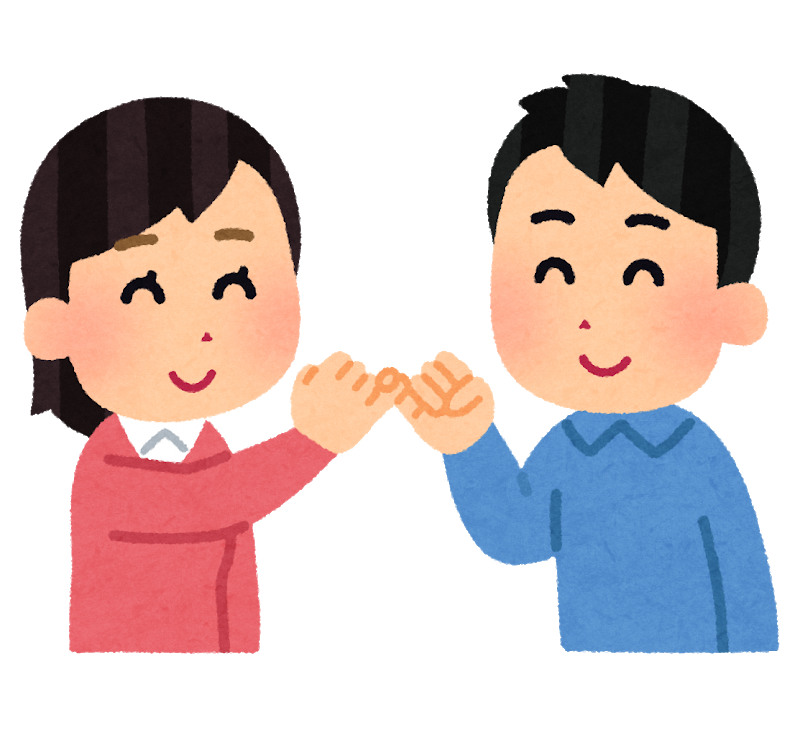
電気が流れていない電気柵に野生動物を触らせない事が一番大切です!
Q:見た感じ簡単に破られそうだけど…
物体を眼で見て,材質や強度などを推測して見抜けるのは基本的に人類くらいです。
普通の動物の視力や視覚では見ただけではそこまで判別できません。
鼻で臭いを嗅ぎ,触れても問題ないと判断してから鼻で押したりし始めます。
逆に言えば,この「鼻で臭いを嗅いで触れても大丈夫かどうか」確認している時が防除の際に一番大事な瞬間です。
鼻で識別している時に感電させて「これは危険だ」と認識させればもう触ろうとしませんし,逆に,鼻で触れて感電しなければ「押しても大丈夫」と判断して,後は鼻先で押し込んで突破を試すだけです。
ですので,「楽落くん」設置マニュアルver2.5(外部サイト)のとおりに正しく設置する必要があるのです。

Q:農地をぐるりと囲うと作業する為のトラクター等が中に入れないんだが
この「楽落くん」は,農作物が最も被害にあう時期のあいだ,野生動物から農作物を守ることを目的に開発されています。
トラクター等大型機械を使って大規模な作業をする時期のあと,収穫期直前から収穫終了までの農作物が被害にあう時期にだけ設置して,収穫が終わったら簡単に片づけられるように作られています。
そのため,扉を作ることは考慮されておらず,農作業の際には跨いで越えて中に入るようになっています。
設置するのは大型機械での作業を行う必要がなくなってから設置してください。
Q:高さが50cmもないけど大丈夫なの?
野生動物が障害物を突破する場合,飛び越えて突破するのは本当に最後の手段です。
飛び越えた先の着地地点が安全とは限らず,もし足を怪我して動けなくなった場合,エサを探せなくなってそのまま飢えて死ぬからです。
野生動物の死因で最も多いのは【餓死】なのです。
ハクビシンが障害物を突破するとき,よじ登り行動から飛び越え行動に切り替える高さが約40cm以上とされています。
また,イノシシ等が障害物を突破するときに,乗越え行動より潜り込み行動を優先するようになる高さも約40cm以上と言われています。
そこで,高さを40cm以下にすることで,「楽落くん」を乗越えたり,よじ登るように誘導しています。
そのためには「楽落くん」のネット部分を必ず地面に接地させて隙間をなくし,「潜り込めない」と認識させることが大切です。
そして,「楽落くん」を上から乗越えようとした時に通電線に触れて,その衝撃で「楽落くんを乗り越えようとするのは危険だ」と学習させるのです。
Q:通電線が一本で大丈夫?ネットの途中に追加で張ったり,ネットの上に張る通電線を二本にしたりした方が安心では?
「楽落くん」を潜るのではなく,上から乗越えるように野生動物を誘導して,「楽落くん」の上端から中に侵入しようとする時に,上端に張られた通電線に触れることで感電させて,「楽落くんを乗り越えようとすると危険だ」と学習させるのが,「楽落くん」の基本構造になります。
地面から上に向かってを鼻先で辿り,ネット部分を越えた所で鼻先が通電線に触れて感電する仕組みですので,ネット部分の途中に通電線を設置したり,「楽落くん」上端に張った通電線のさらに上に通電線を張るのは,通常はそれほど意味がありません。

Q:「楽落くん」のネットや固定用ポールが邪魔で切払機での草刈りがやりにくい。
「楽落くん」のネット部分に雑草が絡んで,漏電防止用の刈払がし辛い,という意見は多く,電気柵対応の防草シートの併用やグランドカバープランツの設置をおすすめしていますが,なにぶん高額です。
そこで,固定用のポール周りだけでも雑草が生えてくるのを抑える方法があります。
固定用のポールを刺す時に,10cm四方程度の段ボールを敷き,そこを貫く形でポールを固定する方法です。
段ボールが簡易の防草シートとして,固定用のポールの周りの地面を覆い,雑草が生えてくるのを抑えます。
段ボールは農作物の収穫後に「楽落くん」を撤去する際に回収して処分してください。
また,電気柵非対応の防草シートでも,内側に部分限定して設置することで,内側の草刈りを減らすことができます。