目的から探す
ホーム > しごと・産業 > 農林水産業 > 農林事務所 > 県北地域 > 県北農林事務所振興・環境室畜産振興課 > 野生動物からの農作物被害を防ぐ > 1.イノシシの生態について
ページ番号:45884
更新日:2020年4月1日
ここから本文です。
1,イノシシの生態について
「子だくさん」など,様々なイメージがイノシシにはついていると思います。
あんがい知られていないイノシシの生態についてです。
1イノシシはどんな環境にいる生き物なのか
イノシシは誤解されやすいのですが,もともと昼行性,つまり人間と同様に太陽の出ている時間帯を生活時間にしている動物です。
「夜しか見ないじゃないか」という人もたくさんいると思いますが,じつは,とても臆病な動物なので,人間に姿を見られない夜に行動様式を変えているだけなのです。
そのため,人間に慣れて警戒心の減ったイノシシは,日中でも姿を見せるようになります。
また,現在のイノシシは山奥に住んでいる生き物ですが,元々は平地の生き物でした。江戸時代の文献などでは,さほど山深くない平地に住んでいるイノシシを狩る記述があったりします。
人間がどんどん生息域を拡げ,山の方へ進出するのに合わせて,イノシシもじりじりと山へ生息域を移していったのです。
ほかにも,イノシシは決まった縄張りというのを持ちません。だいたい2キロメートルの範囲の中で毎日あちこちの地面を掘り返してエサを探す暮らしをしています。
その範囲の中で,安全でお気に入りの場所を寝屋にしています。寝屋は何カ所かあって,その時々で使い分けています。
でも,狩猟の際に猟犬に吠えたてられると1週間以上帰ってこないくらい,簡単に暮らす場所を変えます。
縄張りの取り合いというのもしません。雄同士で喧嘩しているのは,だいたい雌を取り合っているときくらいです。
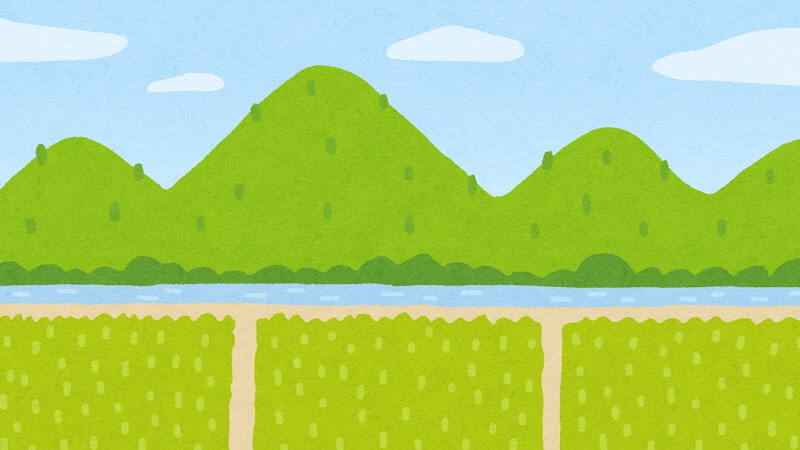
2イノシシは多産なのか
イノシシは子だくさん,というイメージがあります。
イノシシは年に一度,春か秋に妊娠して,一度の出産で4頭前後の子供を産みます。そして,その半数ほどが1歳になる前に飢え等で死にます。
イノシシは春と秋,2回出産すると言う話もよく聞かれますが,春と秋に妊娠のチャンスがある,と言うことであって,時期が来ても子育てが終わるまでは子供を作りません。
春(または秋)に子供を作れなかったり,子供が全て死に絶えた場合に,次の時期に子供を作る場合があります。
(母親と子供を識別しないで捕獲する,括りわなを使わない狩猟者が少なくないのはこのためです。子供を先に捕獲してしまうと,子供を亡くした母親はすぐに妊娠できる状態になります)
最近のイノシシは逃げたブタと交雑してイノブタ化が進み,多産化しているというお話をよく聞きます。
そこで,捕獲したイノシシのDNA調査が行われましたが,イノブタ化はほとんど確認できませんでした。
また,野生の環境で一度に出産できるのは,ブタもイノシシと差はなく,基本的に4頭前後でした。一年後の生存率も同じです。
記録上,6頭以上の子供を産んだブタやイノシシがいますが,あくまでごく稀なケースです。
ブタが多産なのと,子供を出産しても即妊娠するというのは,人間が飼育・管理しているからです。出産したブタから人間が子供を全て引き離すと,すぐに妊娠できる状態になります。
しかし,実際に10頭前後の子供を連れた母親が,たびたび目撃されています。
これは,血縁関係のある複数の親子連れが集団を作り,子供たちをまとめて,母親たちが交替で世話をしているからです。
ですので,10頭前後の子供を連れた母親の周りには,その母親に子供を預けている別の母親達が隠れている可能性が非常に高いのです。

3イノシシは全部駆除できるのか
「イノシシは最終的に全て狩り尽くしてしまえばよいのだ」と言う人がいます。
じつは,これはとても大変なことです。
イノシシは年に4頭ほど子供を産み,そのうち2頭が生き延びて成獣になります。
そして,その親子がまた子供を産み…を繰り返して増えていきます。
サルとシカに関しては,毎年,その地域にいる頭数の半分を駆除すれば,確実に数を減らすことができます。
しかし,イノシシの場合は,毎年7割以上の駆除を続けて,はじめて数が減り始めるのです。
もちろん,狩猟者の人たちが頑張って捕獲してくれていますが,人間が捕獲する数より,イノシシが増える数が勝っているのが現状です。
狩りガールをはじめ,狩猟に興味を持ってくれる人たちが増えて欲しいところです。

4撃退グッズは効果があるのか
音や匂い,光でイノシシを撃退するようなグッズがたくさんありますが,長期間使用していると必ず慣れてしまいます。
イノシシは特定の音に弱い,とか,特定の光は苦手,といったようなことはなく,見知らぬ音や匂い等を警戒しているだけです。
臆病ですが学習能力の高いイノシシは,撃退グッズに対して,突然自分の住んでいる環境に現れた異常な物体を警戒して近寄りません。でも,時間があればその異常な物体に害がないと見破ります。
捕食者であるオオカミの尿を使ってマーキングしても,時間が経過すれば慣れてしまいます。
慣れてしまうと「撃退グッズがある=そこに食べ物がある」と憶えてしまい,逆に目印としてやってくるようになります。
また,イノシシが嫌がる作物というものもありません。
よく,「シソを植えるとイノシシは近寄らない」等と言われていますが,単にシソを食べ物と認識しないで無視しているだけです。

5イノシシは,上から入る?下から入る?
イノシシは障害物に対しては飛び越えるより下を潜る方を選びます。
ペットのイヌやネコが気楽に飛び越えるのを見て,これくらいの高さならイノシシも飛び越えるのでは?と言うような高さのフェンスでも,イノシシは飛び越えません。
跳躍力が不足している訳ではありません。イノシシは1mを超える跳躍力を持っています。でも,なるべく跳ぶことを避けています。
イヌやネコが割と簡単に跳び越えるのは,人間の作ったものに慣れているからですが,野生のイノシシはそうはいきません。
跳び越えて着地したところが安全でなく,ケガをして動けなくなった場合,エサが探せなくなります。そうなれば残るは餓死です。
そこで,イノシシは脚が怪我をするような状況を出来る限り避けます。間伐材を3本束ねて転がしておくと,足元が不安定になるのを嫌って避けて歩くほどです。
結果,ほとんどの場合に障害物を下から潜ります。隙間が無ければ持ち上げたり,地面を掘ったり,下へ侵入する為の隙間を作ろうとします。そして隙間をこじ開けて潜り込みます。
人間が見て,どう見ても不合理に見える状況でも,頑なに跳ぼうとしません。
では,何故「イノシシが上から飛び込む」というイメージが付いているのでしょうか。
基本的にイノシシは下から潜り込みます。たとえ,ちょっと軽くジャンプすれば越えられるような柵でも,着地して怪我をする危険は冒しません。
しかし,これに生命の危機が関われば別です。悠長に潜り込んで追いつかれるより,危険を覚悟して飛び越える方を選ぶことがあります。
柵で覆われた農地の中にイノシシがいるのを見た場合,農家の人はまず間違いなく声を荒げて追い払おうとします。
結果,生命の危機を感じたイノシシは,慌てて逃げるのに「柵を飛び越える」と言う選択をします。
そして,そうやって柵を飛び越えて逃げるイノシシをみて『柵を飛び越えて外に出た』=『中に入る時も飛び越えたに違いない』と印象付けられるのです。
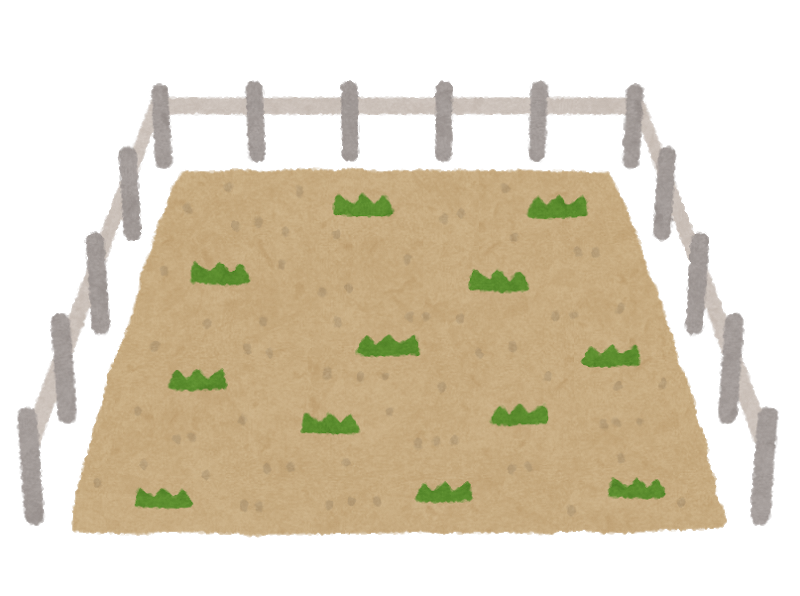
6イノシシの住む島
イノシシの鼻は臭いの内容の識別は得意です。でも,何キロも先の匂いを嗅ぎつける能力はありません。
遠くから匂いだけでエサを見つけられないので,一日中地面の匂いを嗅ぎ,土を掘り返したり,石をひっくり返したりしてエサを探しています。
『匂いを頼りに何キロも先の島まで泳いで移住した』という話がありますが,海を越えた島の匂いを嗅ぎあてたりはできません。
イノシシ狩りで追われたイノシシが,最後の手段として海に飛び込み,偶然泳ぎ着いた結果であり,そこを目指して海に入ったわけではありません。
イノシシは自ら水に入るのは好みませんが,それでも泳ぐのは上手です。
イノシシ狩りの時期は毎年一緒なので,海流の流れもほぼ同じになります。結果として,海に逃れて潮に流された際に,たまたま泳ぎ着ける島も限定されてきます。
そして,特定の島にイノシシが何頭も住んでいるのを見た人たちが「イノシシがこの島を目指して泳いで来た」と後付けで意味を持たせているのです。

7イノシシに出会ったら
イノシシに出会った場合,慌てないでください。
イノシシに逢って驚いている人間以上に,人間に逢ったイノシシは驚いて慌てています。
まず,道路の端に寄って道を開けて下さい。よほど錯乱していなければイノシシはそのまま山に向かって走り去ります。
また,イノシシの視力は0.1程度で,色の区別も青色しかわかりませんので,電柱や壁,樹木等に密着すると人間の見分けが付きにくいのです。
イノシシはとても臆病なので,わざわざ人間に喧嘩を売ってきたりはしません。一刻も早く,安全な所まで逃げようとします。
人間の側が気づくのが遅れたり,パニックに陥った結果,逃げ道を塞ぐ形になってイノシシの攻撃を受ける場合が多いのです。
注 猟などで手負いのイノシシの場合は,パニックを起こしていたりして行動を予測するのが難しくなります。