目的から探す
ホーム > 県政情報 > 県の概要 > いばらき統計情報ネットワーク > いばらき統計情報ネットワーク(統計課) > 分野別≪社会生活≫ > 平成18年社会生活基本調査結果-茨城県民の生活時間と生活行動-
ページ番号:12802
更新日:2015年4月1日
ここから本文です。
平成18年社会生活基本調査結果-茨城県民の生活時間と生活行動-
目次
調査の概要
用語と分類
結果の概要
統計表
調査の概要
1.調査の目的
社会生活基本調査は,国民の生活時間の配分及び自由時間等における主な活動(「インターネットの利用」,「学習・研究」,「スポーツ」,「趣味・娯楽」,「ボランティア活動」及び「旅行・行楽」)について調査し,国民の社会生活の実態を明らかにすることにより,各種行政施策の基礎資料を得ることを目的とするものである。
この調査は,昭和51年の第1回調査以来5年ごとに実施され,今回の調査は7回目に当たる。
なお,前回(平成13年)調査より,生活時間についての詳細な結果を得るために,「調査票A」及び「調査票B」の2種類の調査票を用いて調査している。
2.調査の法的根拠
社会生活基本調査は,統計法(昭和22年法律第18号)に基づく指定統計調査(指定統計第114号を作成するための調査)として,「社会生活基本調査規則」(昭和56年総理府令第38号)に基づいて実施した。
3.調査の範囲
(1)調査の地域
平成12年国勢調査の調査区から,総務大臣の指定する6,696調査区(本県128調査区)において調査を行った。このうち,「調査票A」を用いた調査区は6,344調査区(本県120調査区),「調査票B」を用いた調査区は352調査区(本県8調査区)である。
(2)調査の対象
指定調査区の中から選定した約8万世帯(本県約1500世帯)にふだん住んでいる10歳以上の世帯員を対象とした。
ただし,次の者は調査の対象から除いた。
- ア.外国の外交団,領事団(家族,随員及び随員の家族を含む。)
- イ.外国軍隊の軍人,軍属の構成員(家族を含む。)
- ウ.自衛隊の営舎内又は艦船内の居住者
- エ.刑務所,拘置所の被収容者
- オ.少年院,婦人補導院の在院者
- カ.社会福祉施設の入所者
- キ.病院,療養所等の入院患者
- ク.水上に住居を有する者
4.調査の期日
調査は,平成18年10月20日現在で行った。
ただし,生活時間については,10月14日から10月22日までの9日間のうち,調査区ごとに指定した連続する2日間について調査した。
5.調査事項(調査票A)
(1)すべての世帯員に関する事項
- ア.出生の年月又は年齢
- イ.世帯主との続柄
- ウ.在学,卒業等教育又は保育の状況
(2)10歳以上の世帯員に関する事項
- ア.氏名
- イ.男女の別
- ウ.配偶の関係
- エ.介護の状況
- オ.携帯電話,パーソナルコンピュータその他の情報通信に関連する機器の使用の状況
- カ.インターネットの利用の状況
- キ.学習・研究活動の状況
- ク.ボランティア活動の状況
- ケ.スポーツ活動の状況
- コ.趣味・娯楽活動の状況
- サ.旅行・行楽の状況
- シ.生活時間の配分及び天候
(3)15歳以上の世帯員に関する事項
- ア.就業状態
- イ.就業希望の状況
- ウ.仕事の種類
- エ.従業上の地位
- オ.所属の企業全体の従業者数
- カ.ふだんの1週間の就業時間
- キ.通勤時間
- ク.週休制度
- ケ.連続した休暇の取得の状況
(4)60歳以上の世帯員に関する事項
子の住居の所在地
(5)世帯に関する事項
- ア.世帯の種類
- イ.世帯の年間収入
- ウ.住居の種類
- エ.居住室の数
- オ.自家用車の所有の状況
- カ.介護支援の利用の状況
- キ.不在者の有無
6.集計の概要
<調査票Aに係る集計>
(1)生活行動に関する結果
1)全国結果
- ア.「インターネットの利用」,「学習・研究」,「スポーツ」,「趣味・娯楽」,「ボランティア活動」及び「旅行・行楽」の調査項目ごとに,個人属性及び世帯属性別の行動者数,行動者率及び平均行動日数(「旅行・行楽」を除く。)を集計した。
- イ.基本的な個人属性について,それぞれの種目ごとに,行動の頻度,共にした人(一部の種目のみ)等別の行動者数及び行動者率を集計した。
2)地域別結果
全国結果に準じた内容について,全国,全国人口集中地区・以外,都道府県・都道府県人口集中地区・以外,14地域,8大都市圏及び都市階級別に集計した。
(2)生活時間に関する結果
1)全国結果
個人属性及び世帯属性別に,曜日,行動の種類別の総平均時間,行動者平均時間及び行動者率を集計した。
2)地域別結果
上記(1)の2)に同じ
(3)時間帯に関する結果
個人属性及び世帯属性別に,曜日,15分刻みの時間帯別の行動の種類別行動者率を集計した。
主要結果については,全国のほかに,全国人口集中地区・以外,都道府県,都道府県人口集中地区・以外,14地域,8大都市圏及び都市階級別に集計した。
(4)平均時刻に関する結果
個人属性及び世帯属性別に,曜日別の起床,朝食開始,夕食開始,就寝,出勤,仕事からの帰宅の時刻別行動者数(構成比),平均時刻及び行動者率を集計した。主要結果については,全国のほかに,全国人口集中地区・以外,都道府県及び3大都市圏別に集計した。
<調査票Bに係る集計>
(1)生活時間に関する結果
個人属性及び世帯属性別に,曜日,行動の種類(主行動,主行動・同時行動)別の総平均時間,行動者平均時間及び行動者率を集計する。
なお,集計は全国のみとする。
(2)時間帯に関する結果
個人属性及び世帯属性別に,曜日,15分刻みの時間帯別の行動の種類(主行動,主行動・同時行動)別行動者率を集計する。
なお,集計は全国のみとする。
7.結果の公表
<調査票Aに係る集計>
(1)生活行動に関する結果
平成19年7月9日公表
(2)生活時間,時間帯及び平均時刻に関する結果
平成19年9月28日公表
<調査票Bに係る集計>
平成19年12月21日公表
用語と分類
(生活時間)
1.行動の種類
1日の行動を20種類に分類し,時間帯(15分単位)別の行動状況(同時に2種類以上の行動をした場合は,主なもの一つ)を調査した。
20種類の行動は大きく3つの活動にまとめ,1次活動(睡眠,食事など生理的に必要な活動),2次活動(仕事,家事など社会生活を営む上で義務的な性格の強い活動)及び3次活動(1次活動,2次活動以外で各人が自由に使える時間における活動)とした。
1次活動
睡眠
身の回りの用事
食事
2次活動
通勤・通学
仕事(収入を伴う仕事)
学業(学生が学校の授業やそれに関連して行う学習活動)
家事
介護・看護
育児
買い物
3次活動
移動(通勤・通学を除く)
テレビ・ラジオ・新聞・雑誌
休養・くつろぎ
学習・研究(学業以外)
趣味・娯楽
スポーツ
ボランティア活動・社会参加活動
交際・付き合い
受診・療養
その他
また,必要に応じ次の区分を用いた。
家事関連
家事,介護・看護,育児及び買い物
休養等自由時間活動
テレビ・ラジオ・新聞・雑誌及び休養・くつろぎ
積極的自由時間活動
学習・研究(学業以外),趣味・娯楽,スポーツ及びボランティア活動・社会参加活動
仕事等
通勤・通学,仕事及び学業
2.一緒にいた人
時間帯(15分単位)別に「一緒にいた人」の状態を次の4区分で調査した。なお,睡眠の時間帯については,「一人で」として集計している。
- 一人で
- 家族
- 学校・職場の人
- その他の人
3.平均時間
行動の種類別平均時間は,一人1日当たりの平均行動時間数で,次の種類がある。
総平均
該当する種類の行動をしなかった人を含む全員についての平均
行動者平均
該当する種類の行動をした人のみについての平均
曜日別平均
調査の曜日ごとに平均値を算出したもの。平日平均(月曜日~金曜日の平均値),月曜日~日曜日平均がある。
週全体平均
次の式により曜日別結果を平均して算出した。
![]()
ただし,ある曜日に当該属性を持つ客体が存在しない場合は以下のとおり算出した。
- 週全体の総平均時間
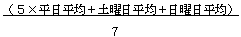
- 週全体の行動者平均時間
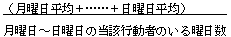
4.平均時刻
連続する2日間の時間帯別の行動の状況から,主な行動の開始又は終了時刻を1日目の午前0時からの経過時間数とし,次の式により平均時刻を算出した。なお,結果表章に用いている曜日は1日目の曜日である。
![]()
各行動の開始又は終了時刻は,次のとおりとした。
起床時刻
12時前に始まり,60分を超えて続く最初の睡眠の終了時刻。なお,睡眠と睡眠の間の睡眠以外の行動が30分以内の場合は睡眠が続いているとした。
朝食開始時刻
4時以降,11時前に始まる最初の食事開始時刻
夕食開始時刻
16時以降,24時(翌日0時)前に始まる最初の食事開始時刻
就寝時刻
17時以降,36時(翌日12時)前に始まり,60分を超えて続く睡眠の開始時刻。
該当の睡眠が2行動以上ある場合は,睡眠継続時間が最長の睡眠(継続時間が同じ場合は,早く現れる方の睡眠)の開始時刻とした。
また,睡眠と睡眠の間の睡眠以外の行動が30分以内の場合は,睡眠が続いているとした。
なお,平成13年の特別集計においては17時以降,28時(翌日4時)前に始まる睡眠の開始時刻とし,該当の睡眠が2行動以上の場合は睡眠継続時間の長短に関わらず,後から現れる睡眠の開始時刻とした。
出勤時刻
0時15分以降,24時(翌日0時)前に始まる最初の仕事の前にある通勤・通学の開始時刻。最初の仕事の前に通勤・通学がなく,他の仕事の前に通勤・通学がある場合は,その次に現れる仕事の前の通勤・通学の開始時刻とし,他の仕事の前にも通勤・通学がない場合は最初の仕事の開始時刻とした。
仕事からの帰宅時刻
0時15分以降,24時(翌日0時)前に始まる最後の仕事の後にある通勤・通学の終了時刻。最後の仕事の後に通勤・通学がなく,それ以前に現れる仕事の後に通勤・通学がある場合は,それ以前に現れる仕事の後の通勤・通学の終了時刻とし,他の仕事の後にも通勤・通学がない場合は最後の仕事の終了時刻とした。
また,最後の仕事の後に通勤・通学はないが,仕事の前に通勤・通学があり,かつそれ以前の仕事の後にも通勤・通学がある場合は,変則勤務又は複数の仕事に従事しているとみなし,仕事からの帰宅時刻は不詳とした。
(生活行動)
1.過去1年間に行った活動
この調査では,「インターネットの利用」,「学習・研究」,「スポーツ」,「趣味・娯楽」,「ボランティア活動」及び「旅行・行楽」について,過去1年間の活動状況をそれぞれの種類別に「行ったか否か」,また,行った場合には,1年間の活動の「頻度」や「目的」,「方法」,「共にした人」などを調査した。
(1)インターネットの利用
仕事や学業などで利用した場合は除く。「インターネットの利用」については,利用の内容により次の7種類に区分し調査した。
- 電子メール
- 掲示板・チャット
- ホームページ,ブログの開設・更新
- 情報検索及びニュース等の情報入手
- 画像・動画・音楽データ,ソフトウエアの入手
- 商品やサービスの予約・購入,支払いなどの利用(ショッピング,バンキング,チケット予約,株取引など)
- その他(クイズや懸賞の応募,アンケート回答,読書,オンラインゲームなど)
(2)学習・研究
個人の自由時間の中で行う学習や研究をいう。社会人の職場研修や,児童・生徒・学生が学業(授業,予習,復習)として行うものは除き,クラブ活動や部活動は含む。「学習・研究」については,その内容を基に次の9種類に分類し調査した。
- 英語
- 英語以外の外国語
- パソコンなどの情報処理
- 商業実務・ビジネス関係
- 介護関係
- 家政・家事(料理・裁縫・家庭経営など)
- 人文・社会・自然科学(歴史・経済・数学・生物など)
- 芸術・文化
- その他
(3)スポーツ
余暇活動として行うスポーツをいう。なお,職業スポーツ選手が仕事として行うものや,学生が体育の授業で行うものは除き,クラブ活動や部活動は含む。スポーツは,次の22種類に分類し調査した。
- 野球(キャッチボールを含む)
- ソフトボール
- バレーボール
- バスケットボール
- サッカー
- 卓球
- テニス
- バドミントン
- ゴルフ(練習場を含む)
- 柔道
- 剣道
- ゲートボール
- ボウリング
- つり
- 水泳
- スキー・スノーボード
- 登山・ハイキング
- サイクリング
- ジョギング・マラソン
- ウォーキング・軽い体操
- 器具を使ったトレーニング
- その他のスポーツ
(4)趣味・娯楽
仕事,学業,家事などのように義務的に行う活動ではなく,個人の自由時間の中で行うものをいう。趣味・娯楽は,次の34種類に分類し調査した。
- スポーツ観覧(テレビ・DVDなどは除く)
- 美術鑑賞(テレビ・DVDなどは除く)
- 演芸・演劇・舞踊鑑賞(テレビ・DVDなどは除く)
- 映画鑑賞(テレビ・ビデオ・DVDなどは除く)
- 音楽会などによるクラシック音楽鑑賞
- 音楽会などによるポピュラー音楽・歌謡曲鑑賞
- CD・テープ・レコードなどによる音楽鑑賞
- DVD・ビデオなどによる映画鑑賞(テレビからの録画は除く)
- 楽器の演奏・邦楽(民謡,日本古来の音楽を含む)
- コーラス・声楽
- 邦舞・おどり
- 洋舞・社交ダンス
- 書道
- 華道
- 茶道
- 和裁・洋裁
- 編み物・手芸
- 趣味としての料理・菓子作り
- 園芸・庭いじり・ガーデニング
- 日曜大工
- 絵画・彫刻の制作
- 陶芸・工芸
- 写真の撮影・プリント
- 詩・和歌・俳句・小説などの創作
- 趣味としての読書
- 囲碁
- 将棋
- パチンコ
- カラオケ
- テレビゲーム,パソコンゲーム(家庭で行うもの,携帯用を含む)
- 遊園地,動植物園,水族館などの見物
- キャンプ
- その他の趣味・娯楽
(5)ボランティア活動
報酬を目的としないで,自分の労力,技術,時間を提供して地域社会や個人・団体の福祉のために行っている活動をいう。「ボランティア活動」については,対象や目的を基に次の11種類に分類し調査した。
- 健康や医療サービスに関係した活動(献血,入院患者の話し相手,安全な食品を広めることなど)
- 高齢者を対象とした活動(高齢者の日常生活の手助け,高齢者とのレクリエーションなど)
- 障害者を対象とした活動(手話,点訳,朗読,障害者の社会参加の協力など)
- 子供を対象とした活動(子供会の世話,子育て支援ボランティア,いじめ電話相談など)
- スポーツ・文化・芸術・学術に関係した活動(スポーツを教えること,日本古来の文化を広めること,美術館ガイド,講演会・シンポジウム等の開催など)
- まちづくりのための活動(道路や公園等の清掃,花いっぱい運動,まちおこしなど)
- 安全な生活のための活動(防災活動,防犯活動,交通安全運動など)
- 自然や環境を守るための活動(野鳥の観察と保護,森林や緑を守る活動,リサイクル運動,ゴミを減らす活動など)
- 災害に関係した活動(災害を受けた人に食べものや着るものを送ること,炊き出しなど)
- 国際協力に関係した活動(海外支援協力,難民支援,日本にいる外国人への支援活動など)
- その他(人権を守るための活動,平和のための活動など)
(6)旅行・行楽
旅行は,1泊2日以上にわたって行うすべての旅行をいい,日帰りの旅行を除く。行楽は,日常生活圏を離れ,半日以上かけて行う日帰りのものをいい,夜行日帰りを含む。
「旅行・行楽」については,国内・海外及び旅行目的を基に次の6種類に分類し調査した。
- 行楽(半日以上の日帰りをいい,夜行日帰りも含む)
- 国内観光旅行(レクリエーション・スポーツなどのための旅行を含む)
- 国内帰省・訪問などの旅行
- 国内業務出張・研修・その他
- 海外観光旅行(レクリエーション・スポーツなどのための旅行を含む)
- 海外業務出張・研修・その他
2.行動者数,行動者率,平均行動日数
(1)行動者数
過去1年間に該当する種類の活動を行った人(10歳以上)の数。なお,数値は母集団における行動者数の推定値である。
(2)行動者率
各属性における行動者数の10歳以上人口に占める割合。次の式により算出した。
行動者率=行動者数÷各属性の10歳以上人口×100(%)
(3)平均行動日数
行動者について平均した過去1年間の行動日数。各行動の「総数」及び「その他」を除く種類ごとに,頻度別の行動者数に基づき,次の式により算出した(「旅行・行楽」は除く。)。
平均行動日数=
![]()
なお,各頻度階級の中央値は次の値とした。
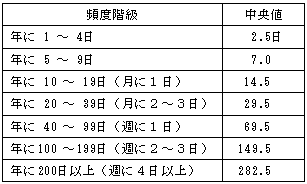
結果の概要
第1.生活時間
1.1日の生活時間の配分
(1)概観
1)2次活動時間は増加,3次活動時間は減少
本県に住んでいる10歳以上の人について,1日の生活時間(週全体平均。以下「週全体」という。)をみると,1次活動時間が10時間43分,2次活動時間が6時間58分,3次活動時間が6時間20分となっている。
平成13年と比べると,1次活動時間は1分の増加とほぼ横ばい,2次活動時間は3分の増加,3次活動時間は3分の減少となっている。(表1-1)
2)1次活動時間の男女差が拡大,2次及び3次活動時間では縮小
生活時間を男女別にみると,男性は1次活動時間が10時間33分,2次活動時間が7時間,3次活動時間が6時間27分,女性は1次活動時間が10時間53分,2次活動時間が6時間55分,3次活動時間が6時間13分となっており,1次活動は女性が長く,2次及び3次活動は男性が長くなっている。
平成13年と比べると,男性は1次活動時間が10分の減少,2次活動時間が23分の増加,3次活動時間が13分の減少,女性は1次活動時間が11分の増加,2次活動時間が17分の減少,3次活動時間が7分の増加となっている。
生活時間の男女差を平成13年と比べると,1次活動時間は1分差が20分差に,2次活動時間は35分差が5分差に,3次活動時間は34分差が14分差になっており,1次活動時間では男女差が拡大したが2次及び3次活動時間では縮小している。(表1-1)
3)平日及び日曜日で2次活動時間が増加,3次活動時間が減少
生活時間を曜日別にみると,平日は1次活動時間が10時間31分,2次活動時間が7時間52分,3次活動時間が5時間37分,土曜日は1次活動時間が10時間57分,2次活動時間が5時間10分,3次活動時間が7時間53分,日曜日は1次活動時間が11時間28分,2次活動時間が4時間11分,3次活動時間が8時間21分となっており,1次及び3次活動時間は日曜日が最も長く,2次活動時間は平日が最も長くなっている。
平成13年と比ぺると,平日及び日曜日は1次活動時間がほぼ横ばい,2次活動時間が増加3次活動時間が減少している。土曜日は1次及び3次活動時間が増加,2次活動時間が減少している。(表1-2)
4)減少が続いていた2次活動時間が平成18年は増加
全国と本県で過去20年間の生活時間の推移を,比較可能な年齢区分である15歳以上の人についてみると,1次活動時間は全国が増加傾向であるのに対し本県は平成8年以降横ばいであり,2次活動時間は全国,本県とも平成13年までは減少傾向であったが18年は増加に転じ,3次活動時間は全国,本県とも平成13年までは増加が続いていたが18年は減少に転じた。(表1-3)
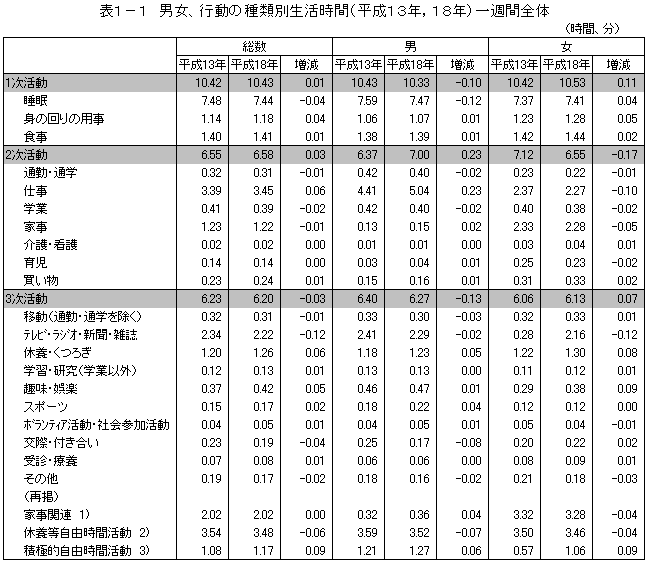
1)家事,介護・看護,育児及び買い物
2)テレビ・ラジオ・新聞・雑誌及び休養・くつろぎ
3)学習・研究(学業以外),趣味・娯楽,スポーツ及びポランテイア活動・社会参加活動
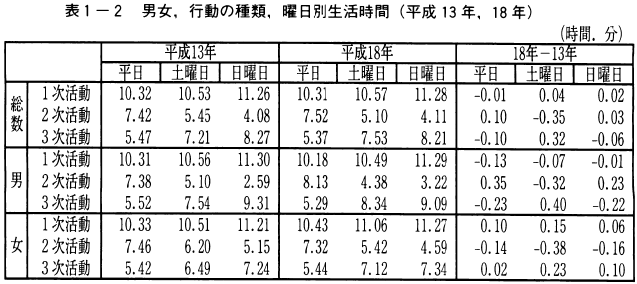
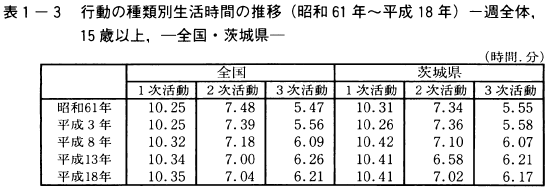
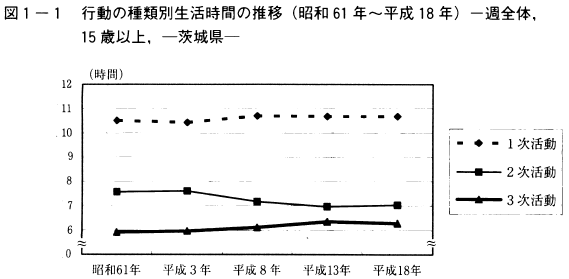
(2)年齢階級別にみる生活時間
1)2次活動時間は女性の35~44歳が最も長い
年齢階級別に生活時間をみると,1次活動時間は,男女とも45~54歳が最も短〈(男性9時間59分,女性9時間50分),75歳以上で最も長くなっている。
2次活動時間は,男性は25歳以上55歳未満の年齢階級で8時間以上であり,45~54歳(8時間39分)が最も長く,女性は35~44歳及び45~54歳で8時間以上であり,35~44歳(8時間43分)が最も長くなっている。
3次活動時間は,男性は45~54歳(5時間22分),女性は35~44歳(5時間16分)が最も短く,男女とも75歳以上で最も長くなっている。(表1-4,図1-2)
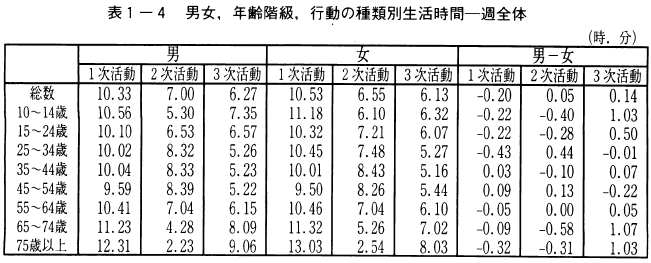
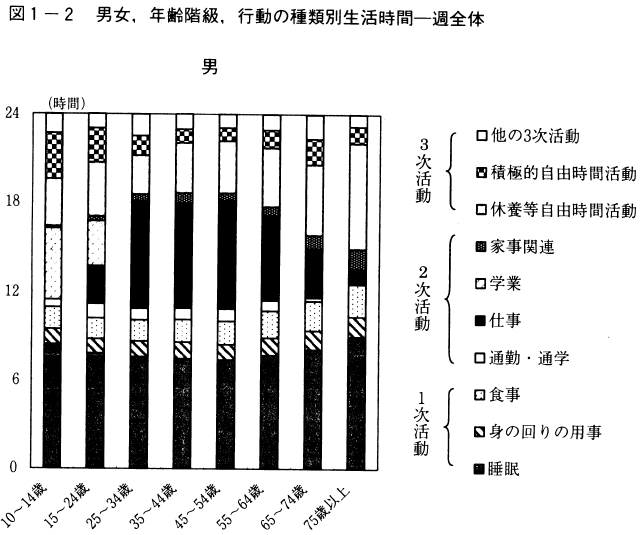
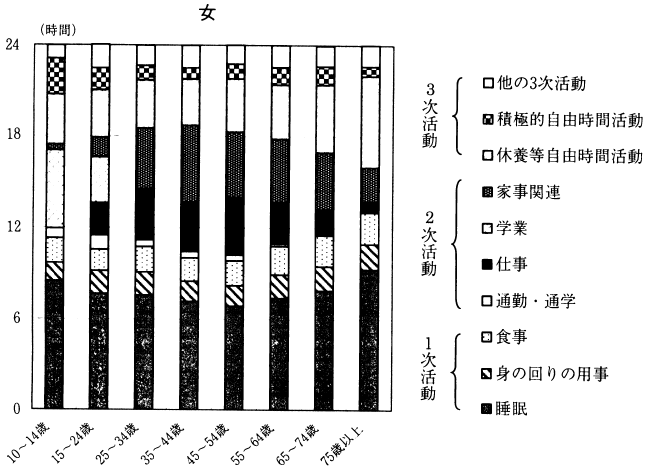
2)男性のすべての年齢階級で2次活動時間が増加
15歳以上の人の生活時間を平成13年と比べると,1次活動時間は,男性は11分の減少,女性は11分の増加となっている。年齢階級別にみると,男性はすべての年齢階級で減少,女性は15歳以上45歳未満の年齢階級と75歳以上で増加,45歳以上75歳未満の年齢階級で減少している。
2次活動時間は,男性は27分の増加,女性は19分の減少となっている。年齢階級別にみると,男性はすべての年齢階級で増加,女性は15歳以上55歳未満の年齢階級で減少,55歳以上の年齢階級で増加している。
3次活動時間は,男性は16分の減少,女性は9分の増加となっている。年齢階級別にみると,男性は35~44歳の年齢階級を除くすべての年齢階級で減少,女性は15歳以上65歳未満の年齢階級で増加,65歳以上の年齢階級で減少している。(図1-3)


(3)時間帯別にみる行動者率
平日に3次活動の行動者率が5割を超えるのは20時から22時までの間
行動者率(人口に占める行動者数の割合)を曜日,時間帯別にみると,3次活動の行動者率が5割を超えるのは,平日では20時から22時までの間,土曜日は13時30分から17時30分までの間及び19時30分から22時30分までの間,日曜日は10時から11時45分までの間,13時から18時までの間及び19時30分から22時までの間となっている。(図1-4)
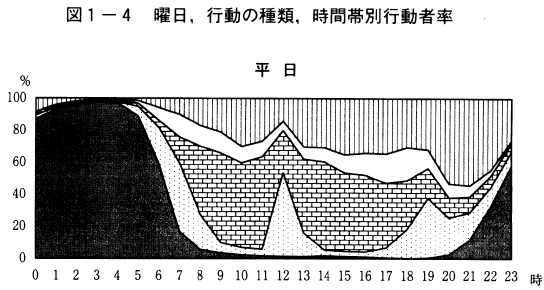
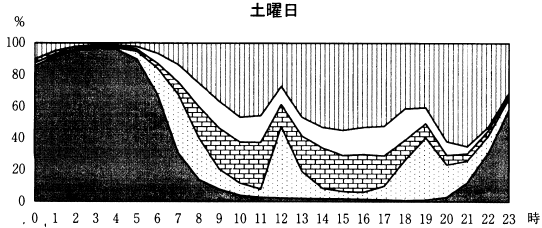
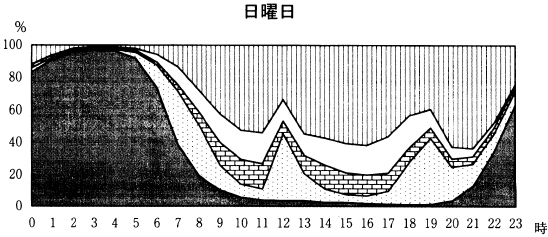
![]()
2.1次活動
(1)睡眠
1)45~54歳で最も短い睡眠時間
睡眠時間は7時間44分で,男性は7時間47分,女性は7時間41分と男性が6分長くなっている。年齢階級別にみると45~54歳が7時間8分と最も短く,次いで35~44歳が7時間19分であり,75歳以上が9時間10分と最も長くなっている。
これを男女別にみると,75歳以上を除くすべての年齢階級で男性が長く,特に35歳以上75歳未満の年齢階級で女性より10分以上長くなっている。(図2-1,表2-1)
2)男性のすべての年齢階級で睡眠時間が減少
睡眠時間を平成13年と比ぺると4分の減少で,男女別にみると,男性は12分の減少,女性は4分の増加となっている。
年齢階級別にみると,25~34歳及び35~44歳を除くすぺての年齢階級で減少し,特に男'性はすべての年齢階級で減少している。(図2-2,表2-1)
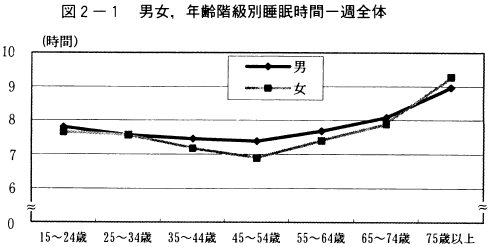
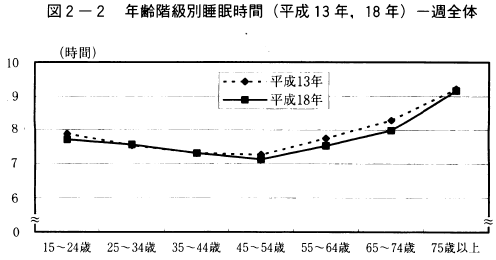
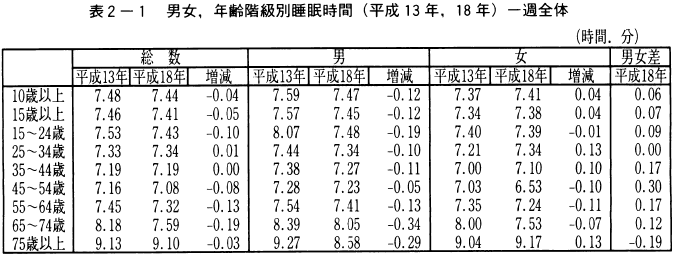
3)すべての曜日で減少した男性の睡眠時間
曜日別に睡眠時間をみると,1日(午前0時から起算する24時間)のうち,平日が7時間34分,土曜日が7時間56分,日曜日が8時間21分となっており,平日に比べ土曜日は22分,日曜日は47分長くなっている。
男女別に平成13年と比べると,男性はすべての曜日で減少,女性は平日及び土曜日で増加し日曜日は横ばいとなっている。(図2-3,表2-2)
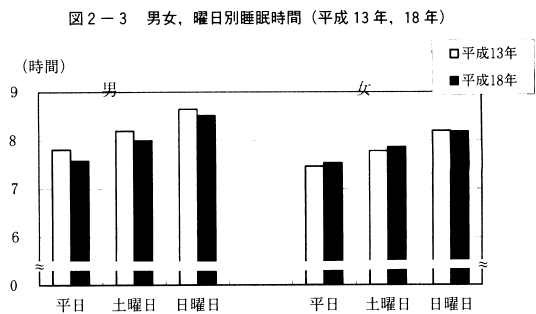
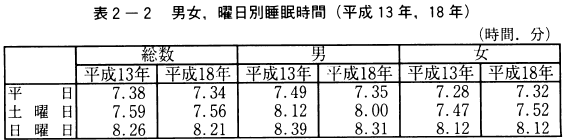
4)過去20年間の推移をみると,男女共に睡眠時間が減少傾向
過去20年間の睡眠時間の推移を,比較可能な年齢区分である15歳以上の人について男女別にみると,男女共に減少傾向となっており,昭和61年と比べると,男性は全国で9分,本県で22分の減少,女性は全国で7分,本県で6分の減少となっている。(表2-3)
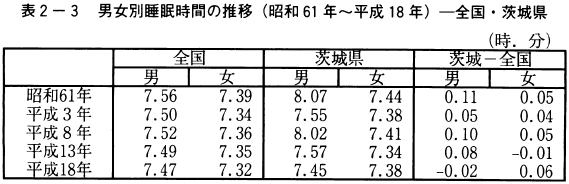
(2)身の回りの用事
1)すべての年齢階級で女性が男性より長い
身の回りの用事の時間は1時間18分で,男性は1時間7分,女性は1時間28分と女性が21分長くなっている。
年齢階級別にみると,45~54歳が1時間11分と最も短く,75歳以上が1時間32分と最も長くなっている。
これを男女別にみると,男性は15~24歳,女性は35~44歳で最も短く,すべての年齢階級で女性が男性より長くなっている。(図2-4,表2-4)
2)多くの年齢階級で増加傾向
身の回りの用事の時間を平成13年と比べると4分の増加となっている。
年齢階級別にみると,55~64歳及び75歳以上を除きすべての年齢階級で増加している。(図2-5,表2-4)
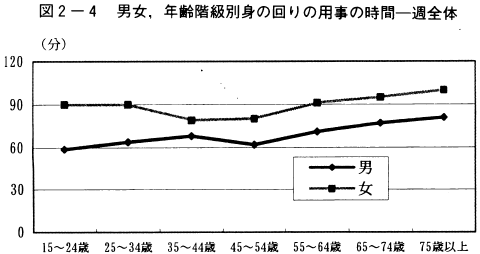
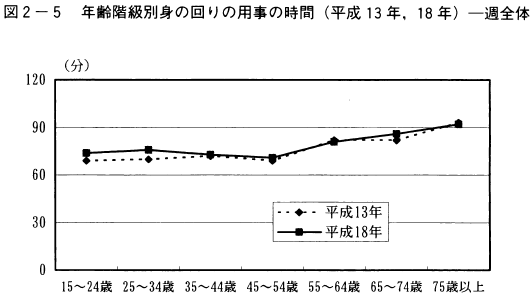
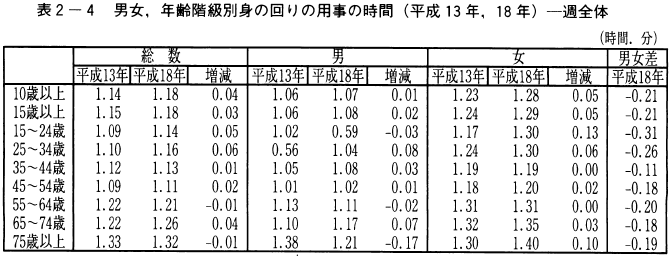
3)20年間で男女共に増加した身の回りの用事の時間
過去20年間の身の回りの用事の時間の推移を,比較可能な年齢区分である15歳以上の人について男女別にみると,男女共に一貫して増加しており,昭和61年と比ぺると,男性は全国で15分,本県で17分の増加,女性は全国で15分,本県で20分の増加となっている。(表2-5)
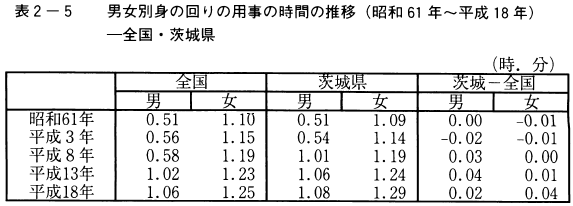
(3)食事
1)高齢層で長い食事時間
食事時間は1時間41分で,男性は1時間39分,女性は1時間44分と女性が5分長くなっている。
年齢階級別にみると,15~24歳が1時間23分と最も短く75歳以上が2時間8分と最も長くなっており,年齢階級が高くなるほど長くなる傾向となっている。
これを男女別にみると,75歳以上を除くすべての年齢階級で女性が長く,特に25~34歳では男性より15分長くなっている。(表2-6)
2)15~24歳及び35歳以上65歳未満で減少している食事時間
食事時間を平成13年と比べると,1分の増加とほぼ横ばいになっている。
年齢階級別にみると,15~24歳及び35歳以上65歳未満の年齢階級で減少しており特に男'性は15歳~65歳未満の年齢階級で減少している。(表2-6)
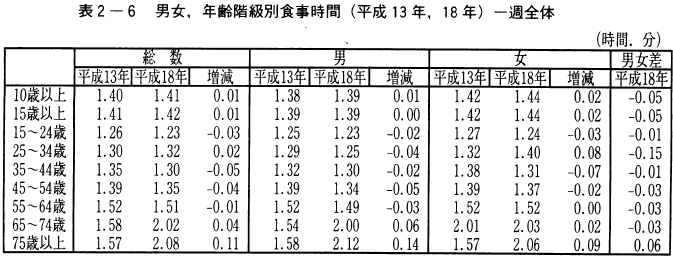
3)男女共に大きな変化は見られない食事時間
過去20年間の食事時間の推移を,比較可能な年齢区分である15歳以上の人について男女別にみると,本県も全国と同様に数分の増減があるものの大きな変化は見られない。(表2-7)
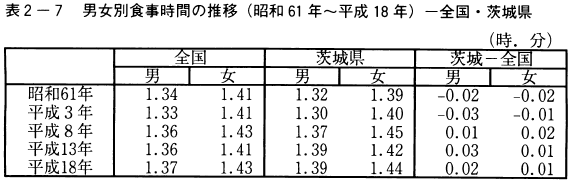
3.2次活動
(1)仕事
1)男性は25~34歳,女性は45~54歳で最も長い仕事時間
有業者(15歳以上,以下同じ。)の1日の仕事時間は6時間4分で,男性は6時間56分,女性は4時間49分となっている。
男女,年齢階級別にみると,男性は25~34歳が7時間45分と最も長く,女性は45~54歳が5時間21分と最も長くなっている。(図3-1,表3-1)
2)男性は増加,女性は減少した仕事時間
有業者の仕事時間を平成13年と比べると,17分の増加となっており,男性は34分,女性は9分の減少となっている。
男女,年齢階級別にみると,男'性は15~24歳を除くすぺての年齢階級で増加している。
一方,女性は45歳以上の年齢階級で増加したが15歳以上45歳未満の年齢階級で減少している。また男女共高年齢層で増加が大きい(図3-2,表3-1)
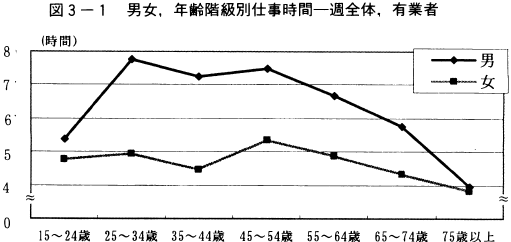
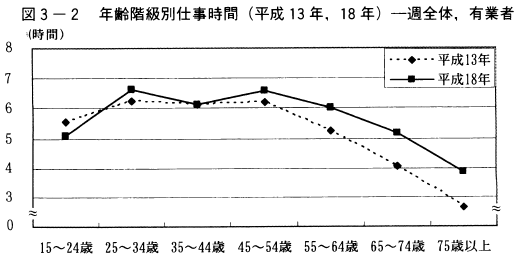
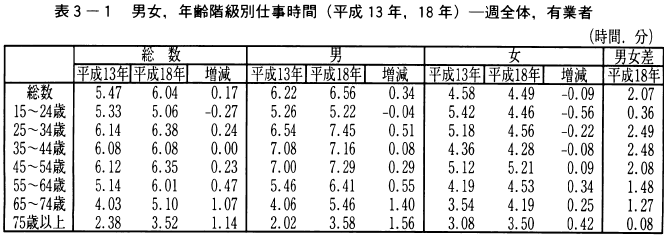
3)仕事時間は平日で増加,士曜日日曜日で減少
有業者の仕事時間を曜日別にみると,平日は7時間13分,土曜日は4時間1分,日曜日は2時間24分となっている。
平成13年と比べると,土曜日及び日曜日は減少しているが,平日は27分増加している。
男女別にみると,男性は平日及び日曜日で増加し土曜日で減少しているが,女性はすべての曜日で減少している。
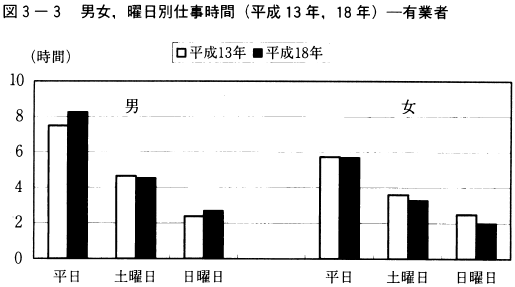
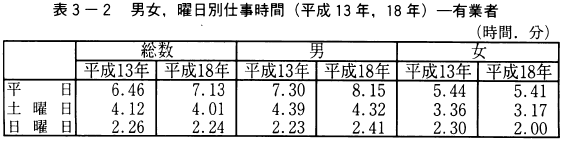
4)減少が続いていた男性の仕事時間が平成18年は増加
有業者について,過去20年間の仕事時間の推移を男女別にみると,本県も全国と同様に男女共に平成13年までは減少が続いていた。18年は全国では男女共に増加に転じたが本県では男性は増加したが女性は減少が続いている。(表3-3)
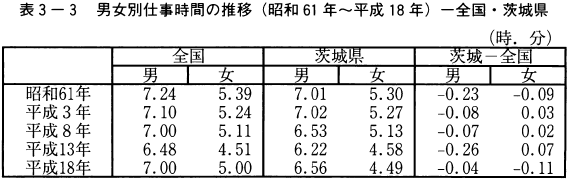
(2)家事関連
1)家事関連時間は35~44歳の女性が最も長い
家事関連時間は2時間2分で,男性は36分,女性は3時間28分と男女の間に大きな差がある。
男女,年齢階級別にみると,男性は75歳以上のみ1時間を越えているが女性は35歳以上65歳未満の年齢階級で4時間以上と長く,特に35~44歳で5時間1分と最も長くなっている。(図3-4,表3-4)
2)男性の家事関連時間が増加
家事関連時間を男女別に平成13年と比べると,男性は4分の増加,女性は4分の減少となっている。
男女,年齢階級別にみると,男性は15~24歳,25歳~34歳及び65~74歳を除くすぺての年齢階級で増加している。一方,女性は15~24歳,25歳~34歳及び45~54歳で増加しているが,それ以外の年齢階級では減少しており,特に35~44歳で36分減少している。(図3-4,表3-4)
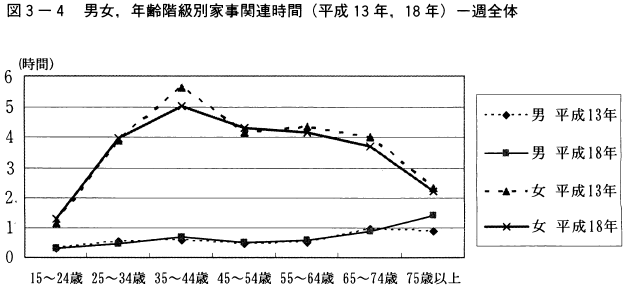
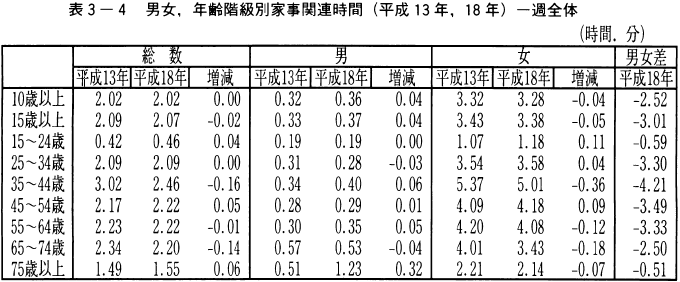
3)男性はすべての曜日で増加,女性は平日で減少,日曜日で増加した家事関連時間
曜日別に家事関連時間をみると,平日が1時間55分,土曜日が2時間14分,日曜日が2時間25分となっており,平日に比べ日曜日は30分長くなっている。
男女別に平成13年と比べると,男性はすべての曜日で増加しているのに対し,女性は平日が減少,土曜日が横ばい,日曜日が増加している。(図3-5,表3-5)
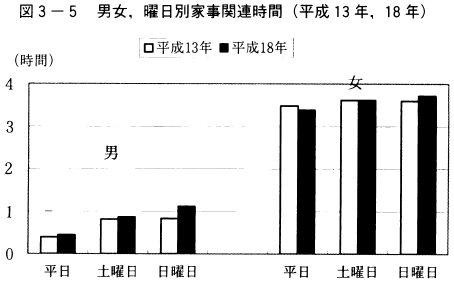
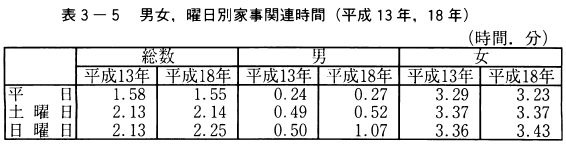
4)男女差は縮小しているが依然として大きい家事関連時間
過去20年間の家事関連時間の推移を,比較可能な年齢区分である15歳以上の人について男女別にみると,本県も全国同様に男性は増加傾向,女性は減少傾向となっているが男女差は依然として大きく約3時間となっている。(表3-6)
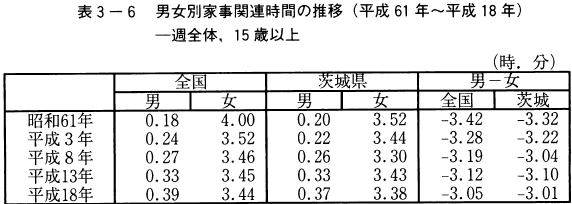
5)共働き世帯でも少ない夫の家事関連時間
共働きの世帯(夫が有業で妻も有業の世帯)と夫が有業で妻が無業の世帯について,夫婦の家事関連時間を比べてみると,夫が有業で妻が無業の世帯の夫が40分であるのに対し共働き世帯の夫は28分であり共働き世帯の夫の方が短くなっている。(図3-6,表3-7)
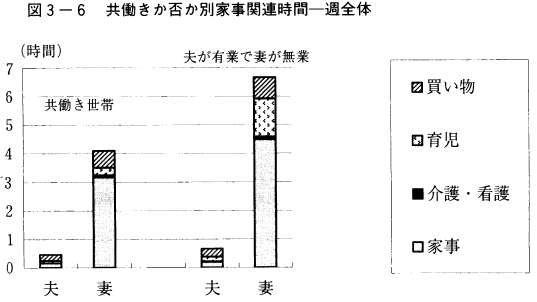
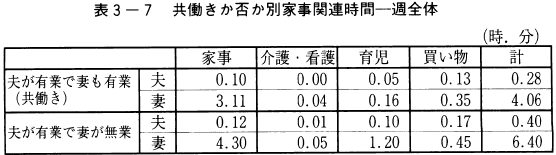
4.3次活動
(1)休養等自由時間活動
1)ほとんどの年齢階級で男性が女性より長い
休養等自由時間活動の時間は3時間48分で,このうちテレビ・ラジオ・新聞・雑誌に費やす時間は2時間22分,休養・くつろぎは1時間26分となっている。(表4-1)
男女,年齢階級別にみると,男性は25~34歳,女'性は35~44歳が最も短く,男女共75歳以上が最も長くなっている。また,25~34歳を除くすべての年齢階級で男性が女'性より長くなっている。(図4-1,表4-1)
2)35歳以上55歳未満を除くすべての年齢階級で休養等自由時間活動の時間が減少
休養等自由時間活動の時間を平成13年と比べると,6分の減少となっておりテレピジオ・新聞・雑誌に費やす時間は12分と大きく減少している。
年齢階級別にみると,35歳以上55歳未満を除くすべての年齢階級で減少している。(図4-2,表4-1)
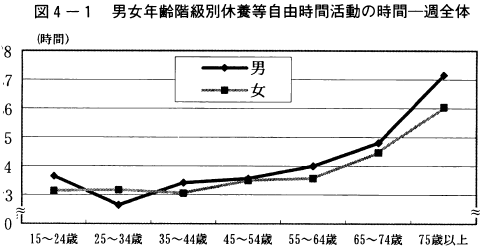
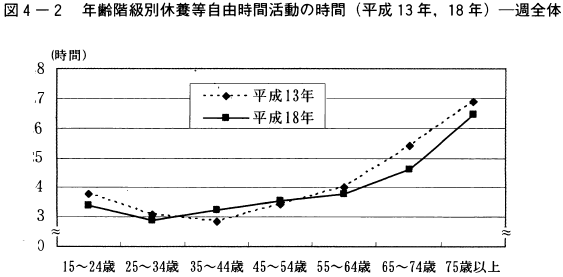
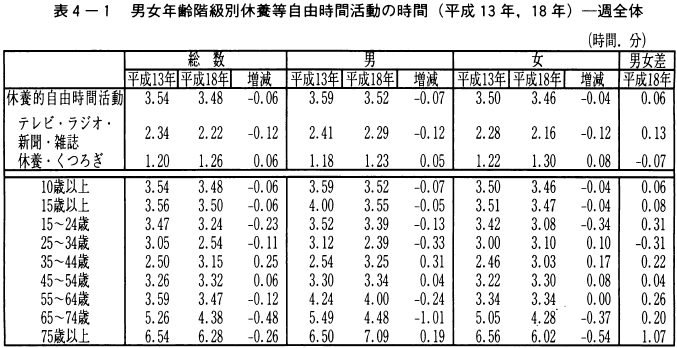
(2)積極的自由時間活動
1)ほとんどの年齢階級で男性が女性より長い
積極的自由時間活動の時間は1時間17分で,このうち趣味・娯楽に費やす時間は42分と最も長く,次いでスポーツ,学習・研究(学業以外)などとなっている。
男女,年齢階級別にみると,男性は1時間27分,女性は1時間6分と男性が21分長くなっており,45~54歳を除くすべての年齢階級で男性が女性より長くなっている。また,男性は35歳以上55歳未満,女性は25歳以上55歳未満及び75歳以上の年齢階級で1時間未満と短くなっている。(図4-3,表4-2)
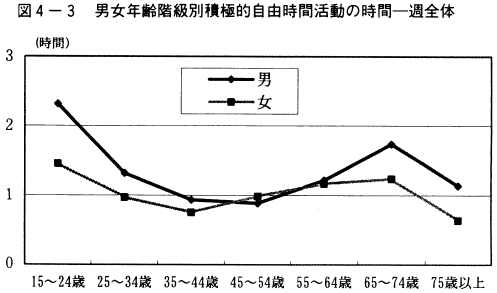
2)ほとんどの年齢階級で積極的自由時間活動の時間が増加
積極的自由時間活動の時間を平成13年と比ぺると,9分の増加となっており,このうち趣味・娯楽が5分の増加で,次いでスポーツが2分の増加となっている。
年齢階級別にみると,35~44歳及び75歳以上を除くすべての年齢階級で増加しており,特に15~24歳,25~34歳,55~64歳及び65~74歳で10分以上増加している。(図4-4,表4-2)
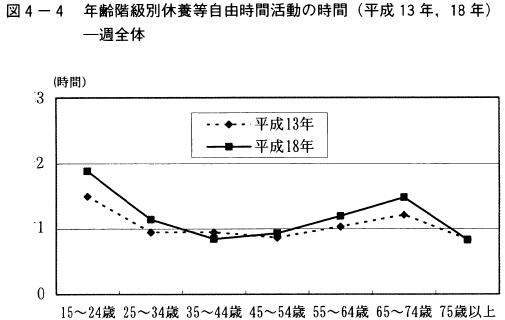
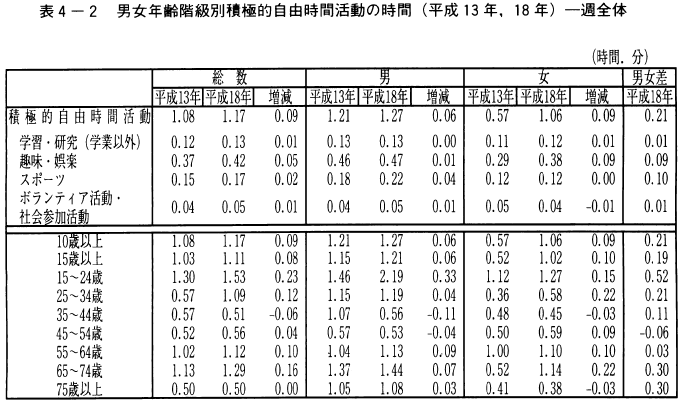
第2.生活行動
1.インターネットの利用
(1)県民男性の59.2%,女性の53.7%がインターネットを利用
過去1年間にインターネットを利用した人(10歳以上。以下同じ。)は,149万3千人で,10歳以上人口に占める割合(行動者率。以下同じ。)は56.4%となっている。
男女別にみると,男性が77万8千人,女性が71万5千人となっており,行動者率は,男'性が59.2%,女'性が53.7%で,男'性が女性より5.5ポイント高くなっている。これを年齢階級別にみると,15~24歳で男性が84.4%,女性が90.6%と最も高く,これより年齢が高くなるにつれて男女とも行動者率は低下している。
行動者率は,仕事や学業での利用も含めた平成13年(45.7%)と比べても,10.7ポイント上昇しており,この5年間でインターネットの利用が広く県民の生活に浸透したことを示している。(図1-1,図1-2)
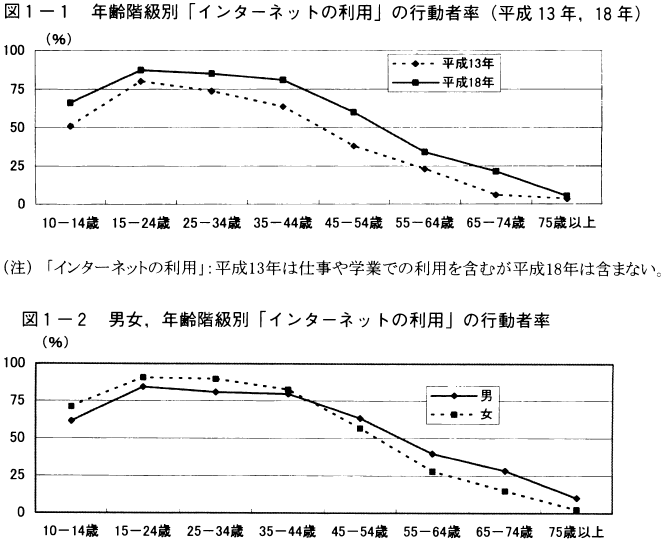
(2)行動者率は「電子メール」が46.3%,「商品やサービスの予約・購入,支払いなどの利用」は21.2%
「インターネットの利用」の種類別に行動者率をみると,「電子メール」が46.3%と最も高く,次いで「情報検索及びニュース等の情報入手」が40.1%,「画像・動画・音楽データ,ソフトウェアの入手」が26.8%,「商品やサービスの予約・購入,支払いなどの利用」が21.2%,「掲示板・チャット」が10.8%,「ホームページ,ブログの開設.更新」が6.0%となっている。
男女別にみると,「ホームページ,ブログの開設・更新」を除き,いずれも男'性の方が高くなっている。(図1-3)
年齢階級別にみると,「電子メール」は男女ともに15歳以上45歳未満の年齢階級で,「'情報検索及びニュース等の情報入手」は,男性が15歳以上55歳未満の年齢階級で,女性が15歳以上45歳未満の年齢階級で5割を超える行動者率となっている。「商品やサービスの予約・購入,支払いなどの利用」は15歳以上35歳未満の年齢階級で女'性の方が高くなっている。(図1-4,図1-5,図1-6)
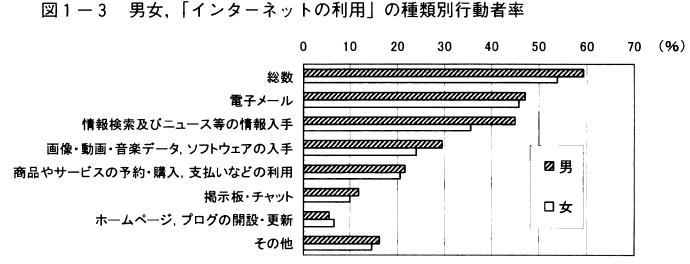
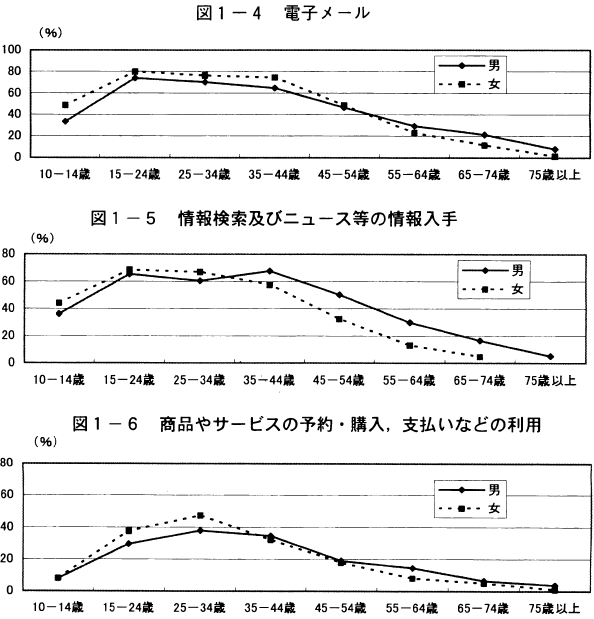
2.学習・研究
(1)1年間に「学習・研究」を行った県民は89万5千人,行動者率は33.8%
過去1年間に何らかの「学習・研究」を行った人は89万5千人で,行動者率は33.8%となっている。男女別にみると,男性が42万3千人,女性が47万2千人となっており,行動者率は男'性が32.1%,女』性が35.5%で,女性が男性より3.4ポイント高くなっている。
行動者率は平成13年と同率であり,これを男女別に見ると,男'性が2.7ポイント低下した一方で女'性が2.6ポイント上昇している。
行動者率を年齢階級別にみると,15歳~24歳が45.1%と最も高くなっており,45歳以上は年齢が高くなるにつれて低下している。これを男女別にみると,15歳以上65歳未満のすべての年齢階級で女'性の方が高くなっている。(図2-1,図2-2)
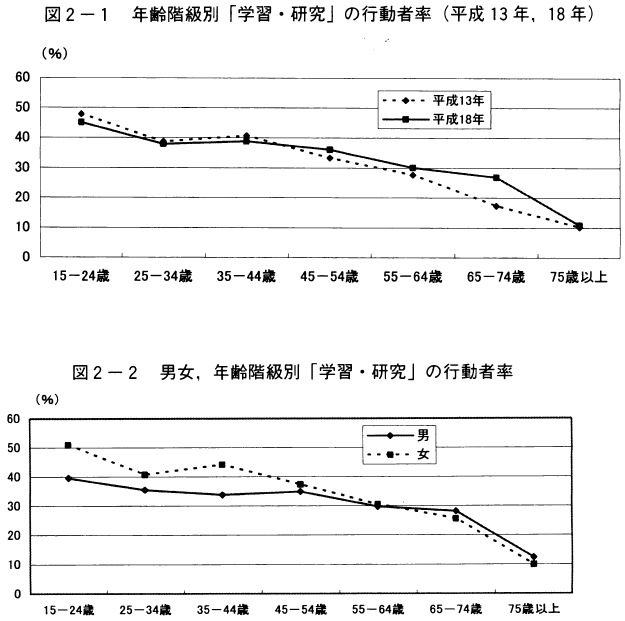
(2)「パソコンなどの情報処理」は行動者率が低下
「学習・研究」の種類別に行動者率をみると,「パソコンなどの情報処理」が11.0%と最も高く,次いで「芸術・文化」が10.2%,「英語」が9.0%などとなっている。これを男女別にみると,男性は「パソコンなどの情報処理」が13.8%と最も高く,次いで「商業実務・ビジネス関係」が10.8%,「英語」が9.0%などとなっている。女性は「家政・家事」が13.5%と最も高く,次いで「芸術・文化」が12.5%,「英語」が9.0%などとなっている。
平成13年と比べると,「パソコンなどの情報処理」が4.1ポイント低下,「芸術・文化」が11.5ポイント上昇などとなっている。(図2-3,図2-4)
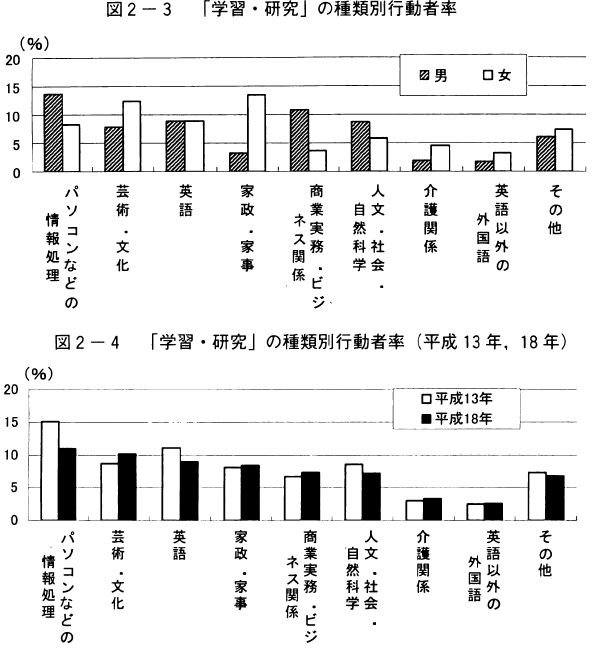
(3)「芸術・文化」の行動者率は,15歳以上65歳未満の年齢階級で女性が男性を上回る
行動者率の高い「学習・研究」の種類について男女別年齢階級別にみると,「パソコンなどの情報処理」では男女とも15~24歳が最も高く,男性は15歳以上65歳未満の年齢階級,女性は15歳以上45歳未満の年齢階級で10%を超えている。「芸術・文化」では,15歳以上65歳未満の年齢階級で女性が男性を上回っている。「英語」は男女とも15~24歳が最も高く,年齢が高くなるにつれて低下している。(図2-5,図2-6,図2-7)
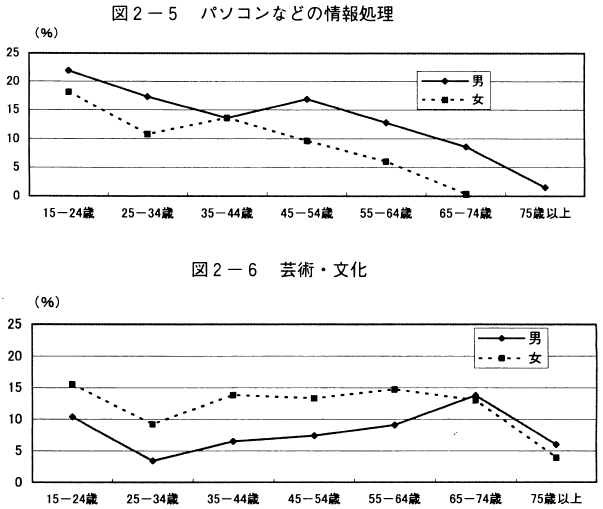
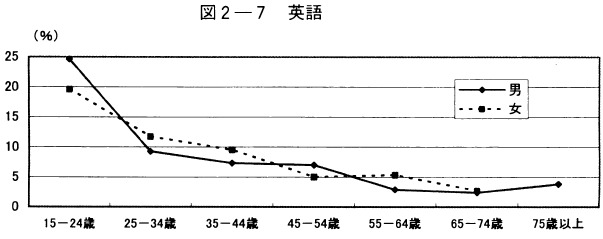
3.スポーツ
(1)1年間に「スポーツ」を行った県民は172万2千人,行動者率は65.1%で5年前より5.0ポイント低下
過去1年間に何らかの「スポーツ」を行った人は172万2千人で,行動者率は65.1%となっている。男女別にみると,男性が91万9千人,女性が80万3千人となっており,行動者率は男性が69.8%,女性が60.4%で,男性が女'性より9.4ポイント高くなっている。
行動者率は平成13年に比ぺ5.0ポイント低下している。これを男女別にみると,男'性が5.5ポイント低下,女性が4.6ポイント低下している。
行動者率を年齢階級別にみると,10~14歳が88.0%と最も高く,年齢が高くなるにつれておおむね低下している。これを男女別にみると,すべての年齢階級で男性の方が高くなっている。(図3-1,図3-2)
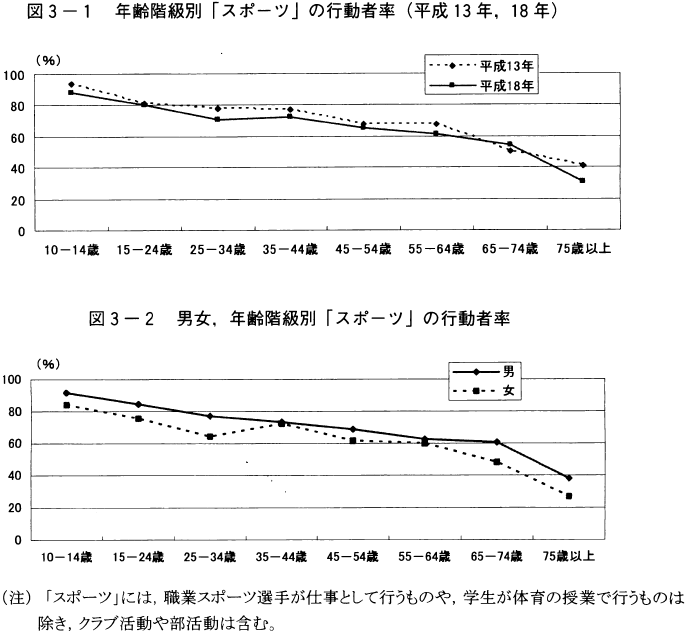
(2)行動者率は全体的に低下傾向
「スポーツ」の種類別に行動者率をみると,「ウォーキング.軽い体操」が34.5%と最も高く,次いで「ボウリング」が19.5%となっている。これを男女別にみると,男女共に「ウォーキング.軽い体操」が最も高く,次いで「ボウリング」となっており,以下,男性は「ゴルフ」,女』性は「水泳」などとなっている。
比較可能な「スポーツ」の種類について,平成13年と比べると,「ウォーキング.軽い体操」が8.2ポイント低下,「水泳」が4.4ポイント低下,「ボウリング」が0.5ポイント低下などとなっており,「サッカー」を除くすぺての種類で行動者率は低下している。(図3-3,図3-4)
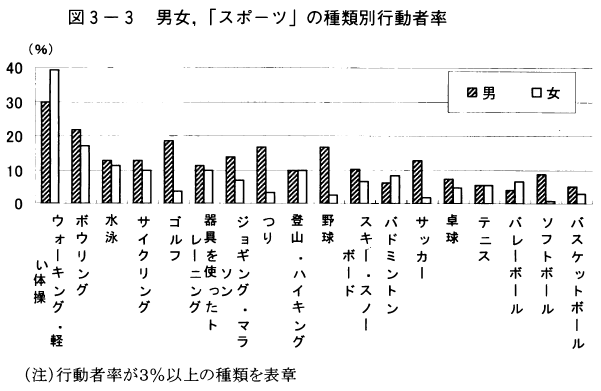
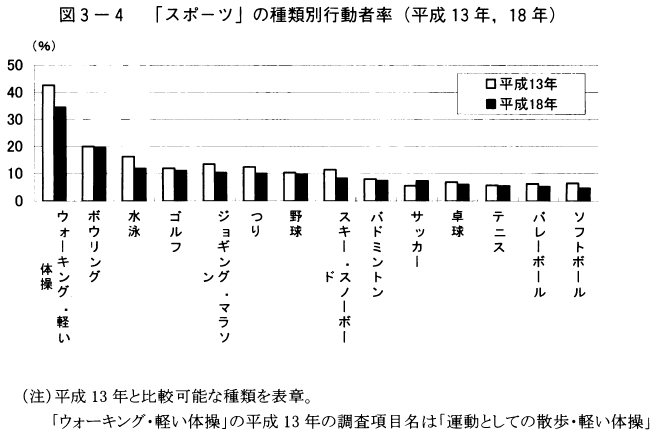
(3)女性の35歳以上65歳未満の年齢階級で「ウオーキング.軽い体操」の行動者率が45%を超える。
行動者率の高い「スポーツ」の種類について男女別年齢別の行動者率をみると,「ウォーキング.軽い体操」では女性の35歳以上65歳未満の年齢階級で45%を超え,ほぼ2人に1人の割合になっている。「ボウリング」では男女共に15~24歳で最も高く,年齢が高くなるにつれて低下している。「水泳」では男女共に10~14歳が最も高く,次に35~44歳が高くなっている。(図3-5,図3-6,図3-7)
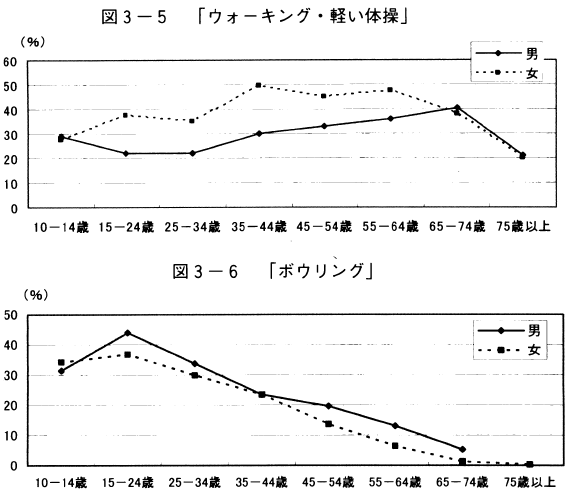
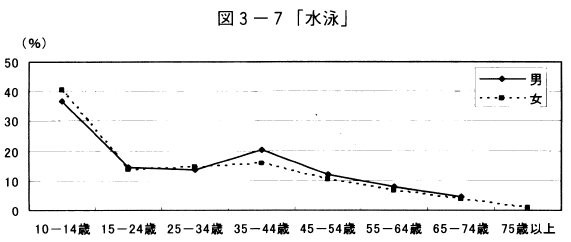
4.趣味・娯楽
(1)1年間に「趣味・娯楽」を行った県民は217万3千人,行動者率は82.1%
過去1年間に何らかの「趣味・娯楽」を行った人は217万3千人で,行動者率は82.1%となっている。男女別にみると,男'性が108万6千人,女性が108万7千人となっており,行動者率は男'性が82.5%,女性が81.7%で,男'性が女性より0.8ポイント高くなっている。
行動者率は平成13年に比べ2.0ポイント低下している。これを男女別にみると,男性が3.1ポイント低下,女,性が1.0ポイント低下している。
行動者率を年齢階級別にみると,15~24歳が91.6%と最も高く,年齢が高くなるにつれておおむね低下している。これを男女別にみると,45歳未満では女性の方が高く,65歳以上では男性の方が高くなっている。(図4-1,図4-2)
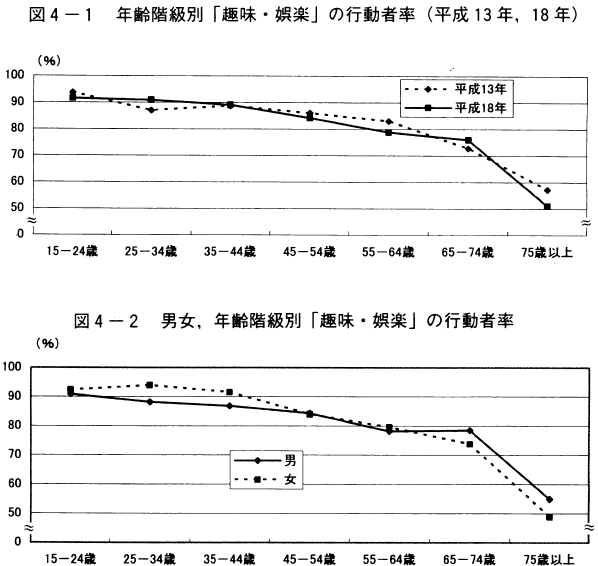
(2)「テレビゲーム,パゾコンゲーム」,「映画鑑賞」,「スポーツ観覧」以外は行動者率が低下
「趣味・娯楽」の種類別に行動者率をみると,「CDなどによる音楽鑑賞」が50.0%と最も高く,次いで「DVDなどによる映画鑑賞」が43.5%,「趣味としての読書」が37.1%などとなっている。これを男女別にみると,男性は,「CDなどによる音楽鑑賞」が48.3%と最も高く,次いで「DVDなどによる映画鑑賞」が44.4%,「テレピゲーム,パソコンゲーム」が38.8%などとなっている。女'性は「CDなどによる音楽鑑賞」が51.8%と最も高く,次いで「DVDなどによる映画鑑賞」が42.7%,「趣味としての読書」が41.6%などとなっている。
比較可能な「趣味・娯楽」の種類について,平成13年と比べると,「テレビゲーム,パソコンゲーム」が4.1ポイント上昇,「スポーツ観覧」が0.9ポイント上昇,「映画鑑賞」が0.3ポイント上昇となっている。一方,「カラオケ」が6.2ポイント低下,「趣味としての読書」が4.5ポイント低下などとなっており,ほとんどの種類で行動者率が低下している。(図4-3,図4-4)
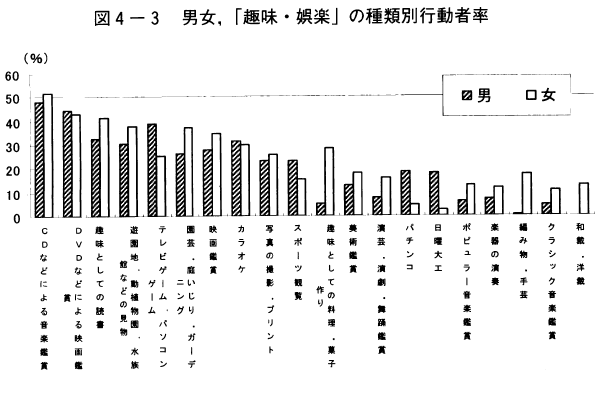
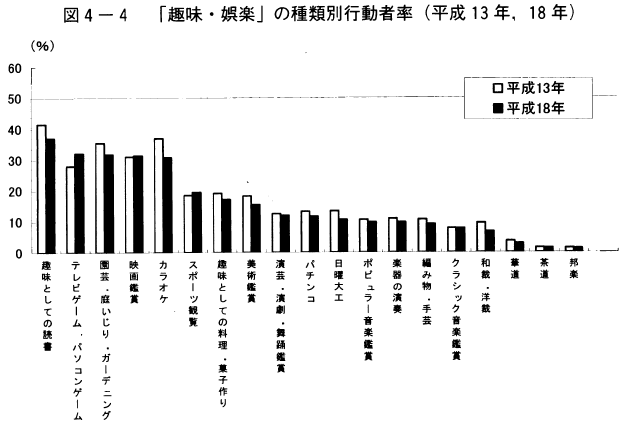
(3)「趣味としての読呑」の行動者率では男女とも35~44歳が最も高い。
行動者率の高い「趣味・娯楽」の種類について男女別年齢階級別にみると,「CDなどによる音楽鑑賞」では男女共に15~24歳が最も高く,「DVDなどによる映画鑑賞」では男女共に25~34歳が最も高く,年齢が高くなるにつれて低下している。「趣味としての読書」では男女共に35~44歳が最も高くなっている。(図4-5,図4-6,図4-7)
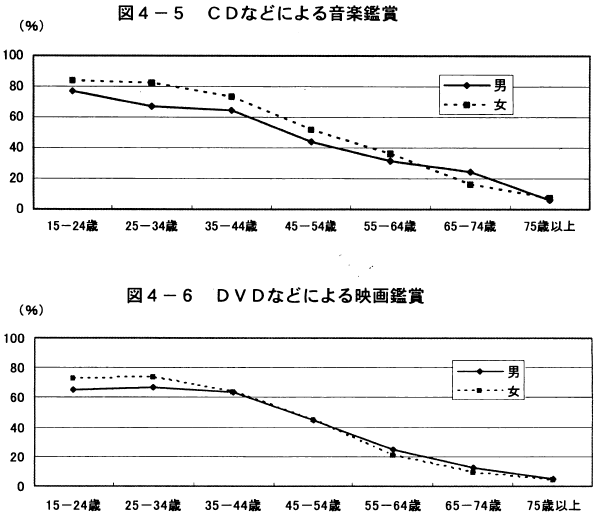
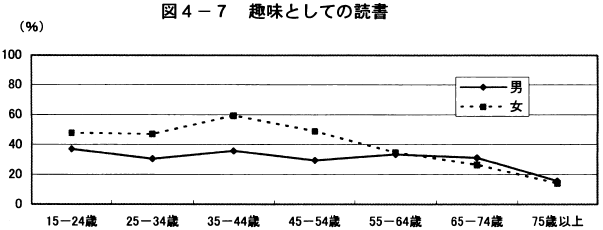
5.ボランティア活動
(1)1年間に「ボランティア活動」を行った県民は70万5千人,行動者率は26.7%で5年前より1.6ポイント低下
過去1年間に何らかの「ボランティア活動」を行った人は,70万5千人で,行動者率は,26.7%となっている。男女別にみると,男性が35万9千人,女性が34万7千人となっており,行動者率は男性が27.3%,女性が26.1%で,男,性が女'性より1.2ポイント高くなっている。
行動者率は平成13年に比べ1.6ポイント低下している。これを男女別にみると,男性が0.8ポイント低下,女'性が2.3ポイント低下している。
行動者率を年齢階級別にみると,35~44歳が35.6%と最も高く,次に45~54歳が34.5%となっている。これを男女別にみると,15~24歳及び35歳以上55歳未満の年齢階級では女性の方が高くなっている。(図5-1,図5-2)
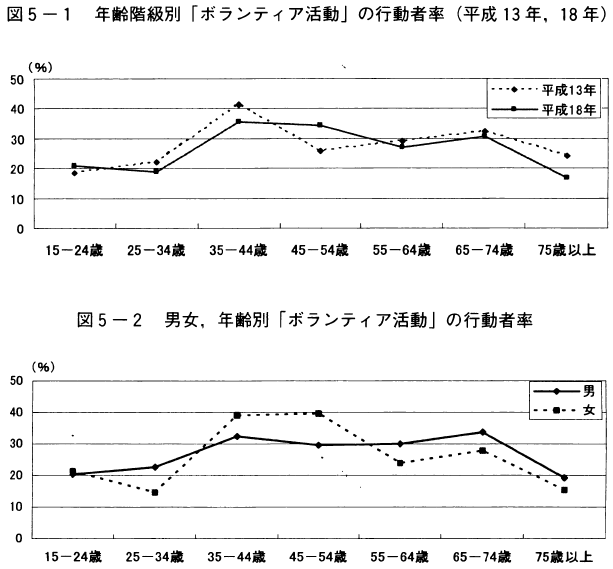
(2)行動者率は全体的に低下傾向
「ボランティア活動」の種類別に行動者率をみると,「まちづくりのための活動」が12.8%と最も高く,次いで,「自然や環境を守るための活動」が7.4%,「安全な生活のための活動」が5.4%などとなっている。これを男女別にみると,男女共に「まちづくりのための活動」が最も高く,次いで男'性は「自然や環境を守るための活動」,「安全な生活のための活動」,女性は「自然や環境を守るための活動」,「子供を対象とした活動」などとなっている。
比較可能な「ボランティア活動」の種類について,平成13年と比べると,「スポーツ・文化・芸術・学術に関係した活動」,「障害者を対象とした活動」などが上昇している。(図5-3,図5-4)
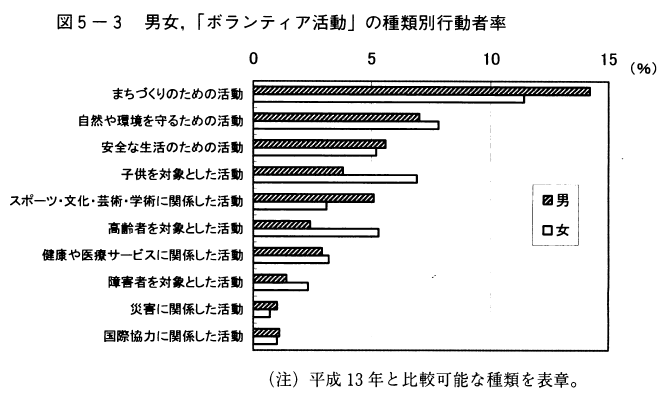
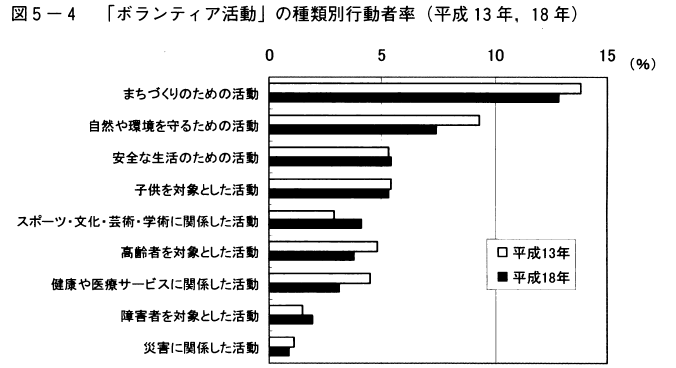
(3)男性の65~74歳,女性の35~44歳で行動者率が高い
行動者率の高い「ボランティア活動」の種類について男女別年齢階級別にみると,「まちづくりのための活動」と「安全な生活のための活動」では男'性の65~74歳,女性の35~44歳の行動者率が最も高く,「自然や環境を守るための活動」では男性の65~74歳,女'性の45~54歳の行動者率が最も高くなっている。(図5-5,図5-6,図5-7)
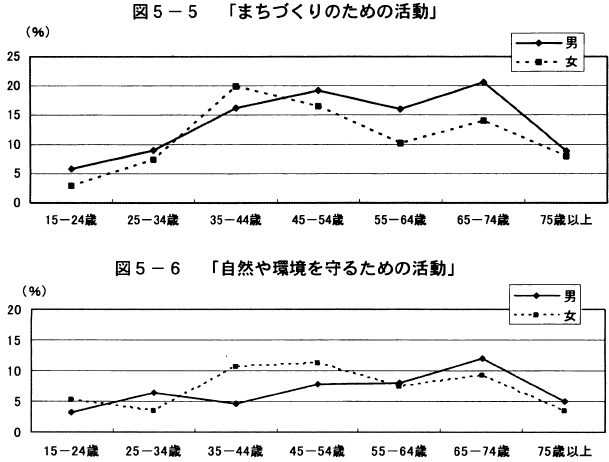
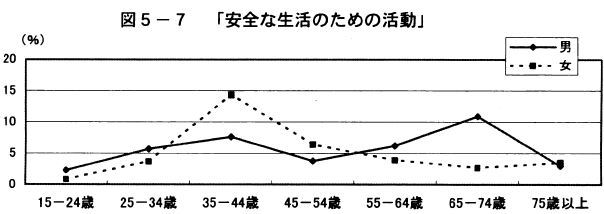
6.旅行・行楽
(1)1年間に「旅行・行楽」を行った県民は196万9千人,行動者率は74.4%で5年前より5.9ポイント低下
過去1年間に何らかの「旅行・行楽」を行った人は,196万9千人で,行動者率は74.4%となっている。男女別にみると,男性が95万6千人,女性が101万3千人となっており,行動者率は男性が72.6%,女性が76.2%で,女性が男性より3.6ポイント高くなっている。
行動者率は平成13年に比ぺ5.9ポイント低下している。これを男女別にみると,男性が6.6ポイント低下,女性が5.2ポイント低下している。
行動者率を年齢階級別にみると,15~24歳から年齢が高くなるにつれて上昇し,35~44歳83.2%と最も高くなり,45歳以上は年齢が高くなるにつれておおむね低下している。これを男女別にみると,45~54歳と65~74歳を除くすべての年齢階級で女性の方が高くなっている。(図6-1,図6-2)
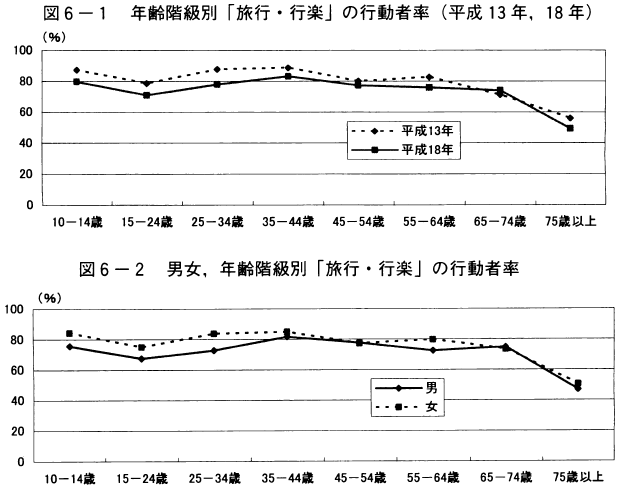
(2)行動者率は「観光旅行(国内)」が46.3%,「観光旅行(海外)」は7.7%
「旅行・行楽」の種類別に行動者率をみると,「行楽(日帰り)」が60.0%,観光旅行では国内が46.3%,海外が7.7%となっている。これを男女別にみると,「行楽(日帰り)」などでは女性が高く,「業務出張・研修・その他(国内)」などでは男性が高くなっている。
平成13年と比ぺると,「行楽(日帰り)」が4.7ポイント低下,「観光旅行(国内)」が9.4ポイント低下などとなっており,「帰省・訪問などの旅行(国内)」を除くすべての種類で行動者率は低下している。(図6-3,図6-4)
(注)旅行とは1泊2日以上の旅行をいう。
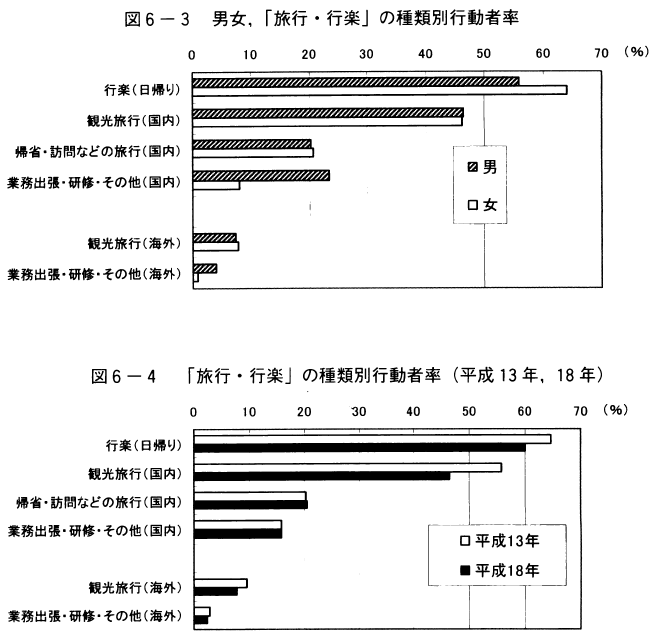
(3)「観光旅行(海外)」では,男性が55~64歳,女性が25~34歳で最も高くなっている
「旅行・行楽」の種類について男女別年齢階級別に行動者率をみると,「行楽(日帰り)」では,すべての年齢階級で女性が男性より高く,25~34歳が74.9%と最も高くなっている。「観光旅行(国内)」では,男性が10~14歳(58.4%),女性が55~64歳(54.3%)で最も高くなっており,「観光旅行(海外)」では,男性が55~64歳(10.3%),女性が25~34歳(13.8%)で最も高くなっている6(図6-5,図6-6,図6-7)
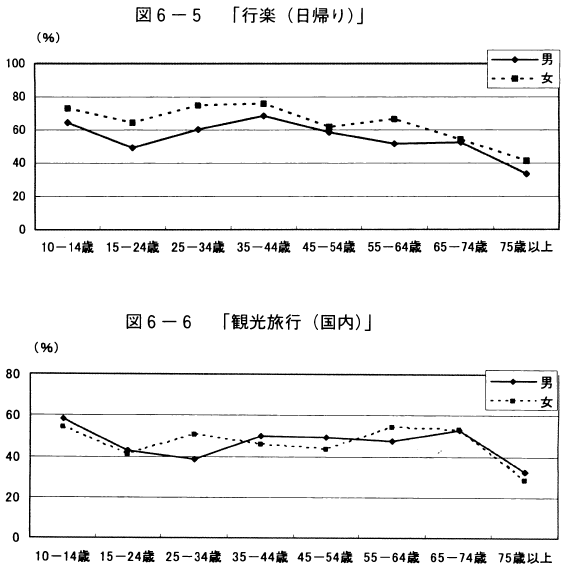
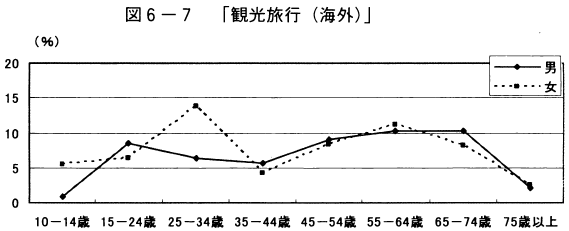
7.全国との比較
上記6つの生活行動の行動者率を全国と年齢階級別に比べてみると,ほとんどの年齢階級で全国並みないし下回っている状況であるが,「ボランティア活動」のみ35歳以上55歳未満で全国平均を上回っている。
全体的な傾向としては,「スポーツ」,「趣味・娯楽」,「ボランティア活動」,「旅行・行楽」は全国と同様に本県も5年前に比べて行動者率が低下している。
「学習・研究」,「スポーツ」,「ボランティア活動」は昭和61年以降全国順位が上昇している。(図7-1~8,表7-1)
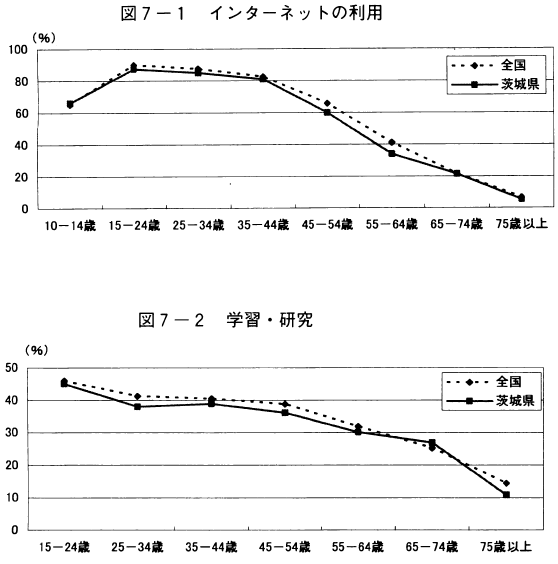
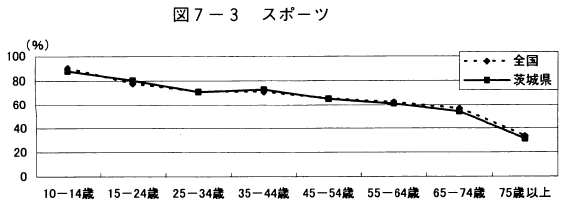
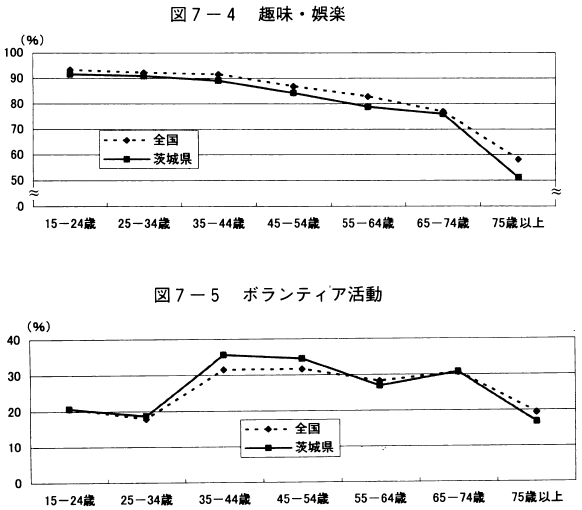
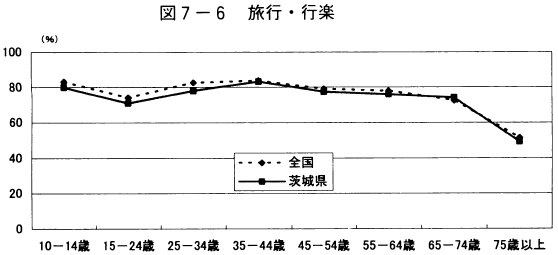
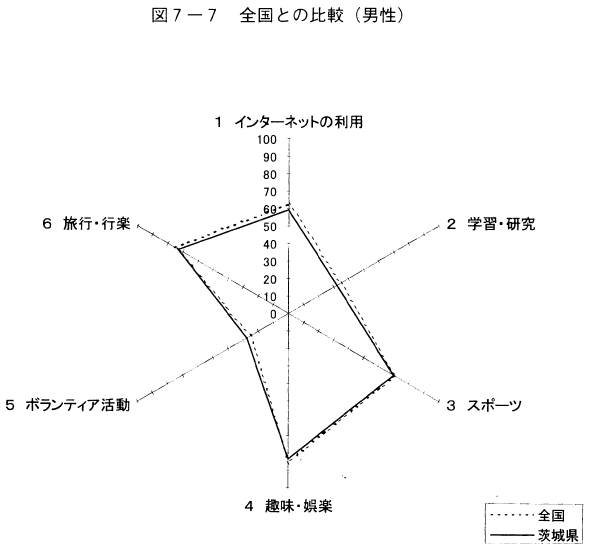
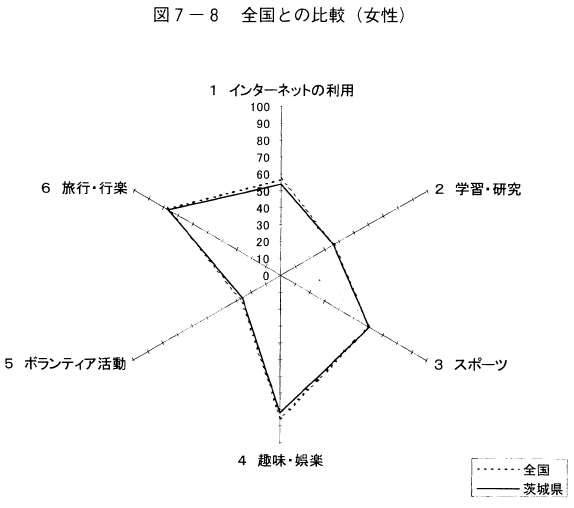
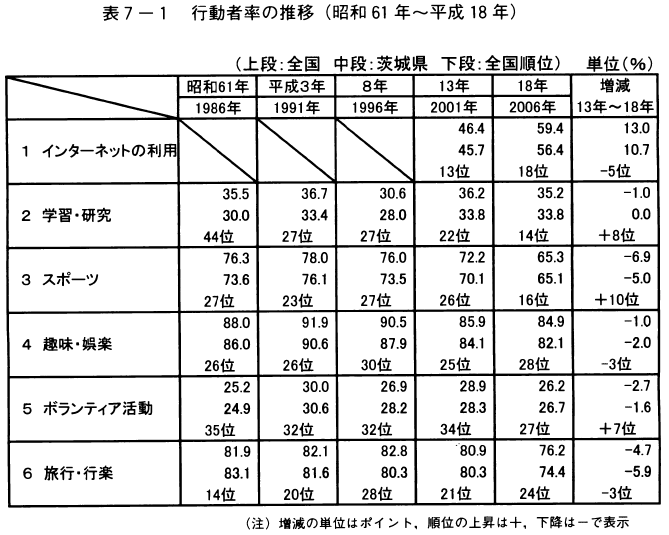
統計表
- 統計表はエクセル形式です。
- 第1表:行動の種類別総平均時間の推移(15歳以上)週全体平均(昭和61年~平成18年)(エクセル:24キロバイト)
- 第2表:男女年齢,行動の種類別総平均時間-全国・茨城県(エクセル:45キロバイト)
- 第3表:曜日,男女,ふだんの就業状態,年齢,行動の種類別総平均時間(エクセル:175キロバイト)
- 第4表:曜日,男女,行動の種類,時間帯別行動者率(エクセル:524キロバイト)
- 第5表:週全体,男女,行動の種類別総平均時間,行動者平均時間及び行動者率(エクセル:321キロバイト)
- 第6表:男女,ふだんの就業状態,年齢,インターネットの利用の種類別行動者数及び行動者率(エクセル:74キロバイト)
- 第7表:男女,ふだんの就業状態,年齢・従業上の地位,雇用形態・職業・週間就業時間,学習・研究の種類別行動者率(15歳以上)(エクセル:77キロバイト)
- 第8表:男女,ふだんの就業状態,年齢,スポーツの種類別行動者率(エクセル:99キロバイト)
- 第9表:男女,ふだんの就業状態,年齢,従業上の地位,雇用形態・職業,趣味・娯楽の種類別行動者率(15歳以上)(エクセル:111キロバイト)
- 第10表:男女,ふだんの就業状態,年齢,従業上の地位,雇用形態・職業,ボランティア活動の種類別行動者数及び行動者率(15歳以上)(エクセル:95キロバイト)
- 第11表:男女,ふだんの就業状態,年齢,旅行・行楽の種類別行動者数及び行動者率(エクセル:75キロバイト)
- 第12表:インターネットの利用の種類別行動者数,行動者率及び平均行動(エクセル:238キロバイト)
- 第13表:学習・研究の種類別行動者率-全国,都道府県(エクセル:195キロバイト)
- 第14表:スポーツの種類別行動者率-全国,都道府県(エクセル:225キロバイト)
- 第15表:趣味・娯楽の種類別行動者率-全国,都道府県(エクセル:329キロバイト)
- 第16表:ボランティア活動の種類別行動者数,行動者率及び平均行動(エクセル:315キロバイト)
- 第17表:旅行・行楽の種類別行動者数及び行動者率-全国,都道府県(エクセル:229キロバイト)
社会生活基本調査結果(茨城県)