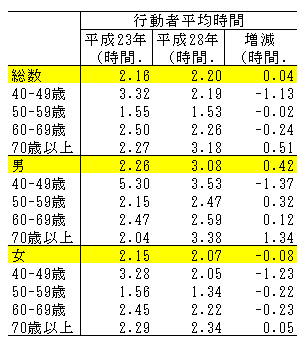目的から探す
ホーム > 県政情報 > 県の概要 > いばらき統計情報ネットワーク > いばらき統計情報ネットワーク(統計課) > 分野別≪社会生活≫ > 平成28年社会生活基本調査結果報告-茨城県民の生活時間と生活行動-
ページ番号:44405
更新日:2018年3月1日
ここから本文です。
平成28年社会生活基本調査結果報告-茨城県民の生活時間と生活行動-
目次
調査の概要
用語と分類
利用上の注意
結果の概要(1)
結果の概要(2)
統計表
報告(印刷用)
調査の概要
1.調査の目的
社会生活基本調査は,国民の生活時間の配分や自由時間等における主な活動(「学習・自己啓発・訓練」,「スポーツ」,「趣味・娯楽」,「ボランティア活動」,及び「旅行・行楽」)について調査し,国民の社会生活の実態を明らかにすることにより,各種行政施策の基礎資料を得ることを目的とするものである。
この調査は,昭和51年以来5年ごとに実施され,今回の調査は9回目に当たる。
なお,平成13年調査より,生活時間についての詳細な結果を得るために,「調査票A」及び「調査票B」の2種類の調査票を用いて調査している。
2.調査の法的根拠
社会生活基本調査は,統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計の作成を目的とする統計調査として,社会生活基本調査規則(昭和56年総理府令第38号)に基づき実施した。
3.調査の範囲
(1)調査の地域
平成27年国勢調査の調査区のうち,総務大臣の指定する調査区(全国約7,300調査区,本県145調査区)において調査を行った。このうち,「調査票A」を用いた調査区は6,900調査区(本県136調査区),「調査票B」を用いた調査区は400調査区(本県9調査区)である。
(2)調査の対象
指定調査区の中から選定した約8万8,000世帯(本県約1,740世帯)にふだん住んでいる10歳以上の世帯員を対象とした。
ただし,次の者は調査の対象から除いた。
- ア.外国の外交団,領事団(家族,随員及び随員の家族を含む。)
- イ.外国軍隊の軍人,軍属の構成員(家族を含む。)
- ウ.自衛隊の営舎内または艦船内の居住者
- エ.刑務所,拘置所の被収容者
- オ.少年院,婦人補導院の在院者
- カ.社会福祉施設の入所者
- キ.病院,療養所等の入院患者
- ク.水上に住居を有する者
4.調査の期日
調査は,平成28年10月20日現在で行った。
ただし,生活時間の配分についての調査は,10月15日から10月23日までの9日間のうちから,調査区ごとに指定された連続する2日間とした。
5.調査事項
<調査票A>
(1)すべての世帯員に関する事項
- ア.世帯主との続柄
- イ.出生の年月又は年齢
- ウ.在学,卒業等教育又は保育の状況
(2)10歳未満の世帯員に関する事項
育児支援の利用の状況
(3)10歳以上の世帯員に関する事項
- ア.氏名
- イ.男女の別
- ウ.配偶の関係
- エ.学習・研究活動の状況
- オ.ボランティア活動の状況
- カ.スポーツ活動の状況
- キ.趣味・娯楽活動の状況
- ク.旅行・行楽の状況
- ケ.生活時間の配分及び天候
(4)15歳以上の世帯員に関する事項
- ア.介護の状況
- イ.就業状態
- ウ.就業希望の状況
- エ.従業上の地位
- オ.勤務形態
- カ.年次有給休暇の取得日数
- キ.仕事の種類
- ク.所属の企業全体の従事者数
- ケ.ふだんの1週間の就業時間
- コ.希望する1週間の就業時間
- サ.通勤時間
- シ.ふだんの健康状態
- ス.仕事からの年間収入
(5)60歳以上の世帯員に関する事項
子の住居の所在地
(6)世帯に関する事項
- ア.世帯の種類
- イ.10歳以上の世帯員数
- ウ.10歳未満の世帯員数
- エ.住居の種類
- オ.自家用車の所有の状況
- カ.世帯の年間収入
- キ.介護支援の利用の状況
- ク.不在者の有無
<調査票B>
(1)すべての世帯員に関する事項
- ア.世帯主との続柄
- イ.出生の年月又は年齢
- ウ.在学,卒業等教育又は保育の状況
(2)10歳未満の世帯員に関する事項
育児支援の利用の状況
(3)10歳以上の世帯員に関する事項
- ア.氏名
- イ.男女の別
- ウ.配偶の関係
- エ.携帯電話,パーソナルコンピュータその他の情報通信に関連する機器の使用の状況
- オ.生活時間の配分及び天候
(4)15歳以上の世帯員に関する事項
- ア.介護の状況
- イ.就業状態
- ウ.従業上の地位
- エ.勤務形態
- オ.年次有給休暇の取得日数
- カ.仕事の種類
- キ.ふだんの1週間の就業時間
- ク.希望する1週間の就業時間
- ケ.ふだんの健康状態
- コ.仕事からの年間収入
(5)世帯に関する事項
- ア.世帯の種類
- イ.10歳以上の世帯員数
- ウ.10歳未満の世帯員数
- エ.住居の種類
- オ.自家用車の所有の状況
- カ.世帯の年間収入
- キ.介護支援の利用の状況
- ク.不在者の有無
6.結果の集計
<調査票Aに係る集計>
(1)生活行動に関する結果
次の事項について,全国,14地域,都道府県,都市階級,大都市圏,人口集中地区の別に集計した。
- ア.1日の生活行動別平均時間,時間帯別の生活行動の状況及び主な生活行動の平均時刻に関する事項
- イ.学習・研究活動,ボランティア活動,スポーツ活動,趣味・娯楽活動及び旅行・行楽の状況に関する事項
<調査票Bに係る集計>
1日の生活行動別平均時間及び時間帯別の生活行動の状況に関する事項について,全国集計した。
7.結果の公表
<調査票Aに係る集計>
(1)生活行動に関する結果
平成29年7月14日公表
(2)生活時間,時間帯及び平均時刻に関する結果
平成29年9月15日公表
<調査票Bに係る集計>
平成29年12月22日公表
用語と分類
(生活時間)
1日の行動を20種類に分類し,時間帯(15分単位)別の行動状況(同時に2種類以上の行動をした場合は,主なもの一つ)を調査した。
1.行動の種類
20種類の行動を大きく3つの活動にまとめ,睡眠,食事など生理的に必要な活動を「1次活動」,仕事,家事など社会生活を営む上で義務的な性格の強い活動を「2次活動」,これら以外の各人が自由に使える時間における活動を「3次活動」とした。
1次活動
睡眠
身の回りの用事
食事
2次活動
通勤・通学
仕事(収入を伴う仕事)
学業(学生が学校の授業やそれに関連して行う学習活動)
家事
介護・看護
育児
買い物
3次活動
移動(通勤・通学を除く)
テレビ・ラジオ・新聞・雑誌
休養・くつろぎ
学習・自己啓発・訓練(学業以外)
趣味・娯楽
スポーツ
ボランティア活動・社会参加活動
交際・付き合い
受診・療養
その他
また,必要に応じ次の区分を用いた。
家事関連
家事,介護・看護,育児及び買い物
休養等自由時間活動
テレビ・ラジオ・新聞・雑誌及び休養・くつろぎ
積極的自由時間活動
学習・自己啓発・訓練(学業以外),趣味・娯楽,スポーツ及びボランティア活動・社会参加活動
仕事等
通勤・通学,仕事及び学業
2.平均時間
行動の種類別平均時間は,一人1日当たりの平均行動時間数で,次の種類がある。
総平均
該当する種類の行動をしなかった人を含む全員についての平均
行動者平均
該当する種類の行動をした人のみについての平均
曜日別平均
調査の曜日ごとに平均値を算出したもの。平日平均(月曜日~金曜日の平均値),月曜日~日曜日平均がある。
週全体平均
次の式により曜日別結果を平均して算出した。
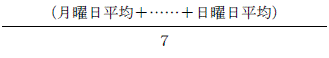
ただし,ある曜日に当該属性を持つ客体が存在しない場合は以下のとおり算出した。
週全体の総平均時間
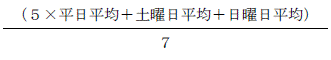
注)平日,土曜日及び日曜日のうち,1つでも当該属性を持つ客体が存在しない場合は,算出せず「・・・」で表章した。
週全体の行動者平均時間
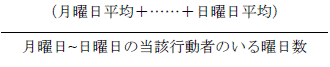
3.行動者数
調査日に当該行動をした人の数。
4.行動者率
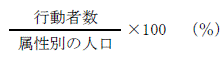
(平均時刻)
1.行動開始・終了時刻
連続する2日間の時間帯別の行動の状況から,主な行動の開始又は終了時刻を次のとおり設定した。
なお,結果表章に用いた曜日は1日目の曜日とした。
起床時刻
12時前に始まり,60分を越えて続く最初の睡眠の終了時刻。なお,睡眠と睡眠の間の睡眠以外の行動が30分以内の場合は,睡眠が続いているとした。
朝食開始時刻
4時以降,11時前に始まる最初の食事開始時刻
夕食開始時刻
16時以降,24時(翌日0時)前に始まる最初の食事開始時刻
就寝時刻
17時以降,36時(翌日12時)前に始まり,60分を超えて続く睡眠の開始時刻。
該当の睡眠が2行動以上ある場合は,睡眠継続時間が最長の睡眠(継続時間が同じ場合は,早く現れる方の睡眠)の開始時刻とした。
なお,睡眠と睡眠の間の睡眠以外の行動が30分以内の場合は,睡眠が続いているとした。
出勤時刻
0時15分以降,24時(翌日0時)前に始まる最初の仕事の前にある通勤・通学の開始時刻。最初の仕事の前に通勤・通学がなく,他の仕事の前に通勤・通学がある場合は最初の仕事を前日からの仕事または持ち帰り仕事とみなし,その次に現れる仕事の前の通勤・通学の開始時刻とした。他の仕事の前にも通勤・通学がない場合は最初の仕事の開始時刻とした。
仕事からの帰宅時刻
0時15分以降,24時(翌日0時)前に始まる最後の仕事の後にある通勤・通学の終了時刻。最後の仕事の後に通勤・通学がなく,それ以前に現れる仕事の後に通勤・通学がある場合は最後の仕事を持ち帰り仕事とみなし,それ以前に現れる仕事の後の通勤・通学の終了時刻とし,他の仕事の後にも通勤・通学がない場合は最後の仕事の終了時刻とした。
なお,最後の仕事の後に通勤・通学はないが,仕事の前に通勤・通学があり,かつそれ以前の仕事の後にも通勤・通学がある場合は,変則勤務又は複数の仕事に従事しているとみなし,仕事からの帰宅時刻は「不詳」とした。
2.行動者数(構成比)
行動者総数に占める各行動(開始又は終了)時刻(15分刻み)別行動者数の割合をいう。
3.行動者率
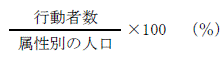
4.平均時刻(時:分)
各行動開始又は終了時刻(1日目の午前0時からの経過時間数)別の行動者数に基づき,次の式により算出した。
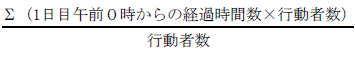
なお,仕事からの帰宅時刻については「不詳」は除いて算出した。
(生活行動)
1.過去1年間に行った活動
「学習・自己啓発・訓練」,「スポーツ」,「趣味・娯楽」,「ボランティア活動」及び「旅行・行楽」について,過去1年間(平成27年10月20日~28年10月19日)に,それぞれの種類別に活動を行ったか否か,行った場合には,活動頻度や目的,共にした人などを調査した。
(1)学習・自己啓発・訓練
個人の自由時間の中で行う学習・自己啓発・訓練で,社会人が仕事として行うものや,学生が学業として行うものは除く。
- 英語
- 英語以外の外国語
- パソコンなどの情報処理
- 商業実務・ビジネス関係
- 介護関係
- 家政・家事(料理・裁縫・家庭経営など)
- 人文・社会・自然科学(歴史・経済・数学・生物など)
- 芸術・文化
- その他
(2)スポーツ
個人の自由時間の中で行うスポーツをいう。
学生が体育の授業で行うものや職業スポーツ選手が仕事として行うものを除き,次の22種類に区分した。
- 野球(キャッチボールを含む)
- ソフトボール
- バレーボール
- バスケットボール
- サッカー(フットサルを含む)
- 卓球
- テニス
- バドミントン
- ゴルフ(練習場を含む)
- 柔道
- 剣道
- ゲートボール
- ボウリング
- つり
- 水泳
- スキー・スノーボード
- 登山・ハイキング
- サイクリング
- ジョギング・マラソン
- ウォーキング・軽い体操
- 器具を使ったトレーニング
- その他のスポーツ
(3)趣味・娯楽
個人の自由時間の中で行うものをいい,次の34種類に区分した。
- スポーツ観覧(テレビ・DVDなどは除く)
- 美術鑑賞(テレビ・DVDなどは除く)
- 演芸・演劇・舞踊鑑賞(テレビ・DVDなどは除く)
- 映画館での映画鑑賞
- 映画館以外での映画鑑賞(テレビ・ビデオ・DVDなど)
- 音楽会などによるクラシック音楽鑑賞
- 音楽会などによるポピュラー音楽・歌謡曲鑑賞
- CD・テープ・レコードなどによる音楽鑑賞
- 楽器の演奏
- 邦楽(民謡,日本古来の音楽を含む)
- コーラス・声楽
- 邦舞・おどり
- 洋舞・社交ダンス
- 書道
- 華道
- 茶道
- 和裁・洋裁
- 編み物・手芸
- 趣味としての料理・菓子作り
- 園芸・庭いじり・ガーデニング
- 日曜大工
- 絵画・彫刻の制作
- 陶芸・工芸
- 写真の撮影・プリント
- 詩・和歌・俳句・小説などの創作
- 趣味としての読書
- 囲碁
- 将棋
- パチンコ
- カラオケ
- テレビゲーム,パソコンゲーム(家庭で行うもの携帯用を含む)
- 遊園地,動植物園,水族館などの見物
- キャンプ
- その他の趣味・娯楽
(4)ボランティア活動
報酬を目的としないで自分の労力,技術,時間を提供して地域社会や個人・団体の福祉増進のために行う活動をいう。
活動のための交通費など実費程度の金額の支払いを受けても報酬とみなさず,その活動はボランティア活動に含む。
なお,ボランティア団体が開催する催し物などへの単なる参加は除く。
- 健康や医療サービスに関係した活動
(献血,入院患者の話し相手,安全な食品を広めることなど) - 高齢者を対象とした活動
(高齢者の日常生活の手助け,高齢者とのレクリエ-ションなど) - 障害者を対象とした活動
(手話,点訳,朗読,障害者の社会参加の協力など) - 子供を対象とした活動
(子供会の世話,子育て支援ボランティア,学校行事の手伝いなど) - スポーツ・文化・芸術・学術に関係した活動
(スポーツを教えること,日本古来の文化を広めること,美術館ガイド,講演会・シンポジウム等の開催など) - まちづくりのための活動
(道路や公園等の清掃,花いっぱい運動,まちおこしなど) - 安全な生活のための活動
(防災活動,防犯活動,交通安全運動など) - 自然や環境を守るための活動
(野鳥の観察と保護,森林や緑を守る活動,リサイクル運動,ゴミを減らす活動など) - 災害に関係した活動
(災害を受けた人に食べものや着るものを送ること,炊き出しなど) - 国際協力に関係した活動
(海外支援協力,難民支援,日本にいる外国人への支援活動など) - その他
(人権を守るための活動,平和のための活動など)
(5)旅行・行楽
仕事や学業などを含めた旅行・行楽を対象としている。
旅行とは,1泊2日以上にわたって行うすべての旅行をいう。
行楽とは,日常生活圏を離れて宿泊を伴わず半日以上かけて行うものをいう。また,夜行日帰りを含む。
国内旅行
- 観光旅行(レクリエーション・スポーツなどのための旅行を含む。)
- 帰省・訪問などの旅行
海外旅行
- 観光旅行(レクリエーション・スポーツなどのための旅行を含む。)
なお,「帰省・訪問などの旅行」には,ついでに観光旅行をした場合も含めた。
2.行動者数
過去1年間(平成27年10月20日~28年10月19日)に該当する種類の活動を行った人の数。
3.行動者率
各属性における行動者数の10歳以上人口に占める割合。次の式により算出した。
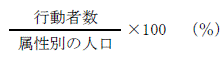
4.平均行動日数
行動者について平均した過去1年間(平成27年10月20日~28年10月19日)の行動日数。
活動頻度別の行動者数に基づき,次の式により算出した。
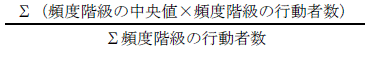
なお,各頻度階級の中央値は次の値とした。
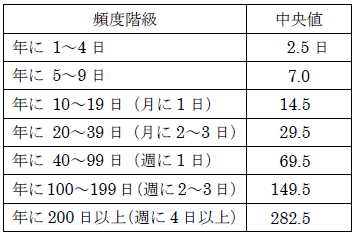
利用上の注意
- 統計表の数字は,表章単位未満の位で四捨五入してあること,また,「総数」に「分類不能」,「不詳」の数を含むことから,「総数」と内訳を合計した数値とは必ずしも一致しない。
- 統計表中の「0」,「0.0」,「0.00」は,集計した数値が表章単位に満たないものである。
- 統計表中の「-」は,該当の行動者が皆無の場合及び同値の人口や標本数が連続するため省略している箇所である。
- 統計表中の「…」は,当該属性の標本数が皆無の場合及び標本数が10未満で,結果精度の観点から表章していない箇所である。
- 生活時間に係る結果の平日及び週全体の総平均時間及び行動者平均時間は各曜日別の平均時間から算出しているため,下記の場合は「…」と表示している。
- 月曜日~金曜日までの当該属性標本がすべてない場合の「平日」の総平均時間及び行動者平均時間
- 平日,土曜日及び日曜日のうち,1つでも総平均時間が「…」で表示される場合,その属性をもった週全体の総平均時間
- 月曜日~日曜日までの当該属性標本がすべてない場合,週全体の行動者平均時間
結果の概要
第1.生活時間
1.1日の生活時間の配分
(1)概観
1.1次活動時間は減少,2次活動時間及び3次活動時間は増加
本県に住んでいる10歳以上の人について,1日の生活時間(週全体平均。以下「週全体」という。)をみると,1次活動1)時間が10時間41分,2次活動2)時間が6時間57分,3次活動3)時間が6時間21分となっている。
平成23年と比べると,1次活動時間は57分の減少,2次活動時間は4分の増加,3次活動時間は2分の増加となっている。(表1-1)
1)睡眠,食事など生理的に必要な活動
2)仕事,家事など社会生活を営む上で義務的な性格の強い活動
3)1次活動,2次活動以外で各人が自由に使える時間における活動
2.睡眠,仕事が減少,家事が増加
生活時間の活動を男女別にみると,男性は1次活動時間が10時間34分,2次活動時間が6時間47分,3次活動時間が6時間38分,女性は1次活動時間が10時間48分,2次活動時間が7時間8分,3次活動時間が6時間4分となっており,1次及び2次活動時間は女性が長く,3次活動時間は男性が長くなっている。
生活時間の活動の内訳をみると,1次活動の睡眠は男性が9分,女性が10分減少しており,総数でも9分減少している。その結果,1次活動は男性が9分の減少,女性が5分の減少,総数では7分の減少である。
2次活動の仕事は,男性が9分,女性が3分減少しており,総数では6分減少している。これに対して,2次活動の家事は男性が3分,女性が5分増加しており,総数では4分の増加である。その結果,家事関連は男性が3分,女性が9分の増加で,総数としては7分の増加となっている。
3次活動の内訳をみると,テレビ・ラジオ・新聞・雑誌において,女性が12分と大きく減少し,総数でも4分の減少となっている。一方,休養・くつろぎにおいては,男性が8分,女性が9分増加し,総数では9分増加している。(表1-1)
3.平日は1次活動時間,土曜日は3次活動時間が減少,日曜日は3次活動時間が増加
生活時間を曜日別にみると,平日は1次活動時間が10時間27分,2次活動時間が7時間52分,3次活動時間が5時間41分,土曜日は1次活動時間が11時間6分,2次活動時間が5時間13分,3次活動時間が7時間41分,日曜日は1次活動時間が11時間28分,2次活動時間が4時間10分,3次活動時間が8時間22分となっており,1次活動時間及び3次活動時間は日曜日が最も長く,2次活動時間は平日が最も長くなっている。
平成23年と比べると,平日は1次活動時間が減少,2次及び3次活動時間が増加となっている。土曜日は2次活動時間が増加,3次活動時間が減少し,日曜日は1次及び2次活動時間が減少,3時活動時間が増加となっている。(表1-2)
表1-1男女,行動の種類別生活時間(平成23年,28年)-週全体
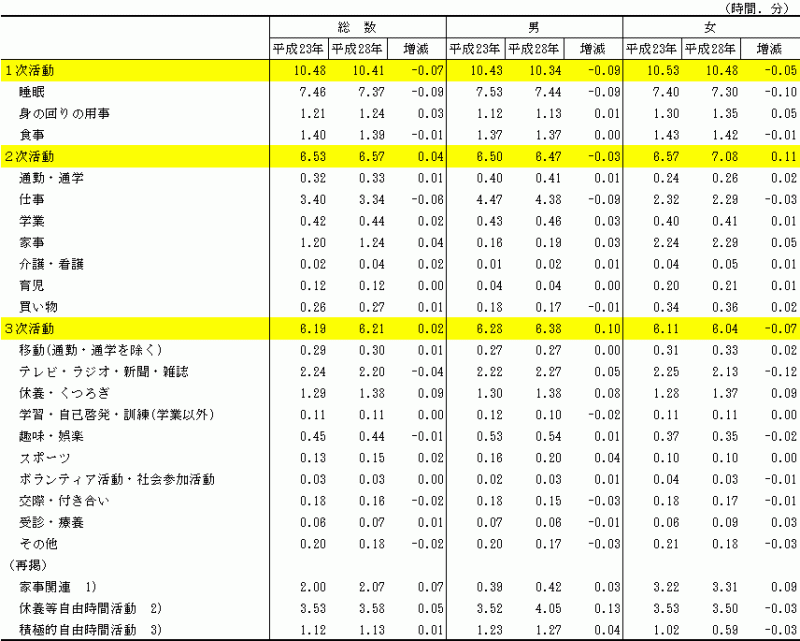
1)家事,介護・看護,育児及び買い物
2)テレビ・ラジオ・新聞・雑誌及び休養・くつろぎ
3)学習・自己啓発・訓練(学業以外),趣味・娯楽,スポーツ及びボランティア活動・社会参加活動
表1-2男女,行動の種類,曜日別生活時間(平成23年,28年)
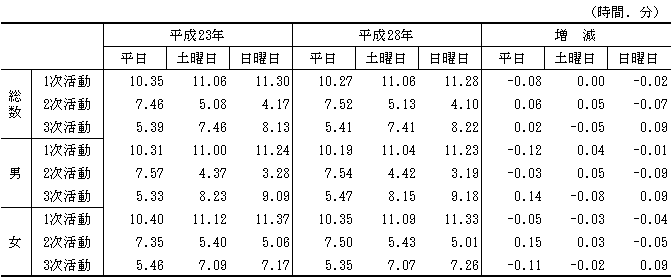
4.1次活動時間,3次活動時間が本県,全国ともに増加
過去25年間の生活時間の推移を,比較可能な年齢区分である15歳以上の人についてみると,本県,全国ともに2次活動時間は減少している。また本県,全国ともに1次活動時間,3次活動時間は増加している。(表1-3,図1-1)
表1-3行動の種類別生活時間の推移(平成3年~平成28年)-週全体,15歳以上,茨城県・全国
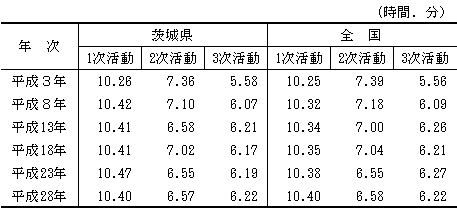
図1-1行動の種類別生活時間の推移(平成3年~平成28年)-週全体,15歳以上
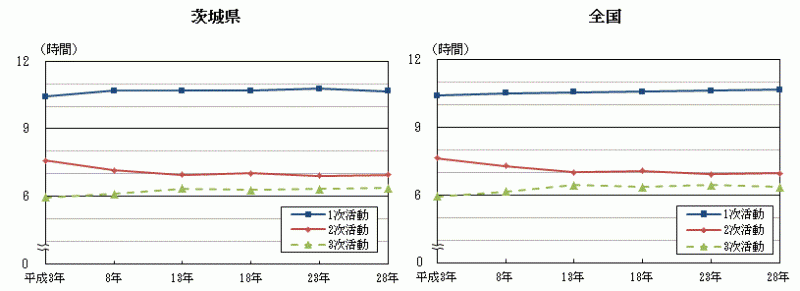
(2)年齢階級別にみる生活時間
1.2次活動時間は男性が45~54歳,女性が35~44歳で最も長い
生活時間を年齢階級別にみると,1次活動時間は,男女ともに45~54歳が最も短く(男性9時間46分,女性10時間3分),75歳以上が最も長くなっている(男性12時間5分,女性12時間18分)。
2次活動時間は,男女ともに25~54歳の各階級で8時間以上であり,男性は45~54歳(8時間59分)が最も長く,女性は35~44歳(9時間33分)が最も長くなっている。
3次活動時間は,男性は45~54歳(5時間15分)が最も短く,75歳以上が最も長くなっている(9時間43分)。女性は35~44歳(4時間24分)が最も短く,75歳以上が最も長くなっている(8時間7分)。(図1-2)
図1-2男女,年齢階級,行動の種類別生活時間-週全体
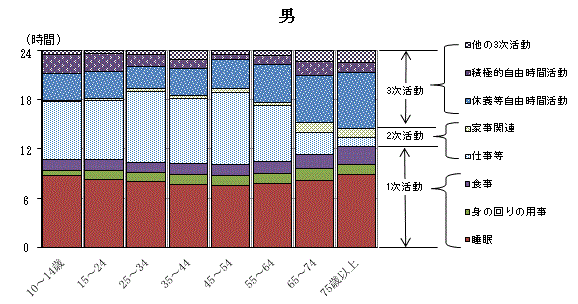
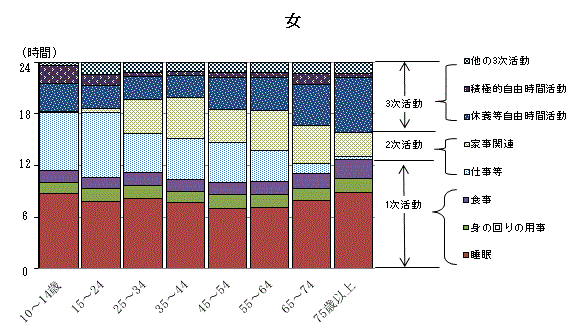
注1)「仕事等」は,「通勤・通学」,「仕事」及び「学業」
注2)「他の3次活動」は,「移動(通勤・通学を除く)」,「交際・付き合い」,「受診・診療」及び「その他」
2.2次活動時間は男性が55~64歳,女性が35~44歳で最も増加
生活時間を年齢階級別に平成23年と比べると,1次活動時間は,男性は9分の減少,女性は5分の減少となっている。年齢階級別にみると,男性は75歳以上で65分と最も減少し,15~24歳及び35~44歳を除くすべての年齢階級で減少している。女性も75歳以上で43分と最も減少し,15~24歳及び55~64歳でも減少している。
2次活動時間は,男性は3分の減少,女性は11分の増加となっている。年齢階級別にみると,男性は35~44歳で48分と大きく減少しているが,その他の年齢階級ではすべて増加している。女性は35~44歳で66分と大きく増加し,15~24歳及び45~54歳を除くすべての年齢階級で増加となった。
3次活動時間は,男性は10分の増加,女性は7分の減少となっている。年齢階級別にみると,男性は75歳以上で47分と大きく増加しているほか,35~44歳及び45~54歳で増加している。女性は35~44歳で67分と大きく減少しているほか,10~14歳,25~34歳及び55~74歳で減少している。(図1-3)
図1-3男女,年齢階級,行動の種類別生活時間の増減(平成23年,28年)-週全体
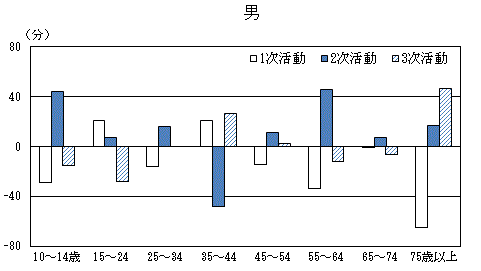
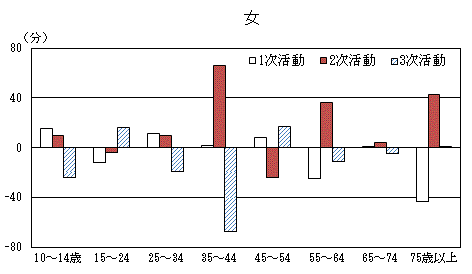
(3)時間帯別にみる行動者率
1.平日に3次活動の行動者率が5割を超えるのは20時15分から22時までの間
行動者率(人口に占める行動者数の割合)を曜日,時間帯別にみると,3次活動の行動者率が5割を超えるのは,平日では20時15分から22時までの間,土曜日は13時30分から17時までの間及び19時45分から22時までの間,日曜日は10時から12時までの間,13時から17時45分までの間及び19時45分から22時までの間となっている。(図1-4)
図1-4曜日,行動の種類,時間帯別行動者率
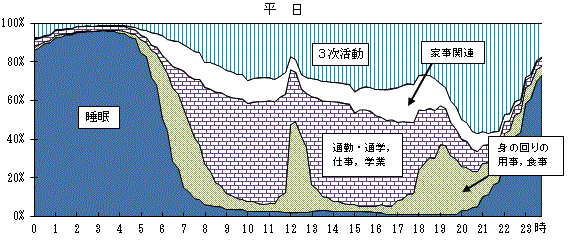
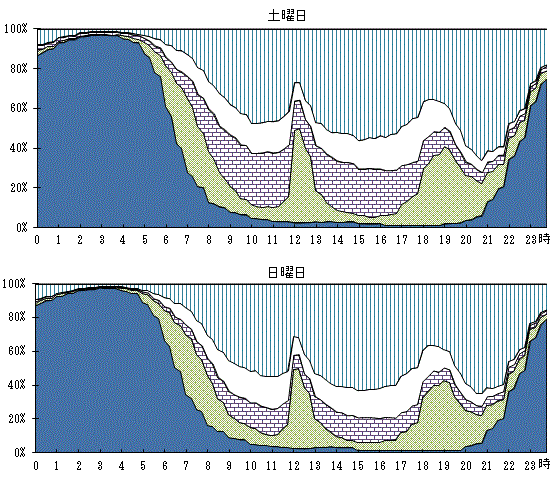
2.家事関連時間
(1)家事関連時間は男性が増加傾向。女性も平成23年と比べて増加
家事関連時間1)を男女別にみると,男性は42分,女性は3時間31分で,平成23年と比べると,男性は3分,女性は9分の増加となっている。(図2-1)
過去20年間の家事関連時間の推移をみると,男性は増加傾向であり,平成8年と平成28年を比べると17分増加している。一方,女性は,平成13年以降減少してきたが,平成28年は平成23年より9分増加した。男女の差は2時間49分で,依然として差は大きい。(表2-1,図2-1)
1)家事関連時間は,「家事」,「介護・看護」,「育児」及び「買い物」
表2-1男女別家事関連時間(平成8年~平成28年)-週全体
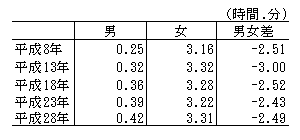
図2-1男女別家事関連時間の推移(平成8年~平成28年)-週全体
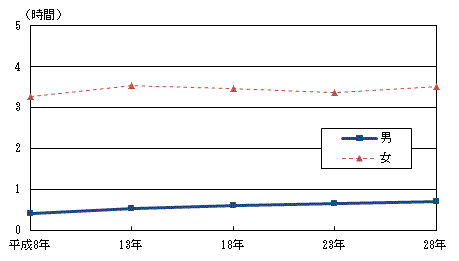
(2)女性は25~34歳,55~64歳などで家事関連時間が増加
家事関連時間を男女,年齢階級別に平成23年と比べると,女性は25~34歳,55~64歳などで家事関連時間が増加している。特に55~64歳は33分と大幅に増加している。一方男性は10~14歳,55~64歳以外のすべての年齢階級で増加している。(図2-2)
図2-2男女,年齢階級別家事関連時間(平成23年,28年)-週全体
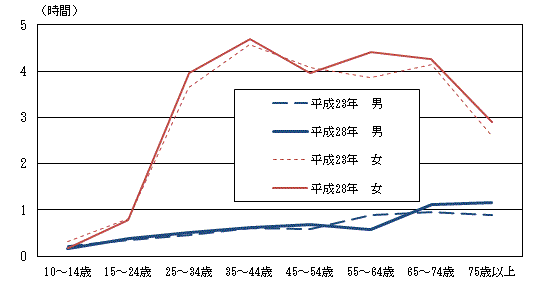
(3)男女ともに各項目で時間が増加
家事関連時間の内訳を男女別に平成23年と比べると,男性の育児及び買い物を除くすべての項目で時間が増加している。男性は家事が3分,介護・看護が1分増加,女性は家事が5分,買い物が2分増加している。(表2-2)
表2-2男女別家事関連時間(平成23年,28年)-週全体
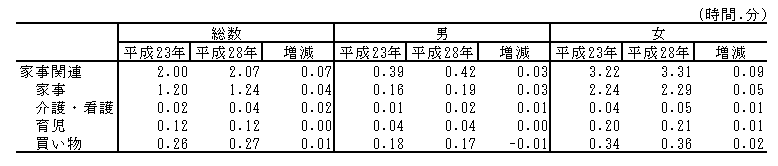
(4)男性の家事時間は増加傾向
家事関連時間のうち家事時間について,男女,年齢階級別に平成23年と比べると,男性は55~64歳で11分減少,女性は45~54歳で14分減少しているが,男性は75歳以上で10分,女性は25~34歳で13分と大きく増加している。(図2-4)
過去20年間の家事時間の推移を男女別にみると,男性は増加傾向,女性は平成13年から23年にかけて減少してきたが,平成28年では増加している。
図2-3男女年齢階級別家事時間(平成23年,28年)-週全体
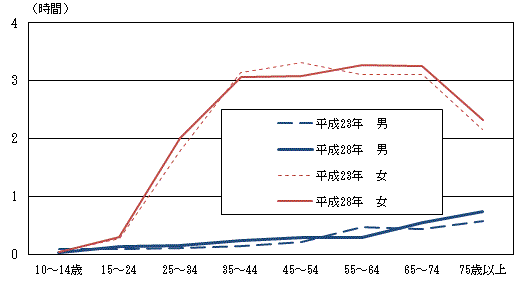
図2-4男女別家事時間の推移(平成8年~平成28年)-週全体
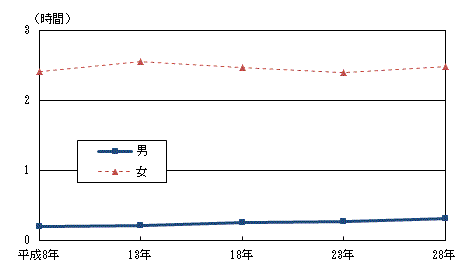
(5)育児時間は35~44歳の女性で20分の増加
家事関連時間のうち育児時間について,男女別,年齢階級別に平成23年と比べると,男性は35~44歳を除くすべての年齢階級で同じか増加している。女性は35~44歳では20分増加した。(図2-5)
過去20年間の育児時間の推移を男女別にみると,男性は平成18年以降,4分で変更がない。女性は減少傾向にあったが,平成28年は平成23年より1分増加した。(図2-6)
図2-5男女,年齢階級別育児時間(平成23年,28年)-週全体
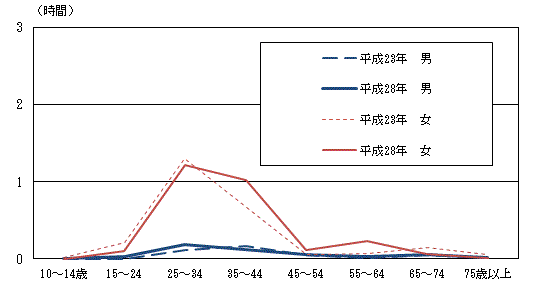
図2-6男女別育児時間の推移(平成8年~平成28年)-週全体
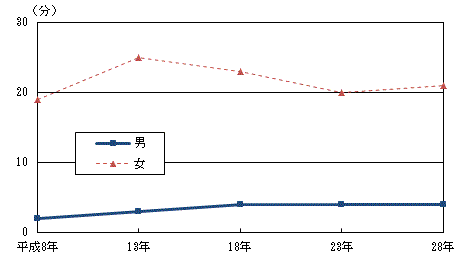
(6)介護・看護時間は男女ともに増加傾向
家事関連時間のうち介護・看護時間について,男女,年齢階級別に平成23年と比べると,女性は35~44歳以外のすべての年齢階級で増加している。特に25~34歳,55~64歳は3分の増加となっている。また男性も45~54歳で3分増加している。(図2-7)
過去20年間の介護・看護時間の推移を男女別にみると,男女とも平成13年以降,同時間が続いたが,平成28年は増加した。(図2-8)
図2-7男女,年齢階級別介護・看護時間(平成23年,28年)-週全体
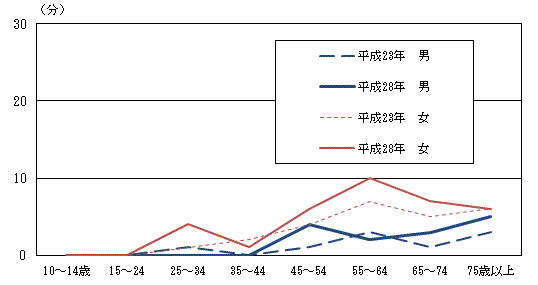
図2-8男女別介護・看護時間の推移(昭和61年~平成23年)-週全体
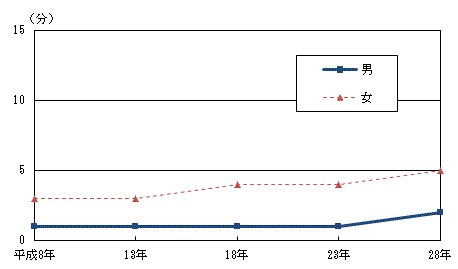
(7)60歳以上の介護者数が増加
15歳以上でふだん家族を介護している人(以下「介護者」という。)は17万人で,平成23年と比べ1千人の減少となっている。男女別にみると,男性が6万4千人で8千人の減少,女性が10万6千人で7千人の増加となっている。年齢階級別にみると,60歳以上が介護者全体の5割を占めている。(表2-3)
介護者のうち,調査当日に実際に介護・看護を行った人の平均時間(行動者平均時間)を平成23年と比べると,男性が3時間8分で42分増加,女性が2時間7分で8分減少している。行動者平均時間は男性が女性を1時間1分上回り,差が平成23年から拡大した。(表2-3)
表2-3男女,年齢階級別介護者数及び行動者平均時間(平成23年,平成28年)-週全体,15歳以上
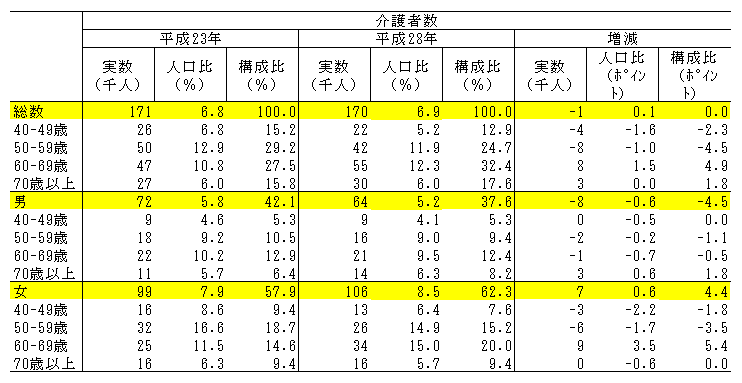
3.仕事時間
(1)仕事時間は男性が45~54歳,女性が35~44歳で最も長い
有業者(15歳以上。以下同じ。)についてみると,有業者数は157万3千人,有業率1)は63.8%となっており,平成23年と比べ,有業者数は1万7千人の減少,有業率は0.2ポイント上昇となっている。(表3-1)
有業者の仕事時間は,男性は6時間45分,女性は4時間39分で,平成23年と比べると,男性は5分,女性は14分の減少となっている。年齢階級別にみると,仕事時間で男性は45~54歳,女性は35~44歳が最も長い。男性は45歳未満のすべての年齢階級で減少となっている。女性は35~44歳及び75歳以上を除くすべての年齢階級で減少した。(表3-2,図3-1)
1)人口に占める有業者の割合(ふだんの就業状態不詳を除き算出)
表3-1男女別有業者数及び有業率(平成23年,28年)-15歳以上
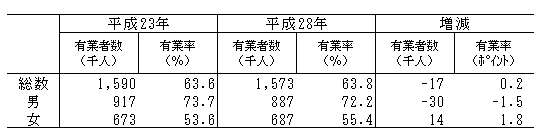
表3-2男女,年齢階級別仕事時間(平成23年,28年)-週全体,有業者
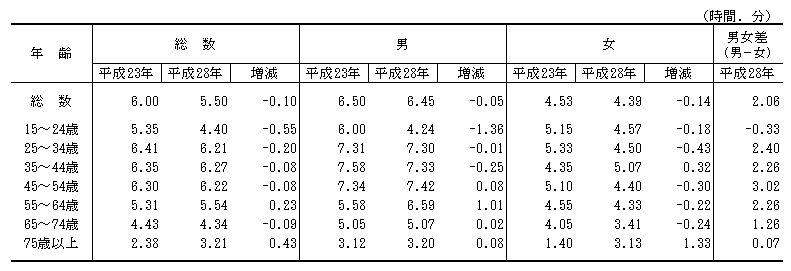
図3-1男女,年齢階級別仕事時間(平成23年,28年)-週全体,有業者
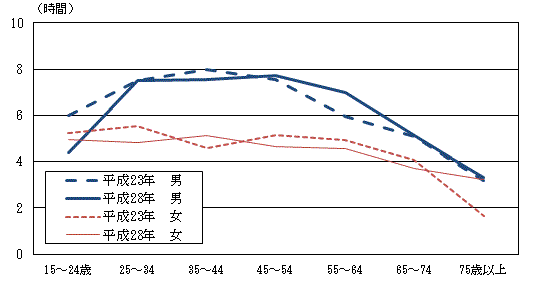
(2)男性は平日の仕事時間が減少,女性はすべての曜日で仕事時間が減少
有業者の仕事時間を曜日別にみると,平日は6時間56分,土曜日は3時間51分,日曜日は2時間19分となっている。
男女別にみると,男性は,平日が8時間2分,土曜日が4時間31分,日曜日が2時間35分となっており,女性は,平日が5時間31分,土曜日が3時間1分,日曜日が1時間57分となっている。平成23年と比べると,男性は,平日が減少,土曜日及び日曜日が増加している。一方,女性は,すべての曜日で減少している。(表3-3,図3-2)
表3-3男女,曜日別仕事時間の推移(平成23年,平成28年)-有業者
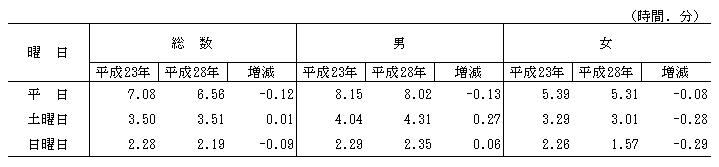
図3-2男女,曜日別仕事時間(平成23年,28年)-有業者
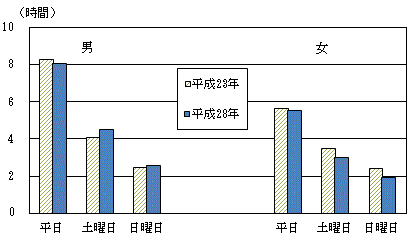
(3)女性の仕事時間は過去25年間で48分減少
過去25年間の仕事時間の推移を,比較可能な年齢区分である15歳以上の人について男女別にみると,男性は平成3年以降減少が続き,18年に増加に転じたが,23年から再び減少した。女性は平成18年まで減少が続き,23年で増加に転じたが28年で再び減少した。
平成3年と比べると,男性が17分,女性が48分の減少となっている。
全国と比較すると,男性は4分,女性は8分下回っている。(表3-4,図3-3)
表3-4男女別仕事時間の推移(平成3年~28年)-週全体,有業者
茨城県・全国
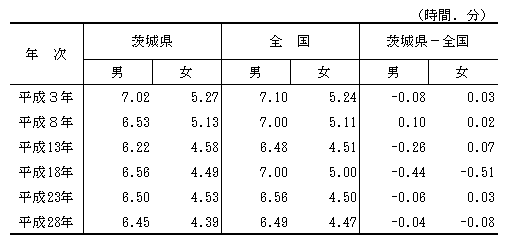
図3-3男女別仕事時間の推移(平成3年~平成28年)-週全体,有業者
茨城県
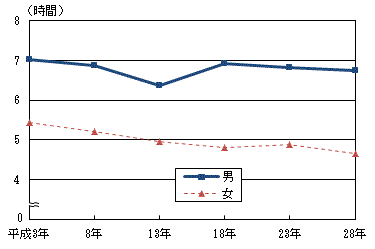
(4)雇用されている人の仕事時間は5時間54分,自営業主は5時間19分
有業者について,従業上の地位別に仕事時間をみると,雇用されている人が5時間54分,自営業主が5時間19分となっている。男女別にみると,男性は雇用されている人が6時間53分,自営業主が5時間46分となっており,女性は雇用されている人が4時間41分,自営業主が3時間35分となっている。
雇用されている人について,雇用形態別に仕事時間をみると,正規の職員・従業員が7時間6分,パートが4時間6分,アルバイトが3時間7分となっている。
これを平成23年と比べると,正規の職員・従業員は16分減少,パートは32分減少,アルバイトは22分減少している。(表3-5,図3-4)
表3-5男女,従業上の地位,雇用形態別仕事時間(平成23年,28年)-週全体,有業者
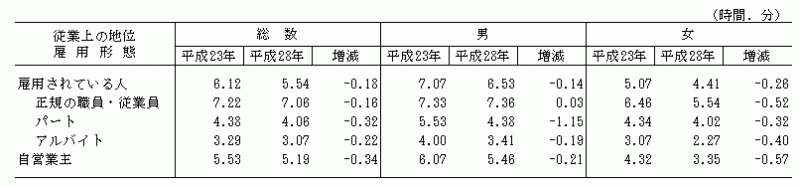
図3-4男女,雇用形態別仕事時間(平成23年,28年)-週全体,雇用されている人
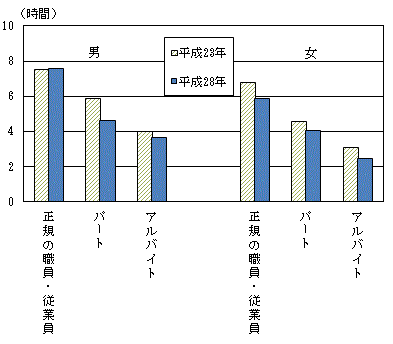
4.夫と妻の生活時間
(1)子供の成長に伴い,妻の家事関連時間は大きく変化
子供がいる世帯の夫と妻の家事関連時間をみると,妻は子供の成長に伴い育児時間が大幅に減少している。0歳の子を持つ妻の育児時間は4時間53分だが,18歳以上の子を持つ妻は4分である。また,妻の家事時間は子の年齢が上がるにつれて増加するが,12~14歳の子を持つ妻の4時間19分の家事時間をピークとして減少している。
子供がいる世帯の夫の家事関連時間をみると,育児時間は0歳の子を持つ夫が1時間24分であり,子供の年齢が上がるにつれて大幅に減少する。また,夫の家事時間は子供の年齢にかかわらず,ほぼ一定の時間である。(表4-1)
表4-1末子の年齢階級別夫・妻の家事関連時間(平成28年)-週全体,夫婦と子供の世帯
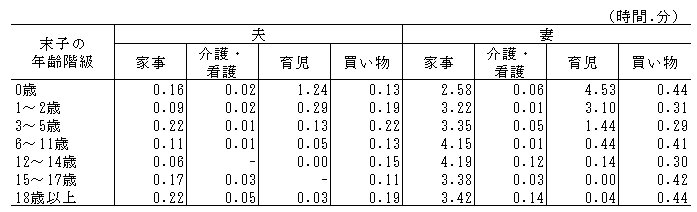
(2)過去10年間で夫・妻ともに家事時間が増加
過去10年間の夫と妻の家事時間の推移を末子の年齢階級別にみると,妻の家事時間は,ほとんどの末子の年齢階級において過去10年間の間に増加している。特に12歳~14歳の末子を持つ妻は,平成18年に2時間52分だった家事時間が平成28年は4時間19分となり,大幅に増加している。夫の家事時間も妻と同様に,過去10年間で増加傾向にある。(表4-2)
過去10年間の夫と妻の育児時間の推移を末子の年齢階級別にみると,平成28年は0歳の末子を持つ夫が,1時間24分と他の年齢階級の末子を持つ夫に比べて格段に長く,平成23年と比べても57分の増加で,増加幅が大きい。妻の育児時間に関しては,過去10年間で0~5歳の末子を持つ妻の育児時間は緩やかな減少傾向であり,6~12歳の末子を持つ妻は緩やかな上昇傾向にある。(表4-3)
表4-2末子の年齢階級別夫・妻の家事時間の推移(平成18年~28年)-週全体,夫婦と子供の世帯の夫・妻
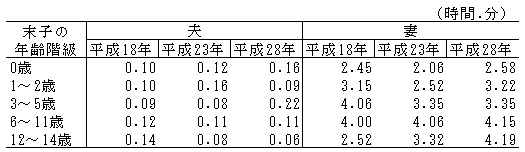
表4-3末子の年齢階級別夫・妻の育児時間の推移(平成18年~28年)-週全体,夫婦と子供の世帯の夫・妻
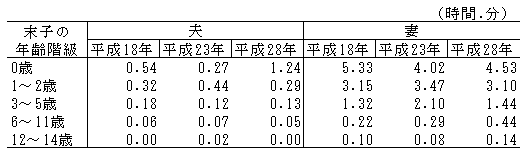
(3)共働き世帯の妻の生活時間は,仕事が減少,家事が横ばいで,育児は増加傾向
子供がいる世帯のうち,「共働き世帯」及び「夫が有業で妻が無業の世帯」について,過去10年間の夫と妻の生活時間の推移をみると,「共働き世帯」の夫は仕事時間,家事時間及び育児時間のすべてにおいて緩やかに増加している。また,「夫が有業で妻が無業の世帯」の夫は仕事時間と家事時間が増加しているが,育児時間はわずかに減少している。
「共働き世帯」の妻は仕事時間が減少,家事時間が横ばいで,育児時間が増加している。「夫が有業で妻が無業の世帯」の妻は家事時間,育児時間ともに増加している。(表4-4)
表4-4共働きか否か,行動の種類別生活時間の推移(平成18年~平成28年)-週全体,夫婦と子供の世帯の夫・妻
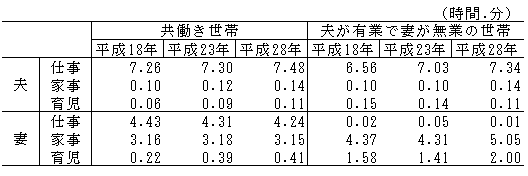
5.高齢者の生活時間
(1)高齢者の仕事等の時間が減少,家事時間は増加
65歳以上の高齢者の生活時間について,平成23年と比べると,仕事等1)時間が7分増加し,家事関連時間は12分増加している。男女別にみると,家事関連の中でも特に家事時間は,男性が8分,女性が12分増加しており,全体でも9分の増加である。続いて買い物時間は男性が2分,女性が6分の増加で,全体では4分増加しており,家事時間の次に増加している。(表5-1)
1)仕事等は,「通勤・通学」,「仕事」及び「学業」
表5-1男女,主な行動の種類別生活時間(平成23年,28年)-週全体・65歳以上
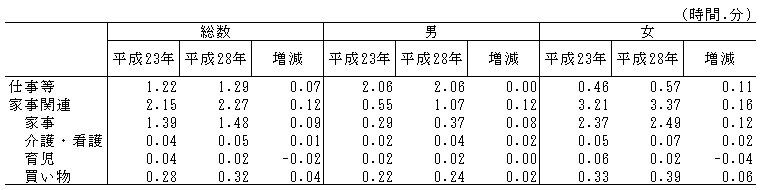
(2)高齢者の有業者数,有業率が増加
65歳以上の高齢者の有業者数は22万4千人で,平成23年と比べると,4万5千人の増加となっており,有業率は1.8ポイント上昇している。男女別に平成23年と比べると,男性が13万6千人で2万人増加,女性が8万7千人で2万4千人増加している。有業率は男性が40.5%で,平成23年と比べると0.5ポイント低下しているが,女性は21.6%で3.4ポイント上昇している。(表5-2)
表5-2男女別有業者数,有業率(平成23年,28年)-週全体,65歳以上有業者
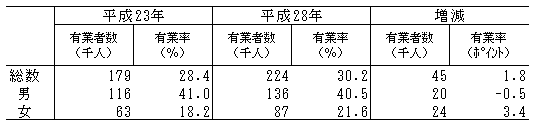
(3)高齢者の仕事時間は減少傾向
65歳以上の高齢者のうち有業者の仕事時間について過去10年間の推移をみると,全体として減少傾向にある。平成28年は4時間9分で,平成18年と比べると45分減少している。平成28年の男性の仕事時間は4時間32分で,平成18年と比べると52分減少し,女性の仕事時間は3時間33分で,平成18年と比べると41分減少している(表5-3)
表5-3男女別仕事時間の推移(平成18年~28年)-週全体,65歳以上有業者
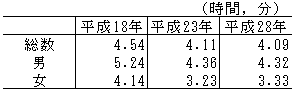
(4)高齢者の介護者数が増加,介護者の介護・看護時間も減少
65歳以上の高齢者のうち,介護者は5万8千人で,平成23年と比べると1万7千人増加している。男性の介護者は2万6千人で,平成23年と比べると9千人増加している。女性の介護者は3万2千人で,8千人増加している。
また,介護者のうち,調査当日に実際に介護・看護を行った人の平均時間(行動者平均時間)をみると,2時間45分で,平成23年と比べると13分の増加である。男女別にみると,男性は3時間35分で,平成23年と比べると1時間25分と大幅に増加した。女性は2時間24分で平成23年と比べ,5分減少した。(表5-4)
表5-4男女別介護者数,行動者平均時間(平23年,28年)-週全体,65歳以上
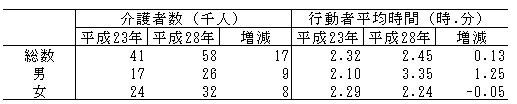
6.スマートフォン・パソコンなどの使用状況
- 注)ここでいう「スマートフォン・パソコンなど」とは,スマートフォン・パソコンのほか,スマートフォン以外の携帯電話,タブレット型端末を含む。
- 注)ここでいう「スマートフォン・パソコンなどの使用」とは,学業,仕事以外の目的で使用した場合をいう。
(1)スマートフォン・パソコンなどを使用した人の割合は,男性は25~29歳,女性は20~24歳で最も高い
スマートフォン・パソコンなどを使用した人の割合1)(以下「使用割合」という。)は,男性が60.6%,女性が57.2%となっている。男女,年齢階級別にみると,男性は25~29歳で91.9%と最も高く,女性は20~24歳で98.3%と最も高くなっている。男女ともに15~54歳にかけて使用割合が70%を超えている。(表6-1,図6-1)
1)スマートフォン・パソコンなどの使用割合は,人口に占めるスマートフォン・パソコンなどを使用した人の割合を算出
表6-1男女,年齢階級別スマートフォン・パソコンなどを使用した人の人数及び割合(平成28年)-週全体
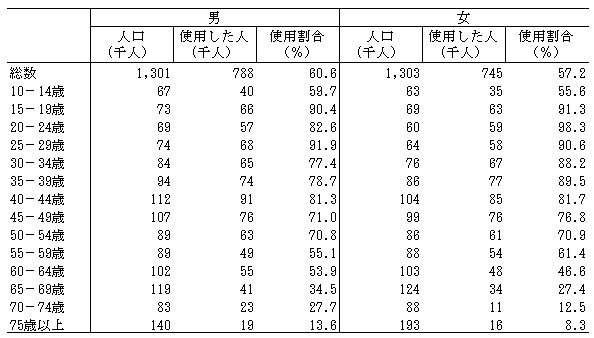
図6-1男女,年齢階級別スマートフォン・パソコンなどの使用割合(平成28年)-週全体
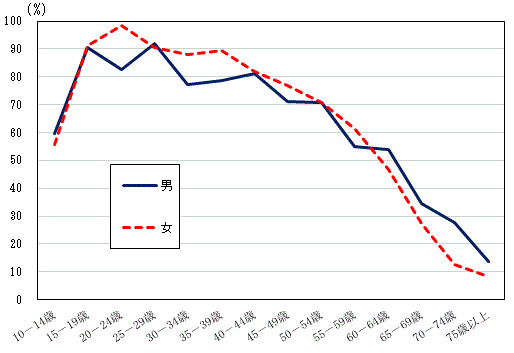
(2)男女とも平日の使用割合が最も高い
曜日別,男女別に使用人数,使用割合をみると,男性は平日が79万7千人で使用割合が61.3%であり,土曜日・日曜日より使用割合が高くなっている。女性も同様に平日が75万9千人,使用割合が58.3%で,土曜日・日曜日より使用割合が高くなっている。男女ともに使用割合は日曜日,土曜日,平日の順で高くなっている。(表6-2,図6-2)
表6-2男女,曜日別スマートフォン・パソコンなどを使用した人の人数及び割合(平成28年)-週全体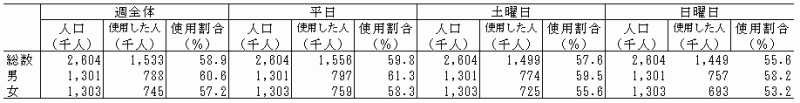
図6-2男女,曜日別スマートフォン・パソコンなどの使用割合(平成28年)-週全体
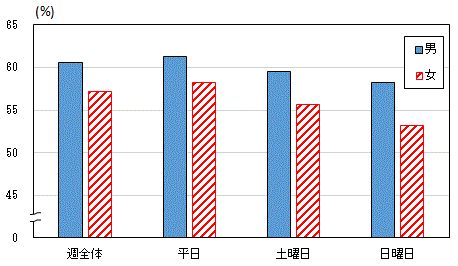
(3)スマートフォン・パソコンなどの使用時間は,1-3時間未満が最多
スマートフォン・パソコンの使用について,使用時間別にみると,男女ともに最も人数が多37.9%である。(表6-3)
表6-3男女,スマートフォン・パソコンなどの使用の有無,使用時間別の人数及び構成比(平成28年)-週全体
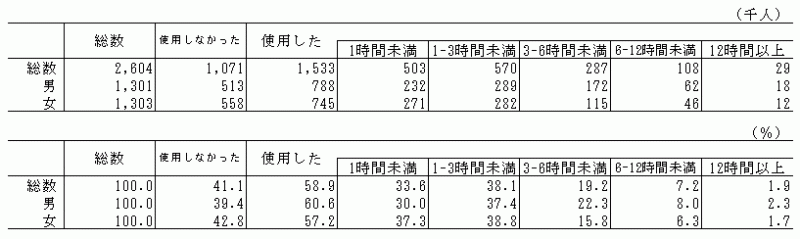
(4)スマートフォン・パソコンなどの使用は,21~24時の時間帯に行動者率が高い
スマートフォン・パソコンなどを使用した人のうち,使用割合が男女共に7割を超えている15~54歳について,年齢階級別に使用した時間帯別の行動者率1)をみると,ほとんどの年齢階級で,21~24時の時間帯の行動者率が最も高くなっている。特に15~19歳の21~24時の時間帯の行動者率は,79.8%と他の年齢階級に比べて最も高くなっている。(図6-3)
1)スマートフォン・パソコンなどを使用した人の人口に占める割合
図6-3年齢階級,スマートフォン・パソコンなどの使用時間帯別行動者率(平成28年)-平日,15~54歳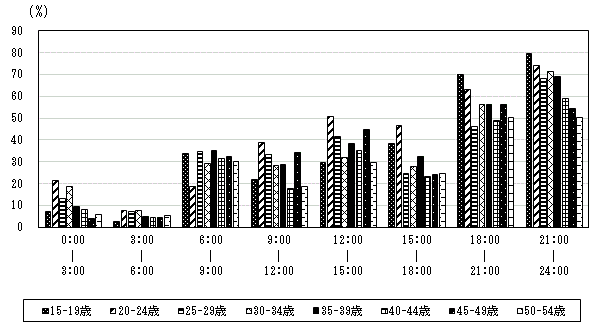
(4)15~24歳では「交際・付き合い・コミュニケーション」の行動者率が最も高い
スマートフォン・パソコンなどを使用した時間帯別の行動者率が最も高い21~24時について,年齢階級,使用目的別1)にみると,15~24歳では「交際・付き合い・コミュニケーション」の行動者率が最も高く,25~49歳では「趣味・娯楽」の行動者率が最も高くなっている。(図6-4)
1)複数回答あり
図6-4年齢階級,スマートフォン・パソコンなどの使用目的別行動者率(平成28年)-平日,21時~24時,15~54歳
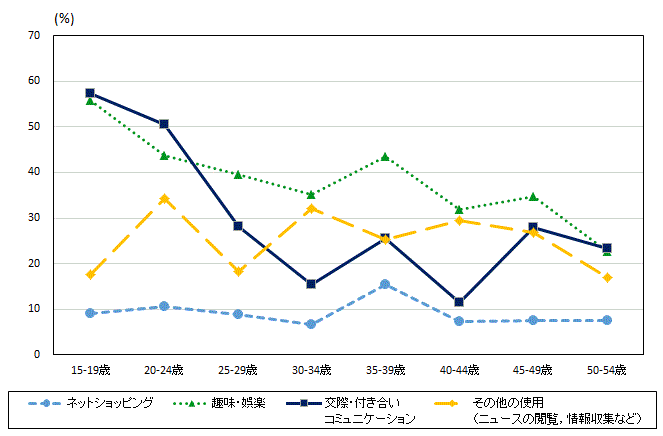
社会生活基本調査結果(茨城県)
総務省統計局(リンク)