目的から探す
ホーム > 県政情報 > 県の概要 > いばらき統計情報ネットワーク > いばらき統計情報ネットワーク(統計課) > 分野別≪物価・景気・家計・経済≫ > 景気動向指数とは
ページ番号:35419
更新日:2024年3月29日
ここから本文です。
景気動向指数とは
景気の様子を数字に表したもの
景気動向指数は、景気の「良し悪し」を数字にしたものです。指数を作るために、県内の景気を表していると考えられる色々な統計データ(経済指標)を集めて加工しています。
景気の循環
茨城県の景気動向指数では、東日本大震災とリーマンショックの時に、下のグラフのようにCIが大きく下降しました。
とくに平成20年9月にリーマンショックが起きた時は、鉱工業生産指数(県統計課)や管内輸出入額(横浜税関貿易統計)、有効求人数(茨城労働局資料)など主要な経済指標が一斉に下降したために、景気は大きく落ち込みました。
しかし、景気は下がれば上がるものです。大きく下降した後に、再び上昇しています。「景気は循環する」ということを景気動向指数は表しています。
茨城県CI一致指数(令和2年(2020年)=100、灰色:茨城県の景気後退期)
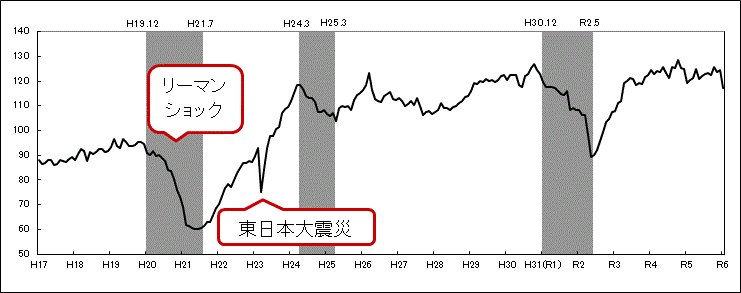
経済データの季節性
経済データは年中行事や自然的な要因によって、定期的なサイクルを持って増減することがよくあります。
一例として、景気動向指数に用いている経済指標のうち、百貨店・スーパー販売額というものがあります。経済産業省が毎月公表しており県内の消費動向が分かります。
この販売額のデータは毎年12月に上昇します。ボーナスがあって買い物が増えるからです。
逆に、生産関連の経済指標で夏場にお盆休みの影響などで落ち込むものがあります。
しかし、これらの動きは季節特有の現象なので、一時的な上がり下がりで景気の良し悪しを判断することはできません。
季節性があるデータは、季節的な影響を取り除く処理(季節調整)をしています。具体的には、前年同月比やX-12-ARIMAという季節調整法を利用しています。
下のグラフは、平成22年1月~平成27年12月の「百貨店・スーパー販売額(茨城県)」の原数値と季節調整値です。季節的な影響を取り除くことで、東日本大震災による消費の落ち込みや消費税増税前の駆け込み需要といった、季節的ではない要因が販売額に影響をもたらしたことがはっきり見て取れるようになります。
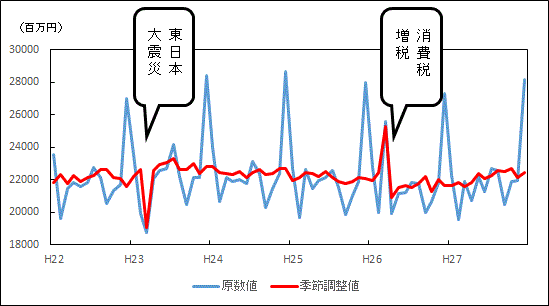
指数の特徴
景気動向指数は、CIとDIの2種類があります。
2つの特徴をまとめると以下のようになります。
CI(コンポジット・インデックス)
- 採用する経済指標を前月と比較する。
- 経済指標の変動を基準化して1つの指数に合成する。
- 景気の変動のテンポや強さを表すことができる。
DI(ディフュージョン・インデックス)
- 採用する経済指標を、3か月前と比較する。
- 上昇(改善)した経済指標の個数を割合で表す。
- 景気の拡張期には割合が50%を上回ることが多くなり、景気の後退期には50%を下回るようになる。
どちらも経済指標の組合せによって、先行、一致、遅行の3つの指数を作成しています。
|
先行指数 |
景気の先行きを表す。 |
|---|---|
|
一致指数 |
現在の景気の様子を表す。 |
|
遅行指数 |
景気の波及ぐあいを事後的に表す。 |
(各指数で採用している経済指標については、毎月公表している月報をご覧ください。)