目的から探す
ホーム > 県政情報 > 県の概要 > いばらき統計情報ネットワーク > いばらき統計情報ネットワーク(統計課) > 分野別≪物価・景気・家計・経済≫ > 平成24年経済センサス-活動調査茨城県結果(確報)
ページ番号:12741
更新日:2023年11月22日
ここから本文です。
平成24年経済センサス-活動調査茨城県結果(確報)
平成25年9月20日掲載
平成26年1月7日更新
平成26年3月20日更新
お知らせ
平成24年経済センサス-活動調査茨城県結果報告(平成25年9月20日公表分)の訂正について
平成24年経済センサス-活動調査茨城県結果報告については,総務省・経済産業省が公表(平成25年8月27日)した集計結果(産業横断的集計(基本編))に基づき,本県分の集計結果をとりまとめ,平成25年9月20日に情報提供したところですが,両省において,平成25年11月27日に公表した集計結果(産業横断的集計(詳細編)等)及び平成26年2月26日に公表した集計結果(存続・新設・廃業別集計編)に関連して,産業分類格付の修正等の誤りを発見したため,これまでの集計結果の一部訂正が行われました。
本県分の集計結果についても,一部訂正を要する箇所がありましたので,両省が11月27日及び2月26日に公表した集計結果の一部訂正データに基づき,改めて本県分の集計結果を取りまとめ,情報提供することにいたしました。なお,訂正した箇所は,本文においては赤字・下線で,表部分においてはセル内を赤色にすることで表示しております。
また,全国の正誤情報等については,次の総務省統計局のホームページを御覧ください。
https://www.stat.go.jp/data/e-census/2012/kakuho/seigo.htm(外部サイトへリンク)
経済センサスについて
経済センサスは,我が国の経済活動を同一時点で網羅的に把握する統計調査です。
経済センサスは,全ての事業所・企業を対象とし,
- 事業所・企業の捕捉,企業構造の把握に重点を置いた「経済センサス-基礎調査」
- 売上高など,経済活動の把握に重点を置いた「経済センサス-活動調査」
の2つの調査で構成されています。
平成21年7月に「平成21年経済センサス-基礎調査」を実施し,その調査で得られた基本的事項や母集団名簿をもとに,平成24年2月に「平成24年経済センサス-活動調査」が実施されました。
平成24年経済センサス-活動調査結果の詳細については,総務省統計局ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
目次
見たい項目をクリックしてください。
結果の概要
調査の概要
利用上の注意
用語の解説
付表
結果の概要
第1.事業所数及び従業者数の状況(事業所に関する集計)
1.概況
事業所数は全国第13位,従業者数は全国第12位
平成24年2月1日現在の県内の事業所数(事業内容等が不詳の事業所を含む。)は122,835事業所(全国の2.1%,第13位),従業者数は1,216,659人(全国の2.2%,第12位)となっている。(第1-1表)
第1-1表:都道府県別事業所数及び従業者数(上位20都道府県)
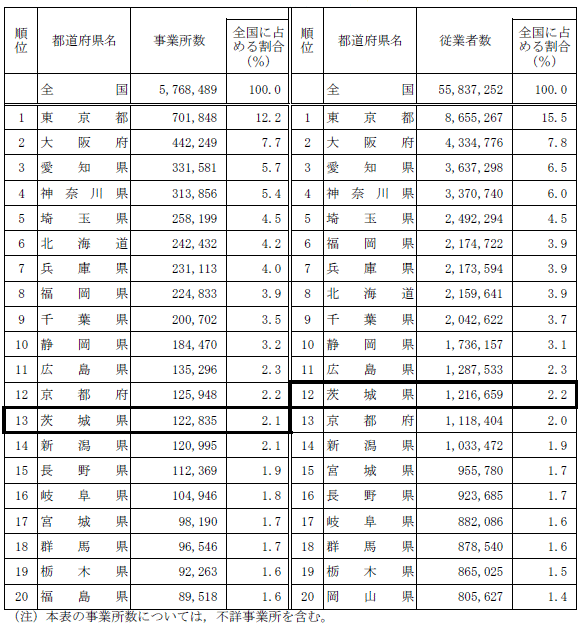
2.産業別
(1)産業別の状況
【産業大分類】
ア.事業所数
「卸売業,小売業」の事業所数が最も多い
県内の事業所数(注:以下,事業所数は,事業内容等が不詳の事業所を除く数値とする。)を産業大分類別にみると,「卸売業,小売業」が30,377事業所(全産業の25.7%)と最も多く,次いで「建設業」が16,092事業所(同13.6%),「宿泊業,飲食サービス業」が13,439事業所(同11.4%)となっており,上位3産業で全体の50.7%を占めている。
全国は「卸売業,小売業」が1,405,021事業所(同25.8%),「宿泊業,飲食サービス業」が711,733事業所(同13.1%),「建設業」が525,457事業所(同9.6%)の順となっている。
産業大分類別構成比を全国と比較すると,「建設業」及び「生活関連サービス業,娯楽業」などで高く,「不動産業,物品賃貸業」及び「宿泊業,飲食サービス業」などで低くなっている。(第1-2表)
第1-2表:産業大分類別事業所数
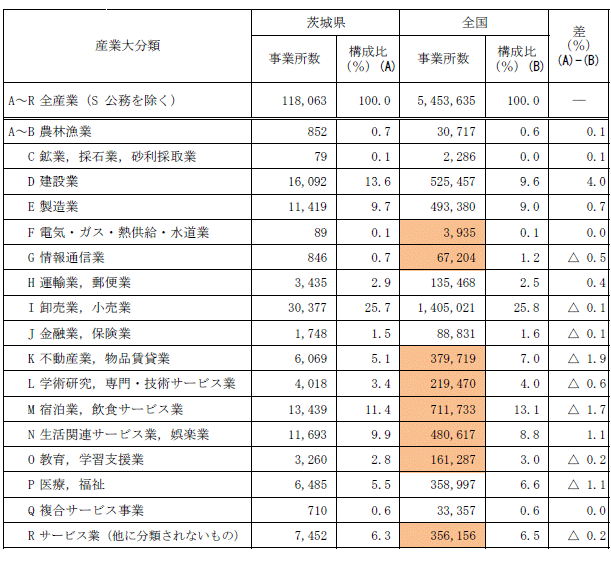
平成21年経済センサス-基礎調査との比較
基礎調査の結果に比べ,「医療・福祉」を除く産業で,事業所数が減少した
県内の産業大分類別事業所数を基礎調査の結果(H21)と比較すると,全産業で9,189事業所(7.2%)減少し,「医療・福祉」が123事業所(1.9%)増加した。(第1-3表及び第1図)
第1-3表:産業大分類別事業所数(民営事業所:前回との比較)
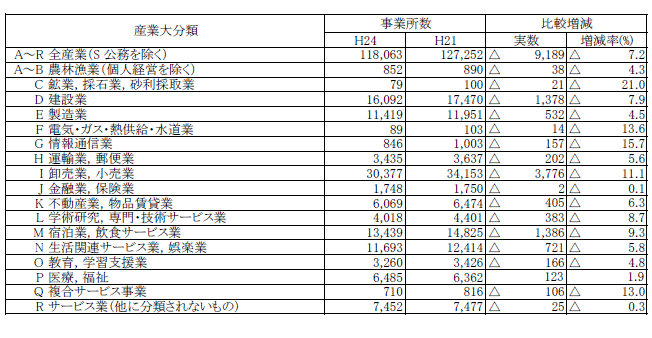
第1図:産業大分類別事業所数の推移
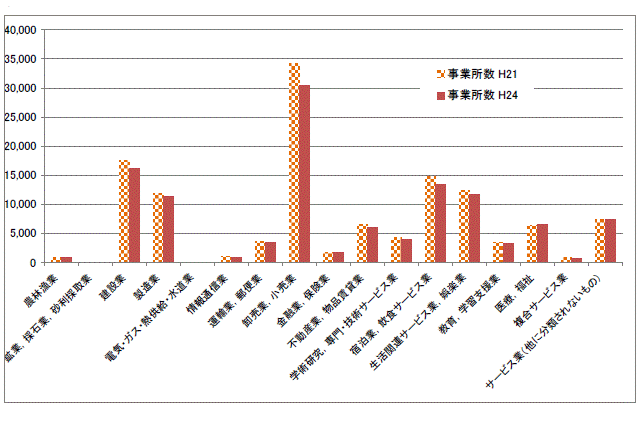
イ.従業者数
「製造業」の従業者数が最も多い
県内の従業者数を産業大分類別にみると,「製造業」が285,796人(全産業の23.5%)と最も多く,次いで「卸売業,小売業」が231,094人(同19.0%),「医療,福祉」が121,019人(同9.9%)となっており,上位3産業で全産業の52.4%を占めている。
全国は「卸売業,小売業」が11,746,468人(同21.0%),「製造業」が9,247,717人(同16.6%),「医療,福祉」が6,178,938人(同11.1%)の順となっている。
産業大分類別構成比を全国と比較すると,「製造業」及び「学術研究,専門・技術サービス業」などで高く,「卸売業,小売業」及び「宿泊業,飲食サービス業」などで低くなっている。(第1-4表)
第1-4表:産業大分類別従業者数
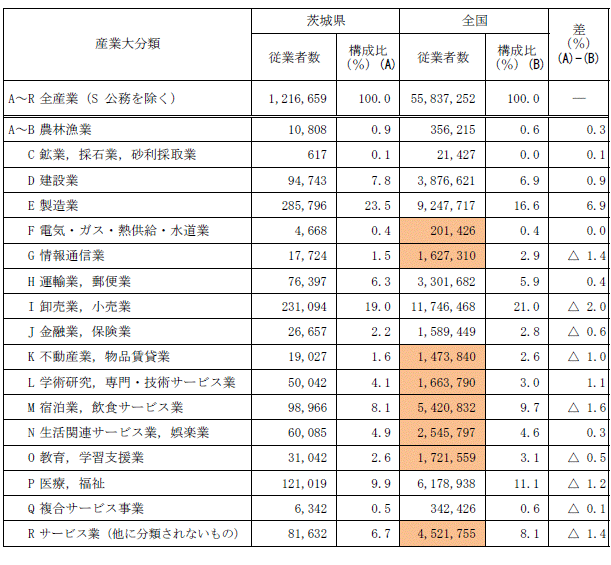
平成21年経済センサス-基礎調査との比較
基礎調査の結果に比べ,「製造業」や「医療・福祉」などで,従業者数が増加した
県内の従業者数を産業大分類別にみて基礎調査の結果(H21)と比較すると,全産業で62,171人(4.9%)減少したが,「製造業」が1,575人(0.6%),「医療・福祉」が7,572人(6.7%)増加した。(第1-5表及び第2図)
第1-5表:産業大分類別従業者数(民営事業所:前回との比較)
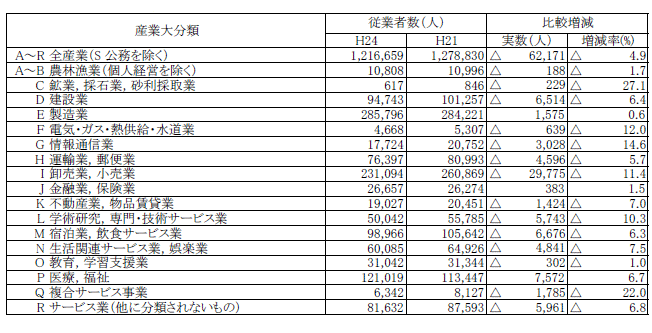
第2図:産業大分類別従業者数の推移
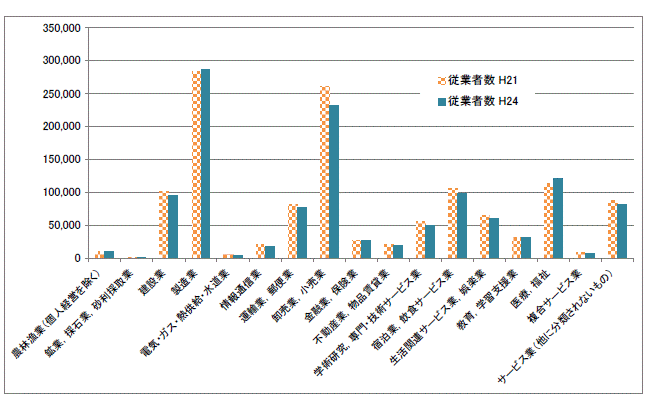
【産業小分類】
ア.事業所数
「美容業」や「専門料理店」の事業所数が多い
産業小分類別に事業所数をみると,「美容業」が4,048事業所(全産業の3.4%)と最も多く,次いで「専門料理店」が3,834事業所(同3.2%),「その他の飲食料品小売業」が3,474事業所(同2.9%)となっている。
全国は「専門料理店」が173,945事業所(同3.2%),「美容業」が169,196事業所(同3.1%),「貸家業,貸間業」が163,207事業所(同3.0%)の順となっている。
産業小分類別構成比を全国と比較すると,「自動車整備業」及び「木造建築工事業」などで高く,「貸家業,貸間業」などで低くなっている。(第1-6表)
第1-6表:産業小分類別事業所数(上位20分類)
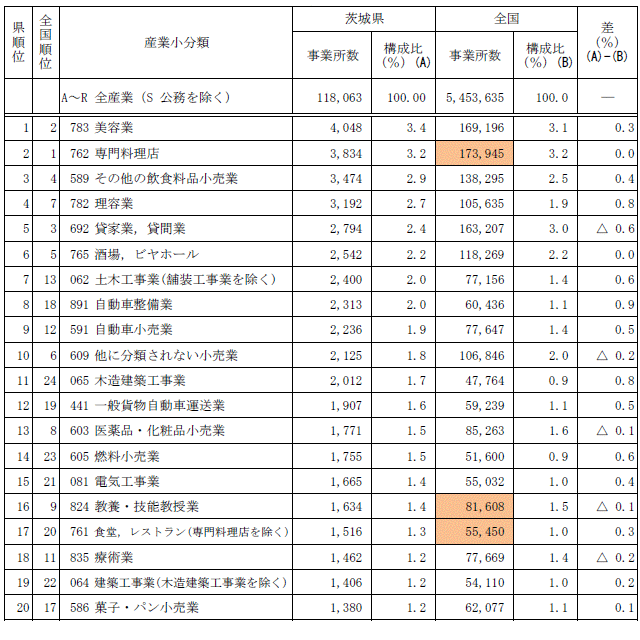
イ.従業者数
「一般貨物自動車運送業」や「病院」の従業者数が多い
産業小分類別に従業者数をみると,「一般貨物自動車運送業」が40,144人(全産業の3.3%)と最も多く,次いで「病院」が39,870人(同3.3%),「老人福祉・介護事業」が34,839人(同2.9%)となっている。
全国は「老人福祉・介護事業」が1,791,286人(同3.2%),「病院」が1,759,677人(同3.2%),「専門料理店」が1,454,268人(同2.6%)の順となっている。
産業小分類別構成比を全国と比較すると,「自然科学研究所」及び「一般貨物自動車運送業」などで高く,「建物サービス業」,「ソフトウェア業」などで低くなっている。(第1-7表)
第1-7表:産業小分類別従業者数(上位20分類)
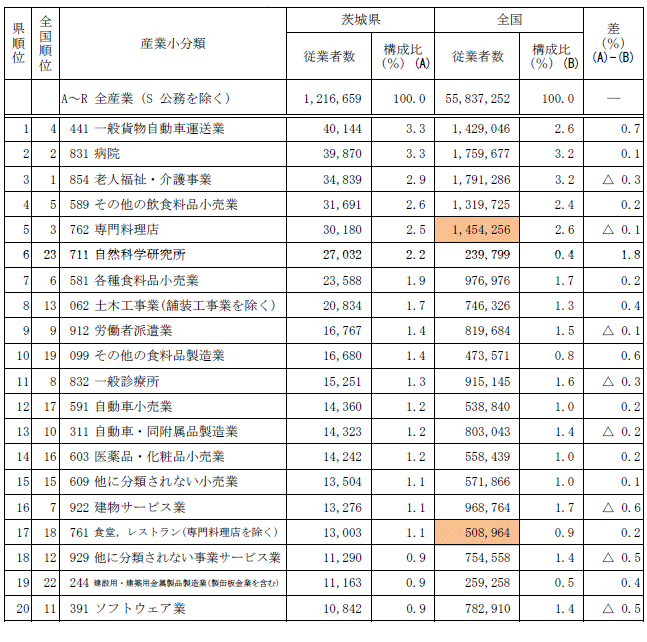
(2)主な産業の状況
ア.「卸売業,小売業」
(ア)【産業中分類】「卸売業,小売業」事業所数
卸売業・小売業の中では,「その他の小売業」や「飲食料品小売業」の事業所数が多い
産業大分類別で事業所数が最も多い,「卸売業,小売業」の事業所数を産業中分類別にみると,「その他の小売業」が8,971事業所(「卸売業,小売業」全体の29.5%)と最も多く,次いで「飲食料品小売業」が7,492事業所(同24.7%),「機械器具小売業」が3,497事業所(同11.5%)などとなっている。
全国は「その他の小売業」が386,453事業所(同27.5%),「飲食料品小売業」が317,983事業所(同22.6%),「織物・衣服・身の回り品小売業」が147,703事業所(同10.5%)の順となっている。
産業中分類別構成比を全国と比較すると,「飲食料品小売業」及び「その他の小売業」などで高く,「その他の卸売業」などで低くなっている。(第1-8表)
第1-8表:「卸売業,小売業」における産業中分類別事業所数

(イ)【産業中分類】「卸売業,小売業」従業者数
卸売業・小売業の中では,「飲食料品小売業」や「その他の小売業」の従業者数が多い
「卸売業,小売業」の従業者数を産業中分類別にみると,「飲食料品小売業」が70,517人(「卸売業,小売業」全体の30.5%)と最も多く,次いで「その他の小売業」が61,801人(同26.7%),「機械器具小売業」が21,527人(同9.3%)などとなっている。
全国は「飲食料品小売業」が3,047,214人(同25.9%),「その他の小売業」が2,512,641人(同21.4%),「機械器具卸売業」が1,058,973人(同9.0%)の順となっている。
産業中分類別構成比を全国と比較すると,「その他の小売業」及び「飲食料品小売業」などで高く,「機械器具卸売業」及び「その他の卸売業」などで低くなっている。(第1-9表)
第1-9表:「卸売業,小売業」における産業中分類別従業者数
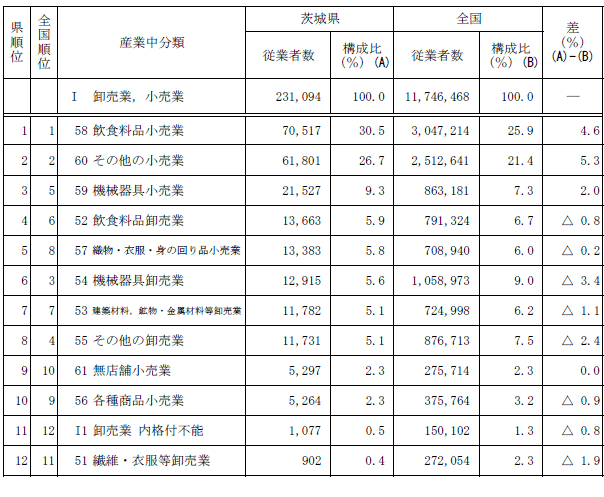
(ウ)【産業小分類】「卸売業,小売業」事業所数
卸売業・小売業の中では,「その他の飲食料品小売業」や「自動車小売業」の事業所数が多い
「卸売業,小売業」の事業所数を産業小分類別にみると,「その他の飲食料品小売業」が3,474事業所(「卸売業,小売業」全体の11.4%)と最も多く,次いで「自動車小売業」が2,236事業所(同7.4%),「他に分類されない小売業」が2,125事業所(同7.0%)などとなっている。
全国は「その他の飲食料品小売業」が138,295事業所(同9.8%),「他に分類されない小売業」が106,846事業所(同7.6%),「医薬品・化粧品小売業」が85,263事業所(同6.1%)の順となっている。
産業小分類別構成比を全国と比較すると,「燃料小売業」及び「自動車小売業」などで高く,「他に分類されない小売業」などで低くなっている。(第1-10表)
第1-10表:「卸売業,小売業」における産業小分類別事業所数(上位20分類)
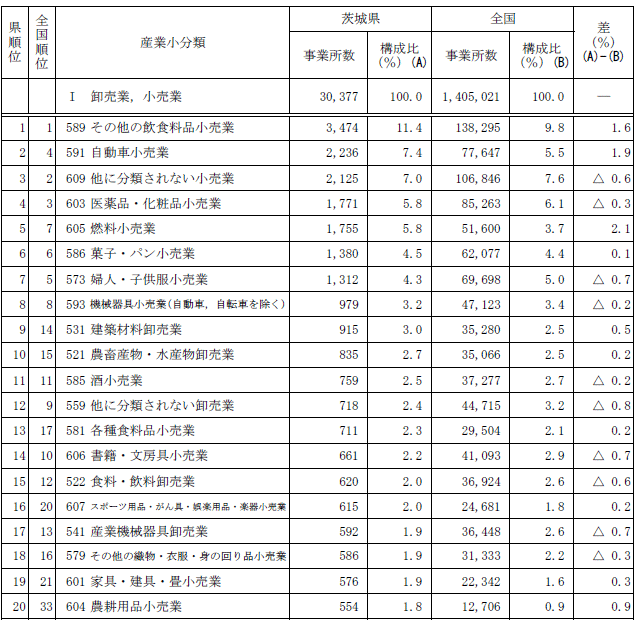
(エ)【産業小分類】「卸売業,小売業」従業者数
卸売業・小売業の中では,「その他の飲食料品小売業」や「各種食料品小売業」の従業者数が多い
「卸売業,小売業」の従業者数を産業小分類別にみると,「その他の飲食料品小売業」が31,691人(「卸売業,小売業」全体の13.7%)と最も多く,次いで「各種食料品小売業」が23,588人(同10.2%),「自動車小売業」が14,360人(同6.2%)などとなっている。
全国は「その他の飲食料品小売業」が1,319,725人(同11.2%),「各種食料品小売業」が976,976人(同8.3%),「他に分類されない小売業」が571,866人(同4.9%)の順となっている。
産業小分類別構成比を全国と比較すると,「その他の飲食料品小売業」及び「各種食料品小売業」などで高く,「電気機械器具卸売業」及び「産業機械器具卸売業」などで低くなっている。(第1-11表)
第1-11表:「卸売業,小売業」における産業小分類別従業者数(上位20分類)
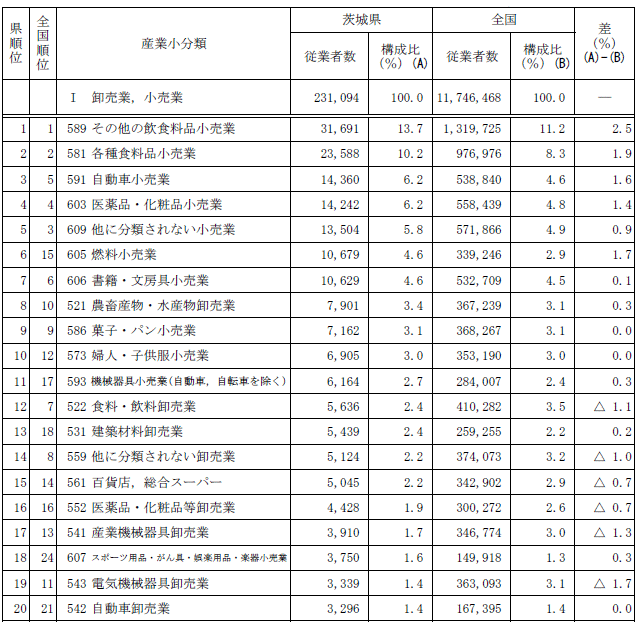
イ.「製造業」
(ア)【産業中分類】「製造業」事業所数
製造業の中では,「金属製品製造業」や「食料品製造業」の事業所数が多い
産業大分類別で従業者数が最も多い,「製造業」の事業所数を産業中分類別にみると,「金属製品製造業」が1,450事業所(「製造業」全体の12.7%)と最も多く,次いで「食料品製造業」が1,338事業所(同11.7%),「窯業・土石製品製造業」が1,032事業所(同9.0%)などとなっている。
全国は「金属製品製造業」が63,083事業所(同12.8%),「食料品製造業」が51,132事業所(同10.4%),「繊維工業」が47,065事業所(同9.5%)の順となっている。
産業中分類別構成比を全国と比較すると,「窯業・土石製品製造業」及び「プラスチック製品製造業」などで高く,「繊維工業」及び「印刷・同関連業」などで低くなっている。(第1-12表)
第1-12表:「製造業」における産業中分類別事業所数
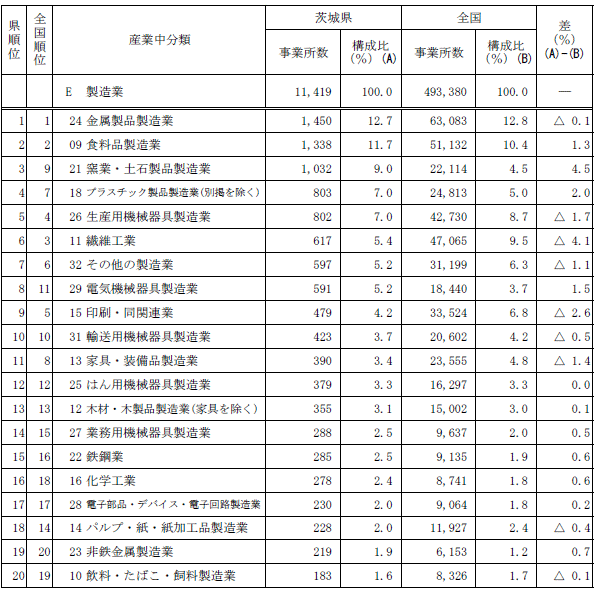
(イ)【産業中分類】「製造業」従業者数
製造業の中では,「食料品製造業」や「電気機械器具製造業」の従業者数が多い
「製造業」の従業者数を産業中分類別にみると,「食料品製造業」が42,348人(「製造業」全体の14.8%)と最も多く,次いで「電気機械器具製造業」が24,550人(同8.6%),「金属製品製造業」が23,664人(同8.3%)などとなっている。
全国は「食料品製造業」が1,288,522人(同13.9%),「輸送用機械器具製造業」が1,068,845人(同11.6%),「金属製品製造業」が713,575人(同7.7%)の順となっている。
産業中分類別構成比を全国と比較すると,「業務用機械器具製造業」及び「電気機械器具製造業」などで高く,「輸送用機械器具製造業」及び「繊維工業」などで低くなっている。(第1-13表)
第1-13表:「製造業」における産業中分類別従業者数
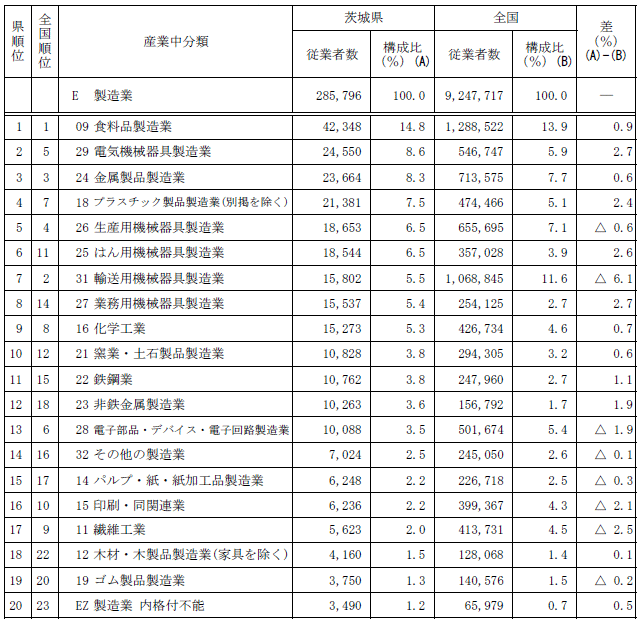
(ウ)【産業小分類】「製造業」事業所数
製造業の中では,「建設用・建築用金属製品製造業(製缶板金業を含む)」や「その他の食料品製造業」の事業所数が多い
「製造業」の事業所数を産業小分類別にみると,「建設用・建築用金属製品製造業(製缶板金業を含む)」の652事業所(「製造業」全体の5.7%)が最も多く,次いで「その他の食料品製造業」が553事業所(同4.8%),「骨材・石工品等製造業」が507事業所(同4.4%)などとなっている。
全国は「印刷業」が26,445事業所(同5.4%),「建設用・建築用金属製品製造業(製缶板金業を含む)」が26,116事業所(同5.3%),「その他の食料品製造業」が19,468事業所(同3.9%)の順となっている。
産業小分類別構成比を全国と比較すると,「骨材・石工品等製造業」などで高く,「印刷業」などで低くなっている。(第1-14表)
第1-14表:「製造業」における産業小分類別事業所数(上位20分類)
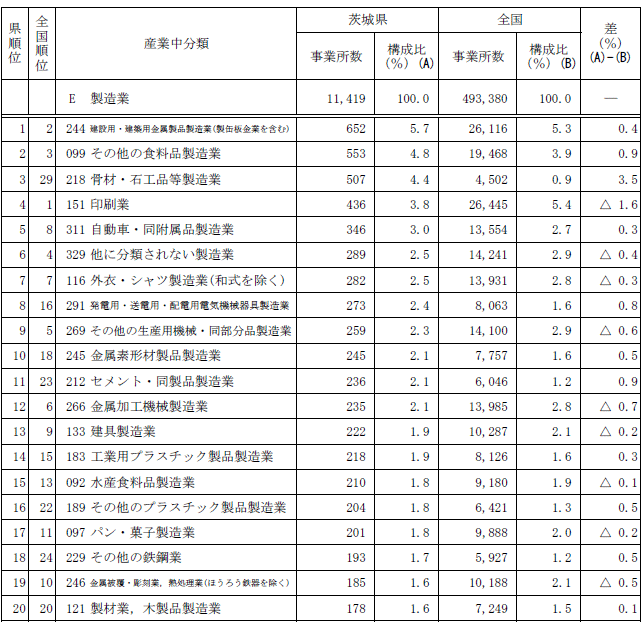
(エ)【産業小分類】「製造業」従業者数
製造業の中では,「その他の食料品製造業」や「自動車・同附属品製造業」の従業者数が多い
「製造業」の従業者数を産業小分類別にみると,「その他の食料品製造業」の16,680人(「製造業」全体の5.8%)が最も多く,次いで「自動車・同附属品製造業」が14,323人(同5.0%),「建設用・建築用金属製品製造業(製缶板金業を含む)」が11,163人(同3.9%)などとなっている。
全国は「自動車・同附属品製造業」が803,043人(同8.7%),「その他の食料品製造業」が473,571人(同5.1%),「印刷業」が314,321人(同3.4%)の順となっている。
産業小分類別構成比を全国と比較すると,「事務用機械器具製造業」などで高く,「自動車・同附属品製造業」及び「印刷業」などで低くなっている。(第1-15表)
第1-15表:「製造業」における産業小分類別従業者数(上位20分類)
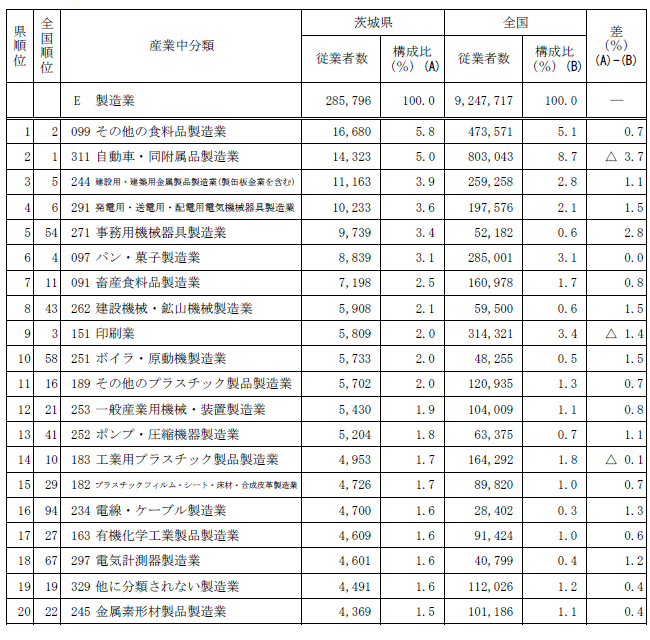
(3)男女別従業者数の状況
性別でみると,男性は「製造業」従業者数が,女性は「卸売業,小売業」従業者数が多い
ア.男性従業者数
産業大分類別に男性従業者数をみると,「製造業」が204,033人(全産業の29.1%),「卸売業,小売業」が110,690人(同15.8%),「建設業」が77,236人(同11.0%)などで高くなっており,この上位3産業で全体の55.9%を占めている。
全国は「製造業」が6,431,556人(同20.5%),「卸売業,小売業」が5,986,965人(同19.1%),「建設業」が3,196,854人(同10.2%)の順となっている。
産業大分類別構成比を全国と比較すると,「製造業」及び「学術研究,専門・技術サービス業」などで高く,「卸売業,小売業」及び「情報通信業」などで低くなっている。(第1-16表)
第1-16表:産業大分類別男性従業者数
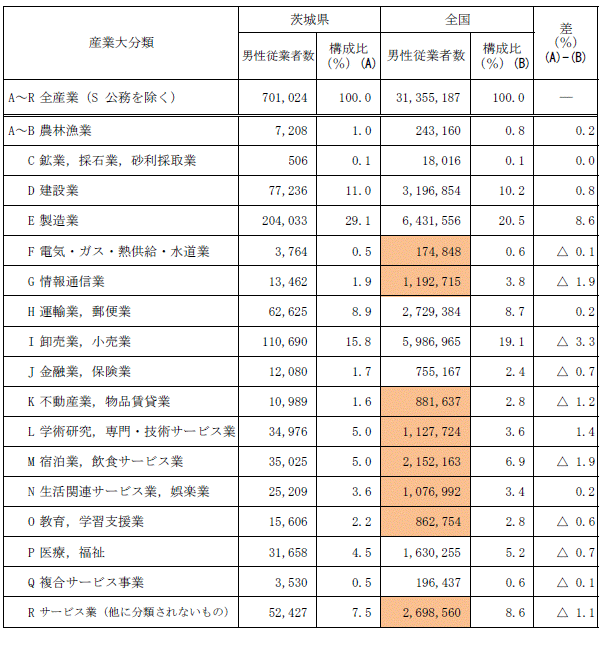
イ.女性従業者数
産業大分類別に女性従業者数をみると,「卸売業,小売業」が119,656人(全産業の23.3%),「医療,福祉」が89,356人(同17.4%),「製造業」が81,763人(同15.9%)などで高くなっており,この上位3産業で全体のの56.7%を占めている。
全国は「卸売業,小売業」が5,731,963人(同23.6%),「医療,福祉」が4,545,432人(同18.7%),「宿泊業,飲食サービス業」が3,186,797人(同13.1%)の順となっている。
産業大分類別構成比を全国と比較すると,「製造業」及び「生活関連サービス業」などで高く,「サービス業(他に分類されないもの)」及び「医療,福祉」などで低くなっている。(第1-17表)
第1-17表:産業大分類別女性従業者数
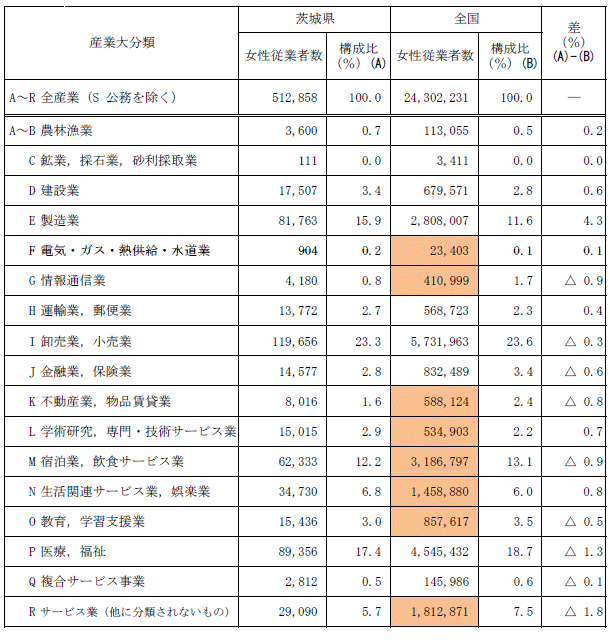
男性従業者数が最も多い産業小分類は「一般貨物自動車運送業」
産業小分類別に男性従業者数をみると,「一般貨物自動車運送業」が34,869人(全産業の5.0%)で最も多く,次いで「自然科学研究所」19,564人(同2.8%),「土木工事業(舗装工事業を除く)」17,065人(同2.4%)の順となっている。
全国は「一般貨物自動車運送業」が1,233,588人(同3.9%),「自動車・同附属品製造業」が676,690人(同2.2%),「専門料理店」が662,283人(同2.1%)の順となっている。
産業小分類別構成比を全国と比較すると,「自然科学研究所」及び「一般貨物自動車運送業」などで高く,「ソフトウェア業」などで低くなっている。(第1-18表)
第1-18表:男性従業者数の多い産業小分類(上位20分類)
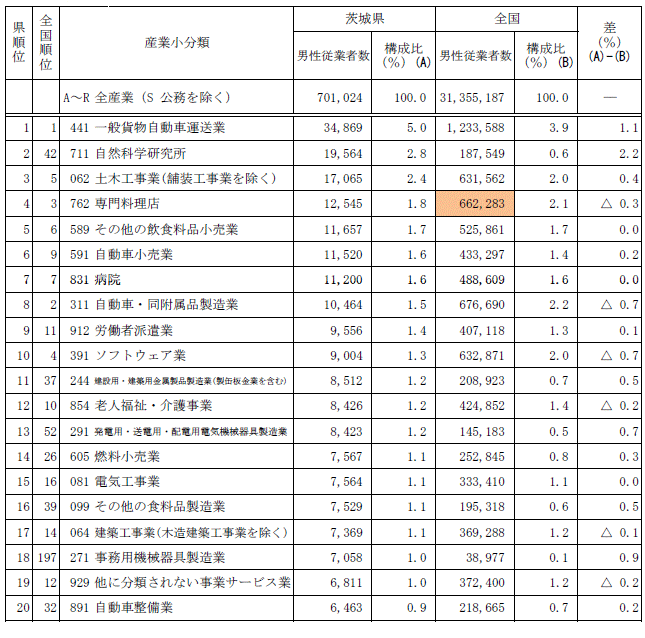
女性従業者数の最も多い産業小分類は「病院」
産業小分類別に女性従業者数をみると,「病院」が28,670人(全産業の5.6%)で最も多く,次いで「老人福祉・介護事業」が26,413人(同5.2%),「その他の飲食料品小売業」が20,034人(同3.9%)の順となっている。
全国は「老人福祉・介護事業」が1,365,966人(同5.6%),「病院」が1,269,196人(同5.2%),「その他の飲食料品小売業」が793,574人(同3.3%)の順となっている。
産業小分類別構成比を全国と比較すると,「自然科学研究所」及び「その他の食料品製造業」などで高く,「建物サービス業」などで低くなっている。(第1-19表)
第1-19表:女性従業者数の多い産業小分類(上位20分類)
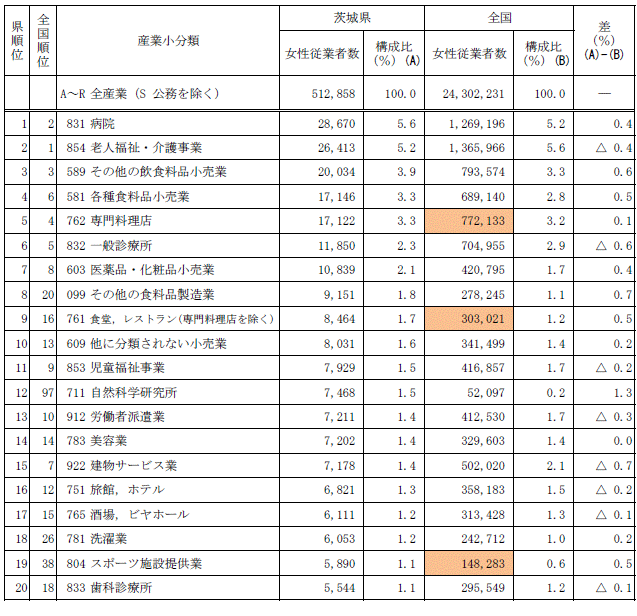
3.経営組織別
「法人」の事業所数及び従業者数の占める割合が高い
ア.事業所数
県内の民営事業所数を経営組織別にみると,「個人」が52,542事業所(民営事業所全体の44.5%),「法人」が65,183事業所(同55.2%),「法人でない団体」が338事業所(同0.3%)となっている。
「法人」のうち,「会社」は58,537事業所(同49.6%),「会社以外の法人」は6,646事業所(同5.6%)となっている。
全国は「個人」が2,204,704事業所(同40.4%),「法人」が3,218,023事業所(同59.0%),「法人でない団体」が30,908事業所(同0.6%)となっている。
「法人」のうち,「会社」は2,839,291事業所(同52.1%),「会社以外の法人」は378,732事業所(同6.9%)となっている。
経営組織別構成比を全国と比較すると,「個人」で高く,「法人」で低い。(第1-20表)
第1-20:経営組織別事業所数
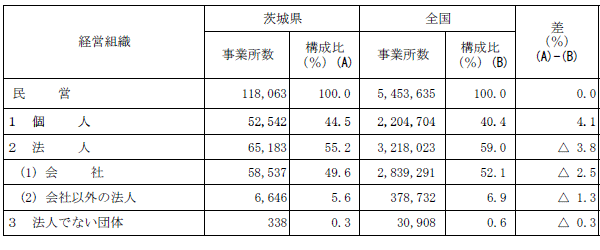
イ.従業者数
県内の民営事業所における従業者数を経営組織別にみると,「個人」が151,557人(従業者全体の12.5%),「法人」が1,063,214人(同87.4%),「法人でない団体」が1,888人(同0.2%)となっている。
「法人」のうち,「会社」は902,263人(同74.2%),「会社以外の法人」は160,951人(同13.2%)となっている。
全国は「個人」が6,374,334人(同11.4%),「法人」が49,327,187人(同88.3%),「法人でない団体」が135,731人(同0.2%)となっている。
「法人」のうち,「会社」は41,921,403人(同75.1%),「会社以外の法人」は7,405,784人(同13.3%)となっている。
経営組織別構成比を全国と比較すると,「個人」で高く,「法人」で低い。(第1-21表)
第1-21表:経営組織別従業者数
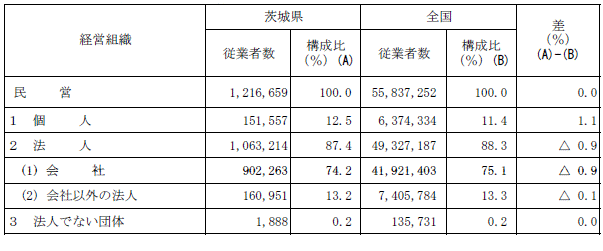
ウ.従業者数の性別による構成
茨城県内の民営事業所の従業者数について,性別による割合を経営組織別にみると,全体では男性従業者数の割合(総数の57.6%)が女性従業者数の割合(同42.2%)より高くなっている。とくに「法人」のうち「会社」経営の事業所においては,男性従業者数の割合(同62.2%)が女性従業者数の割合(同37.5%)より高くなっている。
一方,「個人」経営の事業所においては,男性従業者数の割合(同47.8%)が女性従業者数の割合(同52.2%)より低くなっている(第1-22表及び第3図)
次に,全国の民営事業所の従業者数について,全体では男性従業者数の割合(総数の56.2%)が女性従業者数の割合(同43.5%)より高くなっている。とくに「法人」のうち「会社」経営の事業所において,男性従業者数の割合(同61.0%)は,女性従業者数の割合(同38.6%)より高くなっている。
一方,全国においても「個人」経営の事業所においては,男性従業者の割合(同44.7%)は女性従業者数の割合(同55.3%)よりも低くなっている(第1-23表及び第4図)
第1-22表:経営組織別の男女別従業者数の割合【茨城県】
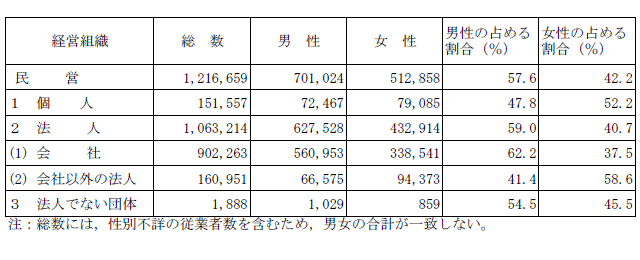
第3図:経営組織別の男女別従業者数の割合【茨城県】
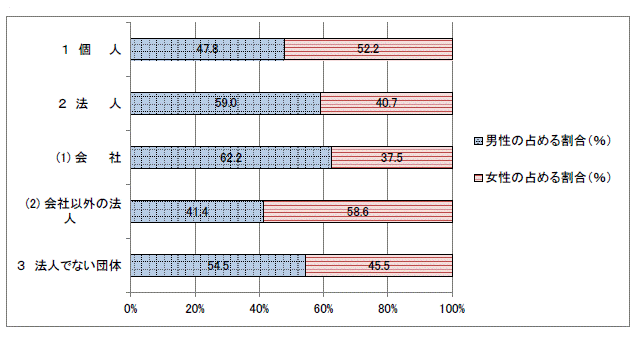
第1-23表:経営組織別の男女別従業者数の割合【全国】
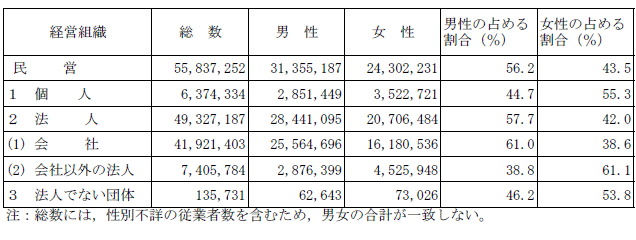
第4図:経営組織別の男女別従業者数の割合【全国】
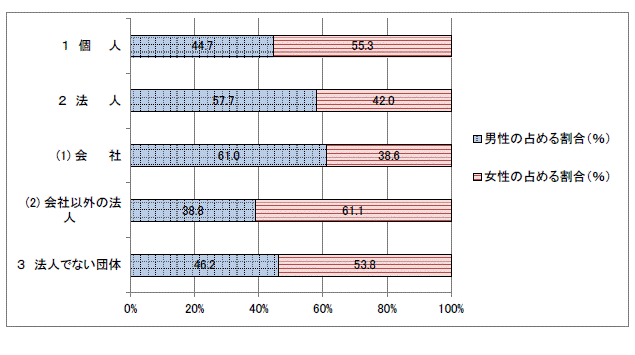
4.地域別
(1)地域別の状況
事業所数,従業者数ともに「県南地域」が最も多い
県内の事業所数を地域別にみると,県南地域が35,283事業所(事業所全体の29.9%)で最も多く,次いで県西地域,県北地域,県央地域,鹿行地域の順となっている。(第1-24表及び第5図)
県内の従業者数を地域別にみると,県南地域が390,788人(従業者全体の32.1%)で最も多く,次いで県北地域,県西地域,県央地域,鹿行地域の順となっている。(第1-24表及び第6図)
第1-24表:地域別事業所数及び従業者数
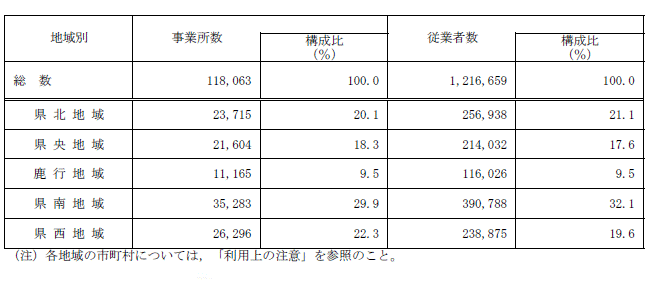
(2)市町村別の状況
事業所数,従業者数ともに上位10市で全体の半数以上を占める
県内の事業所数を市町村別にみると,「水戸市」が13,215事業所(事業所全体の11.2%)と最も多く,次いで「つくば市」が7,876事業所(同6.7%),「日立市」が7,246事業所(同6.1%)の順となっており,上位10市で全体の52.7%を占めている。
県内の従業者数を市町村別にみると,「水戸市」が140,882人(従業者全体の11.6%)と最も多く,次いで「つくば市」が113,530人(同9.3%),「日立市」が93,425人(同7.7%)となっており,上位10市で全体の57.6%を占めている。(第1-25表及び第7図)
第1-25表:市町村別事業所数及び従業者数(上位10市)
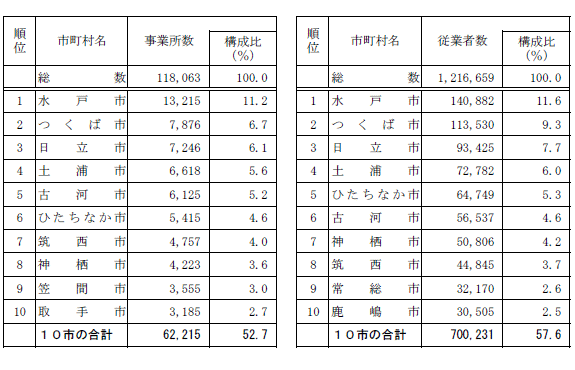
第7図:事業所数と従業者数の分布状況
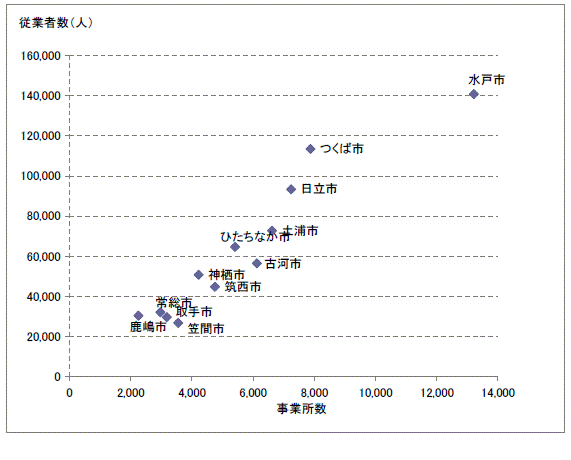
ア.事業所数
事業所数の多い上位10市全てにおいて「卸売業,小売業」の事業所数の占める割合が高い
事業所数の多い上位10市において,産業大分類別に事業所数をみると,全ての市で「卸売業,小売業」の事業所数の占める割合が最も高く,全体の2割を超えている。
「卸売業,小売業」の次に事業所数の割合が高い産業をみると,「建設業」,「宿泊業,飲食サービス業」などとなっている。(第1-26表及び第8図)
第1-26表:事業所数上位10市の産業大分類別事業所数
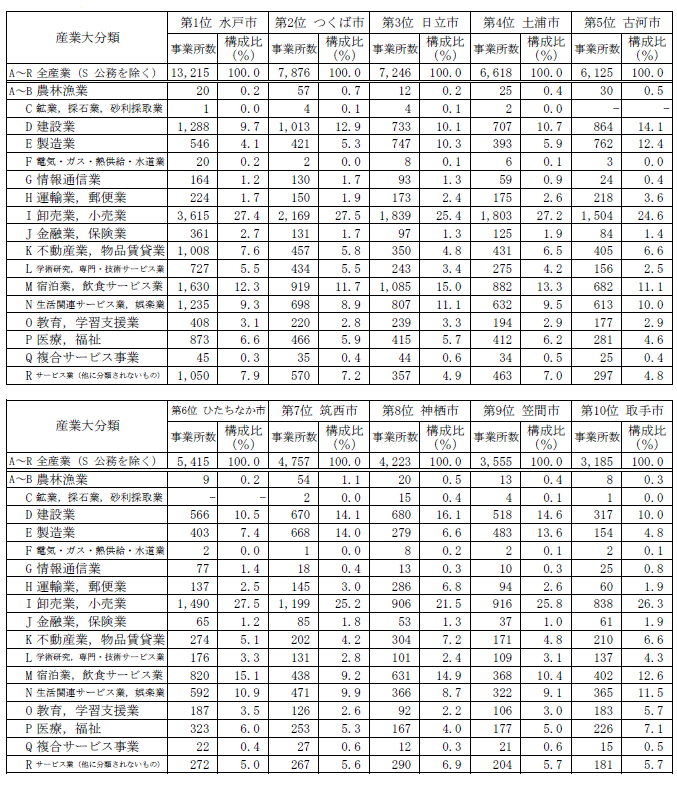
第8図:事業所数上位10市の産業大分類別事業所数
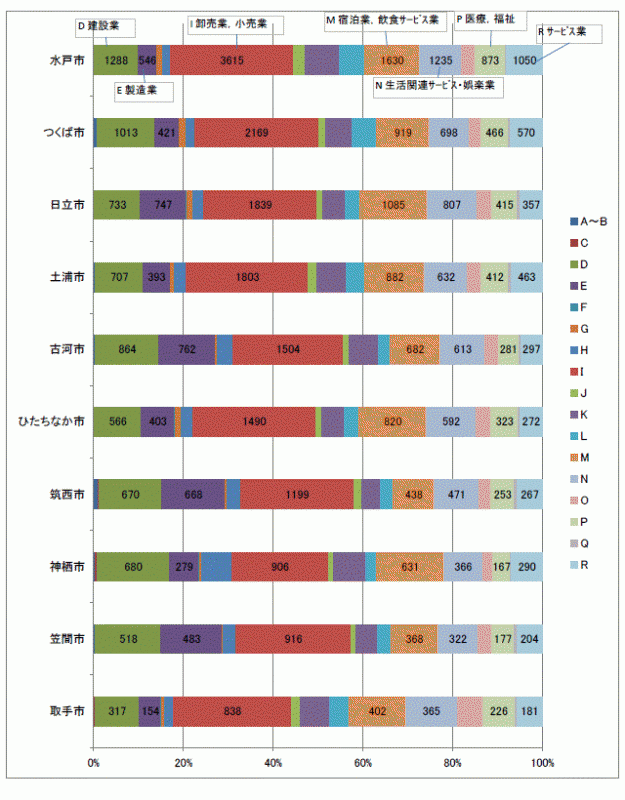
イ.従業者数
従業者数の多い上位10市のうち7市において「製造業」従業者数の占める割合が高い
従業者数の多い上位10市において,産業大分類別に従業者数をみると,7市で「製造業」の従業者数の占める割合が最も高くなっている。
残り3市については,水戸市及び土浦市で「卸売業,小売業」,つくば市で「学術研究・専門,技術サービス業」の従業者数の占める割合が最も高い。(第1-27表及び第9図)
第1-27表:従業者数上位10市の産業大分類別従業者数
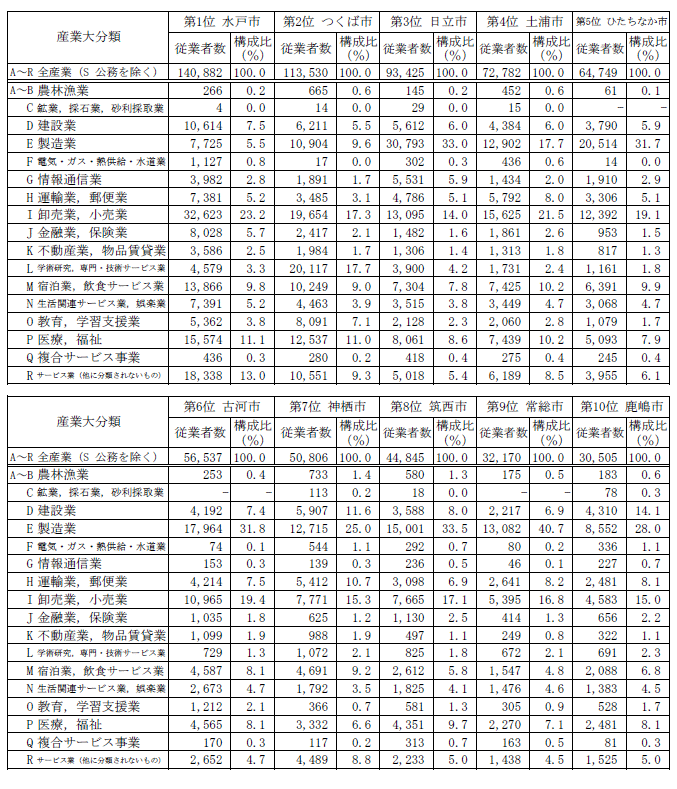
第9図:従業者数上位10市の産業大分類別従業者数
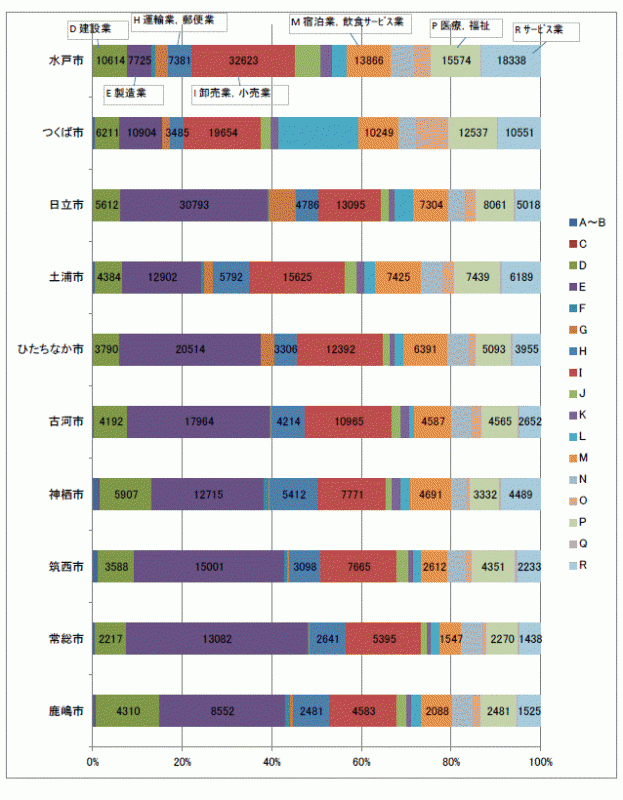
第2.売上高及び付加価値額の状況(事業所に関する集計)
1.産業大分類別売上高(全国及び茨城県)
売上高が高いのは,「製造業」,「卸売業,小売業」,「医療,福祉」などとなっている
産業大分類別に売上高を見てみると,「農林漁業(個人経営を除く)」が1,433億6,500万円で全国第5位,「製造業」が10兆7,894億8,800万円で第9位,「学術研究,専門・技術サービス業」が7,040億3,500万円で全国第7位とそれぞれ上位に位置している。(第2-1表)
第2-1表:大分類別売上高(茨城県・全国)
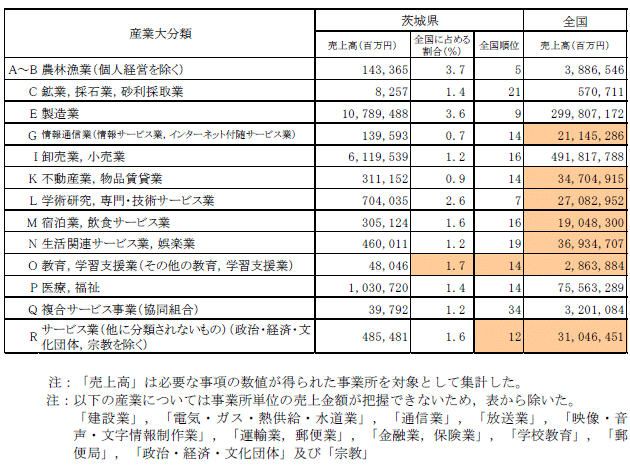
2.産業大分類別売上高(県内市町村)
「製造業」では日立市が県内第1位,「卸売業,小売業」では水戸市が第1位,「学術研究,専門・技術サービス業」ではつくば市が第1位
県内市町村の主な売上高を産業大分類別に見てみると,「製造業」では日立市が1兆3,873億2,600万円で最も多く,次いで神栖市の1兆3,216億1,300万円,ひたちなか市の1兆274億3,600万円の順となっており,上位5市で全体の47.4%を占めている。
「卸売業,小売業」では水戸市が1兆6,201億1,100万円で最も多く,次いでつくば市の7,444億9,100万円,土浦市の4,305億4,500万円の順となっており,上位5市で全体の55.7%を占めている。
「学術研究,専門・技術サービス業」では,つくば市の3,495億1,500万円を筆頭に,東海村の1,134億8,800万円,水戸市の508億9,200万円などの順となっており,つくば市だけで全体の49.6%,上位5市では全体の実に83.1%を占めている。
その他の産業では,「情報通信業(情報サービス業,インターネット付随サービス業)で県内第1位の日立市をはじめ上位5市で全体の88.3%「不動産業,物品賃貸業」で第1位の水戸市をはじめ上位5市で全体の65.2%を占めているのが主な特徴となっている。(第2-2表)
第2-2表:産業大分類別市町村別売上高(上位5位)
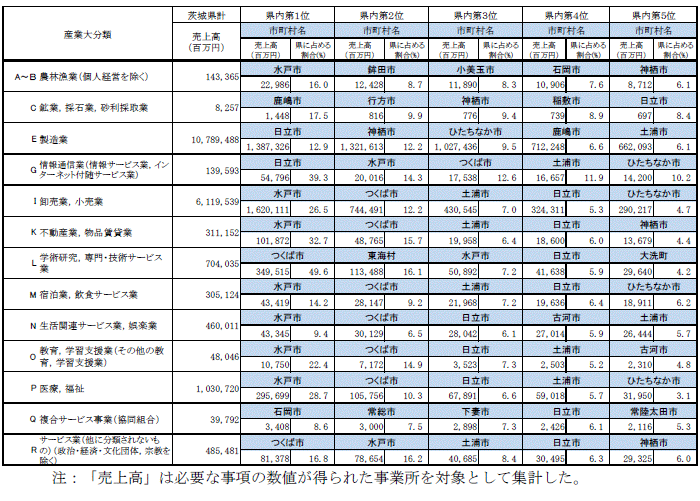
3.産業大分類別付加価値額(全国及び茨城県)
付加価値額が高いのは,「製造業」,「卸売業,小売業」,「医療,福祉」などとなっている
産業大分類別に付加価値額を見てみると,「農林漁業(個人経営を除く)」が347億1,600万円で全国第4位,「製造業」が1兆7,399億3,000万円で第8位,「電気・ガス・熱供給・水道業」が856億1,300万円で第8位,また,「学術研究,専門・技術サービス業」が3,284億5,000万円で全国第7位と上位に位置している。(第2-3表)
第2-3表:大分類別付加価値額(茨城県・全国)
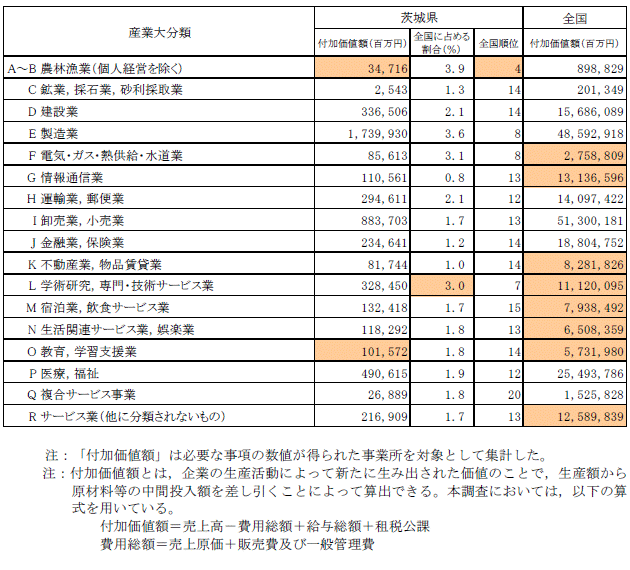
4.産業大分類別付加価値額(県内市町村)
「製造業」では日立市が県内第1位,「卸売業,小売業」では水戸市が同1位,「学術研究,専門・技術サービス業」ではつくば市が同1位
産業大分類別に県内市町村の主な付加価値額を見てみると,「製造業」では日立市が1,396億8,000万円で最も多く,次いでひたちなか市の1,377億6,500万円,神栖市の1,172億6,000万円と続いており,上位5市で全体の35.0%を占めている。
「卸売業,小売業」では水戸市の1,364億8,300万円が最も多く,次いでつくば市の1,088億9,700万円,土浦市の641億2,400万円と続いてており,上位5市で全体の45.7%を占めている。
「学術研究,専門・技術サービス業」ではつくば市の1,389億5,800万円が最も多く,次いで東海村の415億2,200万円,守谷市の221億8,000万円の順となっており,つくば市だけで全体の42.3%,上位5市では全体の73.8%を占めている。
その他の産業では,「情報通信業」で県内第1位の水戸市をはじめ上位5市で全体の87.7%「教育,学習支援業」で第1位のつくば市をはじめ上位5市で全体の70.5%,「電気・ガス・熱供給・水道業」が1位の水戸市をはじめ上位5市で69.9%を占めているのが主な特徴となっている。(第2-4表)
第2-4表:産業大分類別市町村別付加価値額(上位5位)
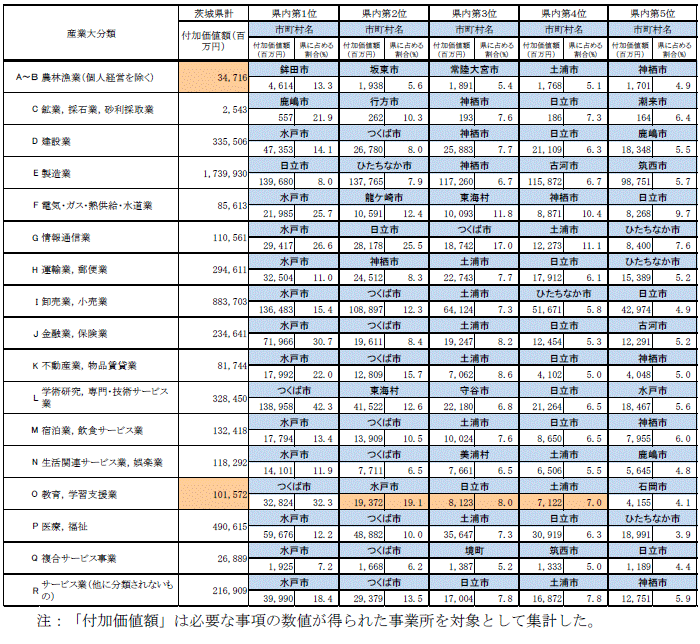
第3.企業等の状況(企業等に関する集計)
1.概況
経営組織では「個人経営」の占める割合が最も高い
県内の企業等数を経営組織別に見てみると,「個人経営」及び「会社以外の法人」を含む企業等の数は90,571企業となっている。
そのうち,「個人経営」が51,935企業(企業等全体の57.3%)となっている。「法人」のうち,「会社企業」(注)は34,410企業(同38.0%)となっている。
全国の企業等の数は4,128,215企業となっている。そのうち,「個人経営」が2,175,262企業(同52.7%)となっている。「法人」のうち,「会社企業」(注)は1,952,954企業(同47.3%)となっている。
経営組織別企業等の構成比を全国と比較すると,本県では「個人経営」で高く,「法人」は低くなっている。(第3-1表)
また,本県の経営組織別構成比を平成21年と比較すると,「個人経営」の割合が減少し,「法人」特に「会社企業」の割合が増加している。(第3-2表)
(注)「会社企業」とは,株式会社(有限会社を含む),合名会社,合資会社,合同会社及び相互会社を合算したものである。
第3-1表:経営組織別企業等数(全国との比較)
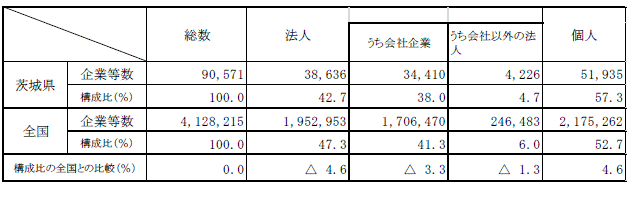
第3-2表:経営組織別企業等数(茨城県:平成21年との比較)
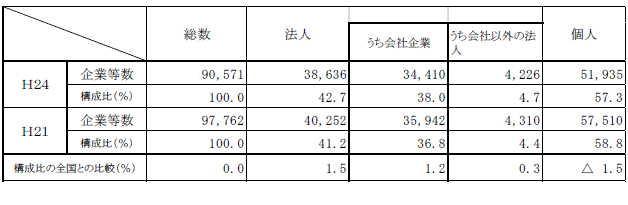
2.産業大分類別企業等数(全国及び茨城県)
企業等数が多いのは,「卸売業,小売業」,「建設業」,「宿泊業,飲食サービス業」の順となっている
県内の企業等数を産業大分類別にみると,「卸売業,小売業」が20,473企業(企業等数全体の22.6%)と最も多く,次いで「建設業」が14,692企業(同16.2%),「宿泊業,飲食サービス業」が10,472企業(同11.6%)となっており,これらの企業で全産業の50.4%を占めている。
全国は,「卸売業,小売業」が930,073企業(同22.5%),「宿泊業,飲食サービス業」が545,801企業(同13.2%),「建設業」が468,199企業(同11.3%)の順となっている。
産業大分類別構成比を全国と比較すると,「建設業」や「生活関連サービス業,娯楽業」などで高く,「不動産業,物品賃貸業」,「宿泊業,飲食サービス業」などで低くなっている。(第3-3表)
第3-3表:産業大分類別企業等数
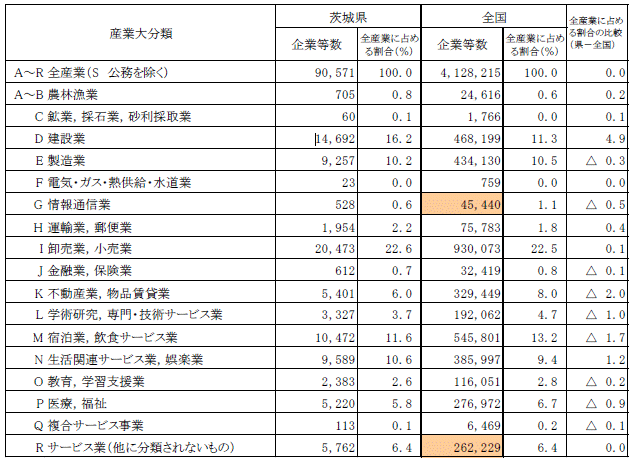
第4.売上高及び付加価値額の状況(企業に関する集計)
1.経営組織別売上高(全国及び茨城県)
経営組織別売上高は,法人が約95%を占めている
本県の売上高を経営組織別に見てみると,「法人」が全体の94.6%を占め,「個人」は5.4%となっている。「法人」のうち「会社企業」が全体の81.0%を占め,「会社以外の法人」は13.6%となっている。
この割合を全国と比較すると,「法人」が3.3%低いのに対し「個人」が3.3%高くなっており,「個人」の占める割合が全国よりやや高くなっている。また,「会社企業」については全国より5.7%低くなっている。(第4-1表)
第4-1表:経営組織別売上高
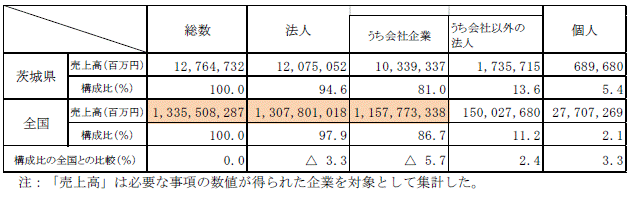
2.経営組織別付加価値額(全国及び茨城県)
経営組織別付加価値額は,法人が約91%を占めている
本県の付加価値額を経営組織別に見てみると,「法人」が全体の90.6%を占め,「個人」は9.4%となっている。「法人」のうち「会社企業」が全体の68.6%を占め,「会社以外の法人」は22.0%となっている。
この割合を全国と比較すると,「法人」が4.7%低いのに対し「個人」が4.7%高くなっており,個人企業の占める割合が全国より高くなっている。また,「会社以外の法人」が7.1%高いのに対し,「会社企業」については11.7%低くなっている。(第4-2表)
第4-2表:経営組織別付加価値額
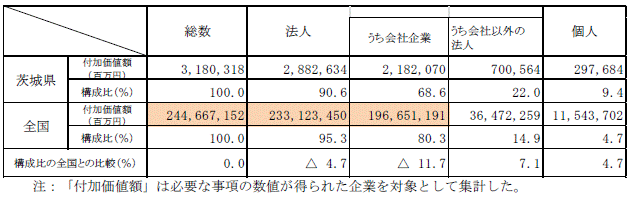
3.産業大分類別売上高(全国及び茨城県)
「卸売業,小売業」,「製造業」,「建設業」の順に売上高が高くなっている
本県の売上高を産業大分類別に見てみると,「卸売業,小売業」が4兆2,377億9,500万円で最も多く,全産業の33.2%を占め,次いで「製造業」の3兆1,051億3,400万円(全産業の24.3%),「建設業」の1兆1,389億8,700万円(全産業の8.9%)の順となっている。
また,全産業に占める割合を全国と比較すると,「学術研究,専門・技術サービス業」が4.2%,「建設業」が2.7%,「卸売業,小売業」が2.1%全国よりそれぞれ高い一方,「金融業,保険業」が6.2%,「情報通信業」が2.4%低くなっている。(第4-3表)
第4-3表:産業大分類別売上高
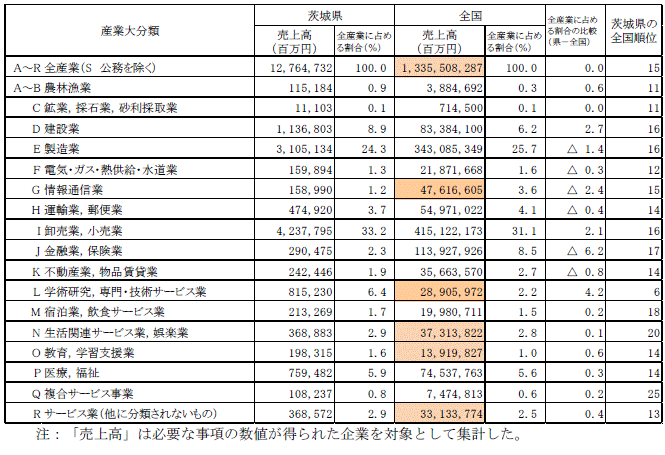
4.産業大分類別付加価値額(全国及び茨城県)
「製造業」,「卸売業,小売業」,「医療,福祉」の順に付加価値額が高くなっている
産業大分類別に付加価値額を見てみると,「製造業」が6,712億3,600万円で全産業の21.1%を占め,次いで「卸売業,小売業」の6,480億3,400万円(全産業の20.4%),「医療,福祉」の4,176億5,900万円(全産業の13.1%)の順となっている。
また,全産業に占める割合を全国と比較すると,「医療,福祉」が3.2%,「学術研究,専門・技術サービス業」が2.9%,「建設業」が2.3%,「卸売業,小売業」が1.8%全国よりそれぞれ高い一方,「金融業,保険業」が4.0%,「情報通信業」が3.1%低くなっている。(第4-4表)
第4-4表:産業大分類別付加価値額
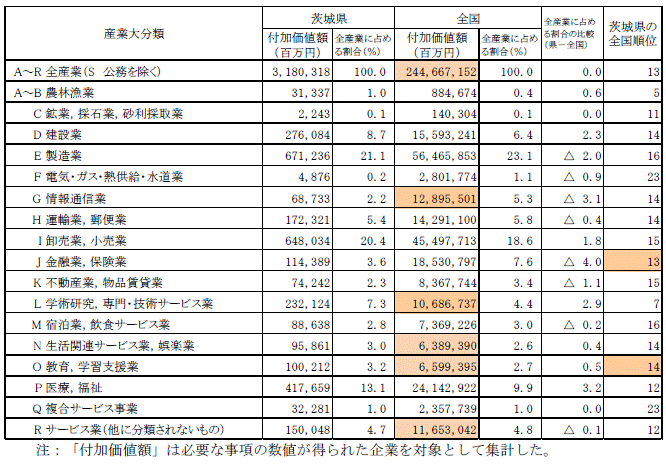
調査の概要
1.調査の目的
経済センサス-活動調査は,我が国の全産業分野における事業所及び企業の経済活動の実態を全国的及び地域別に明らかにするとともに,事業所及び企業を調査対象とする各種統計調査の精度向上に資する母集団資料を得ることを目的として新たに創設された統計調査である。
2.調査日
平成24年2月1日
3.調査対象
(1)地域的範囲
全国(調査日現在において,東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)に関して原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第28条第2項において読み替えて適用される災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第63条第1項の規定に基づく警戒区域又は原子力災害対策本部により設定された計画的避難区域をその区域に含む調査区を除く。)
(2)属性的範囲
調査は,日本標準産業分類に掲げる産業に属する事業所のうち,以下に掲げる事業所並びに国及び地方公共団体の事業所を除く事業所・企業(以下「調査事業所」という。)について行った。
- 1.大分類A-農業,林業に属する個人経営の事業所
- 2.大分類B-漁業に属する個人経営の事業所
- 3.大分類N-生活関連サービス業,娯楽業のうち,小分類792-家事サービス業に属する事業所
- 4.大分類R-サービス業(他に分類されないもの)のうち,中分類96-外国公務に属する事業所
4.調査の単位
原則として,単一の経営者が事業を営んでいる1区画の場所を1事業所とし,これを調査の単位とした。単一の経営者が,異なる場所で事業を営んでいる場合は,それぞれの場所ごとに,また,1区画の場所で異なる経営者が事業を営んでいる場合は,経営者が異なるごとに1事業所とした。
なお,事業所としての取扱いに関し,以下に掲げるものについては,特例を設けた。
(1)建設業
作業の行われている工事現場,現場事業所などは,それらを直接管理している本社,支店,営業所,出張所などの事業所に含めて調査した。また,自営の大工,左官,塗装工事・屋根工事・配管工事・電気工事などの業者については,工事現場では調査せず,それらの業者の事業所又は自宅で,その従業者も含めて調査した。
(2)運輸業
鉄道,自動車,船舶,航空機などによる運輸業は,管理責任者のいる場所を事業所とした。鉄道業について,駅,車掌区,車両工場などは,それぞれを1事業所とした。ただし,駅長,区長などの管理責任者の置かれていない事業所は,管理責任者のいる事業所に含めて調査した。
(3)学校
同一の学校法人に属する幾つかの学校,例えば,大学,高等学校,中学校,小学校,幼稚園などが同一構内にあるような場合,学校ごとにそれぞれ1事業所とした。ただし,高等学校に併設されている定時制課程などは別の事業所とせず,その高等学校に含めて調査した。
5.調査事項
【単独事業所調査票】
全産業的共通事項(単独事業所)
- ア名称及び電話番号
- イ所在地
- ウ経営組織(協同組合においては協同組合の種類)
- エ開設時期
- オ従業者数
- カ売上(収入)金額,費用総額及び費用内訳(協同組合においては経常収益,経常費用及び費用内訳)
- キ事業別売上(収入)金額
- ク主な事業の内容
- ケ電子商取引の有無及び割合(個人経営及び法人のみ)
- コ設備投資の有無及び取得額(個人経営及び法人のみ)
- サ自家用自動車の保有台数(個人経営及び法人のみ)
- シ土地,建物の所有の有無(法人のみ)
- ス資本金等の額及び外国資本比率(会社のみ)
- セ決算月(会社のみ)
産業別に調査する事項
【1】<農業,林業,漁業調査票>
- ア全産業共通事項(単独事業所)
- イ農業,林業,漁業の収入の内訳
【2】<鉱業,採石業,砂利採取業調査票>
- ア全産業共通事項(単独事業所)
- イ給与総額等
- ウ鉱業活動に係る費用
- エ生産数量及び生産金額
【3】<製造業調査票>
- ア全産業共通事項(単独事業所)
- イ人件費及び人材派遣会社への支払額
- ウ原材料,燃料,電力の使用額,委託生産費,製造等に関連する外注費及び転売した商品の仕入額
- エ有形固定資産
- オリース契約による契約額及び支払額
- カ製造品在庫額,半製品,仕掛品の価額及び原材料,燃料の在庫額
- キ製造品出荷額,在庫額等
- ク酒税,たばこ税,揮発油税及び地方揮発油税の合計額
- ケ製造品出荷額等に占める直接輸出額の割合
- コ主要原材料名
- サ工業用地及び工業用水
- シ作業工程
【4】<卸売業,小売業調査票(個人経営者用)>
- ア全産業共通事項(単独事業所)
- イ年間商品販売額等
- ウ商品手持額
- エ小売販売額の商品販売形態別割合
- オセルフサービス方式の採用
- カ売場面積
- キ営業時間
- ク店舗形態
- ケチェーン組織への加盟
【5】<卸売業,小売業調査票(法人・団体用)>
- ア全産業共通事項(単独事業所)
- イ年間商品販売額等
- ウ商品手持額
- エ商品売上原価(法人のみ)
- オ小売販売額の商品群別割合
- カ小売販売額の商品販売形態別割合
- キセルフサービス方式の採用
- ク売場面積
- ケ営業時間
- コ店舗形態
- サチェーン組織への加盟
【6】<医療,福祉調査票>
- ア全産業共通事項(単独事業所)
- イ医療,福祉事業の収入の内訳
- ウ医療,福祉事業の収入の相手先別収入割合
- エ事業所の形態,主な事業の内容
【7】<学校教育調査票>
- ア全産業共通事項(単独事業所)
- イ学校等の種類
【8】<建設業,サービス関連産業A調査票>
- ア全産業共通事項(単独事業所)
- イ主な事業収入の内訳
- ウ業態別工事種類
- エ建設業許可番号
- オ金融業,保険業,郵便局受託業の事業種類
- カ政治・経済・文化団体,宗教団体の団体種類
【9】<協同組合調査票>
- ア全産業共通事項(単独事業所)
【10】<サービス関連産業B調査票(個人経営者用)>
- ア全産業共通事項(単独事業所)
- イサービス関連産業Bの事業収入内訳
- ウ施設・店舗等形態
- エサービス関連産業Bの相手先別収入割合
- オ飲食サービス業の8時間換算雇用者数
- カ宿泊業の収容人数,客室数
- キ物品賃貸業のレンタル年間売上高及びリース年間契約高
- ク特定のサービス業における取扱件数,入場者数,利用者数等
【11】<サービス関連産業B調査票(法人・団体用)>
- ア全産業共通事項(単独事業所)
- イサービス関連産業Bの事業収入内訳
- ウ施設・店舗等形態
- エサービス関連産業Bの相手先別収入割合
- オ飲食サービス業の8時間換算雇用者数
- カ宿泊業の収容人数,客室数
- キ物品賃貸業のレンタル年間売上高及びリース年間契約高
- ク特定のサービス業における取扱件数,入場者数,利用者数等
- ケ特定のサービス業における同業者との契約割合
【産業共通調査票】
全産業共通事項のみ
【12】<産業共通調査票>
- ア事業所の名称及び電話番号
- イ事業所の所在地
- ウ経営組織
- エ事業所の開設時期
- オ事業所の従業者数
- カ事業所の主な事業の内容
- キ本所・支所の別及び本所等の名称・所在地
- ク企業全体の売上(収入)金額,費用総額及び費用内訳
- ケ事業別売上(収入)金額
- コ電子商取引の有無及び割合(個人経営及び法人のみ)
- サ設備投資の有無及び取得額(個人経営及び法人のみ)
- シ自家用自動車の保有台数(個人経営及び法人のみ)
- ス土地,建物の所有の有無(法人のみ)
- セ商品売上原価(法人のみ)
- ソ移転及び名称変更の有無(法人のみ)
- タ資本金等の額及び外国資本比率(会社のみ)
- チ決算月(会社のみ)
- ツ企業全体の主な事業の内容(本所,本社,本店のみ)
- テ支所・支社・支店の数(本所,本社,本店のみ)
- ト企業全体の常用雇用者数(本所,本社,本店のみ)
【企業調査票】
全産業共通事項(企業)
【13】<企業調査票>
- ア名称及び電話番号
- イ所在地
- ウ経営組織
- エ海外支所等の数及び海外支所等の常用雇用者数
- オ企業全体の主な事業の内容
- カ企業全体の売上(収入)金額,費用総額及び費用内訳
- キ企業全体の事業別売上(収入)金額
- ク電子商取引の有無及び割合
- ケ設備投資の有無及び取得額
- コ自家用自動車の保有台数
- サ土地,建物の所有の有無(法人のみ)
- シ商品売上原価(法人のみ)
- ス資本金等の額及び外国資本比率(会社のみ)
- セ決算月(会社のみ)
産業別に調査する事項
【14】<企業調査票(学校教育)>
- ア全産業共通事項(企業)
- イ学校等種類別収入内訳
【15】<企業調査票(建設業,サービス関連産業A)>
- ア全産業共通事項(企業)
- イ主な事業収入の内訳
- ウ業態別工事種類
- エ建設業許可番号
- オ金融業,保険業の事業種類
- カ政治・経済・文化団体,宗教団体の団体種類
【事業所調査票】
全産業共通事項(事業所)
- ア事業所の名称及び電話番号
- イ事業所の所在地
- ウ事業所の開設時期
- エ事業所の従業者数
- オ本所等か否か
- カ管理・補助的業務
産業別に調査する事項
【16】<農業,林業,漁業調査票>
- ア全産業共通事項(事業所)
- イ主な事業の内容
- ウ事業所の売上(収入)金額
- エ事業別売上(収入)金額
- オ農業,林業,漁業の収入の内訳
【17】<鉱業,採石業,砂利採取業調査票>
- ア全産業共通事項(事業所)
- イ主な事業の内容
- ウ事業所の売上(収入)金額
- エ事業別売上(収入)金額
- オ給与総額等
- カ鉱業活動に係る費用
- キ生産数量及び生産金額
【18】<製造業調査票>
- ア全産業共通事項(事業所)
- イ主な事業の内容
- ウ事業所の売上(収入)金額
- エ事業別売上(収入)金額
- オ人件費及び人材派遣会社への支払額
- カ原材料,燃料,電力の使用額,委託生産費,製造等に関連する外注費及び転売した商品の仕入額
- キ有形固定資産
- クリース契約による契約額及び支払額
- ケ製造品在庫額,半製品,仕掛品の価額及び原材料,燃料の在庫額
- コ製造品出荷額,在庫額等
- サ酒税,たばこ税,揮発油税及び地方揮発油税の合計額
- シ製造品出荷額等に占める直接輸出額の割合
- ス主要原材料名
- セ工業用地及び工業用水
- ソ作業工程
【19】<卸売業,小売業調査票>
- ア全産業共通事項(事業所)
- イ主な事業の内容
- ウ事業所の売上(収入)金額
- エ事業別売上(収入)金額
- オ年間商品販売額等
- カ商品手持額
- キ小売販売額の商品群別割合(個人経営以外)
- ク小売販売額の商品販売形態別割合
- ケセルフサービス方式の採用
- コ売場面積
- サ営業時間
- シ店舗形態
- スチェーン組織への加盟
【20】<医療,福祉調査票>
- ア全産業共通事項(事業所)
- イ事業所の売上(収入)金額
- ウ事業別売上(収入)金額
- エ医療,福祉事業の収入の内訳
- オ医療,福祉事業の収入の相手先別収入割合
- カ事業所の形態,主な事業の内容
【21】<学校教育調査票>
- ア全産業共通事項(事業所)
- イ学校等の種類
【22】<建設業,サービス関連産業A調査票>
- ア全産業共通事項(事業所)
- イ主な事業の種類
【23】<協同組合調査票>
- ア全産業共通事項(事業所)
- イ事業所の売上(収入)金額
- ウ事業別売上(収入)金額
- エ協同組合の種類
- オ信用事業又は共済事業の実施の有無
【24】<サービス関連産業B調査票>
- ア全産業共通事項(事業所)
- イ主な事業の内容
- ウ事業所の売上(収入)金額
- エ事業別売上(収入)金額
- オサービス関連産業Bの事業収入内訳
- カ施設・店舗等形態
- キサービス関連産業Bの相手先別収入割合
- ク飲食サービス業の8時間換算雇用者数
- ケ宿泊業の収容人数,客室数
- コ物品賃貸業のレンタル年間売上高及びリース年間契約高
- サ特定のサービス業における取扱件数,入場者数,利用者数等
- シ特定のサービス業における同業者との契約割合(個人経営以外)
6.調査の方法
調査は「調査員調査」と「郵送調査及びオンライン調査」の2種類からなる。
(1)調査員調査
単独事業所(ただし,(2)における特定の単独事業所を除く。)及び新設事業所については,調査員が調査票の配布・回収を行った。または,調査員が調査票を配布し,市区町村が郵送により回収を行った。
- 総務省及び経済産業省-都道府県-市区町村-統計調査員-調査事業所
(2)郵送調査及びオンライン調査
従業者数30人未満の複数事業所を有する企業の事業所については市区及び都道府県が,従業者数30人以上の複数事業所を有する企業の事業所については総務省及び経済産業省が,それぞれ本所事業所に対して郵送により調査票の配布・回収を行った。また,特定の単独事業所及び新設事業所については,総務省及び経済産業省が,郵送により調査票の配布・回収を行った。
なお,郵送調査の調査対象事業所のうち希望する事業所に対しては,オンラインにより調査票の回収を行った。
- ア.市区による調査
同一市区内に全事業所を有する従業者数30人未満の企業の事業所(ウに掲げるものを除く。)
・総務省及び経済産業省-都道府県-市区-調査事業所 - イ.都道府県による調査
同一都道府県内に本所及び支所となる事業所の大半を有する従業者数30人未満の企業の事業所(ア及びウに掲げるものを除く。)
・総務省及び経済産業省-都道府県-調査事業所 - ウ.総務省及び経済産業省による調査
複数の都道府県に本所及び支所となる事業所を有する企業の事業所,従業者数30人以上の企業の事業所並びに総務大臣及び経済産業大臣が定めた事業所並びに東日本大震災の影響により調査員調査の実施に大きな支障が生じている地域として総務大臣及び経済産業大臣が定めた調査区内の単独事業所及び新設事業所
・総務省及び経済産業省-調査事業所
利用上の注意
- この「結果の概要」は,この度新たに公表した確報集計結果に基づき作成したものであり,平成25年1月に公表した速報集計結果とは異なる場合がある。
- 調査は,以下に掲げる事業所を除く事業所・企業について行った。
- 1.国及び地方公共団体の事業所
- 2.日本標準産業分類大分類A-農業・林業に属する個人経営の事業所
- 3.日本標準産業分類大分類B-漁業に属する個人経営の事業所
- 4.日本標準産業分類大分類N-生活関連サービス業,娯楽業のうち,小分類792-家事サービス業に属する事業所
- 5.日本標準産業分類大分類R-サービス業(他に分類されないもの)のうち,中分類96-外国公務に属する事業所
- 売上(収入)金額,費用等の経理事項は平成23年1年間,経営組織,従業者数等の経理事項以外の事項は平成24年2月1日現在の数値である。
- 売上(収入)金額は,以下の産業においては,事業所単位の把握ができないため,全産業に係る集計は企業等に関する集計で行った。
「建設業」,「電気・ガス・熱供給・水道業」,「通信業」,「放送業」,「映像・音声・文字情報制作業」,「運輸業,郵便業」,「金融業,保険業」,「学校教育」,「郵便局」,「政治・経済・文化団体」及び「宗教」 - 事業所単位の付加価値額は,企業単位で把握した付加価値額を事業従業者数により傘下事業所にあん分することにより,全産業について集計した。
- 売上(収入)金額等一部の項目については,必要な事項の数値が得られた事業所(企業)を対象として集計した。
- 調査票の欠測値や記入内容の矛盾などについて精査し,平成21年経済センサス-基礎調査等を基に補足訂正を行った上で結果表として集計した。
- 各項目の金額は,単位未満を四捨五入しているため,内訳の計と合計が一致しない場合がある。なお,比率は,小数点以下第2位で四捨五入した。
該当数字がないもの及び分母が0のため計算できないものは「-」とした。また,増減は,数値がマイナスのものは「△」で表した。
「x」は,集計対象となる事業所(企業)が1又は2であるため,集計結果をそのまま公表すると個々の報告者の情報が推測されるおそれがある場合に該当数値を秘匿した箇所である。また,集計対象が3以上の事業所(企業)に関する数値であっても,集計対象が1又は2の事業所(企業)の数値が合計との差引きで推測される箇所は,併せて「x」とした。
用語の解説
1.事業所
経済活動が行われている場所ごとの単位で,原則として次の要件を備えているものをいう。
- 1.一定の場所(1区画)を占めて,単一の経営主体のもとで経済活動が行われていること。
- 2.従業者と設備を有して,物の生産や販売,サービスの提供が継続的に行われていること。
出向・派遣従業者のみの事業所
当該事業所に所属する従業者が1人もおらず,他の会社など別経営の事業所から出向又は派遣されている人のみで経済活動が行われている事業所をいう。
2.従業者
平成24年2月1日現在で,当該事業所に所属して働いている全ての人をいう。したがって,他の会社などの別経営の事業所へ出向又は派遣している人も含まれる。一方,当該事業所で働いている人であっても,他の会社などの別経営の事業所から出向又は派遣されているなど,当該事業所から賃金・給与(現物給与を含む。)を支給されていない人は従業者に含めない。
なお,個人経営の事業所の家族従業者は,賃金・給与を支給されていなくても従業者としている。
個人業主
個人経営の事業主で,実際にその事業所を経営している人をいう。
なお,個人業主は個人経営の事業所に必ず一人である。
無給の家族従業者
個人業主の家族で,賃金・給与を受けずに,事業所の仕事を手伝っている人をいう。
家族であっても,実際に雇用者並みの賃金・給与を受けて働いている人は,「常用雇用者」又は「臨時雇用者」に含まれる。
有給役員
法人,団体の役員(常勤,非常勤は問わない。)で,役員報酬を受けている人をいう。
重役や理事などであっても,事務職員,労務職員を兼ねて一定の職務に就き,一般職員と同じ給与規則によって給与を受けている人は,「常用雇用者」に含まれる。
常用雇用者
事業所に常時雇用されている人をいう。
期間を定めずに雇用されている人若しくは1か月を超える期間を定めて雇用されている人又は平成23年12月と平成24年1月にそれぞれ18日以上雇用されている人をいう。
正社員・正職員
常用雇用者のうち,一般に「正社員」,「正職員」などと呼ばれている人をいう。
正社員・正職員以外
常用雇用者のうち,一般に「正社員」,「正職員」などと呼ばれている人以外で,「契約社員」,「嘱託」,「パートタイマー」,「アルバイト」又はそれに近い名称で呼ばれている人をいう。
臨時雇用者
常用雇用者以外の雇用者で,1か月以内の期間を定めて雇用されている人又は日々雇用されている人をいう。
他への出向・派遣従業者
従業者のうち,いわゆる労働者派遣法にいう派遣労働者,在籍出向など当該事業所に籍がありながら,他の会社など別経営の事業所で働いている人をいう。
3.他からの出向・派遣従業者
労働者派遣法にいう派遣労働者,在籍出向など出向元に籍がありながら当該事業所に来て働いている人をいう。
4.事業所の産業分類
事業所の売上(収入)金額や主な事業の種類(原則として平成23年1年間の収入額又は販売額の最も多いもの)により,日本標準産業分類(平成19年11月改定)に基づき分類している。なお,確報集計においては,原則として細分類に基づき分類している。
5.経営組織
個人経営
個人が事業を経営している場合をいう。
法人組織になっていなければ,共同経営の場合も個人経営に含まれる。
法人
法律の規定によって法人格を認められているものが事業を経営している場合をいう。以下の会社及び会社以外の法人が該当する。
会社
株式会社,有限会社,相互会社,合名会社,合資会社,合同会社及び外国の会社をいう。
ここで,外国の会社とは,外国において設立された法人の支店,営業所などで,会社法(平成17年法律第86号)の規定により日本で登記したものをいう。
なお,外国人の経営する会社や外国の資本が経営に参加しているいわゆる外資系の会社は,外国の会社ではない。
会社以外の法人
法人格を有する団体のうち,前述の会社を除く法人をいう。
例えば,独立行政法人,社団法人,財団法人,社会福祉法人,学校法人,医療法人,宗教法人,農(漁)業協同組合,事業協同組合,労働組合(法人格を持つもの),共済組合,国民健康保険組合,信用金庫などが含まれる。
法人でない団体
法人格を持たない団体をいう。例えば,後援会,同窓会,防犯協会,学会,労働組合(法人格を持たないもの)などが含まれる。
6.企業等
事業・活動を行う法人(外国の会社を除く。)又は個人経営の事業所をいう。個人経営であって同一の経営者が複数の事業所を経営している場合は,それらはまとめて一つの企業となる。
具体的には,経営組織が株式会社,有限会社,相互会社,合名会社,合資会社,合同会社,会社以外の法人及び個人経営で本所と支所を含めた全体をいう。単独事業所の場合は,その事業所だけで企業としている。
7.会社企業
経営組織が株式会社,有限会社,相互会社,合名会社,合資会社及び合同会社で,本所と支所を含めた全体をいう。単独事業所の場合は,その事業所だけで会社企業としている。
8.企業産業分類
企業単位の産業分類で,支所を含めた企業全体の売上(収入)金額や主な事業の種類(原則として企業全体の平成23年1年間の総収入額又は総販売額の最も多いもの)により分類している。なお,確報集計においては,原則として小分類に基づき分類している。
9.単一・複数の別
企業等を構成している事業所により,以下の2つに区分している。
単一事業所企業
単独事業所の企業等をいう。
複数事業所企業
国内にある本所と国内又は海外にある支所で構成されている企業等をいう(国内に本所があり,海外にのみ支所がある企業を含む。)。
10.単独・本所・支所の別,単独・複数の別
単独事業所
他の場所に同一経営の本所(本社・本店)や支所(支社・支店)を持たない事業所をいう。
本所(本社・本店)
他の場所に同一経営の支所(支社・支店)があって,それらの全てを統括している事業所をいう。本所の各部門が幾つかの場所に分かれているような場合は,社長などの代表者がいる事業所を本所とし,他は支所としている。
支所(支社・支店)
他の場所にある本所(本社・本店)の統括を受けている事業所をいう。上位の事業所の統括を受ける一方で,下位の事業所を統括している中間的な事業所も支所としている。
支社,支店のほか,営業所,出張所,工場,従業者のいる倉庫,管理人のいる寮なども含まれる。なお,経営組織が外国の会社は支所とする。
複数事業所企業の事業所
本所及び支所が含まれる。
11.売上(収入)金額
商品等の販売額又は役務の提供によって実現した売上高,営業収益,完成工事高など。有価証券,土地・建物,機械・器具などの有形固定資産など,財産を売却して得た収入は含めない。なお,「金融業,保険業」の会社,会社以外の法人及び法人でない団体の場合は経常収益としている。
12.事業活動
事業所又は企業等の産業分類を格付けする際は原則として,売上(収入)金額の最も多い主産業によるが,実際には主産業以外にも複数の事業を行っている場合があり,行っている事業を売上(収入)金額で捉えたものをいう。
13.費用
ア.費用総額(売上原価+販売費及び一般管理費)
売上(収入)金額に対応する費用。なお,「金融業,保険業」の会社及び会社以外の法人は経常費用としている。
イ.売上原価(個人経営,「金融業,保険業」の会社及び会社以外の法人を除く。)
費用総額の内数。売上原価は,売上高に対応する商品仕入原価,製造原価,完成工事原価,サービス事業の営業原価及び減価償却費(売上原価に含まれるもの)の総額。
ウ.給与総額(個人経営の場合は給料賃金(専従者給与を除く。))
役員(非常勤を含む。)及び従業者(臨時雇用者を含む。)に対する給与(所得税・保険料等控除前の役員報酬,給与,賞与,手当,賃金等)の総額。別経営の事業所に出向又は派遣している従業者に支給している給与を含む。
エ.福利厚生費(退職金を含む)(個人経営を除く。)
会社負担の法定福利費(厚生年金保険法,健康保険法,介護保険法,労働者災害補償保険法等によるもの),福利施設負担額,厚生費,現物給与見積額,退職給付費用,退職金等の総額。
オ.動産・不動産賃借料(個人経営の場合は地代家賃)
土地,建物,機械等の賃借料の総額。経理上売買扱いとなっているリース支払額は含めない。
カ.減価償却費
固定資産に係る減価償却費。「売上原価」,「販売費及び一般管理費」それぞれに計上された減価償却費の総額。
キ.租税公課(法人税,住民税,事業税を除く。)
営業上負担すべき固定資産税,自動車税,印紙税等の総額。収入課税の事業税(電気業,ガス業)及び税込経理の方法を採っている場合の納付すべき消費税を含む。法人税,住民税,所得課税の事業税は含めない。
ク.外注費(個人経営を除く。)
業務の一部又は全部を他の企業へ委託,下請け,その他の形式で発注した経費。人材派遣会社への支払いを含む。
ケ.支払利息等(個人経営,「62銀行業」及び「63協同組織金融業」を除く。)
借入金等に対する支払利息等の総額。営業外費用に計上する支払利息等が該当する。費用総額の内数ではない。
14.付加価値額
付加価値とは,企業等の生産活動によって新たに生み出された価値のことで,生産額から原材料等の中間投入額を差し引くことによって算出できる。本調査においては,以下の計算式を用いている。
- 付加価値額=売上高-費用総額+給与総額+租税公課
- 費用総額=売上原価+販売費及び一般管理費
なお,本調査の付加価値には,国民経済計算の概念では含まれている国内総生産の項目のうち,以下は含まれていない。
固定資本減耗,雇主の社会保険料負担分,持ち家の帰属家賃
農林漁家,公営企業及び政府サービス生産者の付加価値等
付表
- 付表はExcel形式です
- 付表1:都道府県別事業所数及び従業者数(民営事業所)(エクセル:31キロバイト)

- 付表2:市町村別事業所数及び従業者数(民営事業所)(エクセル:35キロバイト)
- 付表3:大分類別市町村別売上高(民営事業所)(エクセル:28キロバイト)
- より詳細な結果・統計表等については,総務省統計局ホームページの「経済センサス-活動調査調査」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
総務省統計局(リンク)