目的から探す
ホーム > 県政情報 > 県の概要 > いばらき統計情報ネットワーク > いばらき統計情報ネットワーク(統計課) > 分野別≪物価・景気・家計・経済≫ > 平成26年経済センサス-基礎調査茨城県結果(確報)
ページ番号:34895
更新日:2023年11月22日
ここから本文です。
平成26年経済センサス-基礎調査茨城県結果(確報)
目次
見たい項目をクリックしてください。
調査の概要
利用上の注意
用語の解説
結果の概要
調査の概要
1.調査の目的
平成26年経済センサス-基礎調査は,事業所及び企業の経済活動の状態を調査し,全ての産業分野における事業所及び企業の活動からなる経済の構造を全国的及び地域的に明らかにするとともに,各種統計調査実施のための事業所及び企業の名簿を得ることを目的として実施した。
2.調査の沿革
経済センサス-基礎調査は,平成21年に第1回調査を実施し,2回目に当たる平成26年調査では,経済産業省が所管する「商業統計調査」と一体的に実施した。
なお,経済センサスは,経済センサス-基礎調査と経済センサス-活動調査の二つから成り立っており,経済センサス-活動調査は,平成24年に第1回調査を実施した。
3.調査日
平成26年7月1日
4.調査の対象
調査日現在,日本標準産業分類(平成21年総務省告示第175号)に掲げる産業に属する全ての事業所。ただし,次の事業所は調査対象外とした。
- (1)大分類A-農業・林業に属する個人経営の事業所
- (2)大分類B-漁業に属する個人経営の事業所
- (3)大分類N-生活関連サービス業,娯楽業のうち小分類792-家事サービス業に属する事業所
- (4)大分類R-サービス業(他に分類されないもの)のうち,中分類96-外国公務に属する事業所
- (5)また,次の事業所は調査技術上の観点から除外した。
- ア.家事労働の傍ら,特に設備を持たないで賃仕事をしている個人宅
- ア.家事労働の傍ら,特に設備を持たないで賃仕事をしている個人宅
- (6)なお,次の事業所は,経済センサスでいう事業所に含めていない。
- ア.収入を得て働く労働者がいないもの
- イ.休業中でかつ従業者がいないもの
- ウ.季節的に営業する事業所で,調査期日に従業者がいないもの
- ア.収入を得て働く労働者がいないもの
5.調査の単位
原則として,単一の経営者が事業を営んでいる1区画の場所を1事業所とし,これを調査の単位とした。単一経営者が,異なる場所で事業を営んでいる場合は,それぞれの場所ごとに,また,1区画の場所で異なる経営者が事業を営んでいる場合は,経営者が異なるごとに1事業所とした。
なお,事業所としての取扱いに関し,次に掲げるものについては,特例を設けた。
(1)建設業
作業の行われている工事現場,現場事業所などは,それらを直接管理している本社,支店,営業所,出張所などの事業所に含めて調査した。
また,自営の大工,左官,塗装工事・屋根工事・配管工事・電気工事などの業者については,工事現場では調査せず,それらの業者の事業所又は自宅で,その従業者も含めて調査した。
(2)運輸業
鉄道,自動車,船舶,航空機などによる運輸業は,管理責任者のいる場所を事業所とした。
鉄道業について,駅,車掌区,車両工場などは,それぞれを1事業所とした。
ただし,駅長,区長などの管理責任者の置かれていない事業所は,管理責任者のいる事業所に含めて調査した。
(3)学校
小学校,中学校などが併設されている場合は,それぞれを1事業所とした。
したがって,同一の学校法人に属する幾つかの学校,例えば,大学,高等学校,中学校,小学校,幼稚園などが同一構内にあるような場合,学校ごとにそれぞれ1事業所とした。
ただし,高等学校に併設されている定時制課程などは別の事業所とせず,その高等学校に含めて調査した。
(4)国及び地方公共団体の機関
国及び地方公共団体の機関については,法令により独立の機関として設置されている機関を1経営主体とみなし,それぞれの場所ごとに1事業所とした。
ただし,一般行政事務又は立法事務を行っている機関の中に,それ以外の現業的業務を行っている「係」などの組織がある場合は,それらの組織をまとめて別の事業所とした。
6.調査の方法
調査は「甲調査」と「乙調査」の2種類からなり,甲調査においては,対象となる事業所及び企業の規模に応じて,調査員による調査と,総務省,県,市町村による調査に分けて行った。
(1)甲調査
民営事業所を対象とする全数調査
調査員による調査
単独事業所及び新設事業所については,調査票の配布は調査員が行い,取集は調査員による回収又はオンラインにより行った。
- 総務省-県-市町村-統計調査員-調査事業所
総務省,県,市町村による調査
ア.総務省による調査
2以上の都道府県の区域にわたって事業所を有する企業の事業所,従業員数30人以上の企業の事業所
- 総務省-調査事業所
イ.県による調査
県内に大多数の事業所を有する従業員数30人未満の企業の事業所(ア及びウを除く。)
- 総務省-県-調査事業所
ウ.市による調査
市内に全事業所を有する従業員数30人未満の企業の事業所(アを除く。)
- 総務省-県-市町村-調査事業所
(2)乙調査
国及び地方公共団体の事業所を対象とする調査で,市町村の調査事業所にあっては市町村が,県の調査事業所にあっては県が,国の調査事業所にあっては総務省が,オンラインより調査票の配布,取集を行った。
- 総務省-県-市町村-調査事業所
- 総務省-県-調査事業所
- 総務省-各府省-調査事業所
7.調査事項
(1)甲調査
【事業所に関する事項】
- ア.名称
- イ.電話番号
- ウ.所在地
- エ.開設時期
- オ.従業者数
- カ.単独事業所・本所・支所の別
- キ.事業の種類
- ク.業態
- ケ.年間総売上(収入)金額
【企業に関する事項】
- ア.経営組織
- イ.資本金等の額
- ウ.本所の名称
- エ.本所の所在地及び電話番号
- オ.外国資本比率
- カ.決算月
- キ.持株会社か否か
- ク.親会社の有無
- ケ.親会社の名称
- コ.親会社の所在地及び電話番号
- サ.子会社の有無及び子会社の数
- シ.組織全体の常用雇用者数
- ス.組織全体の主な事業の種類
- セ.国内及び海外の支所等の有無及び支所等の数
- ソ.年間総売上(収入)金額
(2)乙調査
- ア.名称
- イ.電話番号
- ウ.所在地
- エ.職員数
- オ.事業の種類
- カ.事業の委託先の名称,電話番号及び所在地
利用上の注意
- この「結果の概要」は,確報集計に基づき作成したものであり,平成27年6月公表の速報結果と異なる場合がある。また,平成27年11月末に公表された国の確報において,売上に関する結果表が除かれたため掲載していない。
- 該当数字がないもの及び分母が0のため計算できないものは,「-」で表した。
- 割合及び比率は,小数点第2位を四捨五入しているため,総数と内訳の合計が一致しない場合がある。
- 調査票の記載不備等により,事業内容等の詳細が不明な事業所を「不詳」として,産業分類別の集計から除外しているため,集計項目の種類により事業所数が異なる。
- 「平成24年経済センサス-活動調査」との比較については,当該調査が「公務」を調査対象としていないため,本調査の「民営」の数値で行っている。
- 男女別の集計表においては,総数に男女不詳が含まれるため,男性と女性の合計と異なる。
- 地域区分について
県内5地域を構成する市町村は以下のとおりである。地域
市町村
県北地域
日立市,常陸太田市,高萩市,北茨城市,ひたちなか市,常陸大宮市,那珂市,那珂郡(東海村),久慈郡(大子町)
県央地域
水戸市,笠間市,小美玉市,東茨城郡(茨城町,大洗町,城里町)
鹿行地域
鹿嶋市,潮来市,神栖市,行方市,鉾田市
県南地域
土浦市,石岡市,龍ケ崎市,取手市,牛久市,つくば市,守谷市,稲敷市,かすみがうら市,つくばみらい市,稲敷郡(美浦村,阿見町,河内町),北相馬郡(利根町)
県西地域
古河市,結城市,下妻市,常総市,筑西市,坂東市,桜川市,結城郡(八千代町),猿島郡(五霞町,境町)
- 事業内容が分りにくい産業分類について
「その他の○○業」や「他に分類されない○○業」などのように,事業内容が分りにくい主な産業分類の事業内容については,以下のとおりである。産業分類
事業内容
大分類
複合サービス業
郵便局,協同組合
中分類
その他の小売業
家具,じゅう器,医療品,化粧品,農耕用品,燃料,書籍,文房具,時計,楽器,たばこなどの小売
その他の卸売業
家具・建具・じゅう器,医薬品・化粧品,紙・紙製品などの卸売
その他の製造業
貴金属・宝石製品,装身具・装飾品,楽器,がん具・運動用具,その他の事務用品,畳などの製造
無店舗小売業
通信販売・訪問販売小売業,自動販売機などによる小売
各種商品小売業
百貨店,総合スーパーなど
各種商品卸売業
繊維・衣服,飲食料品,建築材料,鉱物・金属材料,機械器具などの卸売
小分類
その他の飲食料品小売業
コンビニエンスストア,牛乳,茶類,豆腐,かまぼこ等加工食品,乾物などの小売
その他の食料品製造業
でんぷん,めん類,豆腐・油揚,冷凍調理食品,すし・弁当・調理パン,惣菜などの製造
その他の生産用機械・同部分品製造業
金属用金型・同部分品・附属品,真空装置・真空機器,ロボットなどの製造
その他のプラスチック製品製造業
プラスチック製日用雑貨・食卓用品,プラスチック製容器などの製造
他に分類されない小売業
ホームセンター,たばこ・喫煙具,花・植木,建築材料,ペット・ペット用品,骨とう品などの小売
他に分類されない卸売業
金物,肥料・飼料,スポ-ツ用品,娯楽用品・がん具,たばこ,ジュエリー製品,書籍・雑誌などの卸売
他に分類されない製造業
花火,看板・標識機,モデル・模型,眼鏡などの製造
他に分類されない事業サービス業
ディスプレイ業,産業用設備洗浄業,看板書き業など
用語の解説
1.事業所
経済活動が行われている場所ごとの単位で,原則として次の条件を備えているものをいう。
- 一定の場所(1区画)を占めて,単一の経営主体のもとで経済活動が行われていること。
- 従業者と設備を有して,物の生産や販売,サービスの提供が継続的に行われていること。
(1)民営事業所
国及び地方公共団体の事業所を除く事業所をいう。
(2)出向・派遣従業者のみの事業所
当該事業所に所属する従業者が1人もおらず,他の会社など別経営の事業所から出向又は派遣されている人のみで経済活動が行われている事業所をいう。
(3)事業内容等不詳の事業所
事業所として存在しているが,記入不備等で事業内容が不明の事業所をいう。
2.従業者
調査日現在,当該事業所に所属して働いている全ての人をいう。したがって,他の会社や下請先などの別経営の事業所へ出向又は派遣している人も含まれる。一方,当該事業所で働いている人であっても,他の会社などの別経営の事業所から出向又は派遣されているなど,当該事業所から賃金・給与(現物給与を含む。)を支給されていない人は従業者に含めない。
なお,個人経営の事業所の家族従業者は,賃金・給与を支給されていなくても従業者とした。
(1)個人業主
個人経営の事業所で,実際にその事業所を経営している人をいう。
(2)無給の家族従業者
個人業主の家族で,賃金・給与を受けずに,事業所の仕事を手伝っている人をいう。
家族であっても,実際に雇用者並みの賃金・給与を受けて働いている人は,「常用雇用者」又は「臨時雇用者」に含める。
(3)有給役員
法人,団体の役員(常勤,非常勤は問わない。)で,役員報酬を受けている人をいう。
重役や理事などであっても,事務職員,労務職員を兼ねて一定の職務に就き,一般職員と同じ給与規則によって給与を受けている人は,「常用雇用者」に含める。
(4)常用雇用者
事業所に常時雇用されている人をいう。
期間を定めずに雇用されている人若しくは1か月を超える期間を定めて雇用されている人又は平成26年5月と6月にそれぞれ18日以上雇用されている人をいう。
(5)正社員・正職員
常用雇用者のうち,一般に「正社員」,「正職員」などと呼ばれている人をいう。
(6)正社員・正職員以外
常用雇用者のうち,一般に「正社員」,「正職員」などと呼ばれている人以外で,「契約社員」,「嘱託」,「パートタイマー」,「アルバイト」又はそれに近い名称で呼ばれている人をいう。
(7)臨時雇用者
常用雇用者以外の雇用者で,1か月以内の期間を定めて雇用されている人又は日々雇用されている人をいう。
3.他からの出向・派遣従業者
民営事業所において,労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)にいう派遣労働者,在籍出向など出向元に籍がありながら当該事業所に来て働いている人をいう。
4.民間からの従業者
国,地方公共団体の事業所において,民間の事業所から派遣されている人をいう。
事業所の包括的な管理・運営(指定管理者)や清掃・警備など個々の業務を委託している場合,委託している業務に従事する民間の従業者は含めない。
5.事業従事者
当該事業所で実際に働いている人をいう。
「従業者」から別経営の「他への出向・派遣従業者」を除き,別経営の「他からの出向・派遣従業者」を含める。
6.事業所の産業分類
事業所の主な事業の種類(原則として過去1年間の収入額又は販売額の多いもの)により,日本標準産業分類(平成25年10月改定)に基づき分類している。なお,一部の小分類項目については,小分類項目を分割したものも小分類としている。
7.事業所で行っている産業分類
事業所で行っている全ての事業をいい,一つの事業所が複数の事業を行っている場合は,複数回答となる。
8.経営組織
(1)国,地方公共団体
国,都道府県,市区町村,特別地方公共団体(地方公共団体の組合,財産区など)の事業所をいう。
(2)民営
国,地方公共団体の事業所を除く事業所をいう。
ア.個人経営
個人が事業を経営している場合をいう。
会社や法人組織になっていなければ,共同経営の場合も個人経営に含める。
イ.法人
法律の規定によって法人格を認められているものが事業を経営している場合をいう。
以下の会社及び会社以外の法人が該当する。
ウ.会社
株式会社,有限会社,相互会社,合名会社,合資会社,合同会社及び外国の会社をいう。
ここで,外国の会社とは,外国において設立された法人の支店,営業所などで,会社法(平成17年法律第86号)の規定により日本で登記したものをいう。
なお,国内に設立された会社で,外国人が経営する会社や外国の資本が経営に参加しているいわゆる外資系の会社は,外国の会社ではない。
エ.会社以外の法人
法人格を有する団体のうち,会社以外の法人をいう。
例えば,独立行政法人,一般社団法人,一般財団法人,公益社団法人,公益財団法人,社会福祉法人,学校法人,医療法人,宗教法人,農(漁)業協同組合,事業協同組合,労働組合(法人格を持つもの),共済組合,国民健康保険組合,信用金庫,弁護士法人などが含まれる。
オ.法人でない団体
団体であるが法人格を持たないものをいう。
例えば,協議会,後援会,同窓会,労働組合(法人格を持たないもの)の事業所などが含まれる。
9.事業所の開設時期
会社や企業の創業時期ではなく,当該事業所が現在の場所で事業を始めた時期をいう。
10.業態
(1)主に製造して出荷又は卸売
見込み又は受注によって製造・加工を行い,その製品を出荷又は卸売している場合をいう。
(2)主に製造して通信販売・ネット販売等で小売
見込み又は受注によって製造・加工を行い,その製品を通信販売又はネット販売等で主に消費者に販売する場合をいう。
(3)主に他の業者から支給された原材料により製造・加工
他の業者から原材料の支給を受けて加工処理・製造を行い,加工賃を受け取る場合をいう。
11.企業等
事業・活動を行う法人(外国の会社を除く。)及び個人経営の事業所をいう。個人経営であって同一の経営者が複数の事業所を経営している場合は,それらはまとめて一つの企業等となる。
具体的には,会社企業,会社以外の法人及び個人経営で本所と支所を含めた全体をいう。単独事業所の場合は,その事業所だけで企業等となる。
12.会社企業
経営組織が株式会社,有限会社,相互会社,合名会社,合資会社及び合同会社で,本所と支所を含めた全体をいう。単独事業所の場合は,その事業所だけで会社企業となる。
13.単一・複数の別
企業等を構成している事業所により以下に区分している。
(1)単一事業所企業
単独事業所の企業等をいう。
(2)複数事業所企業
国内にある本所と国内又は国外にある支所で構成されている企業等をいう。
14.国内支所の分布範囲
国内複数事業所企業について以下のとおり区分している。
(1)都道府県内のみに支所をもつ企業等
本所の所在する都道府県内に傘下事業所の全てが所在するものをいう。
市町村内のみに支所をもつ企業等
本所の所在する市町村内に傘下事業所の全てが所在するものをいう。大都市の場合,同一市内他区であっても同一市町村とする。
(2)都道府県外に支所をもつ企業等
本所の所在する都道府県以外に支所が所在するものをいう。
(3)市町村外に支所をもつ企業等
本所の所在する市町村以外に支所が所在するものをいう。大都市の場合,同一市内他区は同一市町村とするので,市町村外に支所をもつこととはならない。
15.単独・本所・支所の別
(1)単独事業所
他の場所に同一経営の本所(本社・本店)や支所(支社・支店)を持たない事業所をいう。
(2)本所(本社・本店)
他の場所に同一経営の支所(支社・支店)があって,それらの全てを統括している事業所をいう。本所の各部門が幾つかの場所に分かれているような場合は,社長などの代表者がいる事業所を本所とし,他は支所としている。
(3)支所(支社・支店)
他の場所にある本所(本社・本店)の統括を受けている事業所をいう。上位の事業所の統括を受ける一方で,下位の事業所を統括している中間的な事業所も支所としている。
支社・支店のほか,営業所,出張所,工場,従業者のいる倉庫,管理人のいる寮なども含まれる。
なお,経営組織が外国の会社は支所とする。
16.資本金額
株式会社及び有限会社については,資本金の額,合名会社,合資会社及び合同会社については出資金の額,相互会社については基金の額をいう。
結果の概要
第1.事業所及び従業者の状況(事業所に関する集計)
1.概況
本県の事業所数は全国第13位,従業者数は全国第12位
平成26年7月1日現在の県内の事業所数(事業内容が不詳の事業所を含む。)は,125,804事業所(全国の2.1%,第13位),従業者数は,1,321,449人(全国の2.1%,第12位)となっている。(第1-1表)
第1-1表:都道府県別事業所数及び従業者数(上位20都道府県)
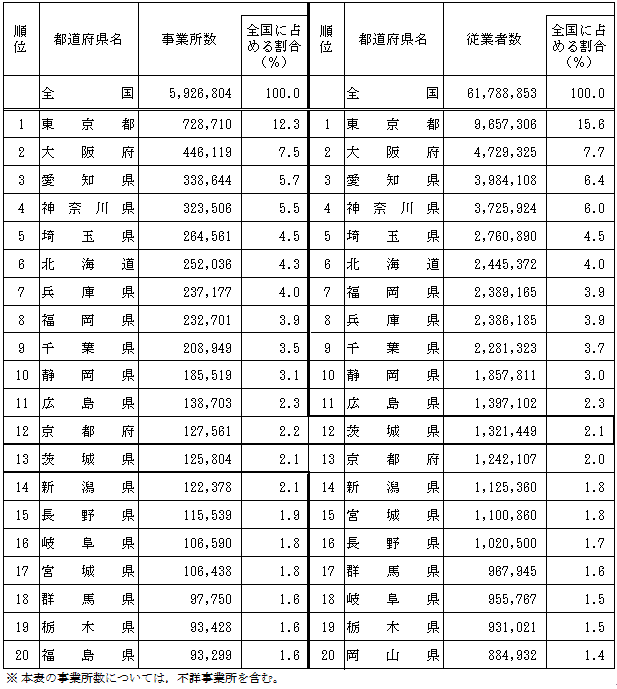
2.産業別の状況
(1)産業大分類別の状況
ア.事業所数
茨城県内では,「卸売業,小売業」の事業所数が最も多い。
県内の事業所数(以下,事業所数は,事業内容等が不詳の事業所を除く数値とする。)を産業大分類別にみると,「卸売業,小売業」が30,497事業所(全産業の24.8%)と最も多く,次いで「建設業」が15,753事業所(同12.8%),「宿泊業,飲食サービス業」13,841事業所(同11.3%)となっており,上位3産業で48.9%を占めている。
全国は,「卸売業,小売業」が1,407,414事業所(全産業の24.7%),「宿泊業・飲食サービス業」728,027事業所(同12.8%),「建設業」が515,080事業所(同9.1%)の順となっている。
産業大分類別構成比を全国と比較すると,「建設業」及び「生活関連サービス業,娯楽業」などで高く,「不動産業,物品賃貸業」,「宿泊業,飲食サービス業」及び「医療,福祉」などで低くなっている。(第1-2表及び第1図)
第1-2表:産業大分類別事業所数
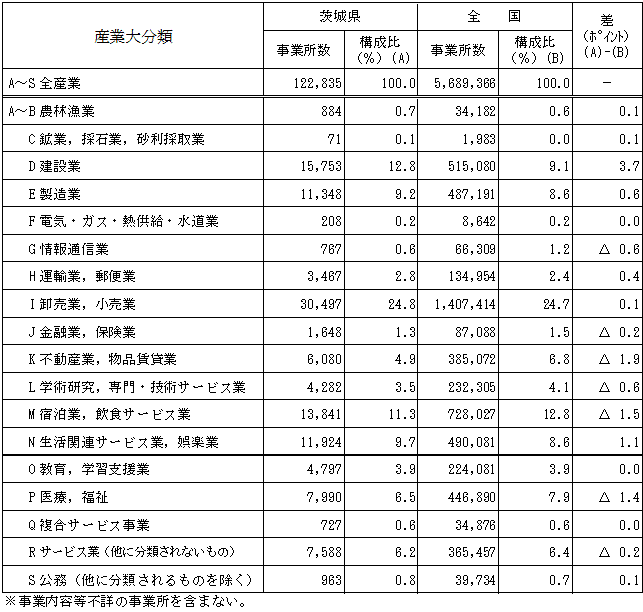
平成24年経済センサス-活動調査との比較(「全産業」(産業大分類)事業所数)
活動調査(平成24年)の結果と比べ,「医療,福祉」の事業所数が著しく増加した。
県内の産業大分類別事業所を活動調査(平成24年)の結果と比較すると,全産業で1,105事業所(0.9%)増加した。中でも「医療,福祉」が930事業所(14.3%)増と増加が著しい。(第1-2表の2)
第1-2表の2:産業大分類別事業所数(民営事業所:前回との比較)
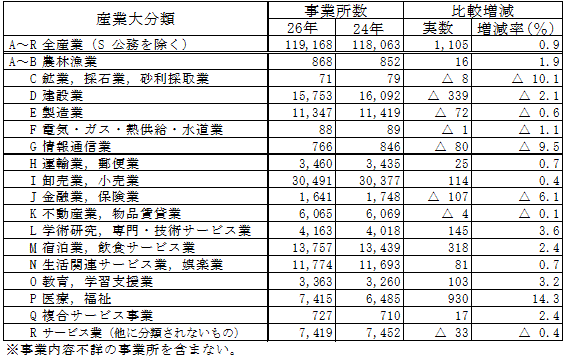
第1図:産業大分類別事業所数の構成比(単位:%)
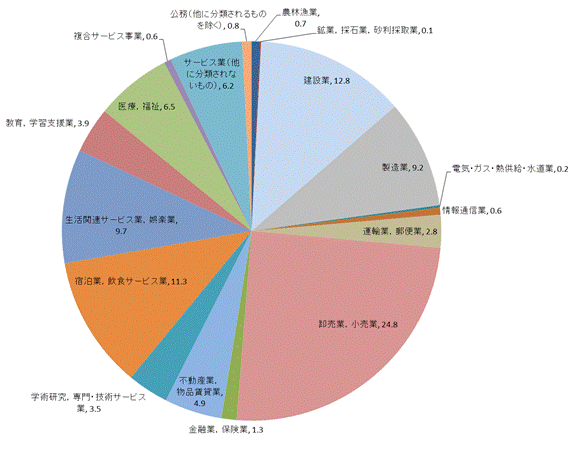
イ.従業者数
茨城県内では,「製造業」の従業者数が最も多い。
県内の従業者数を産業大分類別にみると,「製造業」が281,020人(全産業の21.3%)と最も多く,次いで「卸売業,小売業」が236,828人(同17.9%),「医療,福祉」148,060事業所(同11.2%)となっており,上位3産業で50.4%を占めている。
全国は,「卸売業,小売業」が12,032,863人(全産業の19.5%),「製造業」が9,188,932人(同14.9%),「医療,福祉」が7,932,400人(同12.8%)の順となっている。
産業大分類別構成比を全国と比較すると,「製造業」及び「学術研究,専門・技術サービス業」などで高く,「卸売業,小売業」,「医療,福祉」,「サービス業(他に分類されないもの)」及び「情報通信業」などで低くなっている。(第1-3表及び第2図)
第1-3表:産業大分類別従業者数
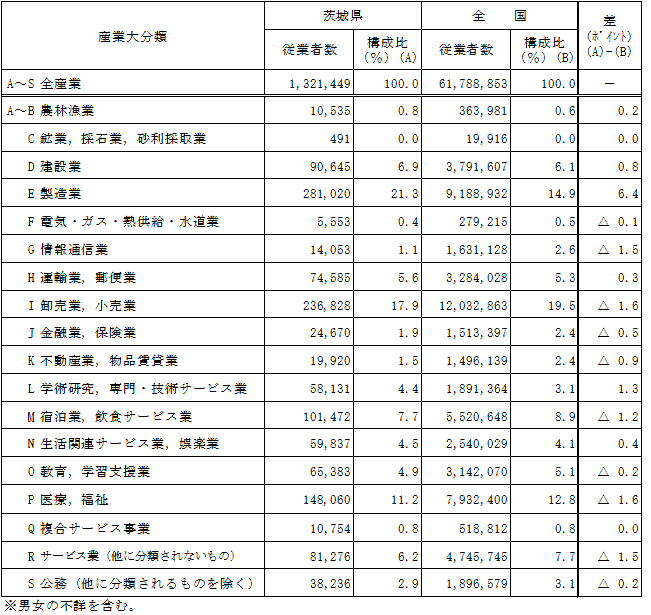
平成24年経済センサス-活動調査との比較(「全産業」(産業大分類)従業者数)
活動調査(平成24年)の結果と比べ,「医療,福祉」の従業者数が著しく増加した。
県内の産業大分類別従業者数を活動調査(平成24年)の結果と比較すると,全産業で12,676人(1.0%)増加した。日本郵政グループ合併の影響で増加率の高い「複合サービス事業」を除き,「医療,福祉」が16,546人(13.7%)増と増加が著しい。(第1-3表の2)
第1-3表の2:産業大分類別従業者数(民営事業所:前回との比較)
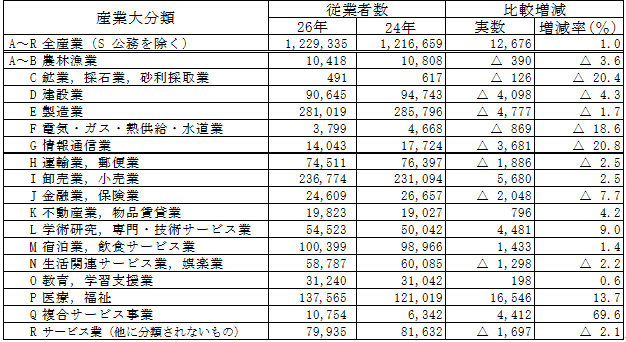
第2図:産業大分類別従業者数の構成比(単位:%)
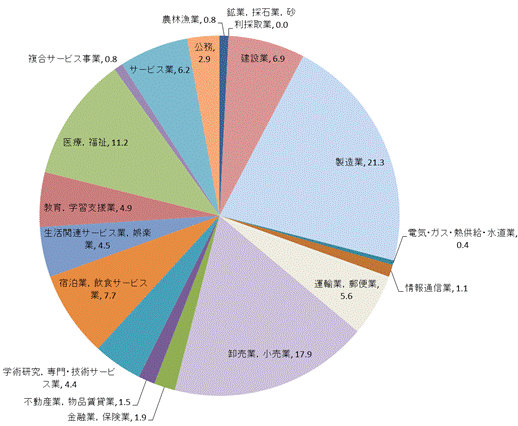
(2)産業小分類別の状況
ア.事業所数
茨城県内では,「美容業」や「専門料理店」の事業所数が多い。
産業小分類別に事業所数をみると,「美容業」が4,188事業所(全産業の3.4%)と最も多く,次いで「専門料理店」が3,889事業所(同3.2%),「その他の飲食料品小売業」3,437事業所(同2.8%)となっている。
全国は,「専門料理店」が177,056事業所(全産業の3.1%),「美容業」が175,488事業所(同3.1%),「貸家業,貸間業」が161,379事業所(同2.8%)の順となっている。
産業小分類別構成比を全国と比較すると,「木造建築工事業」,「理容業」及び「自動車整備業」などで高く,「貸家業,貸間業」,「老人福祉・介護事業」及び「一般診療所」などで低くなっている。(第1-4表)
第1-4表:産業小分類別事業所数(上位20分類)
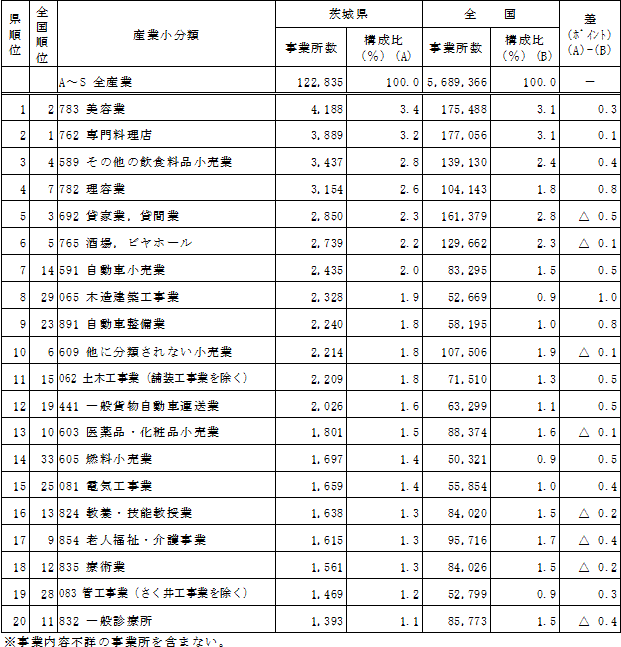
平成24年経済センサス-活動調査との比較(「全産業」(産業小分類)事業所数)
活動調査(平成24年)の結果と比べ,「老人福祉・介護事業」などの事業所数が増加した。
県内の産業小分類別事業所数を活動調査(平成24年)の結果と比較すると,「老人福祉・介護事業」が363事業所(30.0%),「木造建築工事業」が316事業所(15.7%)及び「管工事業」が229事業所(18.5%)増と増加が著しい。(第1-4表の2及び第3図)
第1-4表の2:産業小分類別事業所数(上位20分類)(民営事業所:前回との比較)
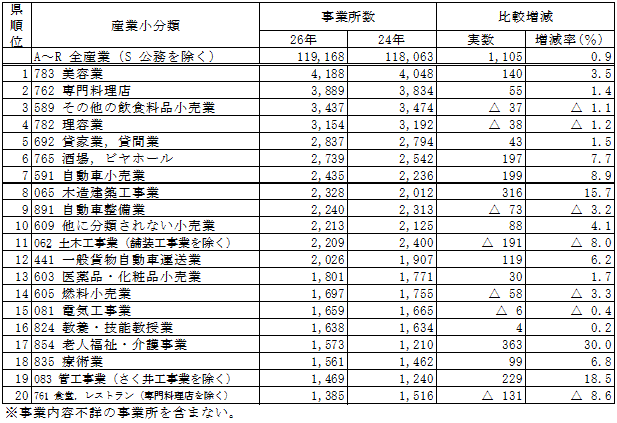
第3図:産業小分類別事業所数の推移〔上位20位〕(単位:事業所)
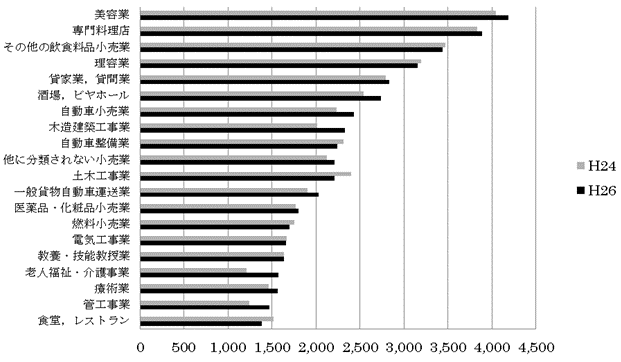
イ.従業者数
茨城県内では,「一般貨物自動車運送業」,「老人福祉・介護事業」及び「病院」の従業者数が多い。
県内の従業者数を産業小分類別にみると,「一般貨物自動車運送業」が44,691人(全産業の3.4%)と最も多く,次いで「老人福祉・介護事業」が43,068人(同3.3%),「病院」42,292人(同3.2%)となっている。
全国は,「老人福祉・介護事業」が2,255,649人(同3.7%),「病院」が2,216,216人(同3.6%),「一般貨物自動車運送業」が1,601,730人(同2.6%)の順となっている。
産業小分類別構成比を全国と比較すると,「自然科学研究所」及び「一般貨物自動車運送業」などで高く,「建物サービス業」,「他に分類されない事業サービス業」などで低くなっている。(第1-5表)
第1-5表:産業小分類別従業者数(上位20分類)
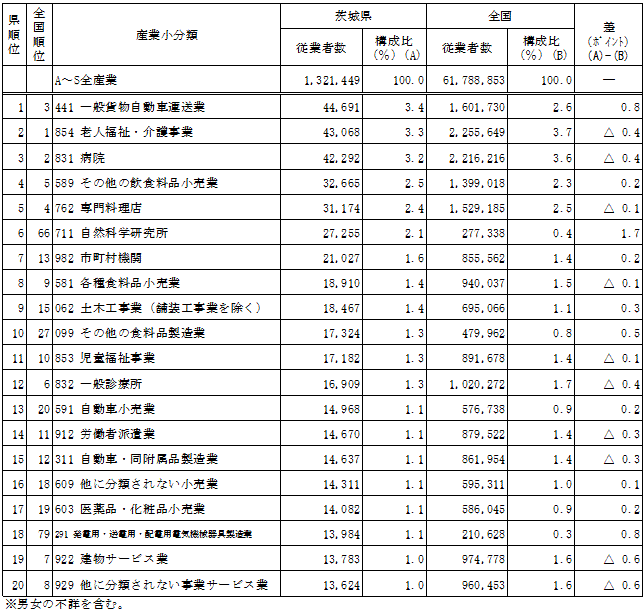
平成24年経済センサス-活動調査との比較(「全産業」(産業小分類)従業者数)
活動調査(平成24年)の結果と比べ,「老人福祉・介護事業」などの従業者数が増加した。
県内の産業小分類別従業者数を活動調査(平成24年)の結果と比較すると,全産業で12,676人(1.0%)増加し,「老人福祉・介護事業」が7,951人(22.8%),「一般貨物自動車運送業」が4,547人(11.3%),「発電用・送電用・配電用電気機械器具製造業」が3,751人(36.7%)及び「児童福祉事業」が3,303人(36.9%)増と増加が著しい。(第1-5表の2及び第4図)
第1-5表の2:産業小分類別従業者数(民営事業所:前回との比較)
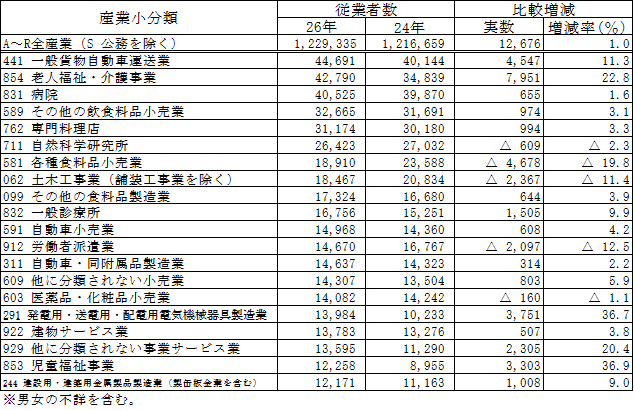
第4図:産業小分類別従業者数の推移〔上位20位〕(単位:人)
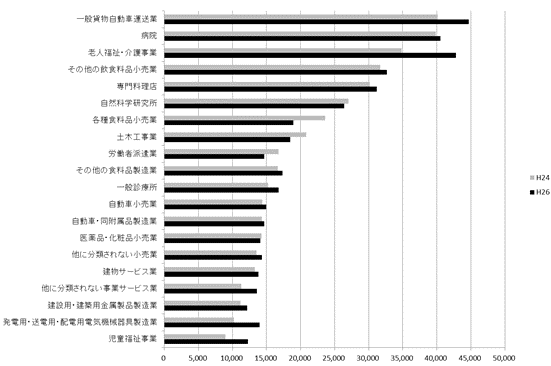
3.主な産業の状況
(1)「卸売業,小売業」(産業中分類)
ア.事業所数
茨城県内の「卸売業,小売業」では,「その他の小売業」や「飲食料品小売業」の事業所数が多い。
産業大分類別で事業所数が最も多い「卸売業,小売業」の事業所数を産業中分類別にみると,「その他の小売業」が8,857事業所(「卸売業,小売業」全体の29.0%)と最も多く,次いで「飲食料品小売業」が7,086事業所(同23.2%),「機械器具小売業」3,714事業所(同12.2%)となっている。
全国は,「その他の小売業」が381,303事業所(同27.1%)と最も多く,次いで「飲食料品小売業」が308,376事業所(同21.9%),「織物・衣服・身の回り品小売業」が149,186事業所(同10.6%)の順となっている。
産業中分類別構成比を全国と比較すると,「機械器具小売業」及び「その他の小売業」などで高く,「その他の卸売業」,「繊維・衣服等卸売業」及び「機械器具卸売業」などで低くなっている。(第1-6表)
第1-6表:「卸売業,小売業」における産業中分類別事業所数
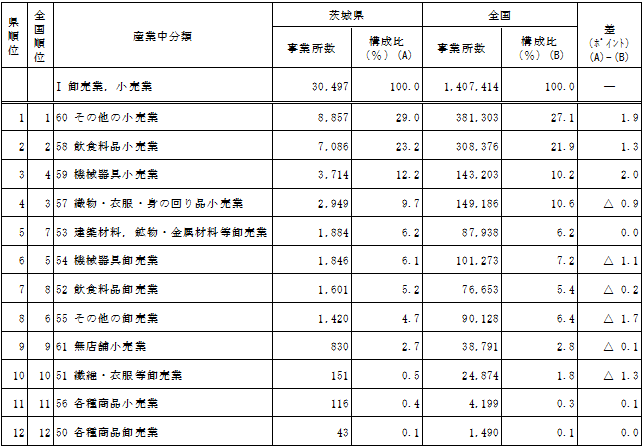
平成24年経済センサス-活動調査との比較(「卸売業,小売業」(産業中分類)事業所数)
活動調査(平成24年)の結果と比べ,機械器具関係事業所数が増加し,「飲食料品小売業」が減少した。
県内の「卸売業,小売業」の産業中分類別事業所数を活動調査(平成24年)の結果と比較すると,「卸売業,小売業」全体で114事業所(0.4%)増加した。「機械器具小売業」が217事業所(6.2%),「機械器具卸売業」が161事業所(9.6%)増と増加が著しく,「飲食料品小売業」が411事業所(-5.5%)減との減少が著しい。(第1-6表の2及び第5図)
第1-6表の2:「卸売業,小売業」における産業中分類別事業所数(民営事業所:前回との比較)
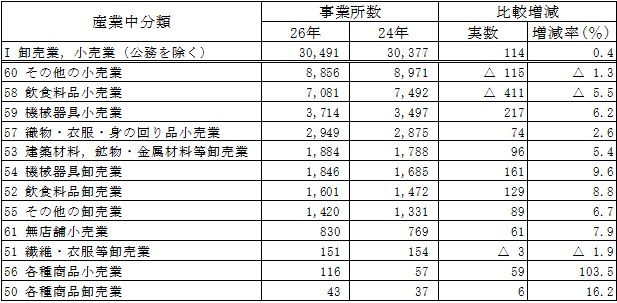
第5図:「卸売業,小売業」(産業中分類)事業所数の推移(単位:事業所)
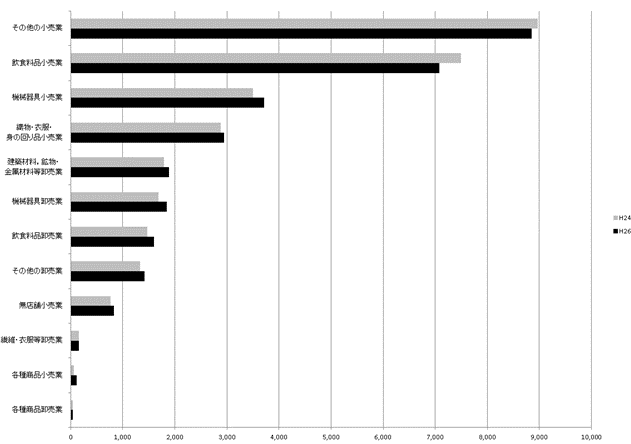
イ.従業者数
茨城県内の「卸売業,小売業」では,「飲食料品小売業」や「その他の小売業」の従業者数が多い。
産業大分類別で最も事業所数が多い「卸売業,小売業」の従業者数を産業中分類別にみると,「飲食料品小売業」が66,744人(「卸売業,小売業」全体の28.2%)と最も多く,次いで「その他の小売業」が62,649人(同26.5%)となっており,上位2産業で全体の54.7%を占めている。
全国は,「飲食料品小売業」が3,111,471人(同25.9%)と最も多く,次いで「その他の小売業」が2,504,978人(同20.8%),「機械器具卸売業」が1,167,264人(同9.7%)の順となっている。
産業中分類別構成比を全国と比較すると,「その他の小売業」及び「飲食料品小売業」などで高く,「機械器具卸売業」,「その他の卸売業」及び「繊維・衣服等卸売業」などで低くなっている。(第1-7表)
第1-7表:「卸売業,小売業」における産業中分類別従業者数
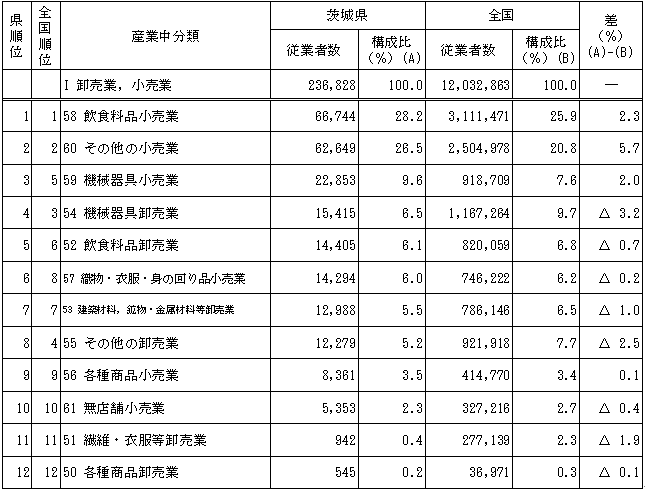
平成24年経済センサス-活動調査との比較(「卸売業,小売業」(産業中分類)従業者数)
活動調査(平成24年)の結果と比べ,「各種商品小売業」が著しく増加した。
県内の「卸売業,小売業」の産業中分類別従業者数を活動調査(平成24年)の結果と比較すると,「卸売業,小売業」全体で5,680人(2.5%)増加した。中でも「各種商品小売業」が3,097人(58.8%)増と増加が著しい。「飲食料品小売業」3,823人(-5.4%)減と事業所数の減少に伴い減少が著しい。(第1-7表の2及び第6図)
第1-7表の2:「卸売業,小売業」における産業中分類別従業者数(民営事業所:前回との比較)
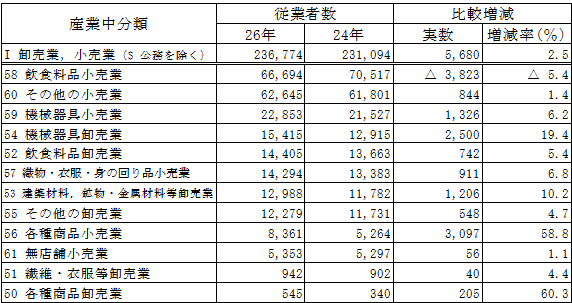
第6図:「卸売業,小売業」(産業中分類)従業者数の推移(単位:人)
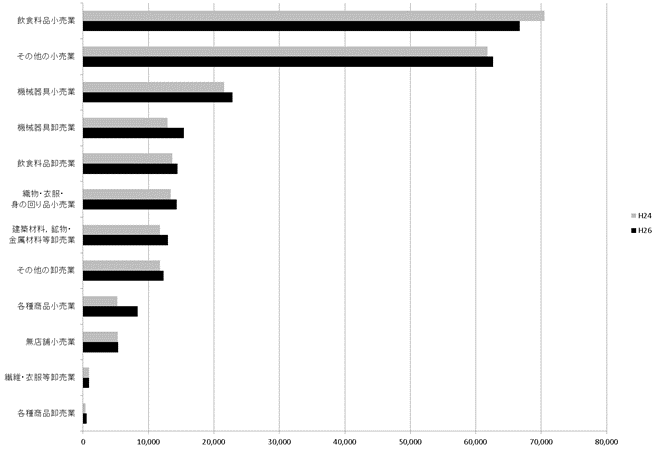
(2)「卸売業,小売業」(産業小分類)
ア.事業所数
茨城県内の「卸売業,小売業」では,「その他の飲食料品小売業」や「自動車小売業」の事業所数が多い。
産業大分類別で最も事業所数が多い「卸売業,小売業」の事業所数を産業小分類別にみると,「その他の飲食料品小売業」が3,437事業所(「卸売業,小売業」全体の11.3%)と最も多く,次いで「自動車小売業」が2,435事業所(同8.0%),「他に分類されない小売業」2,214事業所(同7.3%)の順となっている。
全国は,「その他の飲食料品小売業」が139,130事業所(同9.9%)と最も多く,次いで「他に分類されない小売業」が107,506事業所(同7.6%),「医薬品・化粧品小売業」が88,374事業所(同6.3%)の順となっている。
産業小分類別構成比を全国と比較すると,「自動車小売業」及び「燃料小売業」などで高く,「他に分類されない卸売業」及び「婦人・子供服小売業」などで低くなっている。(第1-6表)
第1-8表:「卸売業,小売業」における産業小分類別事業所数(上位20分類)
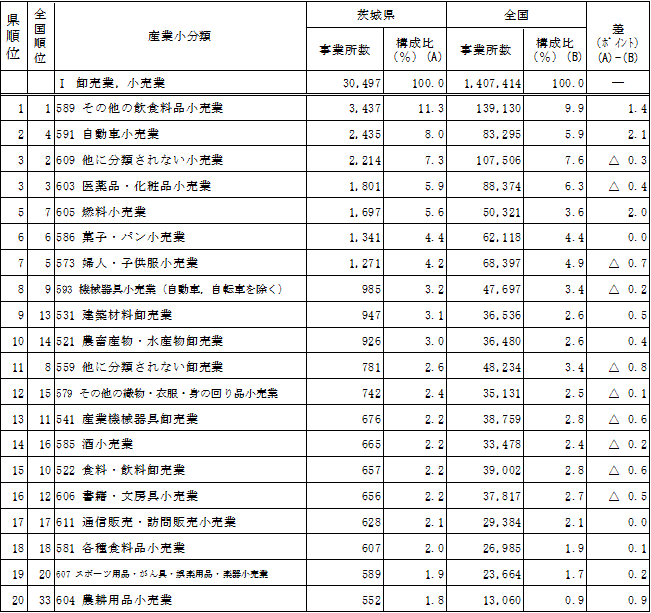
平成24年経済センサス-活動調査との比較(「卸売業,小売業」(産業小分類)事業所数)
活動調査(平成24年)の結果と比べ「自動車小売業」と「その他の織物・衣服・身の回り品小売業」が増加した。
県内の「卸売業,小売業」の産業小分類別事業所数を活動調査(平成24年)の結果と比較すると,「自動車小売業」が199事業所(8.9%),「その他の織物・衣服・身の回り品小売業」が156事業所(26.6%)増と増加が著しい。(第1-8表の2及び第7図)
第1-8表の2:「卸売業,小売業」における産業小分類別事業所数(民営事業所:前回との比較)
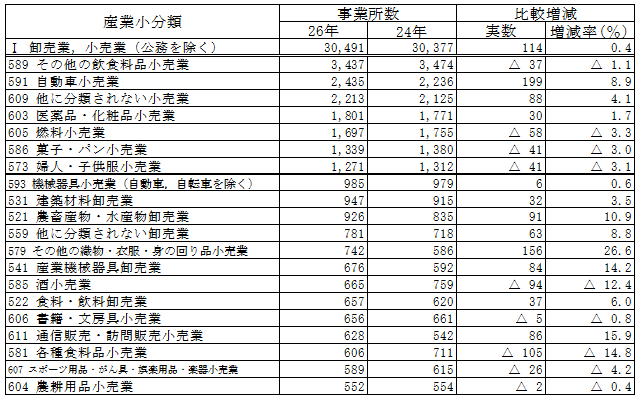
第7図:「卸売業,小売業」(産業小分類)事業所数の推移(単位:事業所)
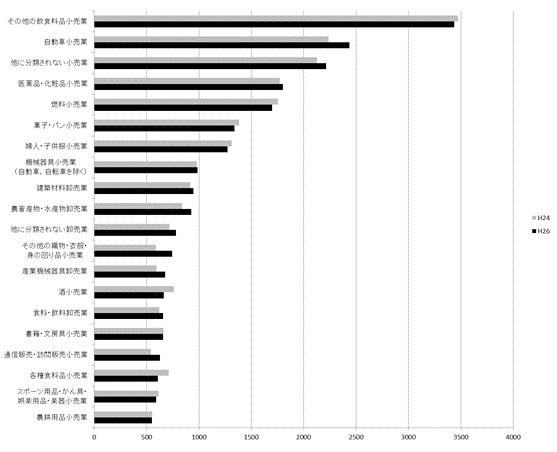
イ.従業者数
茨城県内の「卸売業,小売業」では,「その他の飲食料品小売業」や「各種食料品小売業」の従業者数が多い。
産業大分類別で最も事業所数が多い「卸売業,小売業」の従業者数を産業小分類別にみると,「その他の飲食料品小売業」が32,665人(「卸売業,小売業」全体の13.8%)と最も多く,次いで「各種食料品小売業」が18,910人(同8.0%)となっており,上位2産業で「卸売業,小売業」の2割以上を占めている。
全国は,「その他の飲食料品小売業」が1,399,018人(同11.6%)と最も多く,次いで「各種食料品小売業」が940,037人(同7.8%),「他に分類されない小売業」が595,311人(同4.9%)の順となっている。
産業中分類別構成比を全国と比較すると,「その他の飲食料品小売業」及び「燃料小売業」などで高く,「食料・飲料卸売業」,「他に分類されない卸売業」及び「産業機械器具卸売業」などで低くなっている。(第1-9表)
第1-9表:「卸売業,小売業」における産業小分類別従業者数(上位20位)
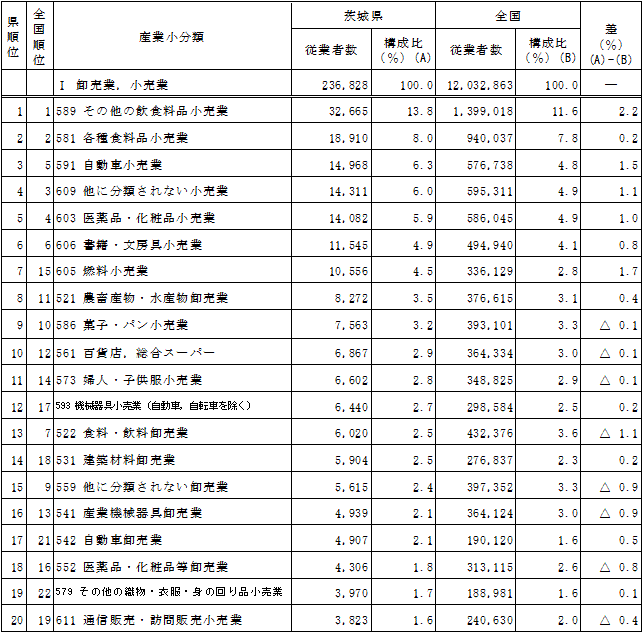
平成24年経済センサス-活動調査との比較(「卸売業,小売業」(産業小分類)従業者数)
活動調査(平成24年)の結果と比べ,「百貨店・総合スーパー」などで増加した。
県内の「卸売業,小売業」の産業中分類別従業者数を活動調査(平成24年)の結果と比較すると,「百貨店・総合スーパー」が1,822人(36.1%),「自動車卸売業」が1,611人(48.9%),「その他の織物・衣服・身の回り品小売業」が1,470人(58.8%),増と増加が著しい。「各種食料品小売業」は,4,678人(19.8%)減と事業所数の減少に伴い減少が著しい。(第1-9表の2及び第8図)
第1-9表の2:「卸売業,小売業」における産業小分類別従業者数(民営事業所:前回との比較)
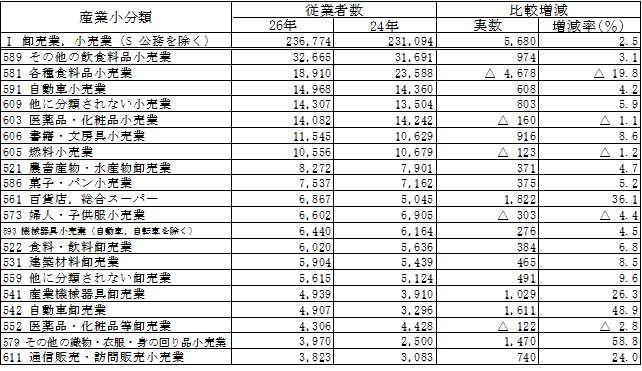
第8図:「卸売業,小売業」(産業小分類)従業者数の推移(単位:人)
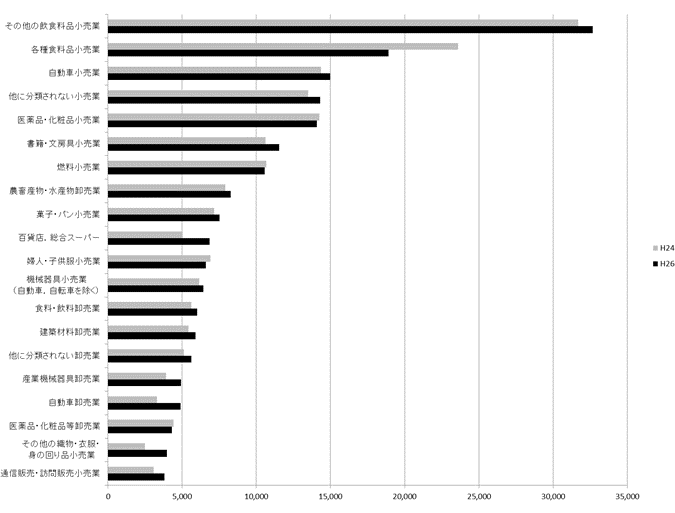
(3)「製造業」(産業中分類)
ア.事業所数
茨城県内の「製造業」では,「金属製品製造業」の事業所数が多い。
産業大分類別で最も従業者数が多い「製造業」の事業所数を産業中分類別にみると,「金属製品製造業」が1,479事業所(「製造業」全体の13.0%)と最も多く,次いで「食料品製造業」が1,394事業所(同12.3%),「窯業・土石製品製造業」1,050事業所(同9.3%)の順となっている。
全国は,「金属製品製造業」が62,656事業所(同12.9%)と最も多く,次いで「食料品製造業」が52,571事業所(同10.8%),「繊維工業」が44,243事業所(同9.1%)の順となっている。
産業中分類別構成比を全国と比較すると,「窯業・土石製品製造業」及び「プラスチック製品製造業」などで高く,「繊維工業」及び「印刷・同関連業」などで低くなっている。(第1-10表)
第1-10表:「製造業」における産業中分類別事業所数
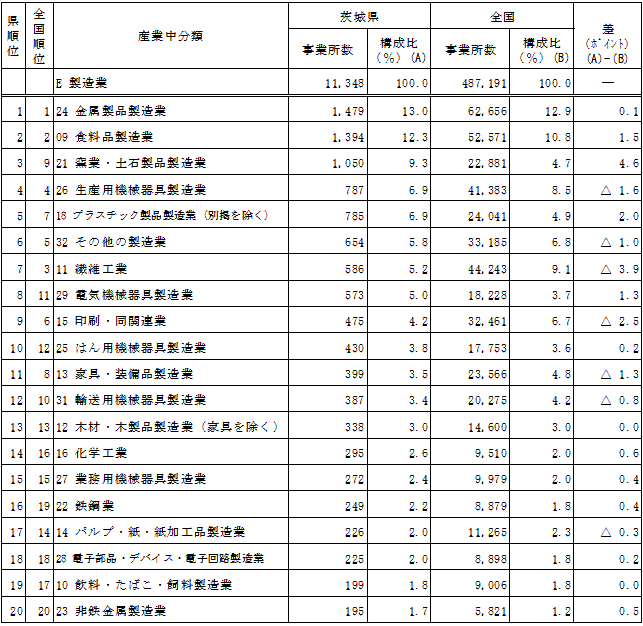
平成24年経済センサス-活動調査との比較(「製造業」(産業中分類)事業所数)
活動調査(平成24年)の結果と比べ,「その他の製造業」が大きく増加した。
県内「製造業」の産業中分類別事業所数を活動調査(平成24年)の結果と比較すると,「製造業」全体で72事業所(0.6%)減少した。中でも「鉄鋼業」や「非鉄金属製造業」といった素材産業の減少が目立っている。(第1-10表の2及び第9図)
第1-10表の2:「製造業」における産業中分類別事業所数(民営事業所:前回との比較)
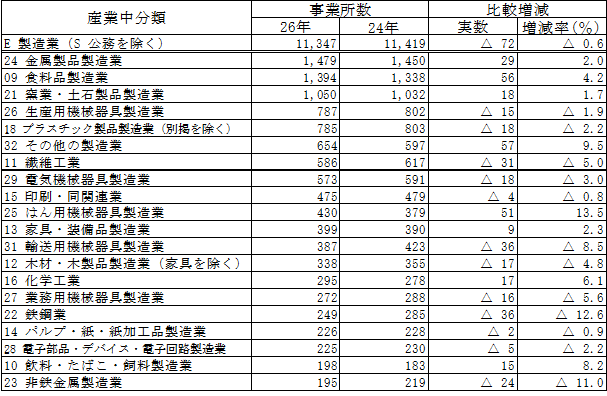
第9図:「製造業」(産業中分類)事業所数の推移(単位:事業所)
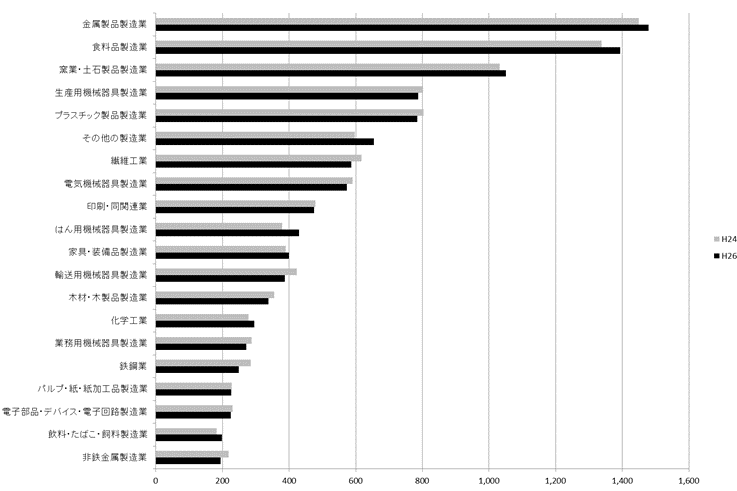
イ.従業者数
茨城県内の「製造業」では,「食料品製造業」の従業者数が最も多い。
産業大分類別で最も従業者数が多い「製造業」の事業所数を産業中分類別にみると,「食料品製造業」が44,347人(「製造業」全体の15.8%)と最も多く,次いで「電気機械器具製造業」が25,893人(同9.2%),「金属製品製造業」24,968人(同8.9%)の順となっている。
全国は,「食料品製造業」が1,294,473人(同14.1%)と最も多く,次いで「輸送用機械器具製造業」が1,071,964人(同11.7%),「金属製品製造業」が740,055人(同8.1%)の順となっている。
産業中分類別構成比を全国と比較すると,「電気機械器具製造業」及び「業務用機械器具製造業」などで高く,「輸送用機械器具製造業」及び「繊維工業」などで低くなっている。(第1-11表)
第1-11表:「製造業」における産業中分類別従業者数
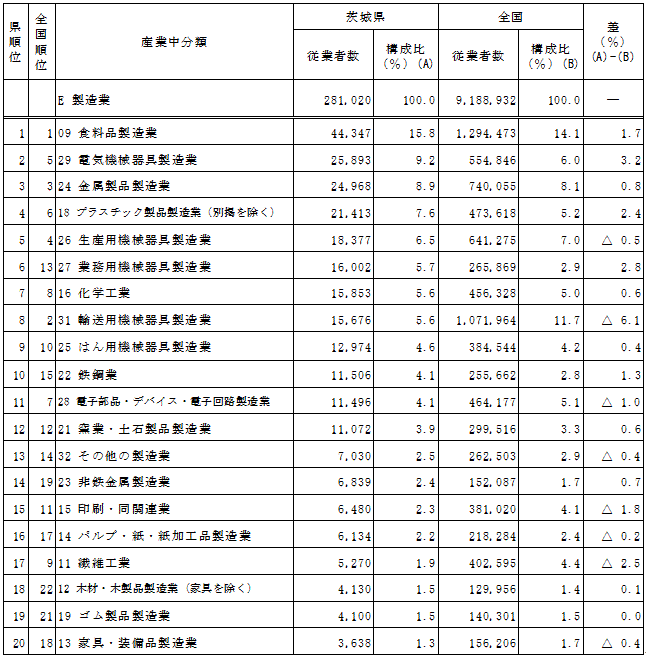
平成24年経済センサス-活動調査との比較(「製造業」(産業中分類)従業者数)
活動調査(平成24年)の結果と比べ,「はん用機械器具製造業」などが大きく減少している。
県内「製造業」の産業中分類別従業者数を活動調査(平成24年)の結果と比較すると,「製造業」全体で4,777人(1.7%)減少した。「食料品製造業」などで増加しているが,「はん用機械器具製造業」や「非鉄金属製造業」で大きく減少している。(第1-11表の2及び第10図)
第1-11表の2:「製造業」における産業中分類別従業者数(民営事業所:前回との比較)
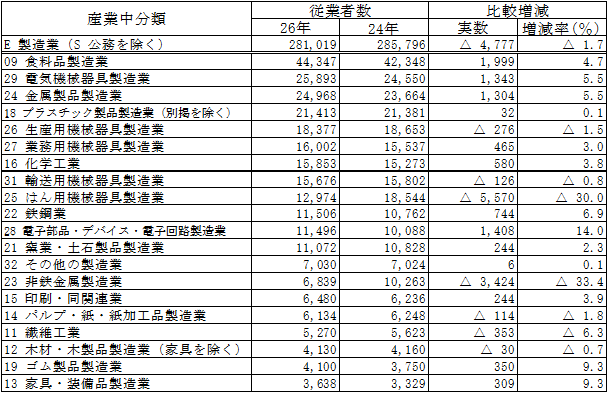
第10図:「製造業」(産業中分類)従業者数の推移(単位:人)
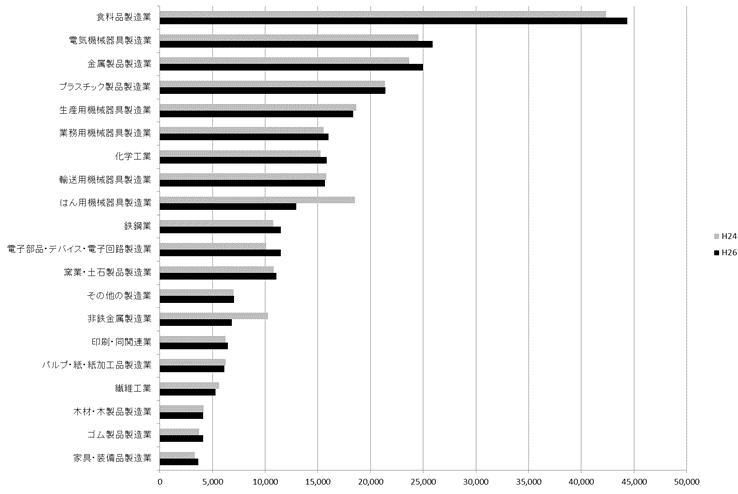
(4)「製造業」(産業小分類)
ア.事業所数
茨城県内の「製造業」では,「建設用・建築用金属製品製造業」の事業所数が多い。
産業大分類別で最も従業者数が多い「製造業」の事業所数を産業小分類別にみると,「建設用・建築用金属製品製造業」が678事業所(「製造業」全体の6.0%)と最も多く,次いで「その他の食料品製造業」が571事業所(同5.0%),「骨材・石工品等製造業」488事業所(同4.3%)の順となっている。
全国は,「建設用・建築用金属製品製造業」が26,799事業所(同5.5%)と最も多く,次いで「印刷業」が26,497事業所(同5.4%),「その他の食料品製造業」が19,602事業所(同4.0%)の順となっている。
産業小分類別構成比を全国と比較すると,「骨材・石工品等製造業」「その他の食料品製造業」及び「セメント・同製品製造業」などで高く,「印刷業」及び「金属加工機械製造業」などで低くなっている。(第1-12表)
第1-12表:「製造業」における産業小分類別事業所数(上位20分類)
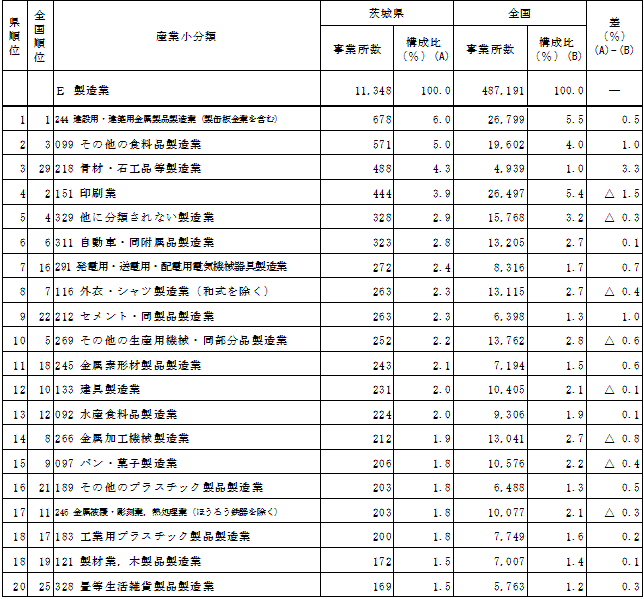
平成24年経済センサス-活動調査との比較(「製造業」(産業小分類)事業所数)
活動調査(平成24年)の結果と比べ,「他に分類されない製造業」が大きく増加した。
県内「製造業」の産業小分類別事業所数を活動調査(平成24年)の結果と比較すると,「他に分類されない製造業」や「セメント・同製品製造業」などで増加し,「自動車・同附属品製造業」や「金属加工機械製造業」で減少した。(第1-12表の2及び第11図)
第1-12表の2:「製造業」における産業小分類別事業所数(民営事業所:前回との比較)
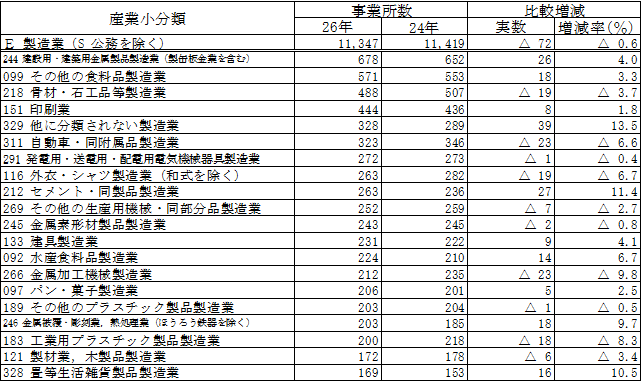
第11図:「製造業」(産業小分類)事業所数の推移(単位:事業所)
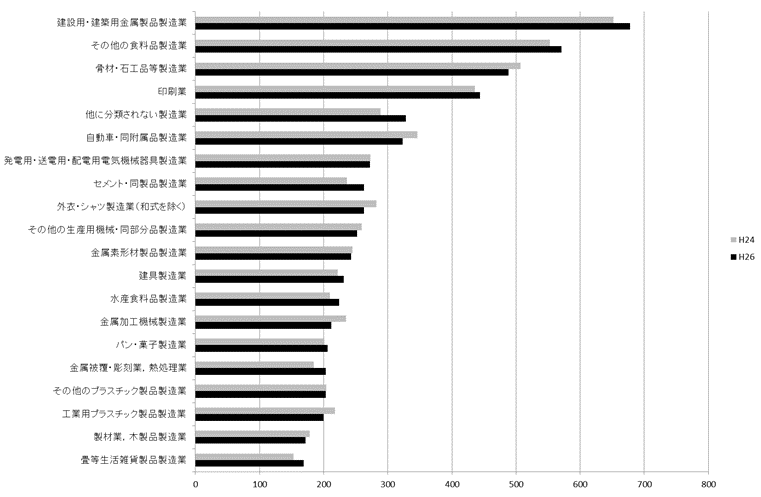
イ.従業者数
茨城県内の「製造業」を産業小分類別に見ると「その他の食料品製造業」の従業者数が最も多い。
産業大分類別で最も従業者数が多い「製造業」の事業所数を産業小分類別にみると,「その他の食料品製造業」が17,324人(「製造業」全体の6.2%)と最も多く,次いで「自動車・同附属品製造業」が14,637人(同5.2%),「発電用・送電用・配電用電気機械器具製造業」13,984人(同5.0%)の順となっている。
全国は,「自動車・同附属品製造業」が861,954人(同9.4%)と最も多く,次いで「その他の食料品製造業」が479,962人(同5.2%),「印刷業」が310,525人(同3.4%)の順となっており,自動車産業の規模の大きさが窺える。
産業小分類別構成比を全国と比較すると,「発電用・送電用・配電用電気機械器具製造業」及び「事務用機械器具製造業」などで高く,「自動車・同附属品製造業」及び「印刷業」などで低くなっている。(第1-13表)
第1-13表:「製造業」における産業小分類別従業者数(上位20分類)
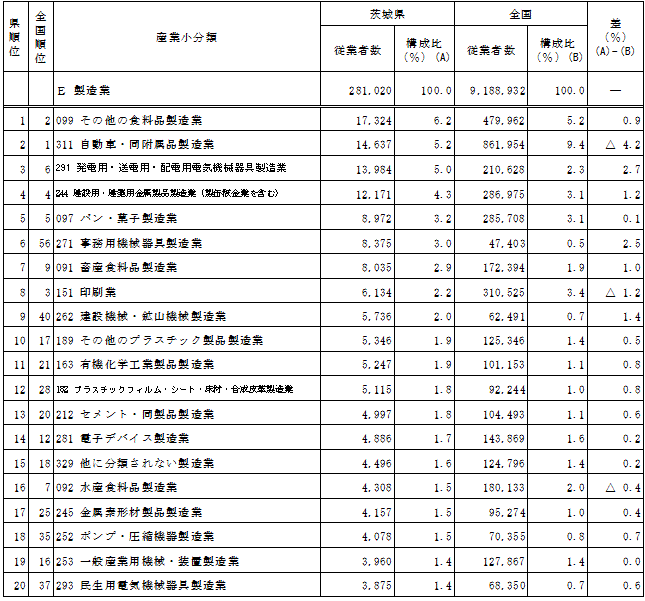
平成24年経済センサス-活動調査との比較(「製造業」(産業小分類)従業者数)
活動調査(平成24年)の結果と比べ,「発電用・送電用・配電用電気機械器具製造業」が大きく増加した。
県内「製造業」の産業小分類別従業者数を活動調査(平成24年)の結果と比較すると,「発電用・送電用・配電用電気機械器具製造業」や「電子デバイス製造業」などで増加し,「一般産業用機械・装置製造業」や「事務用機械器具製造業」で減少した。(第1-13表の2及び第12図)
第1-13表の2:「製造業」における産業小分類別従業者数(民営事業所:前回との比較)
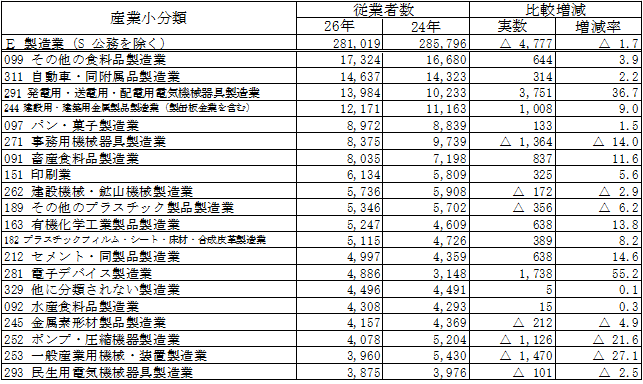
第12図:「製造業」(産業小分類)従業者数の推移(単位:人)
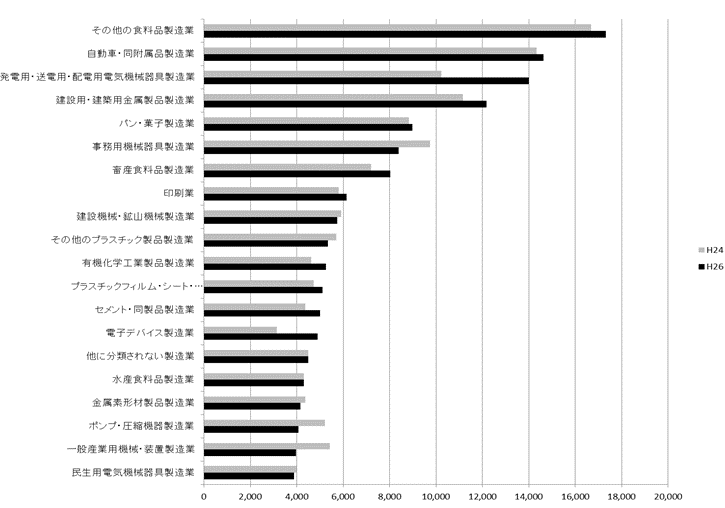
4.男女別従業者数の状況
(1)産業大分類別男性従業者数
産業大分類別の男性従業者数では,「製造業」が最も多い。
県内の男性従業者数を産業大分類別にみると,「製造業」が198,484人(全産業の26.4%)と最も多く,次いで「卸売業,小売業」が115,449人(同15.4%),「建設業」73,254事業所(同9.8%)となっており,上位3産業で51.6%を占めている。
全国は,「製造業」が6,430,741人(全産業の18.7%),「卸売業,小売業」が6,168,435人(同17.9%),「建設業」が3,116,346人(同9.1%)の順となっている。
産業大分類別構成比を全国と比較すると,「製造業」が高く,「卸売業,小売業」及び「情報通信業」で低くなっている。(第1-14表及び第13図)
第1-14表:産業大分類別男性従業者数
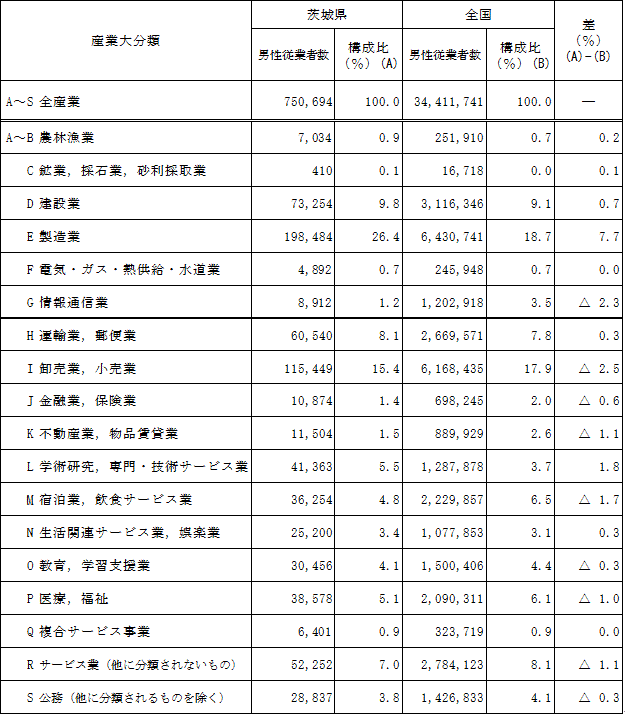
平成24年経済センサス-活動調査との比較(「全産業」(産業大分類)男性従業者数)
活動調査(平成24年)の結果と比べ,「医療,福祉」が大きく増加した。
県内の産業大分類別男性従業者数を活動調査(平成24年)の結果と比較すると,「医療,福祉」,「卸売業,小売業」及び「学術研究,専門・技術サービス業」などで増加し,「製造業」や「情報通信業」などで減少した。(第1-14表の2)
第1-14表の2:産業大分類別男性従業者数(民営事業所:前回との比較)
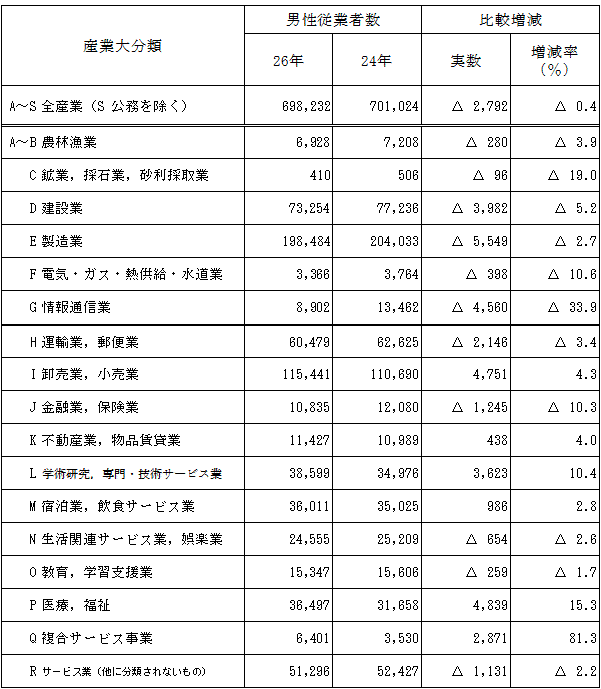
(2)産業大分類別女性従業者数
産業大分類別の女性従業者数では,「卸売業,小売業」が最も多い。
県内の女性従業者数を産業大分類別にみると,「卸売業,小売業」が121,111人(全産業の21.4%)と最も多く,次いで「医療,福祉」が109,482人(同19.3%),「製造業」80,984事業所(同14.3%)となっており,上位3産業で55.0%を占めている。
全国は,「卸売業,小売業」が5,849,222人(全産業の21.4%),「医療,福祉」が5,838,675人(同21.4%),「宿泊業,飲食サービス業」が3,274,052人(同12.0%)の順となっている。
産業大分類別構成比を全国と比較すると,「製造業」が高く,「医療,福祉」などで低くなっている。(第1-15表)
第1-15表:産業大分類別女性従業者数
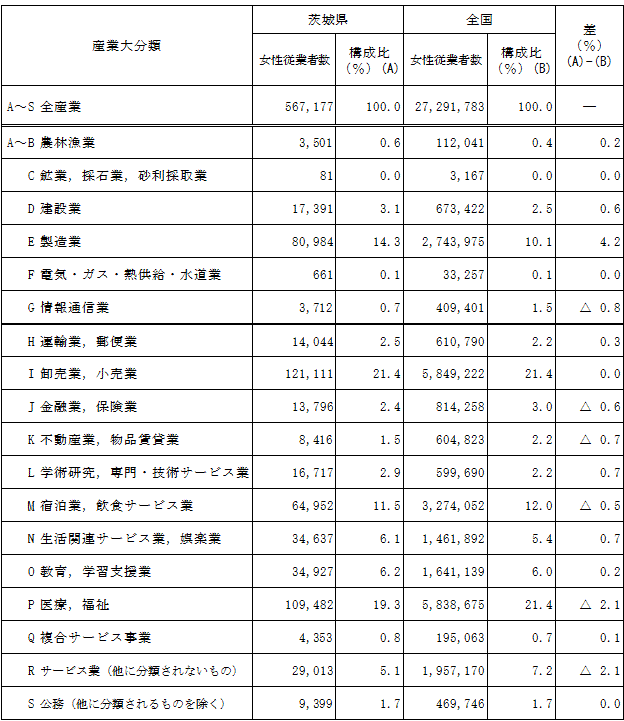
平成24年経済センサス-活動調査との比較(「全産業」(産業大分類)女性従業者数)
活動調査(平成24年)の結果と比べ,「医療,福祉」が大きく増加した。
県内の産業大分類別女性従業者数を活動調査(平成24年)の結果と比較すると,日本郵政グループの合併の影響で増加が著しい「複合サービス業」を除き,「医療,福祉」などで増加し,「金融業,保険業」などで減少した。(第1-15表の2)
第1-15表の2:産業大分類別女性従業者数(民営事業所:前回との比較)
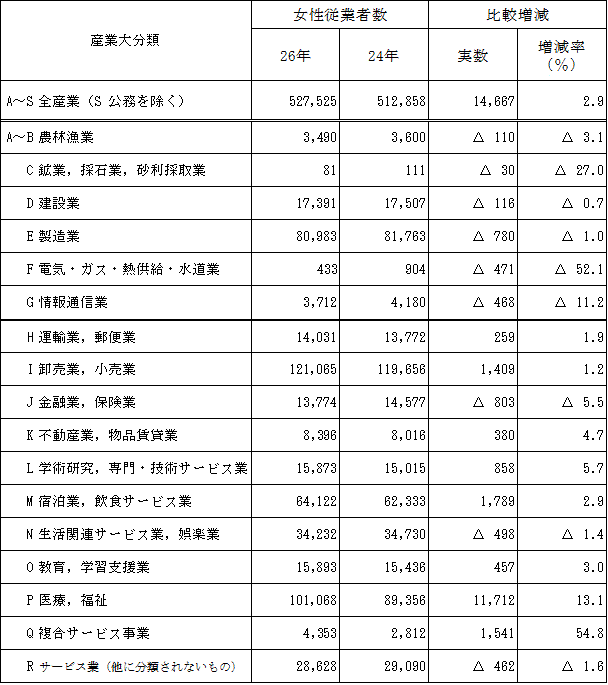
第13図:産業大分類別男女別従業者数構成比(単位:%)
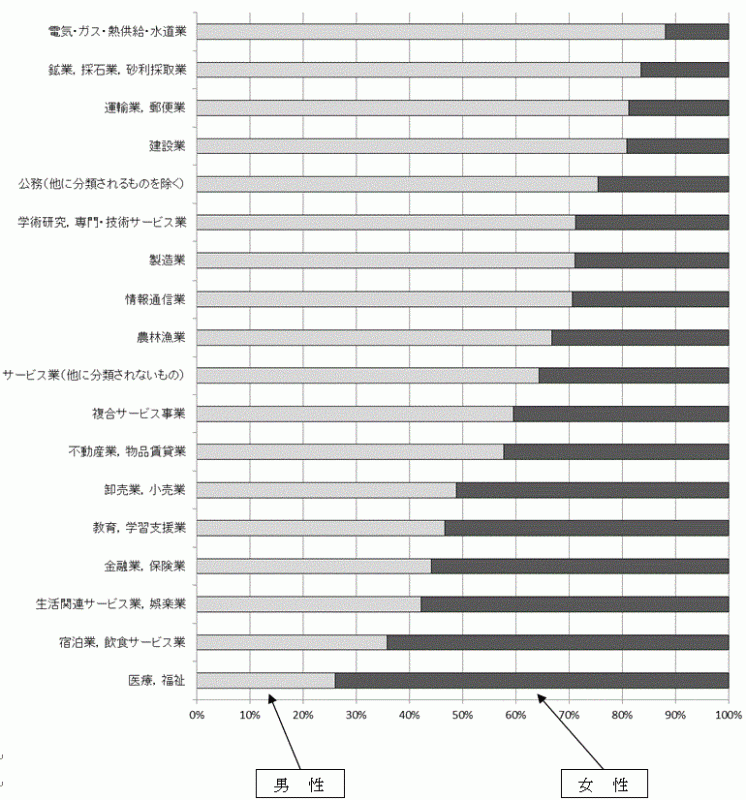
(3)男性従業者数が多い産業小分類
産業小分類別の男性従業者数では,「一般貨物自動車運送業」が最も多い。
県内の男性従業者数を産業小分類別にみると,「一般貨物自動車運送業」が37,223人(全産業の5.0%)と最も多く,次いで「自然科学研究所」が19,492人(同2.6%)の順となっている。
全国は,「一般貨物自動車運送業」が1,313,997人(同3.8%)と最も多く,次いで「自動車・同附属品製造業」が727,270人(同2.1%)の順となっている。
産業小分類別構成比を全国と比較すると,「自然科学研究所」が高く,「自動車・同附属品製造業」で低くなっている。(第1-16表)
第1-16表:男性従業者数の多い産業小分類(上位20分類)
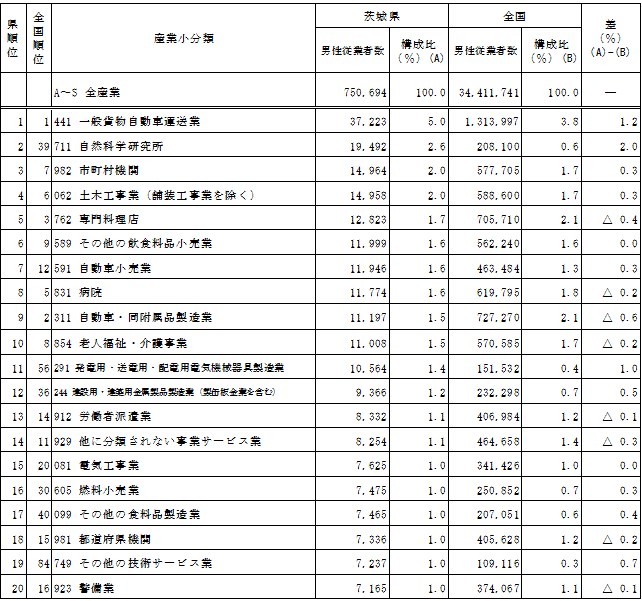
平成24年経済センサス-活動調査との比較(「全産業」(産業小分類)男性従業者数)
活動調査(平成24年)の結果と比べ,「その他の技術サービス業」が大きく増加した。
県内の産業大分類別女性従業者数を活動調査(平成24年)の結果と比較すると,「その他の技術サービス業」や「老人福祉・介護事業」などで増加し,「土木工事業」や「労働者派遣業」などで減少した。(第1-16表の2)
第1-16表の2:男性従業者数の多い産業小分類(民営事業所:前回との比較)
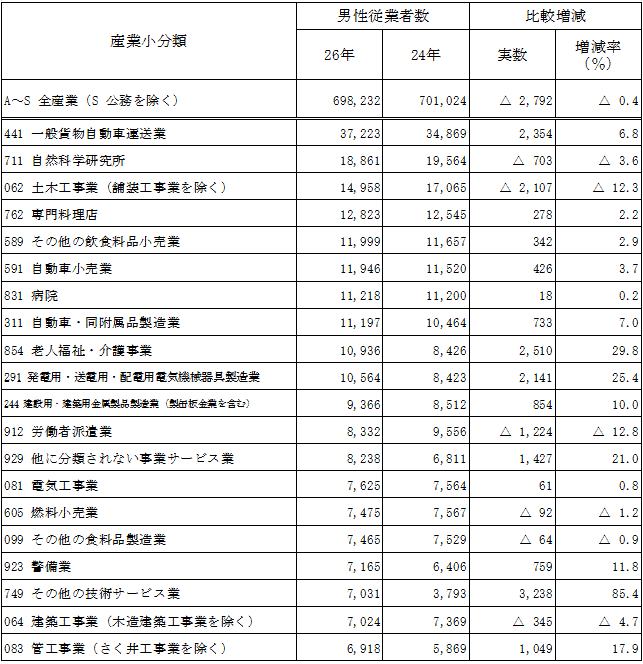
(4)女性従業者数の多い産業小分類
産業小分類別の女性従業者数では,「老人福祉・介護事業」が最も多い。
県内の女性従業者数を産業小分類別にみると,「老人福祉・介護事業」が32,060人(全産業の5.7%)と最も多く,次いで「病院」が30,518人(同5.4%)の順となっている。
全国は,「老人福祉・介護事業」が1,683,803人(全産業の6.2%)と最も多く,次いで「病院」が1,594,792人(同5.8%)の順となっている。
産業小分類別構成比を全国と比較すると,「自然科学研究所」が高く,「労働者派遣業」などで低くなっているが,上位ではほとんど同じ順位となっている。(第1-17表)
第1-17表:女性従業者数が多い産業小分類(上位20分類)
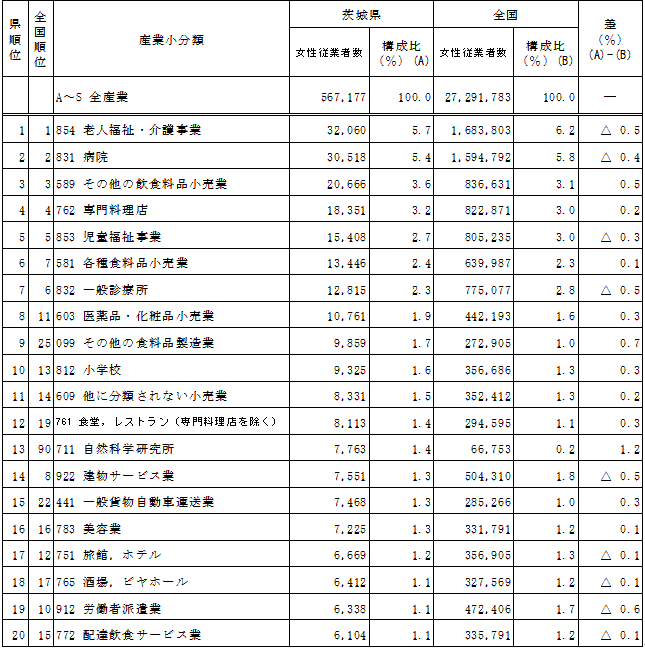
平成24年経済センサス-活動調査との比較(「全産業」(産業小分類)女性従業者数)
活動調査(平成24年)の結果と比べ,「老人福祉・介護事業」が大きく増加した。
県内の産業大分類別女性従業者数を活動調査(平成24年)の結果と比較すると,「老人福祉・介護事業」,「児童福祉事業」及び「一般貨物自動車運送業」で大きく増加し,「各種食料品小売業」などで減少した。(第1-17表の2)
第1-17表の2:女性従業者数の多い産業小分類(上位20分類)
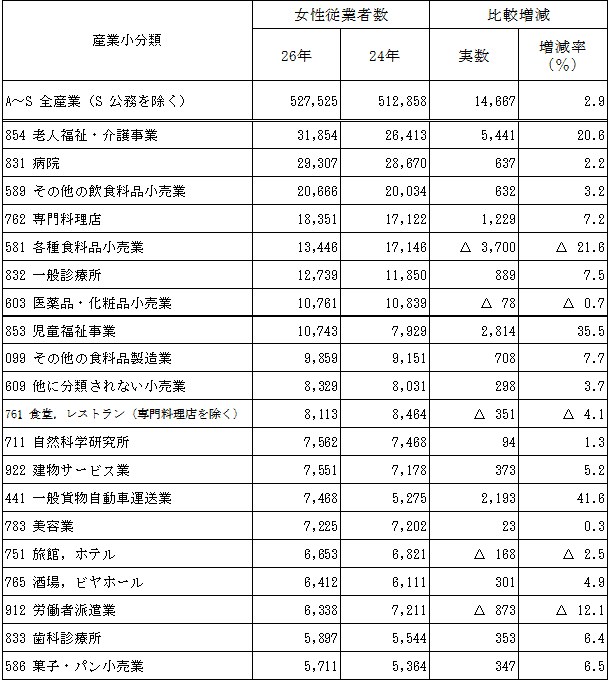
5.経営組織別の状況
(1)経営組織別事業所数
経営組織別の事業所数では,「法人」が55.5%を占めている。
県内の事業所数を経営組織別にみると,「民営」が119,168事業所(全事業所数の97.0%)で,うち「法人」が68,193事業所(同55.5%)と半数以上を占め,全国も同じ傾向となっている。
活動調査(平成24年)の結果と比較すると,「法人」が3,010事業所(4.6%)増加しているのに対し,「個人」が1,901事業所(-3.6%)の減少となった。新会社法(平成18年5月1日施行)で最低資本金制度が撤廃されたことなど,法人設立が容易になったため,今後も法人(会社)の増加が見込まれる。(第1-18表及び第1-18表の2及び第14図)
第1-18表:経営組織別事業所数
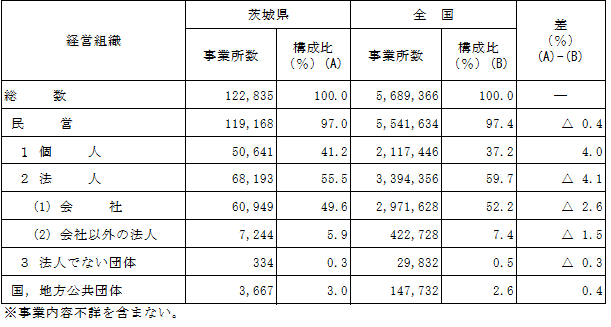
第1-18表の2:経営組織別事業所数(民営事業所:前回との比較)
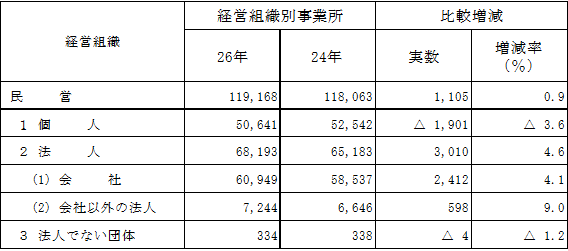
第14図:経営組織別事業所数の構成比
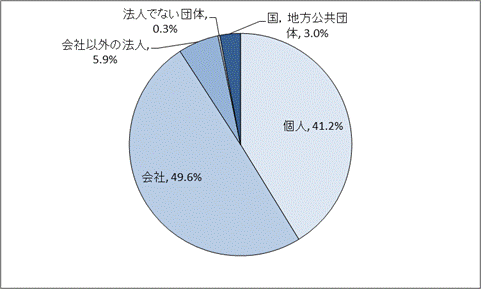
(2)経営組織別従業者数
経営組織別の従業者数では,「法人」が82.1%を占めている。
県内の従業者数を経営組織別にみると,「民営」が1,229,335人(全従業者数の93.0%)で,うち「法人」が1,084,520人(同82.1%)で大半を占め,全国も同じ傾向となっている。(第1-19表及び第15図)
第1-19表:経営組織別従業者数
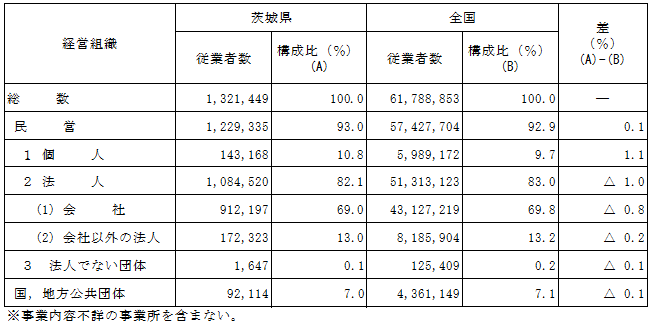
第15図:経営組織別従業者数の構成比
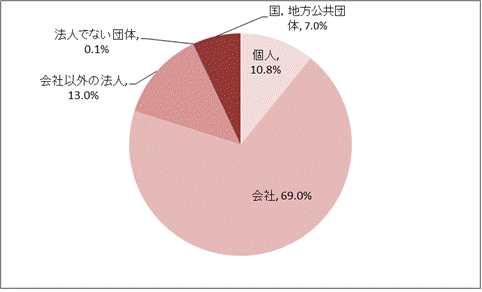
平成24年経済センサス-活動調査との比較
活動調査(平成24年)の結果と比べ,「法人でない団体」の減少が顕著である。
活動調査(平成24年)の結果と比較すると,事業所数の増減に伴い「法人」が21,306人(2.0%)増加したのに対し,「個人」は8,389人減少している。中でも高齢者福祉等を担う社会福祉法人等が属する「会社以外の法人」が11,372人(7.1%)増加となっている。(第1-19表の2)
第1-19表の2:経営組織別従業者数(民営事業所:前回との比較)
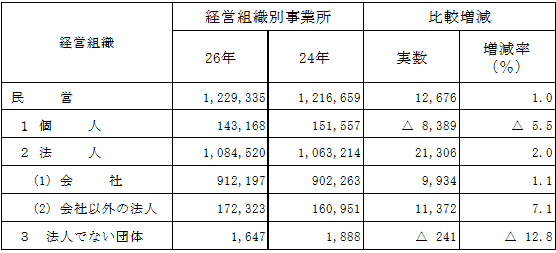
(3)経営組織別,男女別従業者数の割合
経営組織別の男女別従業者数では,「民営」,「国,地方公共団体」とも6割弱が男性従業者
県内の男女別従業者数の割合を経営組織別にみると,「民営」,「国,地方公共団体」とも「総数」と同じ割合(男性57.0%,女性43.0%)となっているが,男性は「会社」(61.6%)及び「国,地方公共団体」(57.0%)で多く,女性は「会社以外の法人」(59.9%)及び「法人でない団体」(57.9%)で多い。全国も同じ傾向となっている。(第1-20表)
第1-20表:経営組織別,男女別従業者数の割合(茨城県)
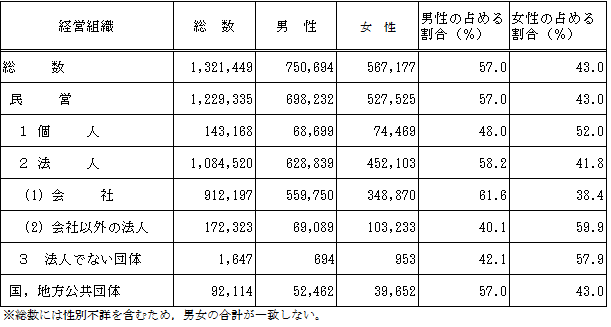
第1-21表:経営組織別,男女別従業者数の割合(全国)
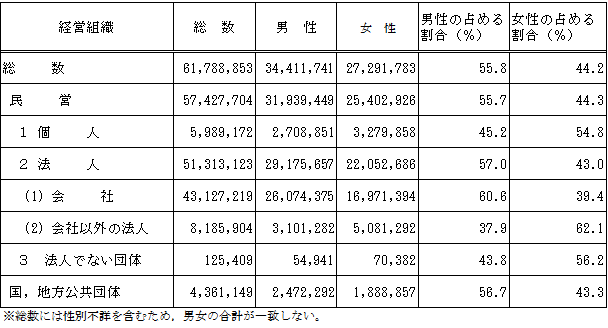
6.従業者規模別の状況
(1)従業者規模別事業所数
従業者規模別の事業所数では,「1~4人」の事業所が5割以上を占める。
県内の事業所数を従業者規模別にみると,「1~4人」が69,925事業所(全事業所の56.9%)で最も多く,次いで「5~9人」が23,792事業所(同19.4%),「10~19人」が15,155事業所(同12.3%)の順となっており,小規模な事業所で88.6%を占めており,全国(88.9%)と同じ傾向にある。(第1-22表及び第16図)
第1-22表:従業者規模別事業所数
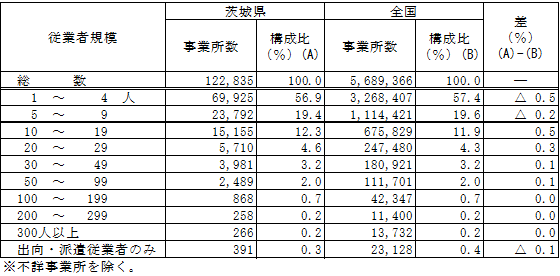
平成24年経済センサス-活動調査との比較
活動調査(平成24年)の結果と比べ,中規模の事業所数の伸びが顕著である。
活動調査(平成24年)の結果と比較すると,「10~19人」から「50~99人」の間の中規模事業所の増加が目立っている。(第1-22表の2)
第1-22表の2:従業者規模別事業所数(S公務を除く,前回との比較)
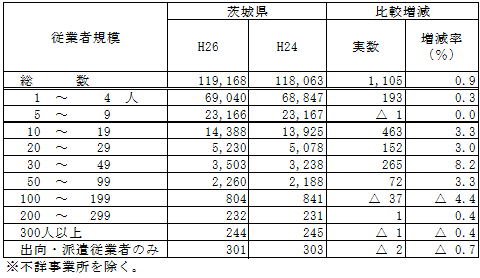
第16図:従業者規模別事業所数(単位:事業所)
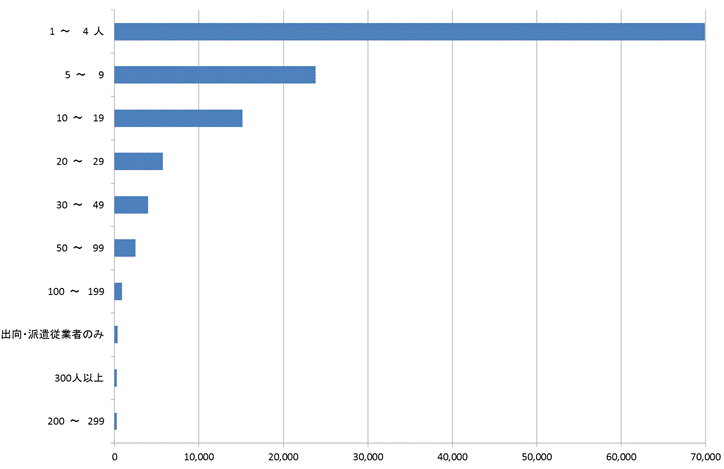
(2)従業者規模別従業者数
各従業者規模とも構成比が10%前後が多く,ほぼ均等に分布している。
県内の従業者数を従業者規模別にみると,「10~19人」(全従業者数全体の15.5%)が多く,「200~299人」(同4.7%)が少ないが,その他は10%前後の構成比率で従業者数はほぼ均等に分布しており,全国と同じ傾向にある。(第1-23表及び第17図)
第1-23表:従業者規模別従業者数
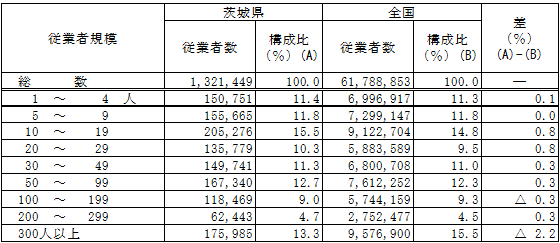
平成24年経済センサス-活動調査との比較
活動調査(平成24年)の結果と比べ,中規模事業所の従業者数の伸びが顕著である。
活動調査(平成24年)の結果と比較すると,事業所数の増加に伴い「10~19人」から「50~99人」の間の中規模事業所の増加が目立っている。(第1-23表の2及び第17図)
第1-23表の2:従業者規模別従業者数(民営事業所:前回との比較)
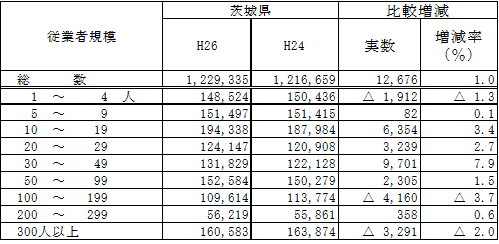
第17図:従業者規模別従業者数(単位:人)
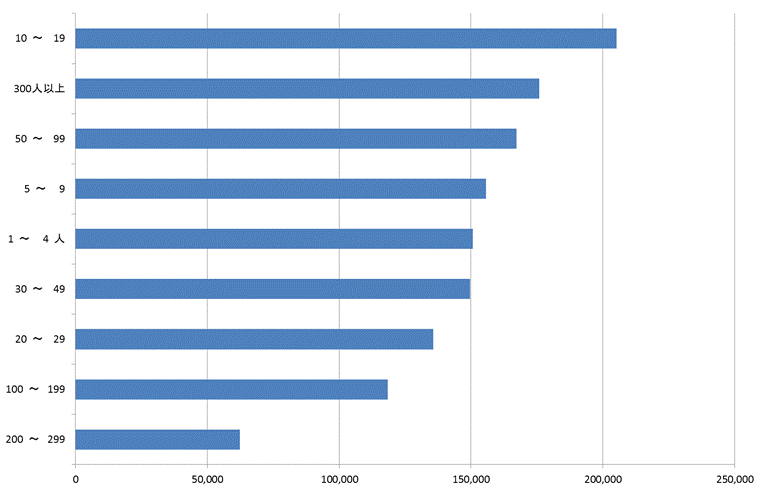
(3)従業者規模別従業者数に占める男女の割合
従業者規模別従業者数では,大規模事業ほど男性の割合が多い。
県内の従業者数に占める男女の割合を従業者規模別にみると,全ての規模で男性が5割以上となっている。特に大規模事業所ほどその割合が多くなっており,全国と同じ傾向にある。(第1-24表,25表)
第1-24表:従業者規模別,従業者に占める男性の割合
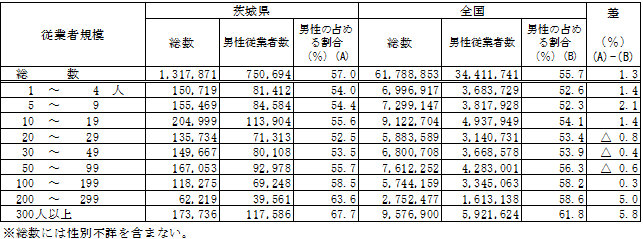
第1-25表:従業者規模別,従業者に占める女性の割合
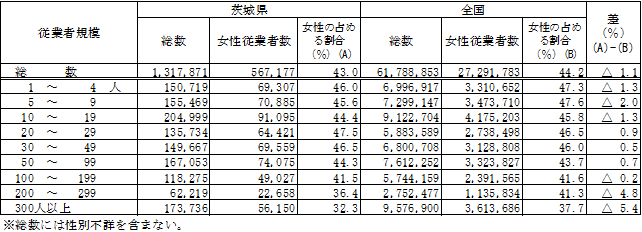
7.従業上の地位別の状況
(1)従業上の地位別男女別従業者数
従業上の地位別男女別の従業者数では,「正社員・正職員」で男性の割合が多い。
県内の従業上の地位別男女別の従業者数をみると,男性雇用者の75.0%が「正社員・正職員」であるのに対し,女性雇用者の「正社員・正職員」は39.5%に止まっており,男女の雇用格差は依然大きい。全国もほぼ同じ傾向にある。(第1-26表)
第1-26表:従業上の地位別,男女別従業者数
【茨城県】
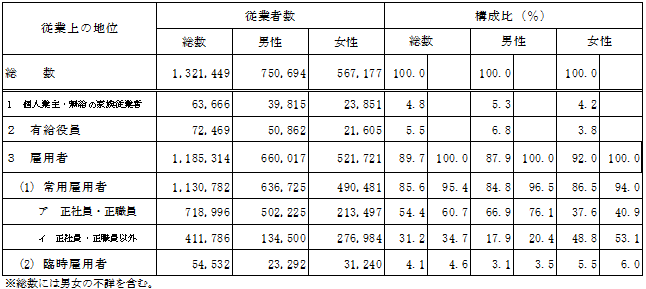
【全国】
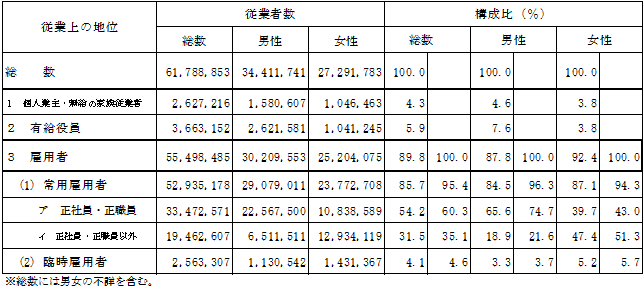
8.地域別の状況
(1)地域別事業所数及び従業者数
地域別の事業所数及び従業者数では,「県南地域」が最も多い。
県内5地域の事業所数及び従業者数をみると,「県南地域」が38,751事業所(30.8%),436,578人(33.0%)とどちらも3割以上を占め最も多い。(第1-27表,第18図及び第19図)
第1-27表:地域別事業所数及び従業者数
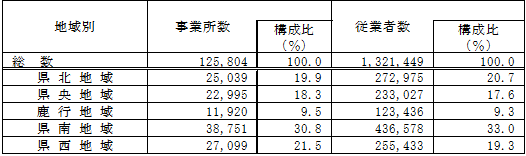
第18図:地域別事業所数の構成比(単位:%)
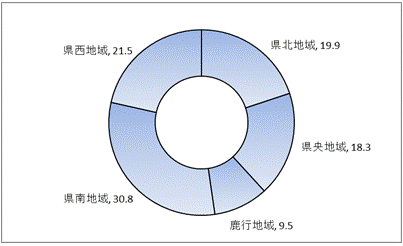
第19図:地域別従業者数の構成比(単位:%)
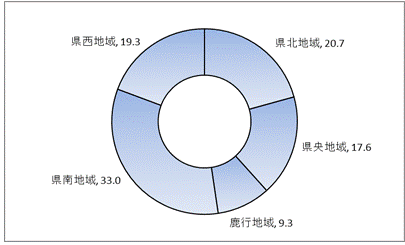
(2)市町村別事業所数及び従業者数
市町村別の事業所数及び従業者数では,「水戸市」が最も多い。
県内市町村別の事業所数及び従業者数ををみると,「水戸市」が14,357事業所(11.4%),152,570人(11.5%)と最も多い。次いで「つくば市」が9,237事業所(7.3%),128,858人(9.8%),「日立市」が7,679事業所(6.1%),93,708人(7.1%)の順となっている。
事業所数に対し,大規模事業所が多い「ひたちなか市」や「神栖市」が従業者数で順位を上げている。(第1-28表及び第20図)
第1-28表:市町村別事業所数及び従業者数(上位10市)
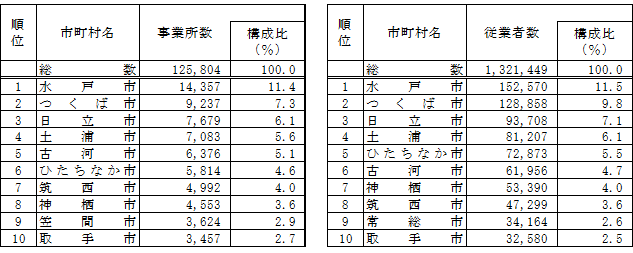
第20図:事業所数と従業員の分布状況
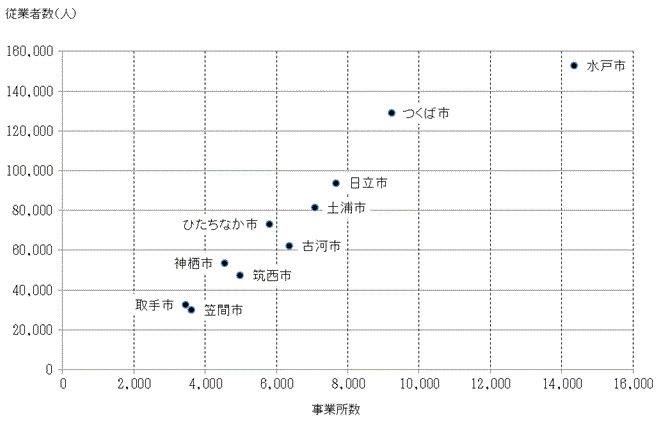
(3)事業所数上位10市の産業大分類別事業所数
事業所数上位10市の産業大分類別事業所数では,「卸売業,小売業」の割合が多い。
事業所数上位10市の事業所数を産業大分類別にみると,人口が多く市街地や住宅地が形成されているため,商店等の事業所が多く「卸売業,小売業」が事業数全体の2割を超えている。同様に「建設業」,「宿泊業,飲食サービス業」及び「生活関連サービス業,娯楽業」の割合が多い。
第1-29表:事業所数上位10市の産業大分類別事業所数
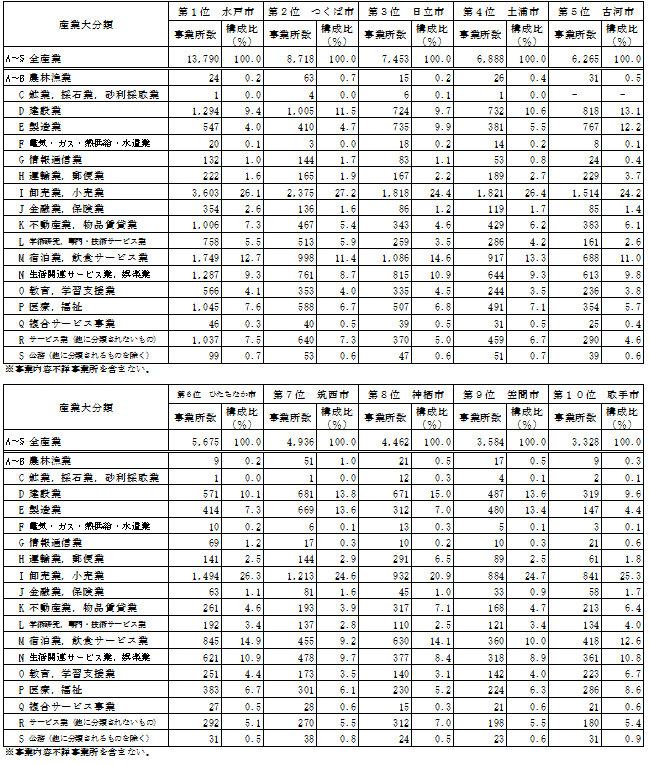
(4)従業者数上位10市の産業大分類別従業者数
従業者数上位10市の産業大分類別従業者数では,「製造業」及び「卸売業,小売業」の割合が多い。
従業者数上位10市の従業者数を産業大分類別にみると,大規模な工場が立地している市では,「製造業」が,大規模な商業施設が立地している市では「卸売業,小売業」が多い。(第1-30表)
第1-30表:従業者数上位10市の産業大分類別従業者数
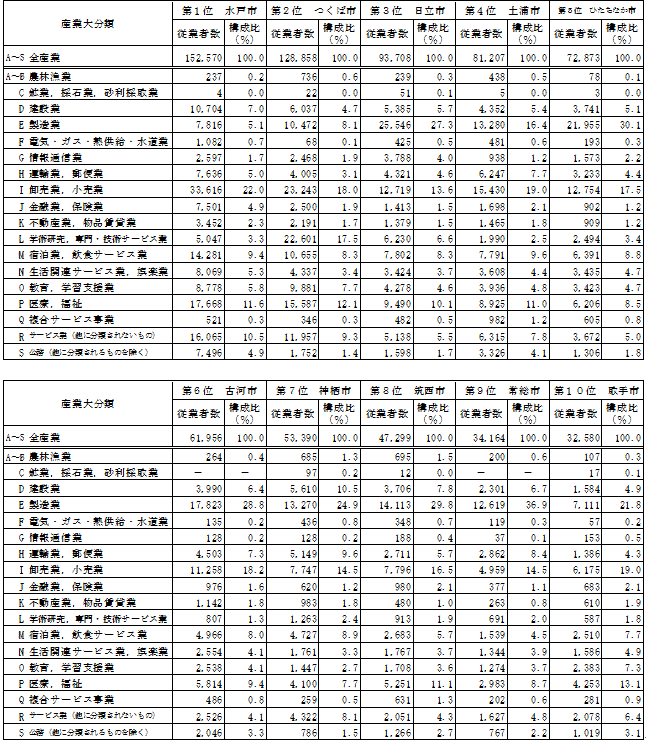
第2.企業等の状況(企業等に関する集計)
1.概況
茨城県の経営組織別の企業等数は,「個人経営」の割合が多い。
平成26年7月1日現在の県内の企業等数は,89,405企業(全国の2.2%)で,「個人経営」が50,038企業(企業等全体の56.0%),「法人」が39,367企業(同44.0%)となっており,「個人経営」の割合が多くなっている。「法人」のうち「会社企業(注)」は34,895企業(同39.0%)で,「法人」の88.6%を占めている。
全国の企業等の数は4,098,284企業で,「個人経営」が2,089,716企業(同51.0%),「法人」が2,008,568企業(同49.0%)となっており,「個人経営」と「法人」が拮抗している。
経営組織別企業等数の構成比を全国と比較すると,本県では「個人経営」が高くなっている。(第2-1表及び第21図)
(注)「会社企業」とは,株式会社(有限会社を含む),合名会社,合資会社,合同会社及び相互会社を合算したものである。
第2-1表:経営組織別企業等数(全国との比較)
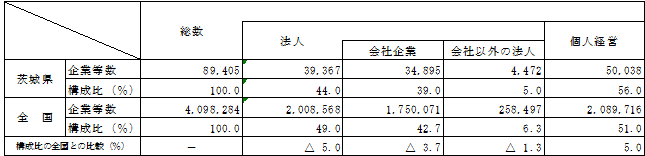
第21図:経営組織別企業等数の構成比
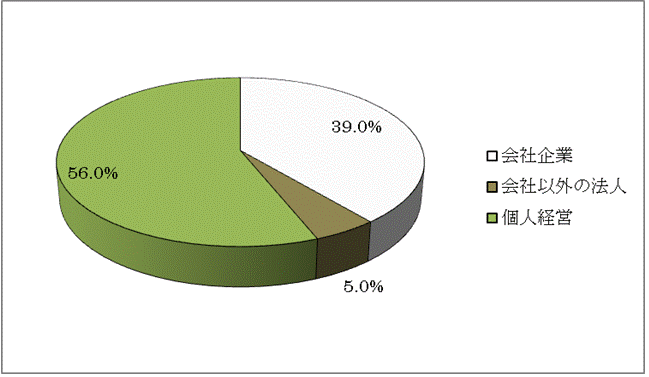
平成24年経済センサス-活動調査との比較
活動調査(平成24年)の結果と比べ,「個人経営」の企業等数は減少しているが依然構成比率は高い。
活動調査(平成24年)の結果と比較すると,総数で1,166企業減少している。「法人」は731企業増加し,「個人経営」で1,897企業減少しているが,依然として「個人経営」の構成比率は高くなっている。(第2-1表の2)
第2-1表の2:経営組織別企業等数(前回との比較)
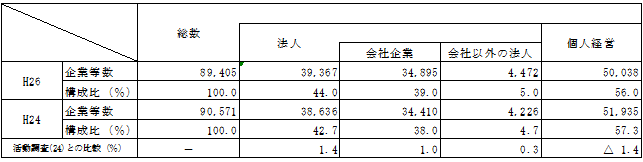
2.産業大分類別企業等数
産業大分類別企業等数では,全国と比較し「建設業」の割合が多い。
県内の企業等数を産業大分類別にみると,「卸売業,小売業」が19,899企業(企業等数全体の22.3%)と最も多く,次いで「建設業」が14,309企業(同16.0%),「宿泊業,飲食サービス業」が10,462企業(同11.7%)の順となっており,これらの企業で全産業の50.0%を占めている。
全国は,「卸売業,小売業」が907,857企業(同22.2%),次いで「宿泊業,飲食サービス業」が546,717企業(同13.3%),「建設業」が456,312企業(同11.1%)の順となっている。
産業大分類別構成比を全国と比較すると,「建設業」や「生活関連サービス業,娯楽業」などで高く,「不動産業,物品賃貸業」などで低くなっている。(第2-2表)
第2-2表:産業大分類別企業等数
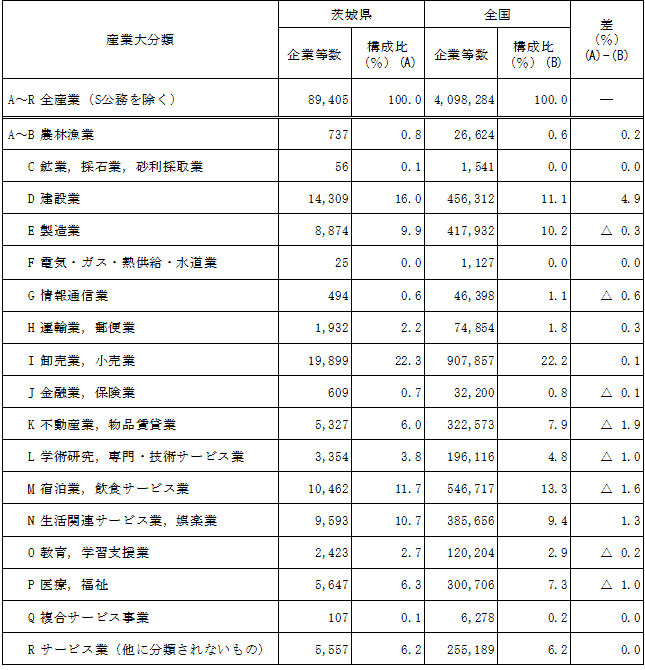
3.常用雇用者規模別企業等数及び雇用者数
常用雇用者規模が20人未満の企業等が多い。
県内の企業等数を常用雇用者規模別にみると,「0~4人」が67,317企業(企業全体の75.3%)と最も多く,次いで「5~9人」が10,125企業(同11.3%),「10~19人」が6,079企業(同6.8%)の順となっており,常用雇用者規模20人未満の企業等が全体の93.4%を占めている。
全国は,「0~4人」が3,046,806企業(同74.3%),「5~9人」が469,759企業(同11.5%),「10~19人」が279,724人(同6.8%)の順となっており,常用雇用者規模20人未満の企業等が全体の92.6%を占めている。(第2-3表)
第2-3表:常用雇用者規模別企業等数
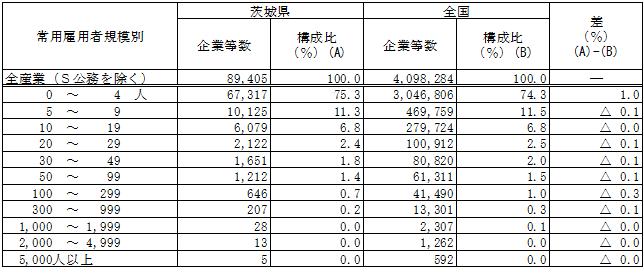
常用雇用者数(海外を含む)をみると,「0~4人」が176,663人(常用雇用者全体の19.6%)となっており,次いで「100~299人」が110,782人(同12.3%),「300~999人」101,828人(同11.3%)の順となっている。
全国は,「5,000人以上」が7,808,447人(同16.2%)と最も多く,「0~4人」は3,123,104人(同6.5%)と低い,常用雇用者規模の小さい企業の雇用者数が少ない傾向にある。
常用雇用者規模別構成比を全国と比較すると,1,000人未満の規模で高く,1,000人以上の規模で低くなっている。(第2-4表)
第2-4表:常用雇用者規模別常用雇用者数
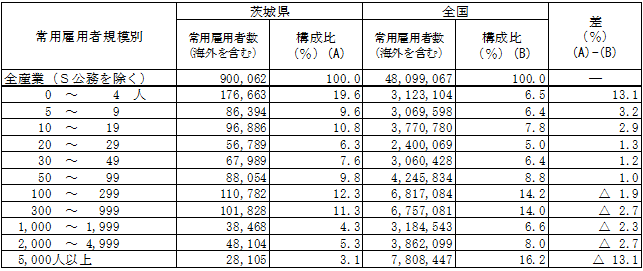
4.資本金階層別企業数
全国と比較すると,資本金が1,000万円未満の企業の占める割合が高い。
県内の会社企業(以下「企業」という。)数を資本金階層別にみると,「300~500万円未満」が12,948企業(企業全体の37.1%)と最も多く,次いで「1,000~3,000万円未満」が10,907企業(同31.3%),「500~1,000万円未満」が5,659企業(同16.2%)の順となっており,資本金3,000万円未満の企業が全産業の90.2%を占めている。
全国は,「300~500万円未満」が605,406企業(同34.6%)が最も多く,次いで「1,000~3,000万円未満」が578,309企業(同33.0%),「500~1,000万円未満」が224,896企業(同12.9%)の順となっており,資本金3,000万円未満の企業が全産業の86.7%を占めている。
資本金階層別構成比を全国と比較すると,資本金1,000万円未満の階層で高く,1,000万円以上の階層で低くなっている。(第2-5表)
第2-5表:資本金階層別企業数
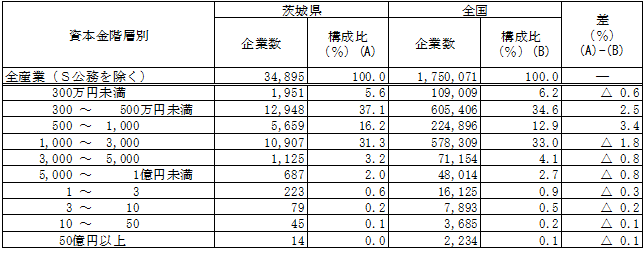
付表
付表1:都道府県別事業所数及び従業者数
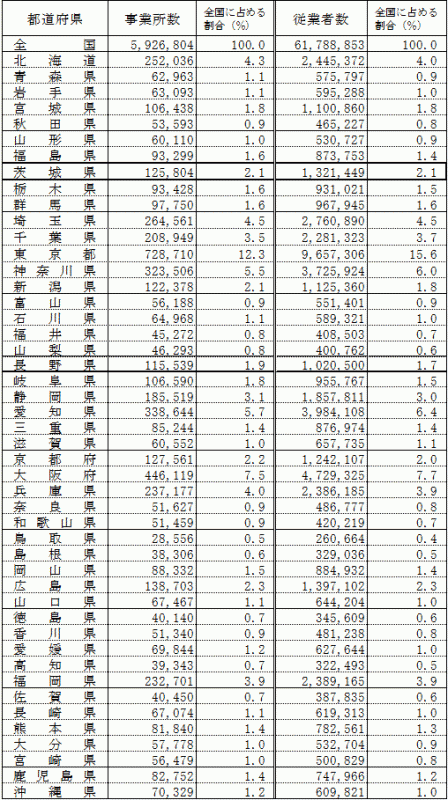
付表2:市町村別事業所数及び従業者数
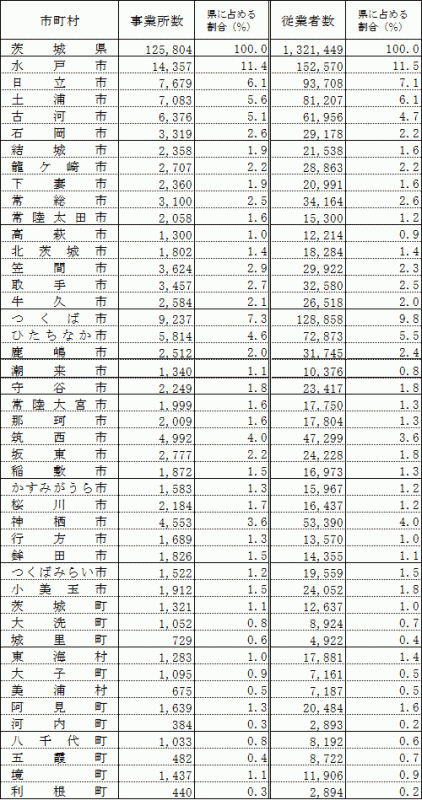
より詳細な結果等については,総務省統計局ホームページの「平成26年経済センサス-基礎調査」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
総務省統計局(リンク)
事業所・企業統計調査
- 平成18年事業所・企業統計調査結果(茨城県)
- 平成13年事業所・企業統計調査結果(茨城県)
- 平成18年事業所・企業統計調査(外部サイトへリンク)(総務省統計局)