目的から探す
ホーム > 県政情報 > 県の概要 > いばらき統計情報ネットワーク > いばらき統計情報ネットワーク(統計課) > 分野別≪物価・景気・家計・経済≫ > 茨城県消費者物価指数年報-平成21年-
ページ番号:12466
更新日:2015年4月1日
ここから本文です。
茨城県消費者物価指数年報-平成21年-
目次
利用上の注意
- この消費者物価指数を算出するにあたり,物価調査を実施している対象地域は,水戸市,日立市,土浦市,古河市,取手市(以上の5市については平成16年11月から平成18年3月までの合併前の旧区域),つくば市,筑西市(旧下館市区域),鹿嶋市(旧大野村を除く区域),神栖市(旧神栖町区域),鉾田市(旧鉾田町区域),つくばみらい市の11市です。
- この消費者物価指数は,水戸市,日立市,土浦市,古河市,笠間市,取手市,つくば市,筑西市,鹿島地方(鹿嶋市,神栖市,鉾田市)の平成17年1年間の品目別平均価格を基準(指数値を100)として作成したものです。したがって,各市の物価の動きを時系列的にみようとするもので,県内各市相互間の物価の地域格差を示すものではありません。
なお,物価の地域格差については,統計表に全国の都市階級,地方及び,都道府県庁所在市等の消費者物価地域差指数を掲載していますので御利用ください。 - 調査対象地域の拡充については,平成4年1月から鹿島地方3市を,平成4年7月から古河市の調査店舗数をそれぞれ拡充しました。
また,つくば市,鹿島地方については平成7年基準から中分類指数を公表しています。
なお,つくばみらい市の指数については,精度の観点から公表していません。 - この報告書の各表における符号の用法は次のとおりです。
「-」該当数字なし
「0」単位未満
1.平成21年茨城県消費者物価指数の動向
1.概況
- 平成21年の茨城県消費者物価指数(県平均)は,総合で100.5(平成17年=100)となり,前年比は1.5%の下落となった。前年比1.5%下落は,比較可能な昭和43以降,過去最大の下落幅となる。
- 下落要因は,平成20年夏頃に急騰したガソリンや灯油が値下がりしたため。なお,食料(酒類を除く)及びエネルギーを除く総合指数は98.8となり,前年比は0.8%の下落となった。
- 総務省が公表した全国消費者物価指数は,総合で100.3となり,前年比は1.4%の下落となっている。全国と本県の指数は,ほぼ同様の動きを示した。
(1)近年の動き
ここ10年間の総合指数は前年比の動きで見ると,平成12年から平成17年までは平成11年からのデフレーションの進行に伴い,消費者物価は下落傾向であった。平成17年を底に上昇基調に転じ,平成19年秋頃から石油製品や食料品などの価格上昇が続き,平成20年は11年ぶりとなる前年比1.5%上昇となった。平成21年には前年の急上昇を収斂する形で推移し,平成19年当時の水準に戻った。各年別の詳細は次のとおりである。
- 平成12年はパソコン,電気こたつ,電子レンジなど家電製品や被服,家具・寝具類の値下がりにより0.8%下落した。
その後も下落傾向は続き,平成13年は0.3%下落,平成14年は1.1%下落,平成15年は0.4%下落となり,平成11年から5年連続で下落した。 - 平成16年はイラク戦争など中東産油国情勢の不透明感と中国の石油消費量の増大などを背景に原油が高騰するに伴い石油製品が値上がりしたことに加え,台風や豪雨の天候不順による生鮮野菜の値上がりと前年の冷夏による米類の値上がりの影響が残り0.1%の上昇となった。
- 平成17年は原油価格が引き続き高騰したが,米類や生鮮野菜が前年の反動から値下がりしたことに加え,パソコン,プリンタ,電気ポットなど家電製品の値下がりや固定電話料金引き下げなどにより0.3%の下落となった。
- 平成18年は耐久消費財や移動電話通信料などが値下がりしたものの,原油の高止まりにより前年に引き続き石油製品が値上がりしたことに加え,年初からの豪雪,6~7月の大雨被害による野菜,果物などの値上がりにより再び0.5%の上昇に転じた。
- 平成19年はテレビ,パソコン,カメラなどの耐久消費財は価格下落の傾向が年間を通じてあったものの,エネルギーや食料が9月まで前年並みの推移から一転,10月からの原油価格高騰,燃料用エタノール生産向け需要増加などの影響により加工食品等の上昇幅が大きくなったため,前年と同水準となった。
- 平成20年は原油価格高騰でガソリンや灯油など石油製品が大幅上昇したことに加え,小麦など穀物価格高騰でパンやめん類が上昇したほか,飼料価格高騰で肉類や卵も値上がりするなど食料品に幅広く値上げや減量の動きがみられた。前年比は1.5%上昇となり,消費税率引き上げのあった平成9年(1.5%上昇)以来,11年ぶりの上げ幅となった。
- 平成21年は平成20年夏頃急騰したガソリン及び灯油などが値下がりしたことに加えて,11月の政府によるデフレ宣言に見られるように,衣類や家具家事用品などの値下がりにより1.5%の下落となった。これは,比較可能な昭和43年以降,過去最大の下落幅であった。
図1消費者物価指数の年別推移
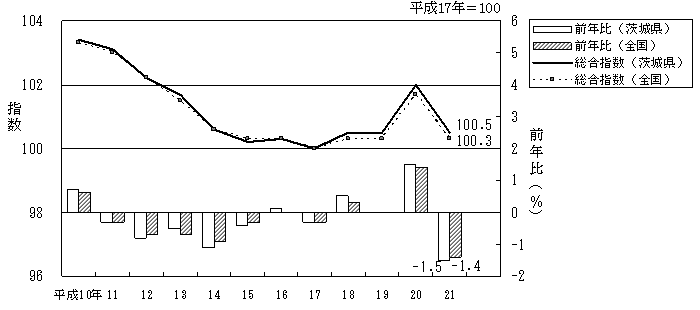
表1:消費者物価指数及び前年比
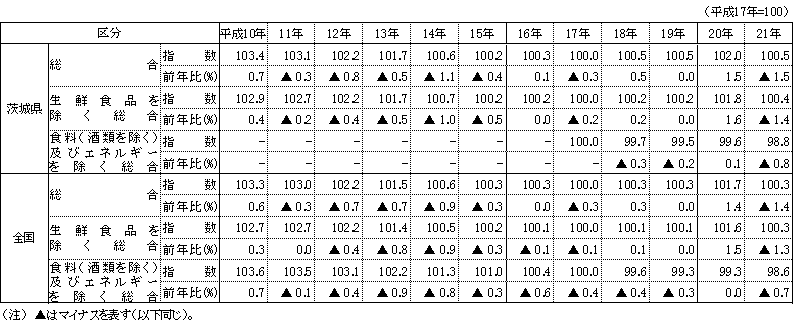
(2)10大費目指数の動き
総合指数の前年比が1.5%と下落なった内訳を寄与度でみると,光熱・水道(灯油,電気代)」,「交通・通信(自動車等関係費)」,「教養娯楽(教養娯楽用耐久財)」などの下落が要因となっている。
- 寄与度…ある品目又は類の指数の変動が,総合指数の変化率のうち,どの程度影響を与えたかを示したもの。
( )内は寄与度の大きい中分類項目を記載。
表2:県平均10大費目指数
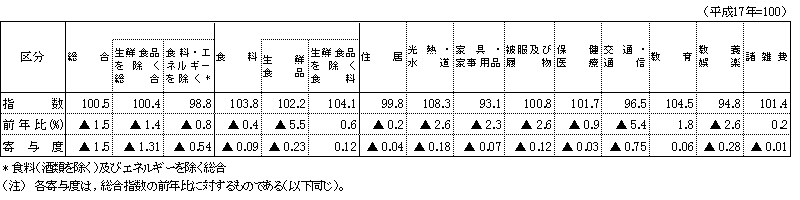
(3)財・サービス分類指数の動き
財・サービス分類指数の動きを前年比でみると,財は2年ぶりにマイナス,サービスは4年ぶりにマイナスとなった。
財は2.8%の下落となった。これは,工業製品や石油製品などが値下がりしたことによるものである。
サービスは0.3%の下落となった。これは,持ち家の帰属家賃や通信・教養娯楽関連サービスなどが値下がりしたことによるものである。
図2:財・サービス分類の前年比の推移
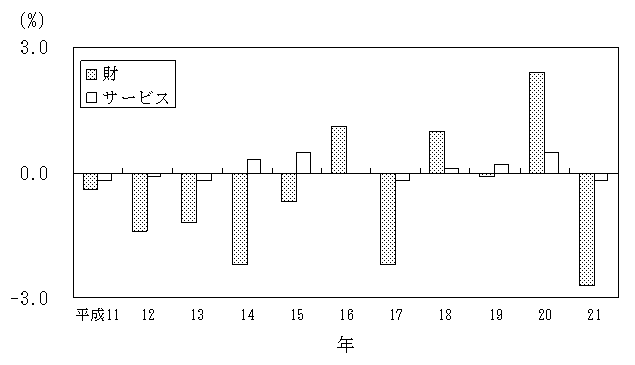
2.月別の動き
- 今年の総合指数を月別の動きでみると,1月を除き,年間を通じて前年同月比マイナスで推移した。
- 2月頃からガソリンや灯油などの価格下落が続き,21年6月の総合指数は前年同月比2.2%下落となった。これは,比較可能な昭和43年1月以降,最大の下落幅となった。6月から11月までは2%台の下落が続くが,12月には下落幅が縮小しているものの,食料品及び日用品などの値下がりにより,下落基調は続いている。
図3:消費者物価指数の月別推移
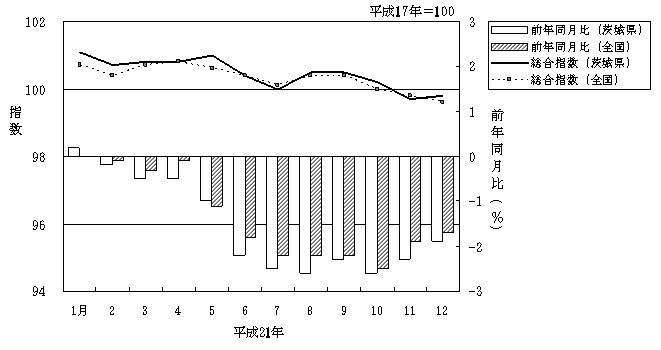
表3:消費者物価指数,前月比及び前年同月比
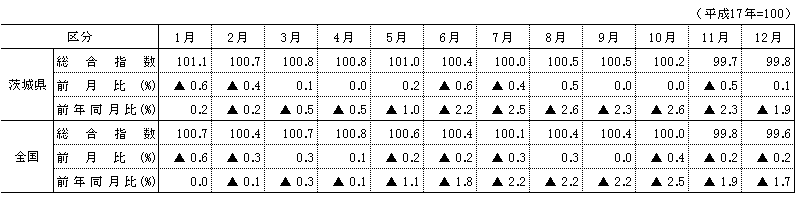
| 上昇率(%) | 主な要因※( )内は変動幅の大きい品目を記載。 |
|---|---|
| 前月比-0.6 (3か月連続でマイナス) |
平成20年夏頃の原油急騰の反動により,ガソリン価格の下落が底打ち。(県内平均価格104円) 教養娯楽サービス(ゴルフプレー料金),自動車等関係費(ガソリン),衣料(婦人コート)などが値下がりしたことによるもの。 |
| 前年同月比0.2 (16か月連続でプラス) |
原油高が光熱水費へ波及。小麦など原材料価格の高騰。電気代,穀類(即席めん,スパゲッティ),菓子類(チョコレート,ケーキ)などが値上がりしたことによるもの。 |
| 上昇率(%) | 主な要因※( )内は変動幅の大きい品目を記載。 |
|---|---|
| 前月比-0.4 (4か月連続でマイナス) |
好天で生育の進んだ野菜や果物の出荷増により値下がり。 衣料(婦人スラックス),生鮮野菜(ブロッコリー),教養娯楽用耐久財(デスクトップ型パソコン)などが値下がりしたことによるもの。 |
| 前年同月比-0.2 (18か月ぶりにマイナス) |
原油急騰の反動によるガソリン価格の下落。 自動車等関係費(ガソリン),灯油,教養娯楽用耐久財(ノート型パソコン),衣料(婦人スラックス)などが値下がりしたことによるもの。 |
| 上昇率(%) | 主な要因※( )内は変動幅の大きい品目を記載。 |
|---|---|
| 前月比0.1 (5か月ぶりにプラス) |
春物衣料品の出始めにより値上がり。 衣料(ワンピース),教養娯楽サービス(外国パック旅行),シャツ・セーター・下着類(子供Tシャツ)などが値上がりしたことによるもの。 |
| 前年同月比-0.5 (2か月連続でマイナス) |
温暖な日が続いたことから野菜の出荷増により値下がり。 自動車等関係費(ガソリン),灯油,教養娯楽用耐久財(ノート型パソコン),生鮮野菜(アスパラガス)などが値上がりしたことによるもの |
| 上昇率(%) | 主な要因※( )内は変動幅の大きい品目を記載。 |
|---|---|
| 前月比0.0 (前月と同水準) |
生鮮野菜(はくさい),シャツ・セーター・下着類(婦人半袖Tシャツ)などが値上がりし,生鮮果物(いちご)などが値下がりしたことによるもの。 |
| 前年同月比-0.5 (3か月連続でマイナス) |
自動車等関係費(ガソリン),灯油,教養娯楽用耐久財(ノート型パソコン),衣料(婦人上着)などが下がりしたことによるもの。 |
| 上昇率(%) | 主な要因※( )内は変動幅の大きい品目を記載。 |
|---|---|
| 前月比0.2 (2か月ぶりにプラス) |
1月で底を打ったガソリン価格が原油高を背景に徐々に値上がり。 生鮮果物(グレープフルーツ),教養娯楽サービス(ゴルフプレー料金),自動車等関係費(ガソリン)などが値上がりしたことによるもの。 |
| 前年同月比-1.0 (4か月連続でマイナス) |
自動車等関係費(ガソリン),教養娯楽用耐久財(ノート型パソコン),灯油などが値下がりしたことによるもの。 |
| 上昇率(%) | 主な要因※( )内は変動幅の大きい品目を記載。 |
|---|---|
| 前月比-0.6 (2か月ぶりにマイナス) |
高い気温,平年並みの降水量や日照時間に恵まれ果物が値下がり。 生鮮果物(メロン),生鮮魚介(ほたて貝),電気代などが値下がりしたことによるもの。 |
| 前年同月比-2.2 (5か月連続でマイナス) |
自動車等関係費(ガソリン),灯油,教養娯楽用耐久財(ノート型パソコン),生鮮魚介(ほたて貝)などが値上がりしたことによるもの。 |
| 上昇率(%) | 主な要因※( )内は変動幅の大きい品目を記載。 |
|---|---|
| 前月比-0.4 (2か月連続でマイナス) |
夏物衣料の値下がり。 生鮮野菜(えだまめ),シャツ・セーター・下着類(婦人半袖Tシャツ),衣料(男児ズボン)などが値下がりしたことによるもの。 |
| 前年同月比-2.5 (6か月連続でマイナス) |
昨年夏の原油急騰した石油製品の値下がり。光熱水費への価格転嫁により値下がり。 自動車等関係費(ガソリン),教養娯楽用耐久財(ノート型パソコン)灯油,電気代などが値下がりしたことによるもの。 |
| 上昇率(%) | 主な要因※( )内は変動幅の大きい品目を記載。 |
|---|---|
| 前月比0.5 (3か月ぶりにプラス) |
長雨・日照不足により野菜や果物の値上がり。 生鮮野菜(レタス),生鮮果物(グレープフルーツ),教養娯楽サービス(外国パック旅行)などが値上がりしたことによるもの。 |
| 前年同月比-2.6 (7か月連続でマイナス) |
ガソリン及び灯油については下げ止まり。 自動車等関係費(ガソリン),灯油,電気代,教養娯楽用耐久財(ノート型パソコン)などが値下がりしたことによるもの。 |
| 上昇率(%) | 主な要因※( )内は変動幅の大きい品目を記載。 |
|---|---|
| 前月比0.0 (前月と同水準) |
秋物衣料出始めにより値上げ。秋が旬の食料が値下がり。 衣料(乳児服),シャツ・セーター・下着類(婦人長袖セーター)などが値上がりし,教養娯楽サービス(外国パック旅行),生鮮魚介(さんま)などが値下がりしたことによるもの。 |
| 前年同月比-2.3 (8か月連続でプラス) |
自動車等関係費(ガソリン),灯油,電気代,教養娯楽用耐久財(ノート型パソコン)などが値下がりしたことによるもの。 |
| 上昇率(%) | 主な要因※( )内は変動幅の大きい品目を記載。 |
|---|---|
| 前月比-0.3 (3か月ぶりにマイナス) |
今夏の長雨・日照不足から天候が回復し,出荷増により値下がり。 生鮮野菜(レタス),生鮮果物(みかん),外食(回転ずし),教養娯楽サービス(外国パック旅行)などが値下がりしたことによるもの。 |
| 前年同月比-2.6 (9か月連続でマイナス) |
自動車等関係費(ガソリン),灯油,電気代,教養娯楽用耐久財(ノート型パソコン)などが値下がりしたことによるもの。 |
| 上昇率(%) | 主な要因※( )内は変動幅の大きい品目を記載。 |
|---|---|
| 前月比-0.5 (2か月連続でマイナス) |
内閣府公表の「月例経済報告」にて2006年6月以来のデフレ認定。 生鮮果物(オレンジ),生鮮野菜(ブロッコリー),教養娯楽サービス(ビデオソフトレンタル料)などが値下がりしたことによるもの。 |
| 前年同月比-2.3 (10か月連続でマイナス) |
自動車等関係費(ガソリン),灯油,電気代,教養娯楽用耐久財(ノート型パソコン)などが値下がりしたことによるもの。 |
| 上昇率(%) | 主な要因※( )内は変動幅の大きい品目を記載。 |
|---|---|
| 前月比0.1 (3か月ぶりにプラス) |
寒波到来により生鮮食品の出荷減により値上がり。 生鮮果物(グレープフルーツ),生鮮魚介(さけ),生鮮野菜(レタス),灯油などが値上がりしたことによるもの。 |
| 前年同月比-1.9 (11か月連続でマイナス) |
教養娯楽用耐久財(ノート型パソコン),電気代,生鮮野菜(キャベツ))などが値上がりしたことによるもの。 |
3.費目別指数の動き
図4:10大費目の前年比
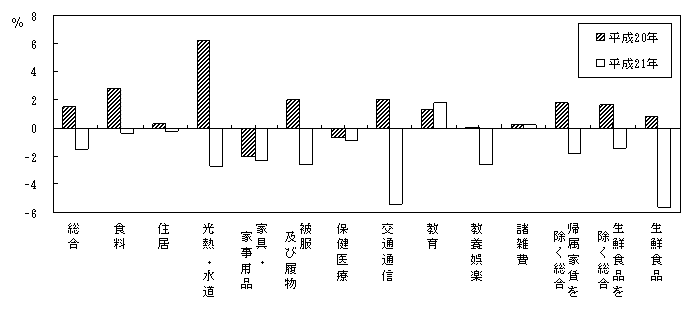
(1)食料
食料は103.8となり,前年比は0.4%の下落となった。
- 生鮮食品についてみると,生鮮野菜が4.5%下落,生鮮魚介が7.3%下落,生鮮果物が5.2%下落となり,生鮮食品全体では5.6%の下落となった。
- 生鮮食品以外では上昇した費目は,乳卵類が2.1%,菓子類が1.8%,油脂・調味料が1.3%,穀類が0.9%,外食が0.9%,調理食品が0.8%であった。一方下落した費目は,肉類が3.1%,飲料が2.3%,酒類が0.7%であった。
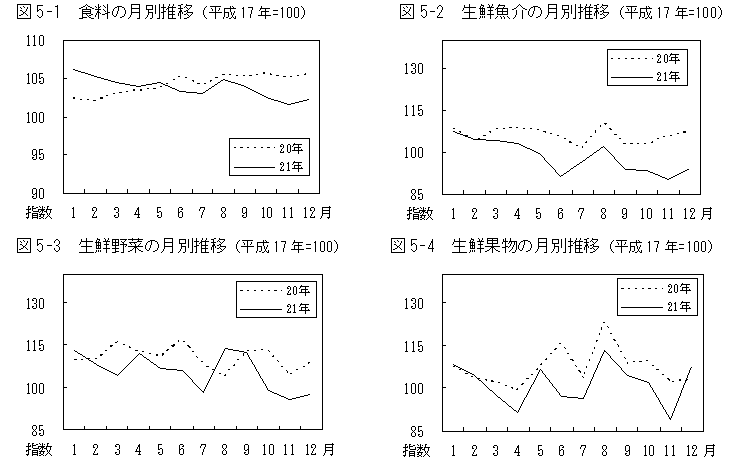
(2)住居
住居は99.8となり,前年比は0.2%の下落となった。
- 費目別では,家賃が0.3%下落したが,設備修繕・維持は1.1%上昇した。
図6:住居の月別推移(平成17年=100)
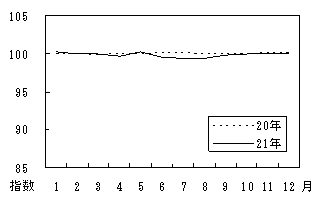
(3)光熱・水道
光熱・水道は108.3となり,前年比は2.7%の下落となった。
- 費目別では,昨年夏頃の原油価格高騰の反動により,灯油が27.6%下落,電気代が2.6%下落した。一方でガス代は2.5%上昇,上下水道料は2.0%上昇となった。
図7:光熱・水道の月別推移(平成17年=100)
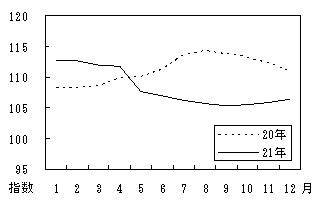
(4)家具・家事用品
家具・家事用品は93.1となり,前年比は2.3%の下落となった。
- 費目別では,室内装備品が5.3%下落,家庭用耐久財が3.3%下落,家事雑貨が2.5%下落,家事用消耗品が1.2%下落,家事サービスが0.8%下落となった。一方,寝具類は0.1%上昇となった。
図8:家具・家事用品の月別推移(平成17年=100)
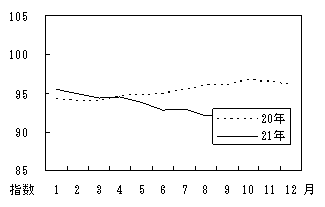
(5)被服及び履物
被服及び履物は100.8となり,前年比は2.6%の下落となった。
- 費目別では,履物類が0.8%上昇,被服関連サービスが0.1%上昇となった。一方,衣料は4.1%下落,他の被服類は2.3%下落,シャツ・セーター・下着類は2.2%となった。
- 衣料の内訳では,洋服が4.2%下落,和服が2.8%下落となった。また,シャツ・セーター・下着類の内訳は,シャツ・セーター類が3.1%下落,下着類は0.1%下落となった。
図9:被服及び履物の月別推移(平成17年=100)
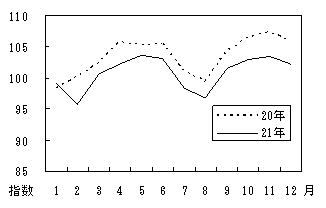
(6)保健医療
保健医療は101.7となり,前年比は0.9%の下落となった。
- 費目別では,保健医療用品・器具が7.5%下落,医薬品・健康保持摂取品が2.2%下落となった。一方,保健医療サービスは2.0%上昇した。
図10:保健医療の月別推移(平成17年=100)
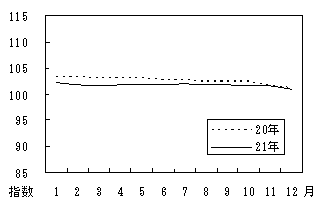
(7)交通・通信
交通・通信は96.5となり,前年比は5.4%の下落となった。
- 費目別では,自動車等関係費がガソリンの値下がりで8.8%下落,交通が1.1%下落,通信が0.2%下落となった。
図11:交通・通信の月別推移グラフ(平成17年=100)
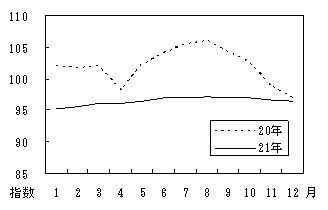
(8)教育
教育は104.5となり,前年比は1.8%の上昇となった。
- 費目別では,教科書・学習参考書が9.5%上昇,授業料等が1.8%上昇,補習教育が0.1%上昇となった。
図12:教育の月別推移(平成17年=100)
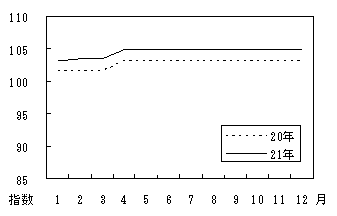
(9)教養娯楽
教養娯楽は94.8となり,前年比は2.6%の下落となった。
- 費目別では,書籍・他の印刷物が0.3%上昇となった。一方,教養娯楽耐久財はパソコンや薄型テレビなどの値下がりで21.6%下落,教養娯楽サービスは外国パック旅行の値下げで2.0%下落,教養娯楽用品は0.1%下落となった。
図13:教養娯楽の月別推移(平成17年=100)
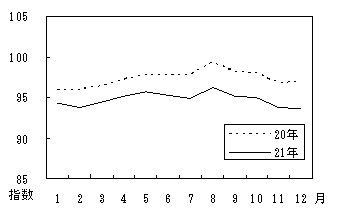
(10)諸雑費
諸雑費は101.4となり,前年比は0.2%の下落となった。
- 費目別では,理美容サービスが0.2%上昇,身の回り用品及び他の諸雑費が0.1%上昇,たばこが同水準となった。一方,理美容用品は1.1%下落となった。
図14:諸雑費の月別推移(平成17年=100)
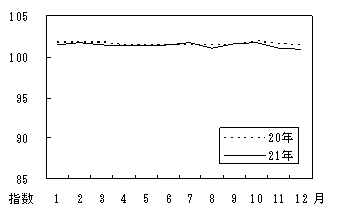
図15:中分類の前年比
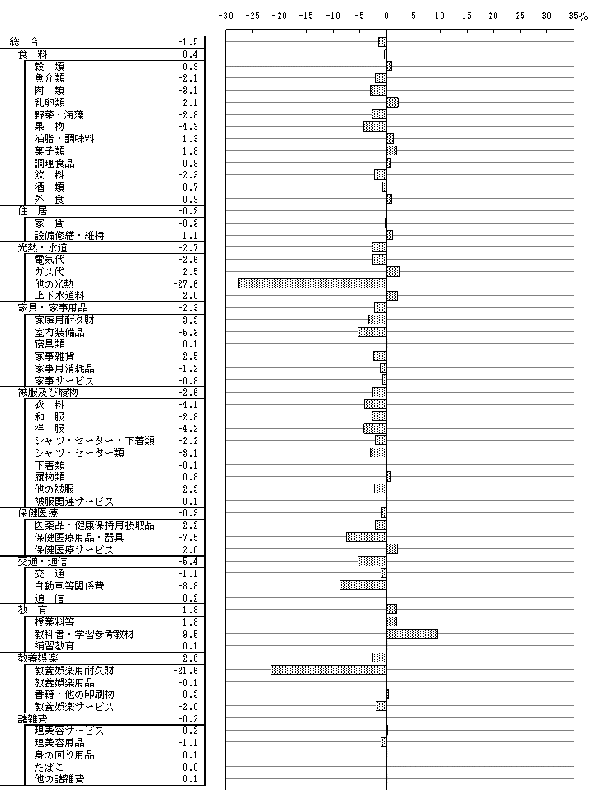
4.寄与度・寄与率
総合指数の前年比が1.5%下落となった内訳を寄与度でみると,押し下げに最も寄与したのは,昨年夏頃の原油急騰の反動によりガソリン価格が値下がりした「交通・通信」(寄与度-0.76)であった。次いで,パソコンや薄型テレビ,外国パックの値下がりで「教養娯楽」(寄与度-0.29),灯油や電気代の値下がりで「光熱・水道」(寄与度-0.18)となっている。
一方,押し上げに最も寄与したのは,教科書・学習参考教材が値上がりした「教育」(寄与度0.07)であった。
表4:10大費目の前年比及び寄与度・寄与率
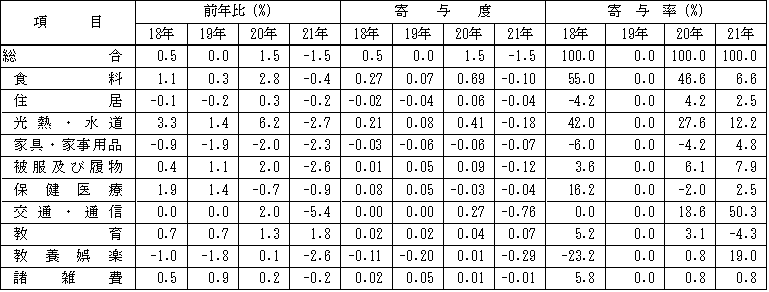
5.財・サービス分類指数の動き
指数作成に用いられる585品目(指数品目)の分類において,統計表第3表から第6表までにある「食料」,「穀類」,「住居」,「家賃」,「光熱・水道」などの大分類及び中分類は消費生活上の観点から分類したものである。
これに対して,財・サービス分類指数は,指数品目を供給側の視点から組み替えたものであり,大別すると財とサービスに分けられる。この財・サービス分類指数で平成21年の動きをみると次のとおりである。
図16:財・サービス分類指数の年別推移(平成17年=100)
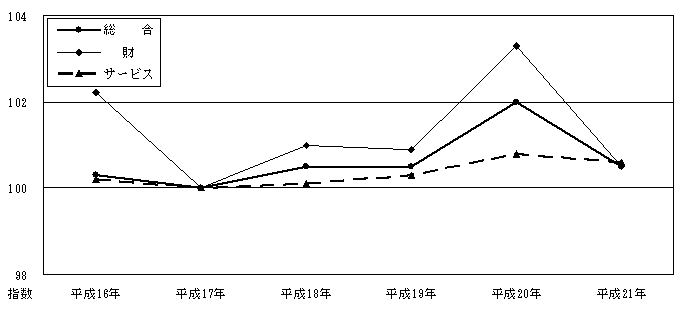
(1)財
財は100.5となり,前年と比べて2.7%下落し,2年ぶりにマイナスとなった。
まず,「農水畜産物」は101.3となり,前年比は3.6%の下落となった。これは,生鮮野菜や生鮮果物などの値下がりで「生鮮商品」が下落(-4.6%)したことによるものである。
「工業製品」は99.9となり,前年比は2.9%の下落となった。これは,昨年夏頃の原油価格高騰の反動で「石油製品」が大幅下落(-16.2%)したことによるものである。
また,「電気・都市ガス・水道」は103.4となり,電気代の値下がりなどで1.0%下落した。
(2)サービス
サービスは100.6となり,前年と比べて0.2%下落し,4年ぶりにマイナスとなった。
「公共サービス料金」は101.0となり,前年比は0.3%の下落となった。これは,航空運賃の値下がりや保険料改定で自動車保険料(自賠責)などが値下がりしたことによるものである。
「一般サービス料金」は100.4となり,前年比は0.3%の下落となった。これは,「持ち家の帰属家賃」や「民営家賃」が下落(-0.6%,-0.4%)したことに加え,家事関連サービス(自動車整備費(定期点検)など)や通信・教養娯楽関連サービス(外国パック旅行など)といった「他のサービス」が下落(-0.2%)したことによるものである。
6.品目別価格指数の動き
平成21年における財・サービス品目別価格指数の上昇・下落の状況は次のとおりである。
表5:財のこの1年における上昇・下落の状況
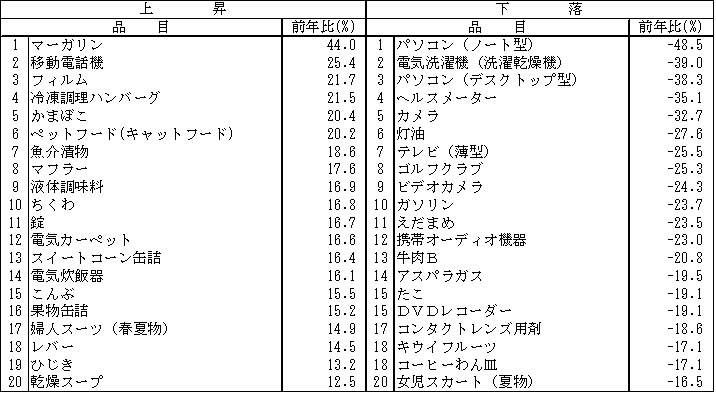
表6:サービスのこの1年における上昇・下落の状況
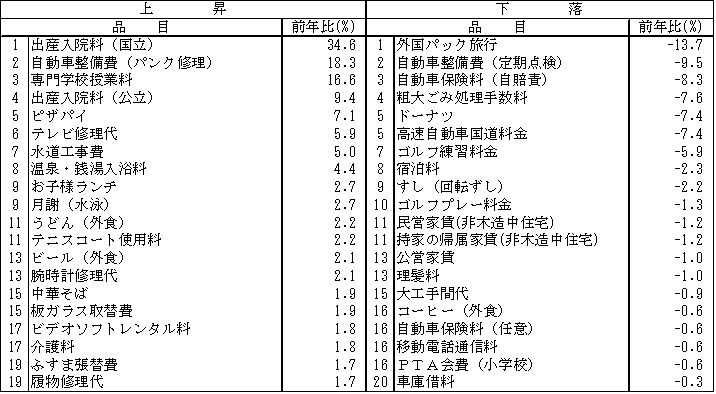
7.市・地方別指数の動き
市・地方別総合指数の前年比をみると,全域が1.0%以上の下落となった。
上昇幅の最も大きかった地域は鹿島地方で2.1%下落,次いで水戸市と日立市が1.6%下落,つくば市が1.5%下落となっている。
図17:市・地方別総合指数の前年比
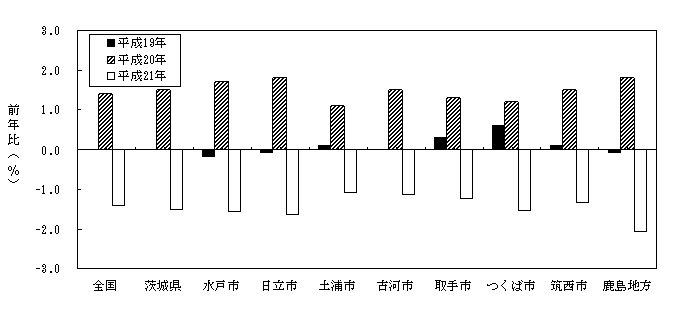
10大費目別の上昇・下落の傾向をみると,「教育」は全域で上昇,「食料」,「交通・通信」及び「教養娯楽」は全域で下落となり,4費目が同様の傾向を示している。
このような傾向を示した原因としては,全国(全県)系列小売業等による統一価格の進展,店舗間の価格競争及び価格情報の入手が容易であることなどが考えられる。
一方,上昇・下落の地域間のばらつきがあったのは「住居」,「諸雑費」であった。
表7:市・地方別10大費目指数の前年比(平成21年)
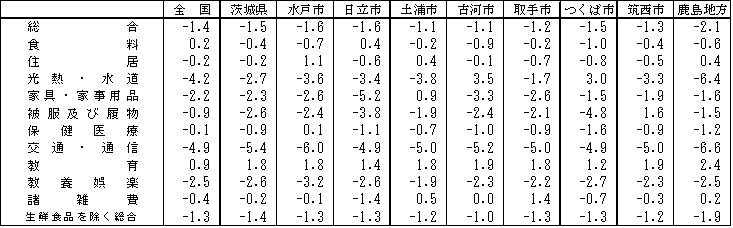
2.統計表
- 統計表はPDFファイルで提供しています。
- (1)第1表:主要指標(PDF:24キロバイト)
- (2)第2表:総合指数(PDF:24キロバイト)
- (3)第3表:茨城県消費者物価指数大分類指数(PDF:129キロバイト)
- (4)第4表:茨城県消費者物価指数中分類指数(PDF:645キロバイト)
- (5)第5表:茨城県消費者物価指数帰属家賃及び生鮮食品等を除く指数(PDF:131キロバイト)
- (6)第6表:茨城県消費者物価指数年次別中分類指数,寄与度,寄与率(PDF:298キロバイト)
- (7)第7表:茨城県消費者物価指数財・サービス分類指数,寄与度,寄与率(PDF:340キロバイト)
- (8)第8表:都市階級別,県庁所在都市別総合及び食料指数(PDF:15キロバイト)
- (9)第9表:都市階級別,県庁所在都市別消費者物価地域差指数(PDF:17キロバイト)
- (10)第10表:全国中分類指数(PDF:21キロバイト)
- (11)第11表:茨城県消費者物価指数主要調査品目の市別年平均価格(PDF:29キロバイト)
茨城県消費者物価指数月報
消費者物価指数四半期報
総務省統計局(リンク)