目的から探す
ホーム > 県政情報 > 県の概要 > いばらき統計情報ネットワーク > いばらき統計情報ネットワーク(統計課) > 統計で知るいばらき > 統計トピックス > 統計インフォメーションNo.89-干支(えと)別人口のカラクリ-
ページ番号:13244
更新日:2015年4月1日
ここから本文です。
統計インフォメーションNo.89-干支(えと)別人口のカラクリ-
年末になると,茨城県統計課や総務省統計局などが,新年の干支(今回は「寅年」生まれ)の人口を推計して公表しています。
干支は,全部で12あります。
その中で,新年の干支の人口は何番目に多いのでしょうか。
茨城県統計課が平成21年12月25日に公表した「寅年」生まれの人口は,元日現在,24万1600人で,十二支中8位となっています。
では,「寅年」生まれの人口は毎年8位なのでしょうか。
来年の今頃,「卯年」生まれの推計人口が公表される頃,「卯年」生まれの人口は「9位」,「寅年」生まれの人口はきっと「1位」になっていることでしょう。
それはいったい,どういうことなのでしょうか。
転入や転出を考えなければ,人口の増減は生死の数によって決まります。
自分の干支の人口が増えるチャンスは,12年のうち1年間しかありません。
例えば「寅年」であれば,過去11年間,「寅年」はありませんでしたので,「寅年」生まれは誕生せず,死亡者数だけが増えていく,つまり,干支人口は毎年減り続けていくことになるのです。逆に,「寅年」が干支になる平成22年(2010年)は,その年に生まれた新生児が「寅年」人口に加わります。
当年の新生児は,決して他の干支生まれになることはありません。
(一部の芸能人や自己紹介の時などで,まれに発生することがあるようですが!)
これで,もうお分かりですね。
結論は,
理論上は,元日現在,新年の干支の人口は最も少なく,
前年の干支人口が最も多い。
ということになります。
ちょっと待ってください。「1年後に「寅年」生まれ人口が1位になるらしいことは分かったけど,干支の前年は最下位の12位でなくて何で8位なの?」
こんな疑問がわいてきますね。
「理論上」は,人口ピラミッドが文字どおりピラミッド型又はきれいな富士山型をしている国ほど強く当てはまります。
しかし,日本では,第二次世界大戦,ベビーブーム,第二次ベビーブーム,丙午(ひのえうま),少子化などが影響して,必ずしも理論どおりの干支人口とはなっていないのです。
茨城県の人口ピラミッド(平成21年1月1日現在)
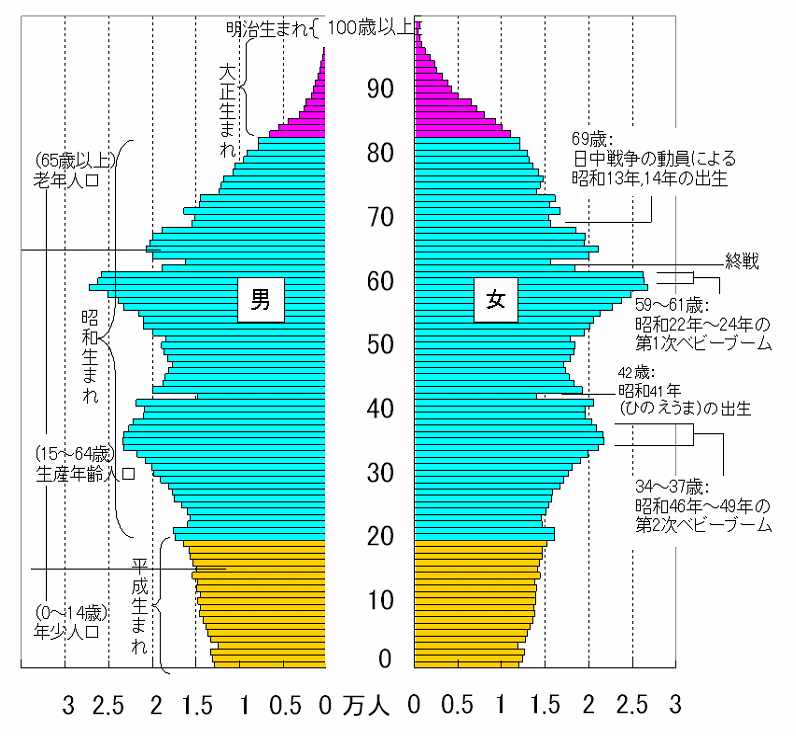
資料:茨城県統計課「茨城県の年齢別人口」から作成
茨城県の人口ピラミッドをみると,昭和19~21年の終戦前後による出生減で「申(さる)」,「酉(とり)」,「戌(いぬ)」年生まれが,昭和41年「ひのえうま」の出生減で「午(うま)」年生まれが影響を受け,それぞれ干支別人口で12位,11位,10位となっています。
一方,昭和22~24年の第一次ベビーブームによる出生増で「亥(い)」,「子(ね)」,「丑(うし)」年生まれが,昭和46~49年の第二次ベビーブームによる出生増で「亥」,「子」,「丑」,「寅」年生まれがそれぞれ影響を受け,「理論上」よりも,人口が多めになります。
(2010年1月4日:茨城県企画部統計課:石井孝一)